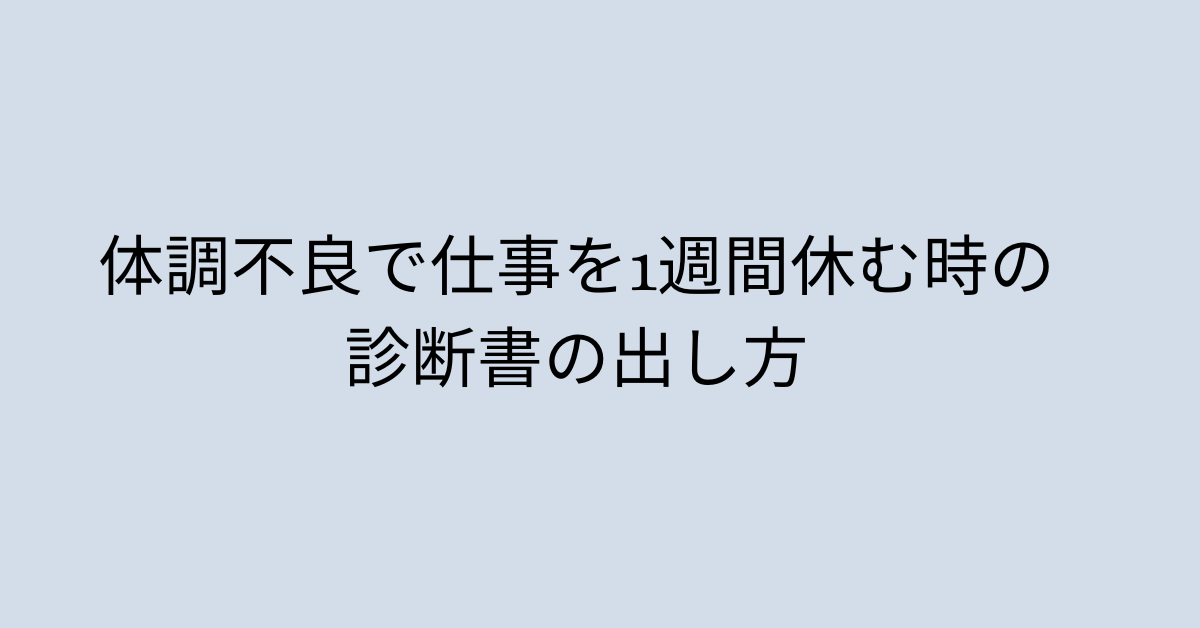突然の体調不良で「1週間も仕事を休まなければならない」となったとき、多くの人が悩むのが、職場への伝え方と診断書の扱い方です。「仮病と思われないか」「メンタル不調でも大丈夫か」「診断書ってどこで出すの?」そんな不安に応えるために、本記事ではビジネスパーソンが知っておくべき対応のポイントを、わかりやすく丁寧に解説していきます。
なぜ1週間休むと診断書が必要なのか?
1〜2日程度の体調不良なら口頭報告やメールで済むケースがほとんどですが、1週間の欠勤となると状況は変わります。多くの企業では、7日以上の欠勤=診断書の提出が必要とされています。これは「就業規則」や「労務管理上の公平性」が関係しています。
診断書があることで、会社側も正式な欠勤処理ができるようになり、後々のトラブルも防ぐことができます。
診断書はどこで出す?費用は?
どんな病院で発行してもらえる?
基本的には、かかりつけの内科やメンタルクリニックなど、通いやすい医療機関でOKです。体調不良の症状が明確であれば、その診察後に「数日〜1週間の安静が必要」と判断され、診断書をもらえるケースが多いです。
診断書の費用相場
診断書の発行は保険適用外になることが多く、3,000〜5,000円前後が一般的な相場です。病院によっては即日発行できないところもあるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
上司への伝え方:誠実さが信頼を生む
報告のタイミング
体調が悪くなったら、できるだけ早く連絡を入れましょう。「数日休むかも」と曖昧に伝えるより、「医師から1週間の安静指示が出た」と明確に説明するほうが信頼につながります。
実際の伝え方の例
「ご迷惑をおかけして申し訳ありません。体調を崩してしまい、医師から1週間の療養が必要と診断されました。診断書も提出可能ですので、どうぞよろしくお願いいたします。」
このように、謝罪・事情説明・対応可能なことをセットで伝えると好印象です。
メンタル不調でも大丈夫?伝え方のコツ
うつ病やストレスによる不調で休むケースも増えています。「会社 一週間 休む うつ」などで検索される背景には、心の問題をどう職場に伝えるかという難しさがあります。
詳細な病名を伝える必要はありません。「体調不良のため」「医師からの指示で休養が必要」といった言い回しで十分です。もし心療内科に通っていることを伝える場合でも、「健康回復のための対応をしている」という前向きな姿勢を見せることが大切です。
仮病と誤解されないためにできること
「1週間休んだら、仮病と思われるのでは…」という不安はよくあります。しかし、きちんと診断書を提出し、欠勤中も必要な連絡やフォローを入れておくことで、そういった誤解は防げます。
また、復帰初日に感謝と簡単な経緯を伝えるだけでも、印象が大きく変わります。
「診断書を出して」と言われたときの対応
会社から正式に「診断書を提出してください」と言われたら、拒まず冷静に対応しましょう。それはあなたの休職を認めるための建前ではなく、制度的な確認作業です。
診断書があれば、仮病と疑われるリスクも減り、会社側の事務処理もスムーズになります。むしろ、出さないことの方が後々面倒になるケースもあります。
休んだ後「行きづらい」と感じたら
「仕事 1週間休む 行きづらい」と感じる人は多いですが、それは自然な感情です。重要なのは、復帰初日の第一印象です。
・朝一番に挨拶する ・「ご迷惑おかけしました」と一言伝える ・可能であれば、休み中の進捗確認や復帰後の意気込みを伝える
こうした小さな行動が、職場での信頼感の回復につながります。
欠勤が7日以上になった場合の注意点
会社によっては、就業規則で7日以上の欠勤時には診断書の提出が必須とされています。知らずに休み続けていると、懲戒や無断欠勤扱いになる可能性もあります。
そのため、体調不良が続きそうだと感じたら、医師の受診と診断書の準備を早めに進めておくことが大切です。
まとめ|安心して休むために、準備と伝え方がカギ
体調を崩して1週間休むのは、決して悪いことではありません。大事なのは、その期間をどう説明し、どう復帰するかです。
診断書を取得し、丁寧に報告し、戻るときは誠実に。これだけで「不信感」ではなく「信頼感」を築ける職場対応が可能になります。
不安な時こそ、しっかり準備して堂々と。正しい手続きで、心身のリセットを安心して行いましょう。