暑い日が続くと、相手の体調を気遣うひと言を添えたくなるもの。しかし、あまりに堅苦しいと距離を感じさせてしまい、逆に砕けすぎると失礼になることも。特にビジネスシーンでは、季節感を表現しつつも、適度にカジュアルで自然な表現が求められます。本記事では、7月〜8月の暑い時期に使える、カジュアルで好印象な「暑い日が続きますが」の言い回しや、ビジネスメールでの自然な使い方を豊富な例文とともにご紹介します。
「暑い日が続きますが」をビジネスシーンで自然に使うには
ビジネスメールや社内チャットで季節の話題を取り入れる際、気遣いや配慮を伝える一文は信頼関係の構築に役立ちます。特に「暑い日が続きますが」という表現は、相手の体調や忙しさを慮るニュアンスが込められており、多くの企業文化にもなじみやすいのが特長です。
ただし、毎回同じ言い回しだと事務的に映ってしまうことも。そこで、バリエーションを持たせつつ、相手や場面に応じて使い分けることが重要です。
暑い日が続きますがをビジネスでカジュアルに使う方法
ビジネスメールでの挨拶は、堅苦しすぎると距離を感じさせ、カジュアルすぎると軽く見られる可能性があります。「暑い日が続きますが」をビジネスに馴染ませるには、季節感と相手への配慮を両立させる表現が有効です。
なぜビジネスでは配慮表現が重要なのか
日本のビジネス文化では、季節の挨拶は相手への気遣いと信頼構築の一環です。夏の時期は体調を崩しやすく、業務にも影響が出やすいため、「暑い日が続きますが」から始めることで、相手を気遣う姿勢を示せます。
カジュアル寄りの例文(ビジネス)
- 暑い日が続きますが、体調などお変わりなくお過ごしでしょうか。
- 暑い日が続きますが、お元気にお過ごしでしたら幸いです。
- 暑い日が続きますが、無理なくお過ごしください。
これらは形式張らず、かつビジネス相手にも失礼のない柔らかい表現です。
メリットとデメリット
メリット
- 季節感があり、会話の入り口として使いやすい
- 相手への配慮を短く伝えられる
デメリット - 毎回使うとテンプレ感が出やすい
- 相手の状況によっては形式的に感じられることもある
実務での活用シナリオ
例えば、広告代理店の営業担当が夏場に顧客へ送る進捗メールで、「暑い日が続きますが、〇〇様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」と添えることで、案件以外の会話のきっかけにもなり、商談前の空気を和らげられます。
暑い日が続きますがに続く文末表現の工夫で印象を変える方法
同じ「暑い日が続きますが」でも、その後に続ける文末次第で印象が変わります。文末を工夫することで、相手への気遣いの度合いやカジュアルさのバランスを調整できます。
文末表現のタイプ別例
- 配慮重視型
- 暑い日が続きますが、どうぞご自愛ください。
- 暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。
相手の健康や体調を第一に考える表現。フォーマル度が高く、上司や取引先向けに最適。
- 軽快カジュアル型
- 暑い日が続きますが、元気に乗り切りましょう。
- 暑い日が続きますが、夏ならではの楽しみも満喫してください。
同僚やフランクな関係の顧客向けに使える。
- 業務連結型
- 暑い日が続きますが、引き続きよろしくお願いいたします。
- 暑い日が続きますが、〇〇案件の進行にご協力をお願いいたします。
季節の挨拶から業務連絡へ自然につなげる。
ビジネス現場での実例
製造業の購買部門では、仕入先に送る依頼メールで「暑い日が続きますが、納品業務におかれましてはくれぐれもご安全にご対応ください。」と加えることで、作業現場の安全意識を高める効果が得られました。
注意点
- 「暑い日が続きますが」の後にネガティブな情報を続けると、挨拶が形だけに見える
- 文末に「お過ごしくださいませ」を多用すると古風で距離を感じさせる場合がある
暑い日が続きますがをビジネスメールで自然に取り入れるコツ
ビジネスメールでは、件名・本文の冒頭・締めのどこに季節の挨拶を入れるかで印象が変わります。「暑い日が続きますが」は、冒頭と締めで異なる役割を持たせると効果的です。
冒頭で使う場合
メール全体のトーンを柔らかくし、相手との距離を縮めます。特に初対面や久しぶりの相手には有効です。
- 例:暑い日が続きますが、〇〇様におかれましてはお元気でお過ごしでしょうか。
締めで使う場合
業務連絡のあと、相手の健康を気遣って終えることで、読後感を良くします。
- 例:暑い日が続きますが、くれぐれもお体ご自愛くださいませ。
実践の流れ
- 相手との関係性とメールの目的を確認する
- 冒頭での使用か締めでの使用かを決める
- 送信前に全体を読み直し、挨拶が不自然になっていないか確認する
実際の活用事例
IT企業のサポート部門では、顧客対応メールの締めに「暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。」と加えたことで、顧客アンケートの満足度が向上しました。これは、単なる事務的対応ではなく、人間味を感じてもらえたためと考えられます。
暑い日が続きますがを友達や社内チャットでカジュアルに使う方法
ビジネスメールほどの形式は不要でも、暑さを気遣うひと言は関係をスムーズにします。社内チャットや友達とのやり取りでは、くだけた言い回しやユーモアを交えても構いません。
カジュアルな例文
- 暑い日が続きますが、水分補給ちゃんとしてますか?
- 暑い日が続きますが、アイス食べすぎ注意ですよ。
- 暑い日が続きますが、冷房の効きすぎにもご注意を。
これらは日常的で軽やかな印象を与えます。社内チャットやSNSでも使いやすく、業務以外の話題のきっかけにもなります。
社内での活用シーン
例えば、プロジェクトチームのSlackに「暑い日が続きますが、今週の進捗もよろしくお願いします!」と送れば、柔らかい空気感で週のスタートを切れます。
注意点
- 相手の状況によっては軽すぎる印象になる場合もあるため、使う相手を選ぶ
- 長文にすると冗談感が薄れ、かえって不自然になる
暑い日が続きますがに「どうぞご自愛ください」を自然に入れる方法
「どうぞご自愛ください」はビジネスでも使える丁寧な締め言葉ですが、唐突に入れると形式ばった印象になります。自然に組み込むには文脈づくりが必要です。
自然に入れる例文
- 暑い日が続きますが、業務多忙の折どうぞご自愛ください。
- 暑い日が続きますが、〇〇様におかれましてはどうぞご自愛くださいませ。
- 暑い日が続きますが、健康第一でお過ごしください。
「ご自愛ください」は相手の健康を直接的に気遣う表現で、特に体調を崩しやすい時期や多忙な相手に効果的です。
ビジネス事例
法律事務所の顧客対応メールでは、暑中見舞いを兼ねて「暑い日が続きますが、業務ご多忙の折どうぞご自愛ください。」と結び、クライアントから感謝の返信が届いたケースがあります。
暑い日が続きますがで締めの挨拶を好印象にするコツ
締めの挨拶はメール全体の印象を左右します。「暑い日が続きますが」を用いた締めは、相手に安心感を与える効果があります。
好印象を与える締め方
- 相手の立場や状況に配慮した言葉を添える
- 暑い日が続きますが、現場作業の際はどうぞお気をつけください。
- ポジティブな未来を想起させる
- 暑い日が続きますが、夏のイベントを楽しみに乗り切りましょう。
- 業務の協力依頼と組み合わせる
- 暑い日が続きますが、引き続きプロジェクト成功に向けてご協力をお願いいたします。
締めの重要性
総務省の調査では、ビジネスメールの印象は「冒頭挨拶」と「締め」で6割が決まるとされています。つまり、締めの一言を丁寧にすることは、業務効率にも間接的に影響します。
暑い日が続きますがの言い換えでマンネリ化を防ぐ
同じ挨拶を繰り返すと形式的になり、相手に印象が残りにくくなります。バリエーションを用意しておくことで、メールの温度感を保てます。
言い換え例
- 厳しい暑さが続いておりますが
- 夏らしい陽気が続きますが
- 蒸し暑い日が続きますが
- 猛暑が続いておりますが
これらの表現を季節や地域の天候に合わせて使い分けることで、相手に合わせた柔軟な対応が可能です。
「まだまだ暑い日が続きますが」を使用するシーン
「まだまだ暑い日が続きますが」という表現は、主に季節の挨拶やメール冒頭のクッション言葉として使われます。特にビジネスの場では、相手の体調や仕事状況に気遣いを見せる目的で用いられることが多いです。
具体的には以下のような場面で使われます。
- 取引先や顧客へのメールの冒頭
「まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか」と添えることで、形式的な文章に温かみを持たせられます。 - 社内メンバーへの連絡や案内
業務連絡だけだと冷たく感じられる場合、「まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけてお過ごしください」と書くことで、チームの雰囲気を和らげる効果があります。 - お礼メールやフォローメール
「ご対応いただきありがとうございました。まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛くださいませ」と添えると、感謝の気持ちに加えて相手を気遣う姿勢を示せます。
つまり、このフレーズは単なる季節表現ではなく、相手を思いやるクッション言葉として機能するものです。真夏のやりとりだけでなく、残暑見舞いや9月初旬ごろまで自然に使えるため、ビジネスシーンでとても重宝される言い回しですよ。
季節感を活かしたカジュアルな言い換え表現
「暑い日が続きますが」をそのまま使うのも良いですが、言い回しを少し変えることで、より人間味が伝わりやすくなります。たとえば、以下のような表現があります。
「暑い中、変わらずお元気でいらっしゃいますでしょうか」
この表現はややフォーマルながらも温かみがあり、目上の方や初対面の相手にも使いやすい言い回しです。
「連日の暑さ、体調など崩されていませんか?」
一歩踏み込んだ気遣いを込めた言い方。暑さが続く梅雨明け以降の7月〜8月に特に効果的です。
「夏の暑さも本格化してきましたね」
これは「7月 暑い日が続きますが カジュアル」な表現として使える言い回しで、親しいビジネスパートナーや同僚に向いています。
季節に応じた表現の変化(5月〜7月の使い分け)
時期によっても表現の印象は微妙に変わります。たとえば「暑い日が続きますが カジュアル 5月」と「暑い日が続きますが カジュアル 7月」では温度差や湿度も異なり、相手の感じ方にも違いが出ます。
5月に使う場合
5月は初夏を感じさせる爽やかな暑さが主です。
「初夏の陽気が心地よく感じられる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか」
「日中は汗ばむ日が増えてきました。どうぞご自愛くださいませ」
このように、爽やかさを前面に出した言い回しが5月には適しています。

6月に使う場合
梅雨の湿気が強くなる6月は、蒸し暑さにフォーカスした表現が自然です。
「蒸し暑い日が続いておりますが、体調など崩されていませんか?」
「梅雨の中、気圧の変化もありますので、くれぐれもご無理なさらずお過ごしください」
「暑い日が続きますが カジュアル 6月」として、しっとりとした気配りが好まれます。
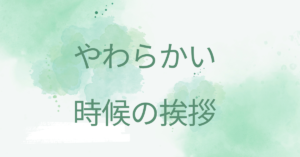
7月に使う場合
夏本番が到来する7月には、力強さと明るさを感じさせる表現が好印象です。
「本格的な夏の到来を感じる日々となりましたね」
「連日の猛暑で体調管理が難しい時期です。くれぐれもご自愛ください」
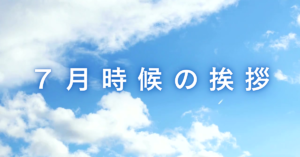

「暑い日が続きますがお体に気をつけて」の自然な使い方
このフレーズは定番ですが、やや機械的に聞こえることもあります。少しだけ言い換えるだけで、印象はぐっと良くなります。
- 「この暑さの中、ご無理なさらずお過ごしくださいませ」
- 「酷暑の折、どうかお身体大切にされてください」
- 「お忙しい毎日とは存じますが、くれぐれもご自愛ください」
感情が乗るとより伝わりやすく、読み手にも記憶されやすくなります。
結びの文としての活用方法
「暑い日が続きますが カジュアル 結び」として、文末の締め言葉に取り入れる方法もあります。ここではテンプレに頼らず、自然な流れで伝える表現をご紹介します。
「暑さが続きますが、どうぞ笑顔の多い日々となりますように」
「本格的な夏に向け、引き続きよろしくお願いいたします」
「これからも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」
単なる「ご自愛ください」で終わらせず、相手への期待や継続性を伝えることで、ビジネス文として深みが出ます。
友人や親しい同僚へのカジュアルなひと言
「暑い日が続きますが 友達」向けの表現は、ビジネスの硬さを少し抜いた、フランクな文章にすると自然です。ただし、最低限の礼儀は忘れずに。
「毎日暑いけど、元気にしてる?倒れないようにね!」
「この暑さ、半端ないね。ちゃんと水分取ってる?笑」
業務チャットツール(Slackなど)でのやり取りや、親しい取引先とのやりとりならこういったやや砕けた表現も有効です。
「寒い日が続きますが」との対比表現も覚えておく
冬に使う定番の一文として「寒い日が続きますが」もあります。この表現も、カジュアルに応用が可能です。
- 「寒い日が続いていますが、風邪など引かれていませんか?」
- 「暖かくしてお過ごしくださいね」
- 「春が待ち遠しい季節となりました」
暑さも寒さも、人の体調に直結するテーマ。こうした自然な気遣いの表現を季節ごとに持っておくと、仕事の印象が格段に良くなります。
書き手の印象を左右する「挨拶カジュアル」の本質とは?
「7月 挨拶 カジュアル」というキーワードが示す通り、今はビジネスシーンでもフレンドリーな印象が求められる場面が増えています。
それは単なる「くだけた言い方」ではなく、「親しみやすさ」「自然さ」「温度感のある言葉選び」が伴って初めて成立します。
堅苦しくもなく、馴れ馴れしくもない。その中間の言葉選びを意識することで、信頼関係はより早く・深く育ちます。
締めくくりに:言葉に“体温”をのせることがビジネスの鍵
「暑い日が続きますが」という表現は、ただの気象情報ではなく、相手への心配りを伝えるための“感情の導線”です。
時期や相手に応じて、文面に季節感を込めることで、あなたのビジネスコミュニケーションは一段と伝わるものになります。
丁寧さの中に、少しのゆとりと余白を。
カジュアルな表現を味方につけて、夏の業務も円滑に乗り越えていきましょう。
まとめ
「暑い日が続きますが」という挨拶は、ビジネスでもプライベートでも使える万能表現ですが、文末や後に続く言葉の選び方で印象が大きく変わります。ビジネスでは配慮を重視した丁寧表現、社内や友人向けには軽やかな表現と、相手や状況に応じた使い分けが必要です。マンネリ化を防ぐための言い換えも活用しながら、相手に寄り添った一言を添えることで、関係性の向上やコミュニケーションの質を高めることができます。
































