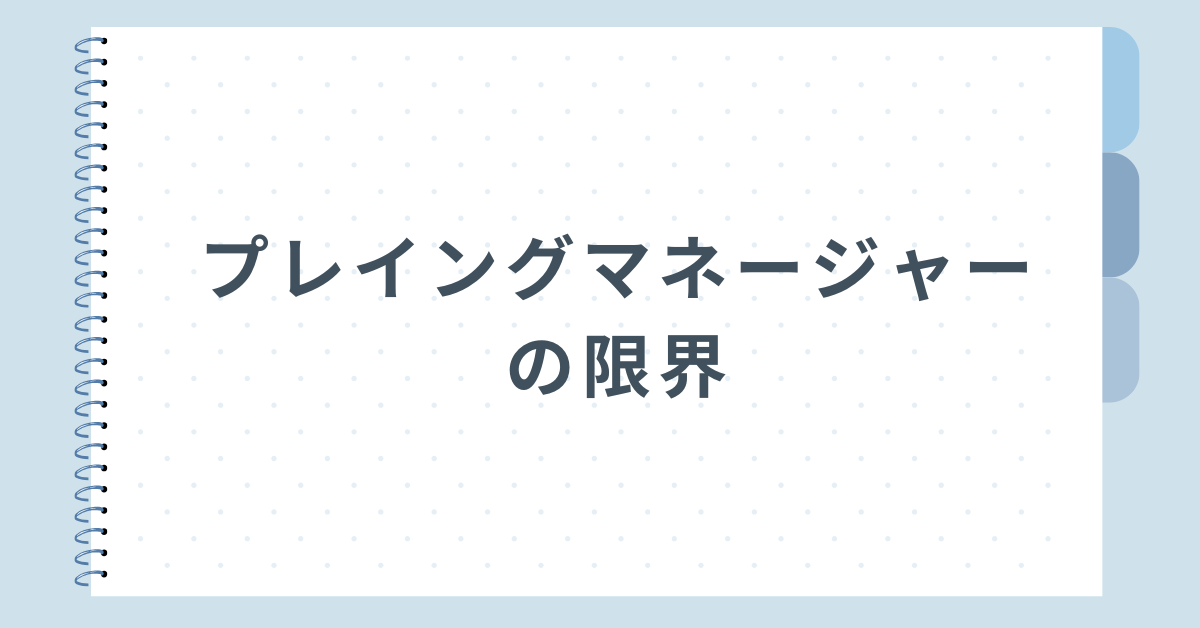プレイングマネージャーという役割は、多くの企業で当たり前のように存在しています。しかし、成果を出す一方で、「激務すぎる」「本当に機能しているのか?」といった疑問の声も増えつつあります。本記事では、プレイングマネージャーという働き方の限界やデメリットにフォーカスし、その背景や組織への影響、さらに実際の失敗例まで徹底的に解説していきます。組織づくりに悩む経営層やマネジメント層にとってのヒントになるはずです。
プレイングマネージャーとは何か?役割の構造を理解する
プレイングマネージャーとは、プレイヤー(実務担当)とマネージャー(管理者)の両面を兼ねる役割のことを指します。一見、柔軟で万能な存在に見えますが、その構造は極めて負荷が高く、組織設計次第で大きな歪みを生む可能性があります。
現場の細かな業務を遂行しつつ、部下の育成や評価、チームマネジメントを行う必要があり、時間も意識も分断されがちです。この“二足のわらじ”状態が、後述するような限界や課題を招く大きな要因になります。
プレイングマネージャーとマネージャーの違いを正確に把握する
多くの混乱は、この違いを組織全体が理解していないことから生じます。一般的なマネージャーは、業務の管理・人材マネジメント・戦略の推進に集中できるのに対し、プレイングマネージャーは日々の業務もこなす必要があります。
つまり、判断や調整だけでなく、手を動かす時間が必須となるため、マネジメントの質が下がりやすい構造なのです。部下のサポートに回る時間がなくなると、評価も育成も中途半端になりがちです。
なぜプレイングマネージャーがダメと言われるのか?
「プレイングマネージャーはダメだ」という声には、いくつかの構造的・心理的理由があります。ひとつは時間的リソースの分散です。プレイとマネジメントの両立は、理想的には聞こえますが、時間やリソースが限られる現場では現実的に困難です。
また、部下から見ると「上司が自分の仕事に集中していて頼れない」「指示が曖昧」といった不満が出やすくなります。その結果、プレイングマネージャーは組織の中で“おかしい役割”と揶揄されることさえあります。
プレイングマネージャーの限界と見えにくい疲弊
表面的には高パフォーマンスに見えても、裏では激務と責任の板挟みによって、メンタル・フィジカル両面で疲弊していることが少なくありません。特に「何でも自分でやる」傾向が強いプレイングマネージャーは、知らぬ間に限界を超えてしまうケースもあります。
休むことに罪悪感を持ち、部下にも頼れない。そんな心理構造が、「辛い」「続けられない」と感じる原因になっています。
プレイングマネージャーにありがちな失敗例
1つ目は「任せられないマネージャー」になってしまうパターンです。すべてを自分で抱え込み、部下に任せる余裕も信頼も持てなくなり、結果としてチームの成長を妨げます。
2つ目は「数字にしか目が向かなくなる」ケース。プレイ面に時間を奪われ、マネジメントの基本である対人ケアや動機付けが疎かになります。その結果、離職率が高まったり、現場の士気が下がったりします。
3つ目は「中長期の視点を失う」こと。日々の業務に埋もれ、将来的な戦略や育成計画が立てられず、目の前の仕事に追われるばかりになります。
プレイングマネージャーのデメリットを整理する
- マネジメントに必要な“考える時間”が確保できない
- 部下からの相談を後回しにしてしまう
- チームの状態を客観的に見られない
- 他部署や経営層との調整役が疎かになる
- 育成や評価が定型業務化し、意義を失う
これらの要素が複合的に重なり、チームとしての機能不全や、マネージャー自身の燃え尽きへとつながります。
プレイングマネージャーのメリットと効果的な活用法
とはいえ、プレイングマネージャーがすべて悪いというわけではありません。現場感覚を保ちつつ、即時の判断・対応ができる点は、変化の激しい職場では武器になります。
また、部下との心理的距離が近くなりやすいことで、日常的なコミュニケーションや現場の声の把握がしやすいという利点もあります。
ポイントは、“一時的かつ戦略的”にプレイングマネージャーを設計すること。制度として恒常化するのではなく、現場の変革期や新規プロジェクトに限って運用するなど、メリハリのある設計が求められます。
限界を迎える前にできること:組織・個人での対策
- 業務の棚卸しと役割の見直しを定期的に行う
- 権限委譲や部下育成を優先事項に組み込む
- マネジメント専任ポジションを段階的に設ける
- プレイング比率を可視化し、過剰化を抑制する
また、マネージャー自身も「自分は何の役割を果たすべきか」を問い直し、組織にフィードバックすることが重要です。無理に全てを背負わない“線引き”も、マネジメントの一部なのです。
まとめ:万能に見えるが、長期的には歪みを生む制度
プレイングマネージャーは、スピード感や柔軟性をもたらす一方で、構造的な課題も多く抱えています。組織の変革期やリーダーシップ不足の場面では効果を発揮しますが、常態化すれば本人もチームも疲弊してしまいます。
だからこそ、「なぜこの制度が必要なのか」「どうすれば健全に運用できるのか」を常に問い続ける姿勢が欠かせません。組織として、役割の定義を曖昧にせず、責任と裁量のバランスを設計していくこと。それが、プレイングマネージャー制度を“ダメ”なものにしないための唯一の道です。