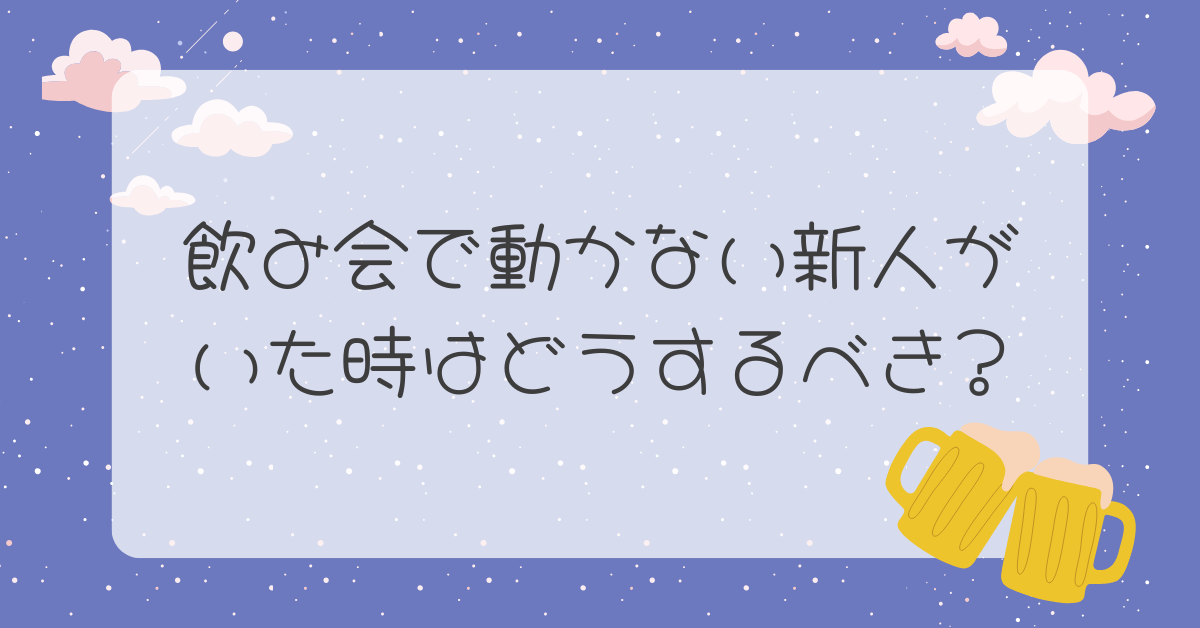飲み会の場で新人が動かない、空気を読まない、そんな状況に戸惑った経験はないでしょうか。現代の働き方や価値観の変化により、従来の飲み会マナーが通用しなくなってきています。本記事では、飲み会で動かない新人にどう対応すべきかを考察しながら、ビジネスパーソンとしての心得やマネジメントの視点も踏まえ、上司としての適切な対応を解説します。
飲み会で新人が動かないと感じたら
昔と今の飲み会文化のギャップを知る
かつての飲み会は、仕事の延長線上として重要な交流の場とされていました。特に新人には、「率先して動く」「上司のお酌をする」「場を盛り上げる」といった振る舞いが当然のように求められ、それによって評価される風潮が根強くありました。
しかし現在では、飲み会そのものを業務外の私的な時間と捉える若手も多く、「飲み会のマナーはくだらない」「無理に気を遣う場にしたくない」といった声が出てきています。このような認識のズレが、「新人が動かない」「気が利かない」といった評価につながっているのです。
飲み会で動けないのは不器用なだけかもしれない
新人が飲み会で動かないからといって、即座にマナー違反や怠慢と断じるのは早計です。場の空気に慣れていない、不安や緊張で身動きが取れないといったケースも多く、「飲み会で動けない」という状態には個人差があります。
また、過剰な気遣いやマナーにプレッシャーを感じている場合もあります。お酌や注文のタイミングが分からないまま、かえってぎこちない立ち回りになってしまう若手もいます。
飲み会での立ち回りに関する価値観の変化
動かない新人を「めんどくさい」と感じる前に
「気が利かない」「空気が読めない」といった評価を新人に下す前に、まずは自分たちの常識が時代遅れになっていないかを省みる必要があります。特に、飲み会を通じて上下関係を築こうとする文化は、現代のフラットな組織運営と相容れない場合があります。
上司が「新人が動かない=やる気がない」と短絡的に判断することで、優秀な若手の心を離れさせてしまうリスクすらあります。価値観の違いを前提にしたコミュニケーションの工夫が求められる時代です。
飲み会のマナーは「押し付け」ではなく「共有」へ
たとえば、「新人はお酌をするべき」といった旧来の慣習は、必ずしも若手の共感を得られるとは限りません。お酌をされること自体を気まずく感じる上司もいれば、性別や文化的背景からそれを不快に思う人もいます。
現代の飲み会では、誰もが自然体で参加できる雰囲気づくりが求められています。上司側があらかじめ「お酌や注文は気にしなくていい」と伝えるだけで、新人もリラックスして場に参加しやすくなるでしょう。
新人が動かないことで起こる誤解とその解消法
飲み会での挨拶や注文に不慣れなだけかもしれない
「飲み会で新人が挨拶しない」「注文もせずに黙って座っている」といった場面に遭遇すると、周囲は不満を感じるかもしれません。しかし、その背景には「何を言えばいいか分からない」「どう振る舞えばいいか分からない」といった不安がある場合が多いのです。
新人が飲み会のルールや雰囲気を理解する前に、場に放り出されてしまうと、委縮してしまうのも無理はありません。むしろ、気後れしてしまう新人にこそ、上司が気を配る必要があると言えるでしょう。
正しいマナーよりもコミュニケーションが重要
飲み会のマナーに正解はありません。注文のタイミングやお酌の有無よりも大切なのは、その場でどれだけ自然なコミュニケーションが取れているかです。
仮に新人が動かなかったとしても、話しかければ笑顔で返す、質問に素直に答える、といった反応があるならば、それで十分な場合もあります。マナーにとらわれず、人間関係の構築に注力すべきでしょう。
上司が取るべき行動と意識のアップデート
飲み会を評価基準にしない職場づくり
飲み会の場での立ち回りを評価基準に含めるような風潮は、若手社員の離職を招きやすくなります。「飲み会で気が利かない若手=仕事ができない」という誤ったラベリングがされないよう、上司や中堅社員が率先して意識改革を行うことが重要です。
飲み会の目的を「親睦」と明示し、業務外の場での振る舞いによって社員を評価しないという方針を共有しておくことで、安心して場に参加できる空気を作ることができます。
飲み会に慣れていない新人への声かけのコツ
新人が飲み会の中で緊張しているようなら、上司や先輩が積極的に話しかけて安心させることが大切です。「無理に動かなくていいよ」「今日は楽しんでね」と一言添えるだけで、新人の表情が和らぐことも少なくありません。
また、飲み会が苦手な若手には無理に誘わず、参加の自由を尊重することも大切です。現代の職場では「飲み会に来ない=非協力的」といった偏見も改める必要があります。
飲み会文化を見直し、職場の関係性を再構築する
時代の変化に合わせて、職場のコミュニケーションスタイルも見直す必要があります。従来の飲み会文化は、一定の役割を果たしてきた一方で、現代では多様な価値観に配慮できる柔軟性が求められています。
新人が飲み会で動かないと感じたとき、それを単なるマナー違反と捉えるのではなく、背景にある心理や環境要因に目を向けましょう。上司側の理解と工夫次第で、より良い人間関係と職場の風土を育てることができるのです。
飲み会はあくまで人間関係づくりの一環です。そこに過度な期待やプレッシャーをかけず、互いに気持ちよく過ごせる場にしていくことが、現代のマネジメントに求められています。