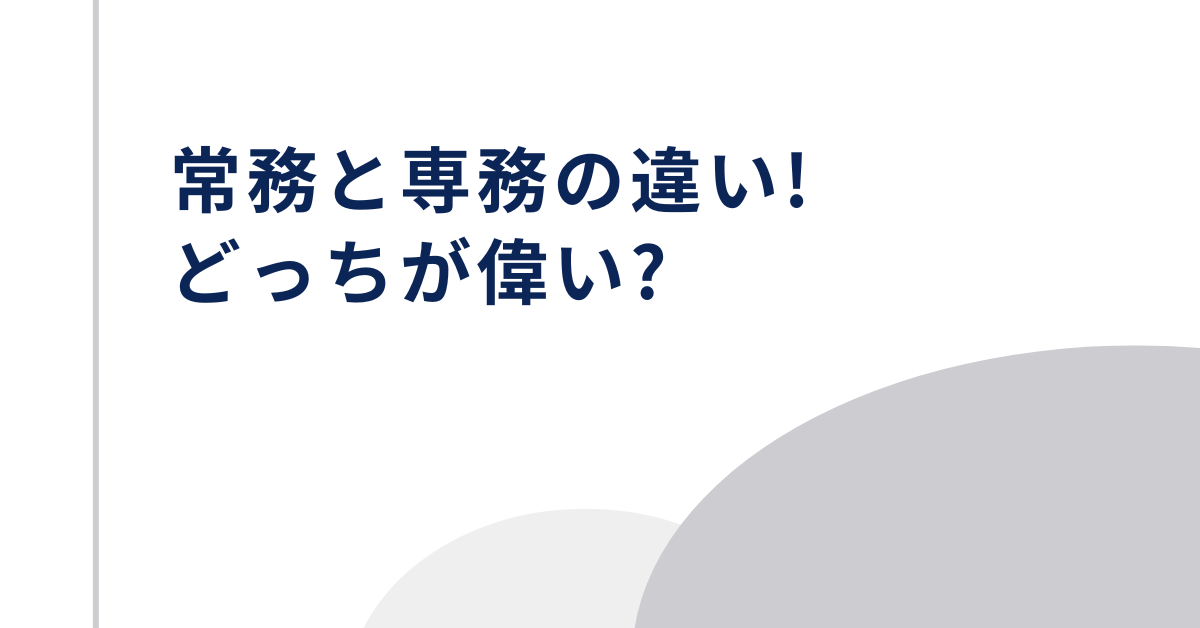企業の役員構造は複雑で、特に「常務」と「専務」の違いは社内でも意外と正確に理解されていません。本記事では、役員の立ち位置や権限、組織図上の序列をわかりやすく解説します。常務と専務の役割の差を明確にし、年収や昇進ルート、経営会議での影響力など、ビジネス現場で即役立つ知識を提供します。社内外の関係構築やキャリア戦略にも活かせる実践的な内容です。
常務と専務はどっちが偉いのかを序列と役割で理解する
役員序列において、専務と常務のどちらが上位かという問いは、就職活動中の学生や転職希望者だけでなく、現役のビジネスパーソンからもよく寄せられます。結論から言えば、専務取締役は常務取締役よりも上位の役職です。これは会社法や定款に明確な記載がなくても、日本企業の慣習や組織運営上ほぼ共通している序列です。
役員序列の一般的な構造
日本企業では、取締役会における序列は次のようになることが多いです。
- 代表取締役社長
- 代表取締役副社長
- 専務取締役
- 常務取締役
- 取締役(部門長などを兼務する場合あり)
この序列は、意思決定の権限や管轄部門の規模に直結します。専務は複数部門を横断的に統括し、社長や副社長の右腕的な存在となるのに対し、常務は特定の事業部門や機能に集中して責任を持つケースが多いです。
ビジネス現場での違い
例えば製造業の大手企業では、専務が全工場の生産戦略を統括し、常務が特定工場の業務効率化プロジェクトを指揮するといった役割分担が見られます。意思決定のスピードや影響範囲が異なるため、日々の業務の進め方や社内での影響力も変わります。
海外企業との比較
海外企業では「Executive Vice President(EVP)」が専務、「Senior Vice President(SVP)」が常務に近い役割を担うことがあります。ただし、米国などでは明確な序列よりも職務内容や契約による権限が重視されます。
メリットとデメリット
- 専務のメリット:経営全体への影響力が大きく、戦略策定の中心になれる
- 専務のデメリット:責任範囲が広く、失敗時のリスクも大きい
- 常務のメリット:専門分野に集中でき、成果が明確に出やすい
- 常務のデメリット:経営全体への関与度は専務よりも低い
注意点
企業によっては役職名が名誉職的に使われる場合もあり、必ずしも序列や権限の強さを反映しないことがあります。人事異動や昇格の背景も確認することが重要です。
常務とは何をする役職なのかを具体的に知る
常務取締役は、取締役の中でも特定の事業部門や機能部門の責任者として位置づけられることが多いです。会社法上は取締役の一種であり、常務という呼称自体に法的な定義はありませんが、慣習的に経営幹部としての役割が与えられています。
常務の業務範囲
常務は、営業本部長・人事部長・開発部門統括など、社内の重要な部門のトップを兼任するケースが多いです。たとえば大手IT企業では、常務取締役が国内営業全体の売上責任を負い、年間数百億円規模の予算を管理する事例もあります。
常務の立ち位置
専務と社長の間には副社長が置かれる場合が多いですが、常務はその下のレイヤーで各部門のトップとして動きます。現場の課題を経営会議に持ち込み、意思決定をサポートする役割も果たします。
昇進の経路
課長や部長として長年業績を残し、取締役に昇格後、特定分野でのリーダーシップが認められれば常務への昇進が見込まれます。近年は、海外経験やデジタル戦略の推進力を持つ人材が常務に抜擢されるケースも増えています。
常務取締役の年収
大手上場企業では常務の年収は2,000万〜3,000万円程度が相場で、賞与やストックオプションを含めればさらに上回る場合もあります。非上場企業では規模によって1,000万〜1,500万円台が一般的です。
失敗事例と注意点
常務は部門内での指揮権限が強いため、トップダウンが過ぎると現場の反発を招きます。あるメーカーでは、常務が急進的なコスト削減策を導入した結果、製品品質が低下しブランドイメージが損なわれた事例もあります。
専務とはどのような役職かと社長との違い
専務取締役は、取締役会において社長の次に経営全体を統括する役割を担います。会社法上の定義はなく、企業によって職務範囲が異なりますが、多くの場合、経営戦略・財務管理・複数部門の横断的統括など、広範な業務を担当します。
専務と社長の違い
- 社長:会社全体の最終責任者。株主総会や取締役会での意思決定を代表し、外部に対して会社を代表する。
- 専務:社長の方針を実行に移し、複数の常務や部門長を統括して現場の運営を管理する。
このため、専務は「社長の右腕」としての性格が強く、経営会議でも発言力が大きいです。
専務の業務範囲
専務は、営業・開発・人事・財務といった全社的機能を横断して指揮することが多いです。たとえば、自動車メーカーの専務は国内外の販売戦略を統括し、各地域の常務取締役と連携して市場シェアの拡大を進めます。
海外での専務に相当する役職
米国企業では「Chief Operating Officer(COO)」が専務に近い役割を担います。COOは社長(CEO)の戦略を実行し、日々の業務オペレーションを監督します。
専務のメリットとデメリット
- メリット:経営全体の意思決定に深く関与できる。将来的に社長への昇格の可能性が高い。
- デメリット:責任が極めて重く、失敗が株主や市場からの信頼低下に直結する。
注意点
専務は社長と一心同体で動くため、社長交代時には立場が変化するリスクがあります。新社長の方針と合わなければ、役職を外れる可能性もあります。
専務・常務・副社長・取締役・執行役員の違いを明確にする
役員クラスの呼称は似ていても、職務範囲や責任の重さは大きく異なります。誤解されやすいのが、副社長や執行役員との違いです。ここでは、各役職の特徴を整理し、企業内での序列や実務の違いを明らかにします。
副社長
副社長は、社長の代行権限を持つことが多く、社長不在時には意思決定を行うことができます。専務よりも序列が上であり、将来の社長候補と見なされる場合もあります。ただし、名誉職として置かれることもあり、その場合は実務権限が限定的です。
取締役
取締役は会社法で定められた役員で、経営方針の決定や監督を行います。常務や専務は取締役の一種であり、役割の範囲が特定部門や経営全般に広がるかで呼称が変わります。
執行役員
執行役員は、会社法上の役員ではなく、実務執行に特化したポジションです。取締役会のメンバーでない場合もあり、株主総会での選任は不要です。グローバル企業では、取締役が戦略策定、執行役員がオペレーションという分業が一般的です。
専務・常務との比較表
| 役職 | 序列の目安 | 主な職務範囲 | 法的役員か |
|---|---|---|---|
| 社長 | 最高責任者 | 経営全般、外部代表 | ○ |
| 副社長 | 社長補佐 | 社長代行、戦略統括 | ○ |
| 専務取締役 | 常務の上位 | 全社的経営、複数部門統括 | ○ |
| 常務取締役 | 専務の下位 | 特定部門統括、経営会議参加 | ○ |
| 取締役 | 経営会議メンバー | 経営方針決定、監督 | ○ |
| 執行役員 | 実務執行 | 部門運営、戦略実行 | × |
この表を理解することで、社内の力学や昇進ルートを把握しやすくなります。
常務と専務の立ち位置を組織図で把握する
組織図を見ると、常務と専務の立ち位置がより明確になります。多くの企業で採用される縦型の組織図では、専務は常務を含む複数の取締役を統括する位置にあります。
一般的な組織図の例
コピーする編集する代表取締役社長
│
副社長
│
専務取締役
├── 常務取締役(営業担当)
├── 常務取締役(開発担当)
└── 常務取締役(管理部門担当)
立ち位置の意味
この構造からわかるように、専務は経営全体のバランスを取りながら複数部門を監督し、常務は担当部門の目標達成に集中します。
企業規模による違い
- 大企業:専務の下に複数の常務が配置され、さらにその下に執行役員や部長がいます。
- 中小企業:専務と常務の役割が兼務されることもあり、明確な階層分けがない場合があります。
注意点
組織図は表面的な序列を示すもので、実際の権限は社長や株主との関係、創業者の影響力によって変動します。
年収・昇格条件・求められるスキルを比較する
役員ポジションを目指すうえで、年収や求められるスキルは大きな関心事です。常務と専務の待遇差や昇格の条件を具体的に解説します。
年収の目安
- 専務取締役:大手上場企業で3,000万〜5,000万円、中堅企業で1,500万〜2,500万円
- 常務取締役:大手で2,000万〜3,000万円、中堅で1,000万〜1,500万円
この差は、責任範囲の広さや経営会議での影響力の大きさに比例します。
昇格条件
- 専務昇格には、常務としての実績だけでなく、複数部門の横断的マネジメント経験が必須です。
- 常務昇格には、特定部門での業績改善やリーダーシップが重要視されます。
求められるスキル
- 専務:戦略思考、財務知識、社外折衝能力、リスクマネジメント
- 常務:専門分野の知識、現場マネジメント力、課題解決スキル
実際の企業事例と海外比較から見る専務・常務の役割
役員職の役割や序列は、企業規模や業種、さらには国ごとの商習慣によっても変わります。ここでは、日本国内の具体的な企業事例と海外の役職制度を比較しながら、専務と常務の立ち位置をより立体的に理解します。
国内企業の事例
事例1:製造業大手A社(上場企業)
A社では、専務は生産・営業・財務の3本柱を統括し、各部門ごとに常務を配置しています。常務は部門別の中期戦略策定と日々のオペレーション管理を行い、専務が全体の戦略調整を担う形です。例えば、海外工場の新設を検討する際、常務は各部門の収益性やリスク分析を行い、専務はそれを統合して経営会議で社長に提案します。
事例2:ITサービスB社(中堅企業)
B社では常務と専務の役割がやや流動的で、専務が実質的な営業統括を行う一方、常務が新規事業部門の責任者を兼ねるケースがあります。これは中小〜中堅規模では珍しくない形で、役職名よりも実際のミッションで業務内容が決まる傾向が強いです。
海外の役職制度との比較
海外、特に米国企業では「専務」「常務」といった呼称はほぼ存在せず、代わりに COO(最高執行責任者) や EVP(Executive Vice President) が類似の役割を担います。
- COOは専務に近く、企業全体のオペレーション最適化を担います。
- EVPは部門統括の色合いが強く、日本の常務と類似しています。
欧州企業の場合は、取締役会と執行役が完全に分離しており、役職名よりも職務記述書(ジョブディスクリプション)で役割を定義することが一般的です。
海外比較のメリット
海外制度と照らし合わせることで、専務や常務の役割をグローバル人材育成や社内制度改革の観点から再設計できます。日本企業も外資との取引やM&Aが増える中で、役職名だけでなく職務範囲の明確化が求められています。
キャリア戦略として役員知識を活用する方法
専務や常務の役割と序列を理解することは、経営層を目指す人にとって戦略的なキャリア形成に直結します。単なる肩書きの理解にとどまらず、次のような具体的な活用方法があります。
自分のポジションを戦略的に設計する
役員を目指すなら、自分が将来「専務型」か「常務型」かを早めに見極めることが重要です。専務型はゼネラリスト寄りで全体最適の視点を持つ必要があり、常務型はスペシャリスト寄りで特定分野の成果が評価されます。
人脈構築と影響力の拡大
専務や常務への昇格は、実績だけでなく経営層や株主との信頼関係によっても左右されます。役員層の仕事ぶりや判断基準を理解すれば、効果的な提案やコミュニケーションが可能になります。
他社事例の研究
同業他社の組織図や役員構成を分析すると、自社で不足しているスキルやポジションが見えやすくなります。特にM&Aや事業提携を視野に入れる企業では、役員ポストの空きや世代交代のタイミングがキャリアチャンスとなります。
海外企業との接点を活かす
外資系との共同プロジェクトや海外出向の経験は、将来的に専務・常務クラスへの昇格に有利です。グローバルな役職体系を理解していることは、社内外での評価に直結します。
まとめ
専務と常務の違いは単なる序列の差ではなく、経営全体を統括するか、特定部門を深く掘り下げるかという役割の方向性の違いにあります。専務は企業全体の戦略調整役、常務は部門経営の実行責任者という性質が強く、それぞれ求められるスキルセットも異なります。
この記事で解説した
- 役職ごとの責任範囲
- 組織図での立ち位置
- 年収・昇格条件
- 海外比較による理解の深化
を踏まえれば、社内での自分の位置づけやキャリアの方向性をより明確に描くことができます。
経営層を目指す人は、役職名の意味と実務の本質を正しく理解し、日々の業務にその視点を取り入れることが重要です。これが、昇格や報酬アップだけでなく、企業全体の成長に貢献する第一歩となります。
専務・常務の責任範囲を図解で整理する
文章だけでは役職の立ち位置や序列感がイメージしづらいため、ここで組織図の例を用いて解説します。特に大企業と中小企業では、役職名は同じでも業務範囲や権限の幅が異なります。
大企業の役員構造例(製造業・上場企業)
objectivecコピーする編集する社長(CEO)
│
├─ 副社長(Vice President)
│
├─ 専務取締役(Executive Managing Director)
│ ├─ 常務取締役(Managing Director)
│ │ ├─ 部長(General Manager)
│ │ │ ├─ 課長(Section Manager)
│ │ │ │ └─ 担当者(Staff)
│ │ └─ 部門別チーム
│ └─ 企画・総務など複数部門統括
└─ CFO・CTOなどの専門役員
この例では、専務は常務を束ね、経営全体を俯瞰する立場です。一方、常務は部門単位での責任を負い、より現場寄りの戦略実行を担います。
中小企業の役員構造例(IT企業)
コピーする編集する社長(CEO)
│
├─ 専務(兼営業本部長)
│
├─ 常務(兼新規事業責任者)
└─ 部長(複数部門兼務)
中小企業では、専務や常務が複数部門を兼務し、直接オペレーションにも関わることが多いです。このため、大企業と比べると役職ごとの職務分担が明確でないケースが多くなります。
常務や専務を目指すために必要なスキルセット
役職の定義を理解したうえで、自分が将来このポジションを目指す場合に必要な能力を整理します。
専務に求められるスキル
- 全社的視点:部門横断の戦略立案や調整ができる能力
- 財務リテラシー:PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)をもとに意思決定できる
- リーダーシップ:経営層と現場の橋渡し役としての統率力
常務に求められるスキル
- 専門分野の深い知識:営業、製造、開発など特定領域の高い専門性
- 実行力:現場を動かし、短期的な成果を出せる能力
- 部門戦略立案:中期的な計画と短期の改善施策を両立できる
年収レンジと昇格条件のリアル
役員報酬は企業規模や業種によって大きく変動しますが、一般的な傾向を以下に示します。
| 役職 | 年収レンジ(上場企業) | 年収レンジ(中小企業) |
|---|---|---|
| 専務取締役 | 1,500万〜3,000万円 | 800万〜1,500万円 |
| 常務取締役 | 1,200万〜2,500万円 | 700万〜1,300万円 |
昇格の条件としては、売上拡大への貢献やコスト削減、M&Aの成功などの経営的成果が評価されます。単に年功序列で昇格するケースは減少傾向にあり、成果主義の傾向が強まっています。
失敗事例から学ぶ役員昇格の落とし穴
実際に昇格後に成果を出せず短期間で退任となるケースもあります。よくある原因は以下です。
- 現場感覚の喪失:経営層に上がった途端、現場の課題に鈍感になる
- 社内政治への偏重:実務より社内の人間関係や派閥に時間を割きすぎる
- 変革への抵抗:新しいビジネスモデルやDX推進に消極的
これらは役員昇格前から意識的に回避すべきポイントです。
専務・常務の違いを活かした組織マネジメント戦略
専務と常務は階層上の違いだけでなく、業務領域や関与度も異なります。この特性を活かすことで、組織のパフォーマンスを最大化するマネジメントが可能です。
専務を活用するマネジメント
専務は「全社戦略の旗振り役」としての役割が強いため、次のような場面で力を発揮します。
- 新規事業の立ち上げ
- 複数部門にまたがる組織再編
- 海外進出やM&Aなどの大型案件推進
例えば、製造業A社では専務が直接海外子会社のM&Aプロジェクトを指揮し、3年で売上を40%伸ばしました。社長は全体の意思決定に専念し、専務は実行面をコントロールする役割分担が奏功した事例です。
常務を活用するマネジメント
常務は「現場の旗振り役」としての役割が強いため、戦略を現場レベルに落とし込む際に不可欠です。
- 部門ごとの目標設定とKPI管理
- プロジェクトの実行監督
- 部下育成と現場のモチベーション向上
IT企業B社では、新規SaaS事業の立ち上げ時に常務が開発・営業・マーケティングを横断的に管理。現場での課題を即座に経営会議へフィードバックし、半年で黒字化に成功しました。
海外企業との比較で見る専務・常務の位置づけ
海外の役員制度と比較すると、日本の専務・常務は役割がやや独特です。
- アメリカ企業
CEO(最高経営責任者)、COO(最高執行責任者)、CFO(最高財務責任者)など、役職名は機能別に明確化。日本の専務はCOOに、常務は部門VP(Vice President)に近い役割。 - ヨーロッパ企業
マネジメントボード(経営執行会)とスーパーバイザリーボード(監査・監督会)が分かれ、専務・常務のような中間的経営役職は存在しないことも多い。
このため、日本企業が海外進出する際は役職名の翻訳や役割説明が必要です。特に取引先との交渉や契約書での役職明記時に誤解が生じやすいため注意が必要です。
専務・常務ポジションを効果的に配置するための実践手順
実際に専務や常務を組織に配置・任命する際のプロセスを整理します。
- 組織の戦略目標を明確化する
例:売上成長率15%アップ、海外市場売上比率20%到達など。 - 専務・常務の役割定義を策定する
部門統括・新規事業推進・経営管理など、明確なミッションを設定。 - 候補者のスキル・適性を評価する
実績・リーダーシップ・財務知識・社内外の信頼度などを総合評価。 - 就任後の評価制度を設計する
売上・利益・プロジェクト達成度などKPIを設定し、定期評価を行う。
このプロセスを踏むことで、役職の権限と責任を明確化でき、昇格後のミスマッチや短期退任リスクを下げられます。
専務・常務の人事判断で失敗しないための注意点
役員人事は組織に大きな影響を与えるため、次の点に注意が必要です。
- 人物評価の偏り:長年の付き合いや派閥による選出は避け、客観的指標を重視する
- 業務負担の過多:兼務が多すぎると戦略遂行力が低下する
- 後継者育成の遅れ:役員層が高齢化し、後任育成が進まないリスク
特に中小企業では、専務・常務が社長の右腕的存在として長く居座りすぎると、新しい経営人材が育たず、事業承継の壁となる場合があります。
まとめ
専務と常務の違いは、単なる序列だけでなく「経営戦略の視点」と「現場実行の視点」の違いにあります。
専務は全社的な戦略推進、常務は部門レベルでの実行力発揮が役割であり、この2つがバランスよく機能することで組織は持続的成長を実現できます。
役員人事を戦略的に行い、適材適所で配置することが、企業競争力の源泉となります。