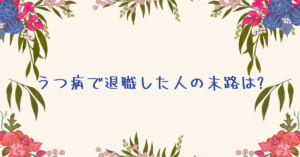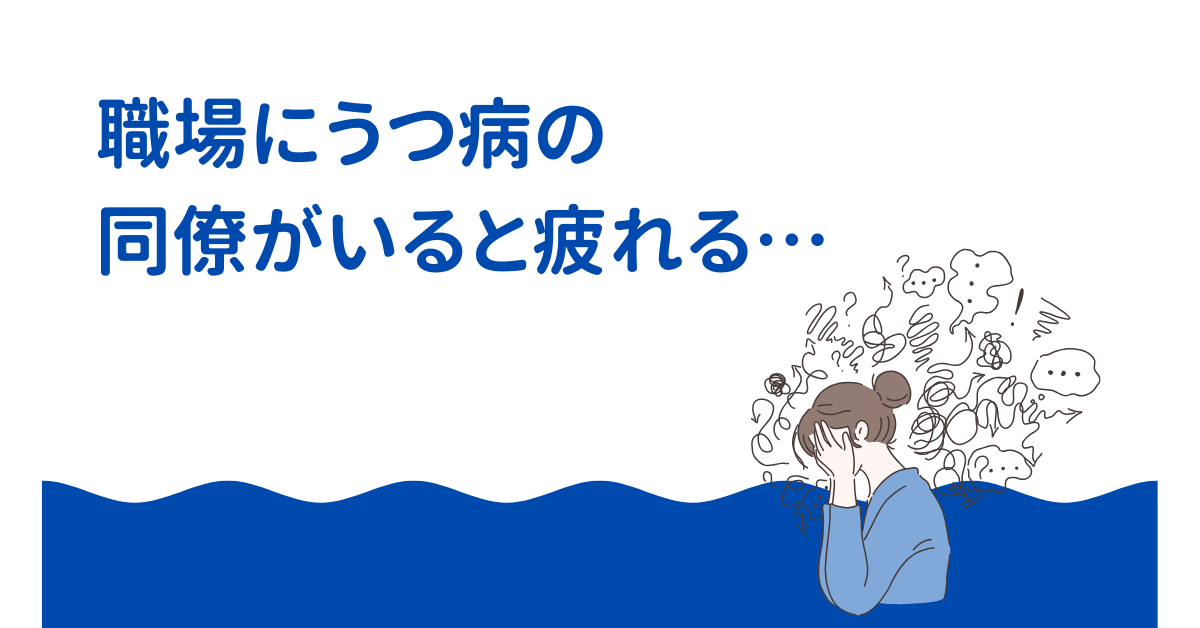職場にうつ病の同僚がいると、サポートする側も心身の疲れを感じることがあります。自分の業務が増えたり、コミュニケーションがぎこちなくなったりと、知らず知らずのうちにストレスを抱えてしまう人も少なくありません。この記事では、「うつ病 周りが疲れる 職場」や「職場にうつ病 しわ寄せ」といった悩みを抱える方に向け、関わり方の工夫と組織としての改善策を具体的に解説します。負担感を減らしつつ、互いが安心して働ける環境を作るヒントをお届けします。
なぜうつ病の同僚がいると周囲が疲れやすくなるのかを理解する
まず大切なのは、「なぜ疲れるのか」を冷静に整理することです。感情的に「迷惑」と感じる前に、背景を知るだけで心の負担が少し軽くなる場合もあります。
背景にある心理的・業務的負担
うつ病の同僚がいる職場では、次のような状況が起こりがちです。
- 業務のしわ寄せが一部の人に集中する
- 体調の波によって急な欠勤や休職がある
- 会話や依頼の仕方に気を遣う場面が増える
- 同僚の変化に気づきつつも、どう接すればいいか分からない
これらは単なる「気疲れ」ではなく、心理学的には共感疲労(他人の苦しみを見続けることで自分も疲弊する状態)やロールストレス(役割の負担や不明確さからくるストレス)に該当します。
ビジネス現場での実例
ある中堅メーカーの営業部では、うつ病で時短勤務になった社員の業務を、同僚3人が分担して引き受ける状況が半年以上続きました。結果、担当者だけでなく引き受けた側も残業続きとなり、別のメンバーが体調を崩す「負の連鎖」に発展しました。このケースでは、負担分散のルールや外部サポート体制がなかったことが問題でした。
海外の職場文化との比較
海外、特に北欧の職場では、メンタル不調者への支援と同時に「支援する側のケア」も制度化されています。これはセカンダリーケアと呼ばれ、支援者自身が疲弊しないようカウンセリングや休暇取得を推奨する仕組みです。日本ではまだ浸透していませんが、導入事例は少しずつ増えています。
メリットとデメリットの整理
メリット
- 職場全体での支援体制が整えば、離職率低下やチームの信頼向上につながる
- 互いの理解が深まり、人間関係の質が向上する
デメリット
- 初期段階では業務負担の偏りが発生しやすい
- 周囲のサポート疲労が顕在化しやすい
理解を深めることは、感情的な反発を減らす第一歩です。ここからは、実際にどんな関わり方が有効なのか見ていきます。
周囲が消耗しない関わり方を身につける
「優しくしなければ」と思いすぎて、自分が疲弊してしまうのは本末転倒です。周囲が疲れない関わり方には、距離感の調整と役割の明確化が欠かせません。
無理に励まさない、過度に同情しない
うつ病の同僚に対して「頑張って」「元気出して」という言葉は逆効果になることがあります。精神医学の専門家によると、うつ状態ではポジティブな言葉もプレッシャーとして感じやすく、自己否定感を強めてしまう可能性があるそうです。
その代わりに、次のようなニュートラルな言葉が有効です。
- 「今日はどのくらいできそうですか?」
- 「必要があれば手伝いますよ」
- 「無理せず行きましょう」
これらは評価や感情を含まないため、相手の負担を減らしつつ関わることができます。
役割分担の透明化
業務のしわ寄せを防ぐには、チームで役割分担を可視化することが重要です。たとえば、共有スプレッドシートやタスク管理ツールを使い、誰がどの仕事を担当しているかを全員が見える状態にします。これにより、業務量の偏りを早期に発見できます。
実践手順
- 現状の業務量を見える化
タスクや進捗をチーム全員で共有します。 - 負担調整ミーティングを設定
月1回程度、業務配分を見直す時間を確保します。 - 支援役のローテーション
特定の人に負担が集中しないよう、サポート役を交代制にします。
注意点と失敗事例
あるIT企業では、サポート役を固定してしまった結果、その社員が半年後に燃え尽き症候群に。サポートする側のケアや交代制度を怠ると、長期的に組織全体が疲弊します。
しわ寄せや負担感を軽減するための組織的な工夫
個人レベルの工夫だけでは限界があります。組織としての仕組みづくりがないと、しわ寄せや「迷惑感情」は根本的に解消されません。
柔軟な働き方の導入
フレックスタイムやリモートワーク制度は、うつ病の同僚だけでなく、周囲の負担軽減にも効果的です。急な欠勤や通院にも対応しやすくなり、業務の穴を最小限にできます。
外部リソースの活用
業務が逼迫する時期は、短期派遣や業務委託を活用するのも手です。これは一時的なコスト増に見えるかもしれませんが、長期的には社員の離職防止につながり、結果として経済的メリットが大きいです。
海外事例:イギリスの「Wellbeing Manager」
イギリスのある企業では、メンタル不調者とその周囲のサポートを専任で行うWellbeing Managerを配置しています。社員の業務負担と心理的負担の両方をモニタリングし、問題が深刻化する前に調整します。
実践ステップ
- 現状分析
欠勤・休職データ、残業時間、離職率をチェック。 - 制度の設計
柔軟勤務・外部サポート・カウンセリング制度を組み合わせる。 - 周知と教育
管理職やメンバーへのメンタルヘルス研修を実施。 - 定期的な効果測定
制度導入後の業務負担や満足度を評価。
周囲の人が疲弊しないためのセルフケア法
サポートする側が倒れてしまっては本末転倒です。うつ病の同僚に限らず、長期的に人を支える立場にある人は、自分のコンディション管理を最優先にすべきです。
感情の「距離感」を持つ
人の悩みや不調に寄り添うとき、大切なのは「共感」と「同化」を混同しないことです。同化してしまうと、自分も同じように気分が沈み、疲弊します。心理カウンセリングの世界では、これを**エモーショナルバウンダリー(感情の境界線)**と呼びます。
たとえば、同僚の辛さを理解しても、「私まで落ち込む必要はない」と心の中で線引きすること。これは冷たさではなく、自分を守るための方法です。
日常的なストレス解消ルーティンを持つ
- 1日30分のウォーキング
- 趣味や創作活動に没頭する時間
- 寝る前の深呼吸や瞑想
こうした習慣は、自律神経を整え、気持ちをリセットする効果があります。実際、厚生労働省のメンタルヘルス調査でも、日常の軽い運動や趣味の時間が職場ストレス軽減に寄与することが示されています。
「抱え込み過ぎ」を避ける
サポート役になっていると、「自分が頑張らないと」と思いがちです。でも、心理学者の間では、支援者が支援を手放すタイミングを持つことも重要とされています。必要であれば、上司や人事に相談して業務やサポートの負担を調整してもらいましょう。
家族や恋人など職場外での関わりにおける注意点
うつ病の人と関わるのは職場だけとは限りません。恋人、友人、家族など、日常生活でも同じような疲労感を感じるケースがあります。
家族の場合
家族は距離を取りづらいため、**「しわ寄せ」や「限界感」**を抱えやすくなります。特に同居している場合は、自分の生活リズムや感情が相手に大きく影響されることも。
実例として、ある読者から寄せられた体験談では、「朝起きる時間や食事のタイミングがすべて相手に合わせる形になり、数か月で自分の生活が崩れた」とのこと。この場合、家族間でも役割分担や休息時間を意識的に設ける必要があります。
恋人や友人の場合
恋人や友人関係では、義務感よりも感情的な関わりが強くなるため、相手の落ち込みに引きずられやすいです。特に恋人の場合、「支えなければ」という気持ちが強すぎて燃え尽きるパターンが多いです。
海外の研究でも、メンタル不調者と恋愛関係にある人は、一般よりうつ傾向や不安症状の発症率が高まるとされています。だからこそ、互いに負担を分散できるよう、第三者や専門家の介入を早めに検討するべきです。
「迷惑」と感じてしまう心理との向き合い方
職場にうつ病の同僚がいると、「迷惑」という感情を持つ自分を責めてしまう人もいます。でも、この感情は自然なものです。感情を押し殺すより、理解して整理するほうが健全です。
感情の正体を知る
- 業務的負担(残業増加、仕事量の偏り)
- 感情的負担(気遣いや精神的ストレス)
- 将来への不安(この状況が続くのではという心配)
これらが積み重なって「迷惑」という感情に変わります。自分を責めるのではなく、「負担を感じるのは正常な反応」と受け止めましょう。
感情を建設的に変える
心理的アプローチとして有効なのは、感情ラベリングです。これは、感じた感情を言葉にして外に出すことで、感情のコントロールを助ける手法です。
例:「私は、業務量が増えて疲れている」「私は、相手にどう接すればいいか分からず不安だ」
このように言語化すると、感情を問題の原因と切り離して捉えやすくなります。
まとめ
うつ病の同僚や身近な人と関わるとき、周囲が疲れるのは珍しいことではありません。でも、距離感を持つ関わり方や組織的なサポート体制があれば、その負担は大きく減らせます。
- 個人レベルでは、感情の境界線を引く・日常のセルフケアを続ける
- 組織レベルでは、役割分担の明確化や外部リソースの活用
- 職場外でも、休息時間と役割分担を意識する
そして、「迷惑」と感じる気持ちを持つ自分を否定しないこと。感情を整理し、行動に変えることが、周囲が消耗しないための第一歩です。
このテーマは、職場だけでなく家庭や恋愛関係にも関わる深い問題です。今日からできる小さな工夫が、長期的な関係性と自分の健康を守ることにつながります。