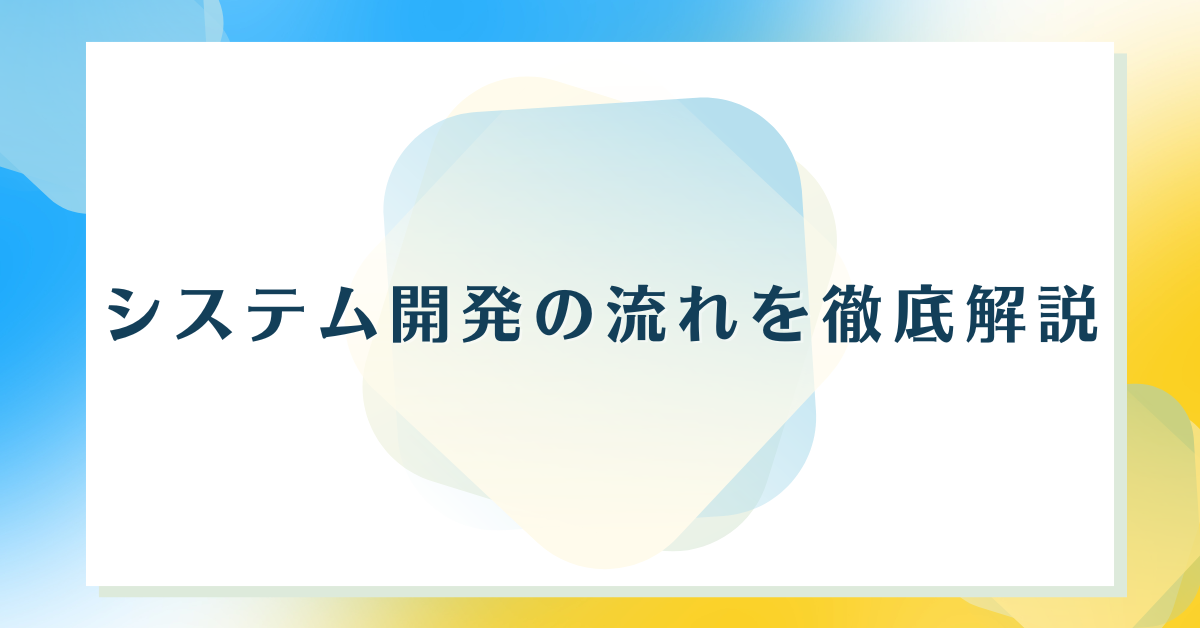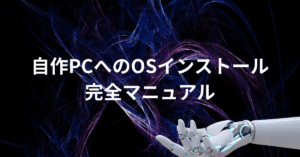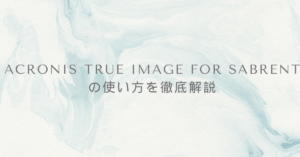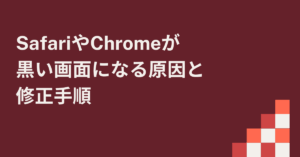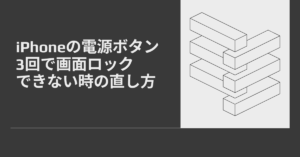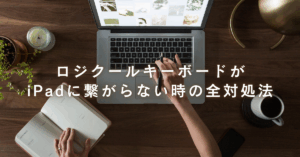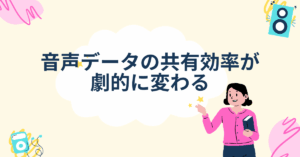新しいシステムを導入するとき、どのような流れで進むのかを理解していないと「何から始めればいいのか分からない」「要件が曖昧で途中でやり直しになった」といったトラブルが起こりがちです。特に業務効率化やIT投資を進める企業では、システム開発の工程を正しく把握することがプロジェクト成功の第一歩になります。本記事では、システム開発の流れを図や具体例を交えてわかりやすく整理し、要件定義からテスト、運用までの工程表を実務で役立つ形で解説します。初心者から実務担当者まで参考になる内容になっていますよ。
システム開発の流れを図で理解する方法
システム開発は複雑に見えますが、全体の流れを図で整理すると一気にイメージがつかみやすくなります。多くの企業で用いられているのは「ウォーターフォールモデル」と呼ばれる進め方で、上から下へ水が流れるように工程が順に進んでいきます。
システム開発 流れ 図の基本
一般的な流れを図にすると以下のようになります。
- 要件定義
- 外部設計
- 内部設計
- 実装(プログラミング)
- テスト
- 運用・保守
この図を頭に入れておくだけで、今自分がどの段階にいて、次に何をすべきかが明確になります。
図解で得られるメリット
例えば営業部門の担当者が「今の開発がどのステップにあるのか分からない」と不安に思うケースは多いです。図で流れを共有することで、非エンジニアのメンバーもプロジェクト全体を理解でき、意思決定のスピードが上がります。実際にITベンダーと発注企業の間で誤解が減り、再作業が少なくなるという効果も期待できます。
システム開発の流れと要件定義の重要性
システム開発で最も重要なフェーズが「要件定義」です。ここをおろそかにすると、後の工程で手戻りが発生し、コストと時間が大幅に膨れ上がってしまいます。
システム開発 流れ 要件定義の内容
- 業務要件:現場の課題や改善したい点を整理する
- 機能要件:システムが備えるべき機能を明文化する
- 非機能要件:セキュリティ、性能、運用体制などを定める
例えば営業支援システムを作る場合、「顧客情報を一元管理したい」「外出先からスマホで参照したい」といったニーズを具体的に言語化します。これを明確にすることで、後の設計やテストもスムーズに進みます。
要件定義で失敗しないコツ
- 現場担当者を巻き込んでヒアリングする
- 曖昧な表現を避け、数値や条件で具体化する
- 必須要件と希望要件を分ける
ある企業では「顧客データを簡単に検索できる」とだけ定義してしまい、開発後に「顧客名だけでなく住所や電話番号でも検索したい」と追加要望が出て大幅な改修が必要になりました。このような事態を避けるためにも、最初の段階で丁寧に要件を固めることが欠かせません。
システム開発 工程 略語を正しく理解する
システム開発の流れを学んでいると、多くの略語が出てきます。エンジニアは日常的に使っていますが、ビジネス担当者にとっては分かりにくい言葉の壁になりがちです。略語を理解することで、会議や資料の内容がスッと頭に入るようになります。
よく使われる略語
- RFP(Request for Proposal):提案依頼書。ベンダーに見積もりや提案を求める際に使う文書。
- WBS(Work Breakdown Structure):作業分解構成図。大きなプロジェクトを細かいタスクに分解して管理する手法。
- SLA(Service Level Agreement):サービス品質保証契約。稼働率や応答時間などを数値で定義する。
- UT(Unit Test):単体テスト。プログラムの最小単位ごとに正しく動くかを確認する。
- IT(Integration Test):結合テスト。複数のモジュールを組み合わせて動作確認を行う。
略語を押さえるメリット
例えば、会議でエンジニアが「このフェーズはUTが終わって次はITに進みます」と言ったときに意味が分からないと置いていかれてしまいますよね。略語の意味を知っているだけで議論に参加しやすくなり、コミュニケーションの齟齬が減ります。プロジェクト進行のスピードにも直結する大事なポイントです。
システム開発 工程表を活用する方法
システム開発の進行管理には「工程表」が欠かせません。工程表とは、プロジェクトの各ステップをスケジュールに沿って整理した表のことです。
工程表の基本構成
- フェーズ(要件定義、設計、実装、テストなど)
- タスク(各フェーズで実行する作業)
- 担当者
- 期間と期限
工程表の効果
例えば、工程表がない状態で進めると「誰がいつまでに何をやるのか」が不明確になり、遅延や責任の所在不明が発生します。逆に工程表を作成すると、全員が同じスケジュール感を共有でき、遅れが出た時にすぐに調整できます。プロジェクトマネージャーだけでなく、現場メンバーにとっても安心材料となります。
システム開発 工程 ipaが示す標準モデル
IPA(情報処理推進機構)は日本のIT標準を策定している公的機関です。システム開発のプロセスにおいても、IPAが推奨する標準モデルを知っておくと安心です。
IPAが示す工程モデル
- 企画
- 要件定義
- 外部設計
- 内部設計
- プログラミング
- テスト(単体、結合、システム)
- 運用・保守
実務での活用
IPAモデルを基準にすれば、ベンダーや発注側で「工程の呼び方が違う」といった混乱を防げます。特に公共系システムの入札では、IPA準拠で工程を説明することが求められるケースもあるため、標準を理解しておくことは実務的にも重要です。
開発プロセス 具体例で学ぶ進め方
理論だけではイメージがつかみにくいので、具体例を見てみましょう。ここでは営業管理システムを開発するケースを考えます。
具体的な進め方
- 要件定義:営業担当にヒアリングし「顧客情報を一元化」「訪問履歴をモバイルで入力」などを決定
- 設計:画面のレイアウトやデータベース設計を行う
- 実装:プログラマーがシステムを構築
- テスト:顧客登録から検索、レポート出力まで動作確認
- 運用:リリース後に不具合対応や改善を行う
学びのポイント
実際の業務をベースに具体的に落とし込むと「なぜ要件定義が大事なのか」「テストで何を確認するのか」が理解しやすくなります。特にユーザー部門を巻き込んでプロセスを進めると、現場に根ざしたシステムが完成します。
開発プロセスを図で整理するメリット
文章だけでは分かりにくい工程も、図で表現すると一目で理解できます。開発プロセスを図にまとめることで、関係者全員が同じイメージを共有できます。
図の活用シーン
- プロジェクトのキックオフで全体像を説明するとき
- ベンダーと進行状況を確認するとき
- 経営層に報告するとき
例えば「要件定義→設計→開発→テスト→運用」という流れを矢印付きで図示するだけで、専門外の人もスッと理解できます。これが結果的に意思決定のスピードを高め、無駄な説明コストを削減してくれるのです。
開発工程とは何かを整理する
最後に「開発工程とは」という問いに立ち返りましょう。開発工程とは、システムを作るために必要な一連の作業プロセスのことを指します。工程ごとに役割や成果物が異なり、それらが積み重なって最終的なシステムが完成します。
開発工程の本質
- 計画的に順序立てて進めることで品質を担保する
- 工程を分けることで担当の役割を明確化する
- 手戻りを減らし、コストや納期をコントロールする
工程を単なる「ステップ」と捉えるのではなく「品質と効率を守る仕組み」と理解すると、システム開発の全体像がよりクリアに見えてきます。
まとめ
システム開発の流れは、要件定義から始まり設計、実装、テスト、運用へと進みます。工程表や図を使って整理することで、関係者全員が同じイメージを共有でき、プロジェクトの成功率が高まります。
- 要件定義を丁寧に行うことが成功の鍵
- 略語やIPA標準を理解して共通認識を持つ
- 工程表や図を活用して進行管理を見える化する
- 具体例を踏まえて実務に落とし込む
システム開発は一見難しそうに思えますが、流れを理解し工程を意識することでぐっと身近になります。この記事を参考に、自社のプロジェクトに活かし、失敗しないシステム導入を目指してください。