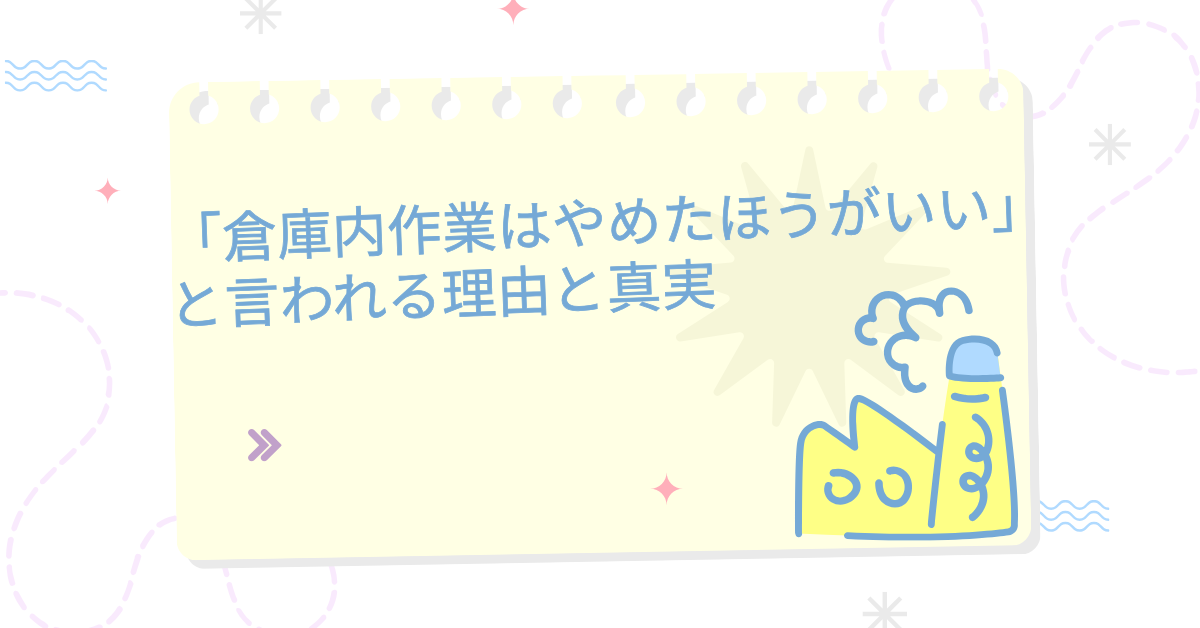倉庫内作業は、求人の数こそ多いものの「やめたほうがいい」「きつい」「続かない」といった言葉がネット上で数多く見られます。実際、倉庫で働いた経験を持つ人のなかには、体力的・精神的な負担から短期間で退職するケースも少なくありません。しかし、すべての倉庫仕事が悪いわけではなく、“合う人・環境”を見極めることで安定した働き方を実現している人もいます。
この記事では、倉庫内作業の離職率が高い理由と続けられる人の特徴、働きやすい職場の見極め方を、ビジネス視点・現場視点の両面から詳しく解説します。今の職場を辞めるべきか、続けるべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
倉庫内作業が「やめたほうがいい」と言われる主な理由
倉庫内作業が敬遠される背景には、仕事内容・人間関係・将来性の3つの問題があります。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
倉庫内作業がきついと言われる理由
倉庫内作業は「軽作業」と書かれている求人が多いですが、実際には体を使う仕事が多く、想像以上にハードです。
特にピッキング(商品の取り出し)や仕分け、梱包作業では以下のような負担があります。
- 長時間立ちっぱなしで腰や膝を痛めやすい
- 大きな段ボールを何十箱も運ぶことがある
- 夏は高温多湿、冬は寒い倉庫環境での作業
- 1分単位で作業ノルマが設定されることも
このような作業環境では、体力がない人や集中力が続かない人にとって「きつい」「もう無理」と感じるのも自然です。
しかし、倉庫によっては作業の自動化や冷暖房の導入など、働きやすさを改善している企業も増えています。
“やめたほうがいい”と言われる倉庫は、そうした環境改善が進んでいない古い職場に多い傾向があります。
倉庫作業に向いてない人の特徴
「倉庫 作業 向いて ない人」には、ある共通点があります。
- 同じ作業を繰り返すのが苦手な人
単純作業が多いため、変化や刺激を求める人には退屈に感じられます。 - 時間管理が苦手な人
出荷スケジュールに合わせて作業スピードが求められるため、のんびり屋の人はストレスを感じやすいです。 - チームワークよりも個人主義の人
倉庫内はチームで作業を進めるため、協調性や連携が不可欠です。
一方で、「決められた作業をコツコツこなすのが得意」「時間を守るのが得意」という人には向いています。
つまり、“倉庫仕事そのもの”が悪いのではなく、性格との相性が大きなポイントになるのです。
パワハラや人間関係が原因で辞めるケースも
「倉庫内 作業 パワハラ」という検索が多いのは、現場の人間関係が閉鎖的になりやすいからです。
少人数の職場では、上司やリーダーの性格が職場の雰囲気を左右します。
指導が厳しい人や怒鳴るタイプの管理者がいると、短期間で辞めてしまう人が続出します。
ただし、これは全ての倉庫に当てはまりません。
最近は「パワハラ防止法」により、管理職向けのハラスメント研修を行う企業も増えています。
人間関係の良し悪しは入社前には見えにくいため、口コミサイトや派遣会社の担当者への事前確認が非常に重要です。
倉庫内作業で辞める人が多い理由と離職率の現実
倉庫業界は慢性的な人手不足です。求人が多い一方で、「倉庫 辞める人が多い」と言われるほど離職率も高いのが現実です。
では、なぜ続かないのでしょうか。
入社前のイメージと現実のギャップ
求人では「未経験歓迎」「簡単な軽作業」と書かれていますが、実際にはスピードと正確さが求められる“重労働”です。
このギャップに驚いて辞めてしまうケースが圧倒的に多いです。
とくに、未経験で入った正社員が「正直バイトのほうが楽だった」と感じるほど、責任やノルマが重くなる現場もあります。
「倉庫内作業 正社員 きつい」という声の多くは、
- 生産性を数値で管理されるプレッシャー
- 部下をまとめる責任
- 現場作業+書類処理の二重負担
といった理由が背景にあります。
給与と労働負担のバランスが取れていない
倉庫の平均時給は1,100〜1,300円程度。重い荷物を扱う割には給料が低いという不満を持つ人が多いです。
とくに地方倉庫では、時給が1,000円を下回ることもあります。
「きついのに給料が安い」と感じれば、長く続けるモチベーションを維持するのは難しいでしょう。
一方で、フォークリフト免許を取得して昇給したり、ライン管理者になったりすることで年収を上げている人もいます。
“単純作業で終わらせるか、スキルを磨くか”が、倉庫仕事を「やめたい仕事」にするか「安定した仕事」にするかを分ける境目です。
倉庫は「底辺だらけ」と言われる背景
SNSで見かける「倉庫 底辺だらけ」という言葉には、少なからず誤解があります。
たしかに、学歴や経験を問わない仕事が多く、非正規雇用が中心という現状はあります。
ですが、それは「誰でも働ける門戸が広い」という意味でもあり、社会に不可欠な存在でもあります。
物流が止まれば、通販も流通も成立しません。
この業界を支えるのが倉庫作業員であり、AIやロボットでも完全に代替できない仕事です。
むしろ今後は、倉庫DX(自動化・在庫管理システム導入)によって、現場経験者のキャリア価値が上がる可能性もあります。
倉庫内作業を女性が選ぶときの注意点と働きやすい職場の見極め方
倉庫仕事は男性が多いイメージですが、近年は女性の割合も増えています。
特に「倉庫内作業 女性歓迎」や「軽作業スタッフ募集」といった求人は年々増加中です。
しかし、女性が働く場合には設備・作業内容・雰囲気など、チェックすべきポイントがあります。
女性が働きづらいと感じる理由
女性スタッフの口コミでは、次のような悩みがよく見られます。
- トイレや更衣室が少なく、使いづらい
- 力仕事を頼まれることがある
- 休憩スペースで気を使う
- 冷えやすく、体調を崩しやすい
とくに冷凍倉庫や長時間立ち仕事の職場では、体調面の負担が大きいです。
女性が働きやすい職場を選ぶには、空調・休憩環境・作業分担のバランスが整っているかを確認しましょう。
女性に向いている倉庫業務の種類
女性が多く活躍しているのは、以下のような軽作業です。
- 化粧品・雑貨・食品の検品・梱包
- アパレル商品のタグ付けや包装
- ネット通販商品のピッキング
これらの作業は比較的軽く、空調の整ったクリーンな倉庫で行われることが多いです。
また、パートや派遣など柔軟なシフト制で働けるため、子育て世代にも人気があります。
女性が長く続けるための工夫
- 靴選びを重視する:クッション性の高いスニーカーで足腰の負担を軽減
- 防寒対策を徹底する:冷えやすい現場では重ね着やカイロを活用
- 同僚と情報交換する:職場内の悩みは同僚と共有することでストレスを減らせる
こうした工夫を取り入れることで、体力や環境の不安をかなり軽減できます。
倉庫内作業を正社員で続けるためのキャリア戦略
倉庫内作業はアルバイトや派遣の印象が強いですが、正社員として長期的に働く人も多くいます。
ただし、「倉庫内作業 正社員 きつい」という声にあるように、責任や負担が大きいのも事実です。
正社員が抱える課題
- 生産性の数値管理プレッシャーが強い
- 残業が多く、休日出勤が発生しやすい
- 現場作業と管理業務の両立が難しい
しかし、これらを乗り越えると管理職・物流マネージャー・品質管理担当など、キャリアの幅が広がります。
倉庫業界では「現場経験のある管理者」は非常に重宝されます。
スキルを積むことで、年収400万円以上のポジションに昇進するケースもあります。
キャリアを伸ばすためにできること
- フォークリフト免許を取得する
現場作業の幅が広がり、時給・月給ともに上がる傾向にあります。 - 在庫管理システム(WMS)の操作を覚える
デジタル管理の知識は昇進の近道になります。 - 物流資格(物流管理士など)を目指す
倉庫から物流全体を見渡す力を身につけることで、転職にも有利になります。
倉庫業界の今後と働き方の変化
倉庫業界は「人が辞める職場」というイメージから脱却しつつあります。
AI・ロボティクスの導入が進み、人が行う作業は「品質管理・判断業務」へと変化しています。
また、在宅勤務が難しい業界だからこそ、安定した需要がある職種とも言えます。
企業によっては、データ分析をもとに作業効率を改善する“物流コンサル職”へのキャリア転換を支援する動きもあります。
つまり、現場での経験を積むことが、将来の“マネジメント職”や“DX推進人材”への第一歩になるのです。
まとめ:やめたほうがいいのは「環境選びを誤ったとき」だけ
倉庫内作業が「やめたほうがいい」と言われるのは、仕事自体ではなく、“職場環境との相性”が原因です。
体力・人間関係・温度・給与条件——これらが合わなければ、どんな仕事も続けるのは難しいものです。
しかし、正しい職場を選び、スキルを身につければ、倉庫の仕事は安定した収入と経験をもたらしてくれます。
最後に大切なのは次の3点です。
- 仕事内容より「環境の質」を見て選ぶ
- 単発ではなく“将来性”を意識して働く
- 自分の強み(正確さ・忍耐力・協調性)を活かす
「やめたほうがいい」と言われる職場の多くは、“準備不足で選ばれた現場”です。
倉庫業界そのものを否定するのではなく、“自分に合った働き方”を見つけることこそが、長く続けるための最善策ですよ。