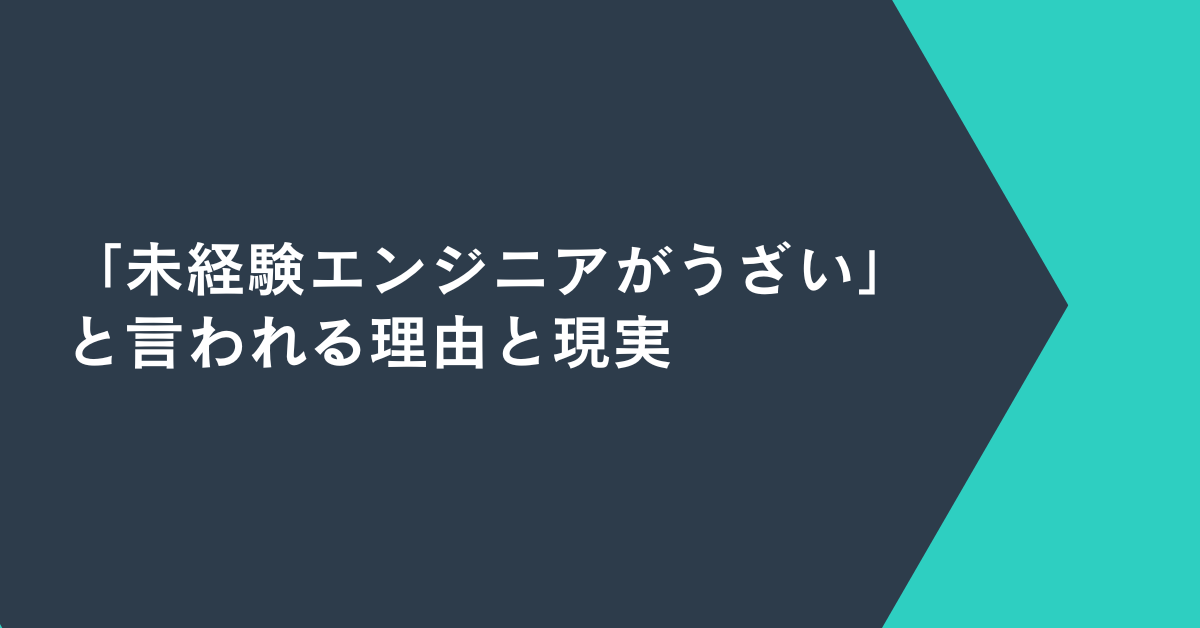「未経験からエンジニアになりたい」と思う人が増えています。SNSを見ても「スクールに通えば転職できた」「在宅で年収600万」など、キラキラした情報があふれていますよね。
しかし同時に、ネット上ではこんな言葉も聞こえてきます。「未経験エンジニアはうざい」「現場の足を引っ張る」「もう飽和してる」。せっかく夢を持って挑戦しているのに、なぜそんな否定的な声が出てしまうのでしょうか。
この記事では、なぜ未経験エンジニアが“うざい”と思われてしまうのか、そしてどうすれば現場で信頼される存在になれるのかを、現場目線・人間関係・キャリア心理の3方向から徹底解説します。
実際に未経験からエンジニアになった人の“リアルな失敗談と成功例”も交えながら、「現場で浮かない生き方」を具体的に紹介します。
未経験エンジニアが増えすぎた背景と現場の変化
まず知っておきたいのは、「未経験エンジニアが増えた」のは一時的なブームではなく、社会全体の構造変化による必然だということです。
プログラミングスクールの量産と「誰でもエンジニアになれる」空気感
2019年以降、プログラミングスクールやオンライン学習サイトが爆発的に増えました。
「たった3ヶ月でエンジニア転職!」「未経験から在宅フリーランスに!」という広告を一度は見たことがあるはずです。
スクール自体は悪ではありません。
ただ、「3ヶ月で誰でもエンジニアになれる」という誇張されたメッセージが独り歩きし、“努力すればなんとかなる”という幻想だけが転職希望者の頭に残ってしまったのです。
現場に入ったときに、そのギャップが一気に露呈します。
「学んだことがほとんど通用しない」「バグが出ても原因がわからない」「上司が冷たい」と感じる人が多いのも、この背景があるからです。
エンジニア不足という「入口の広さ」が生んだひずみ
企業側にも事情があります。慢性的なIT人材不足により、「未経験可」「ポテンシャル採用」という門戸を広げざるを得ません。
しかし本音では「即戦力が欲しい」というのが現場の声。
採用担当は「未経験OK」と言う一方で、現場リーダーは「教育の余裕がない」と悩んでいます。
この矛盾が、現場の摩擦の根本原因です。
「未経験エンジニアがうざい」という言葉の裏には、教える側の疲労と不満が積み重なっているのです。
なぜ「未経験エンジニアはうざい」と言われるのか?現場の本音
ここでは、実際に現場で未経験エンジニアが“煙たがられる”理由を、人間関係・姿勢・スキル面から掘り下げます。
これは批判ではなく、“信頼されるエンジニアになるためのヒント”でもあります。
1. 「教えてもらって当然」という姿勢が透けて見える
ベテランエンジニアが最もストレスを感じるのが、「調べずにすぐ聞く」タイプです。
ある企業のチームリーダーはこう話します。
「“ググってもわからなかった”って言うけど、そもそも検索ワードがズレてる。
自分で考えようとしてないのが伝わるんです。」
この「受け身の姿勢」は、どんなに明るくても好印象にはなりません。
エンジニアは“自走力”が命。つまり「自分で調べ、仮説を立てて、失敗しながら学ぶ力」です。
この力を身につけていない人ほど、現場で孤立しやすくなります。
2. 「勉強してるアピール」が空回りする
SNSや社内チャットで「昨日もUdemyで勉強しました!」という投稿をよく見かけます。
しかし、それが現場の問題解決と直結していないと、「意識高いだけ」「うざい」と感じられてしまうことも。
たとえばReactを学んでいるのに、今の現場はLaravelの保守。
「それ今じゃなくない?」と思われるケースです。
「勉強しているか」よりも、「現場の課題を理解しようとしているか」が信頼されるポイントです。
3. 理想だけ語って、地道な作業を避ける
「設計をやりたい」「AI開発に携わりたい」。
こうした希望を持つのは素晴らしいことです。
しかし入社直後の現場で任されるのは、テスト・デバッグ・既存コードの修正など、いわば地味な仕事。
ここで「思っていたのと違う」と態度に出すと、一気に“うざい”認定されます。
実際にはこの下積み期間こそ、コードの癖や開発プロセスを体で覚える大事なフェーズです。
ベテランの多くも、この泥臭い時期を乗り越えて今があります。
「未経験エンジニアの闇」と呼ばれる現実的な問題点
SNS上で「未経験エンジニアの闇」と呼ばれる投稿は多くあります。
その内容を冷静に整理すると、次のような構造的問題が見えてきます。
スクール卒業=即就職ではない
プログラミングスクールを出た人の中には、転職エージェントのサポートが終わった途端、求人が見つからず数ヶ月が経つ人もいます。
「未経験OK」と書いてあっても、実際には「1年以上の実務経験が望ましい」と条件がついていることも多いです。
つまり、「入り口が広そうに見えて、実際には狭い」。これが闇の正体です。
低単価・客先常駐の現実
「エンジニアになれた!」と喜んでも、最初の職場がSES(客先常駐)で、派遣のように各プロジェクトを転々とするケースも多いです。
しかもスキルアップにつながらず、給料も安定しない。
結果、「夢見ていた年収とはほど遠い」と気づき、早期退職してしまう人も。
「フリーランスになれば自由」という幻想
未経験者の中には、「数年経験を積めばフリーランスになって在宅で稼げる」と考える人もいます。
しかし現実には、フリーランスは営業・見積・契約・確定申告すべて自分で行うため、スキル+ビジネス力+人脈が求められます。
スキルが浅いまま独立しても、継続案件が取れず苦しむ人が多いのが実情です。
「未経験エンジニアいらない」と言われる裏側の本音
ネットで「未経験エンジニアいらない」と検索すると、辛辣なコメントが並びます。
しかしこの言葉の裏には、「教育リソースが足りない」「評価制度が追いついていない」といった現場の構造的課題があります。
教える側の疲弊
エンジニアは納期に追われています。1日のタスクが分単位で埋まる中、未経験者の質問対応を何度も行うのは想像以上に大変。
「教えたいけど、時間がない」が本音なのです。
その結果、冷たく見えてしまう態度や、「もう自分でやって」と突き放す発言につながります。
評価制度が「スキル偏重」
多くの企業では、“成果主義”が採用されています。
そのため、努力しても成果が数値に出ない未経験者は評価されにくい。
「頑張っているけど給料が上がらない」「意見が通らない」と感じてしまう構造です。
これは人間関係の摩擦だけでなく、組織的な課題でもあります。
未経験からでも信頼されるエンジニアになるための思考法
ここからは、「未経験なのに評価される人」が実際にやっていることを紹介します。
難しい技術論よりも、“人として信頼される行動”がカギになります。
1. わからないことを「整理して聞く」
「○○がわかりません」ではなく、「AとBを試しましたが、Cの動きが理解できません」と伝える。
これだけで“自分で考えている”と伝わります。
質問の仕方一つで印象は180度変わります。
2. エラーを恐れず、自分の仮説を試す
未経験者はエラーを見ると焦ってしまいがちですが、実はエラーは“次のステップを示すサイン”です。
「この原因を探る力」こそが、経験者との差を埋める最短ルートです。
一つのバグを3時間かけて直した経験は、どんな教材にも勝ります。
3. 技術だけでなく「人の信頼」を積む
現場では、スキルよりも「一緒に働きやすいか」が重視されます。
報告・連絡・相談を丁寧に行う人は、自然と周囲に信頼され、案件の中心に呼ばれるようになります。
“人に迷惑をかけない”ではなく、“人の手を借りやすい関係をつくる”ことが、長く生き残る鍵です。
未経験エンジニアの年収とキャリアの伸ばし方
「未経験から年収を上げたい」と考えるなら、**“技術×業務理解”**のバランスを意識することが大切です。
最初の年収は低くても焦らない
未経験の初任給は平均300〜350万円程度。しかし、実力がつけば急激に伸びます。
たとえば、入社3年目で年収500万を超える人も珍しくありません。
大切なのは「安定して学び続けること」。
3年後、同じ現場で信頼を得ていれば、フリーランスとして月単価70〜90万円の案件を取ることも可能です。
技術だけでなく「業界知識」を持つ
システム開発では「何を作るか」が明確な業務知識が必要です。
物流・金融・医療など、業界の構造を理解しているエンジニアは重宝されます。
つまり、「技術者でありながらビジネスを理解する人」が、真の強者です。
まとめ|“未経験エンジニアがうざい”と言われない人になるには
「未経験エンジニアがうざい」と言われるのは、知識不足よりも姿勢の問題です。
現場が求めているのは、スキルよりも「自分で考えて動ける人」「チームで成果を出せる人」です。
最後に、今日からできる3つの行動を挙げます。
- わからないことは「調べた上で質問する」
- 自分の成長を“他人に依存しない”
- 感謝と謙虚さを忘れない
これだけで、周囲の評価は確実に変わります。
未経験という肩書きは、数年後には消えます。
残るのは、「一緒に仕事をしたいと思われる人間力」です。
その力を磨く人こそ、エンジニアの世界で長く生き残れるのです。