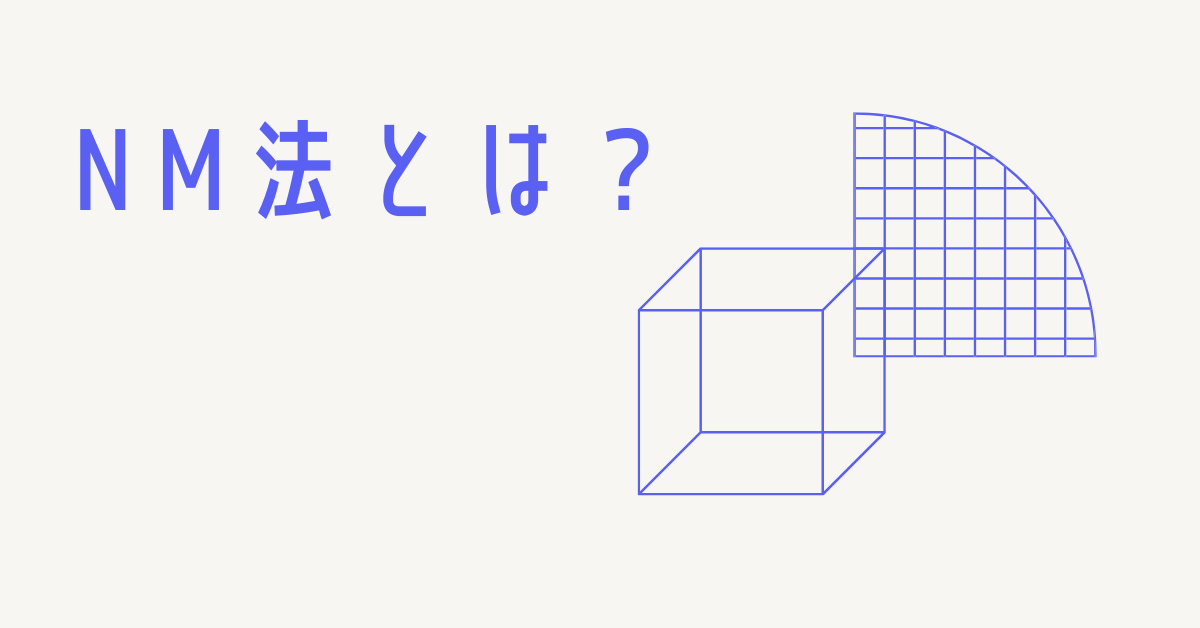会議で「アイデアが出ない」「同じ発想に戻ってしまう」と感じたことはありませんか?
そんなときに役立つのが、NM法という創造的発想技法です。ブレーンストーミングをさらに進化させた手法で、個人でもチームでも使える「思考をズラす」方法論として知られています。この記事では、NM法の意味や略語の由来、具体的なやり方、ゴードン法・シネクティクス法・類比法との違い、そして実際の事例までをわかりやすく解説します。今日から“発想の壁”を打ち破るヒントが見つかりますよ。
NM法とは?意味と由来をわかりやすく解説
NM法とは、「New Method(ニュー・メソッド)」の略で、日本で開発された独自のアイデア発想法です。もともとはブレーンストーミングの弱点を補うために考案されたもので、単なる「数を出す」発想ではなく、「既存の枠組みを意図的にずらす」ことで新しい視点を得ることを目的としています。
NM法は何の略か
前述の通り、「N」は「New(新しい)」、「M」は「Method(方法)」の略です。つまり「新しい方法=NM法」。アイデア創出の既存枠を超えることを意図したネーミングです。1960年代以降、日本企業の製品開発や企画分野で使われるようになりました。特に電機メーカーや広告代理店では「NM法で考えよう」というフレーズが当たり前のように使われていた時期もあります。
ブレーンストーミングとの違い
ブレーンストーミングは複数人で自由に意見を出し合う手法ですが、発言者の思考パターンに引きずられたり、発想が同じ方向に偏る傾向があります。NM法は、意図的に「無関係なテーマ」や「異なる視点」を持ち込み、脳を再活性化させるのが特徴です。そのため、同じテーマでも“異なる切り口”のアイデアが出やすくなります。
NM法が注目される理由
近年では、デザイン思考やAI支援によるアイデア生成など、多様な発想法が注目されていますが、NM法の強みは「人間の経験と思考を活かした創造性」にあります。特に、既存製品の改良や広告キャンペーンのアイデア出しなど、制約の中で新しさを出す現場では、ブレーンストーミングよりも現実的かつ創造的な手法として評価されています。
NM法の基本手順と進め方を実例で理解する
NM法の進め方は一見シンプルですが、コツを押さえると発想の質が劇的に変わります。ここでは、代表的な手順と実際の例を紹介します。
NM法の基本プロセス
NM法は大きく5つのステップで進めます。
- テーマ設定
課題を一文で明確にします。例:「新しいカフェの集客方法を考える」 - 関連要素の分解
テーマを構成する要素を洗い出します。上記の場合は「商品」「空間」「接客」「価格」「場所」「時間」など。 - 無関係な要素を取り込む
関係のない言葉や概念を持ち込みます。新聞の見出しや辞書、雑誌、写真などをランダムに選び、要素と組み合わせて考えます。 - 結合・転換を考える
無関係な要素から連想を広げ、「もし○○と組み合わせたら?」と考えます。 - アイデアの整理と実用化
出てきた発想を評価軸(実現性・独自性・効果など)で整理し、実際の企画案に落とし込みます。
NM法の例(カフェ企画の場合)
テーマ:「平日の昼間に若者を集客する方法」
- 無関係な要素:「図書館」「祭り」「SNSのライブ配信」
- 組み合わせ発想:「図書館×カフェ=静かに勉強できるコーヒースポット」
- 具体化:「“Study Latte”という勉強向けカフェタイムを導入」
このように、NM法は論理的な分析ではなく“飛躍”を促す発想を重視します。
NM/T法との違い
派生形として「NM/T法」も存在します。こちらは「NM法+テーマ変換(Theme Transformation)」の略で、テーマ自体を置き換えながら発想を進める方法です。たとえば「販売促進を考える」を「買いたくなる体験を作る」と言い換えることで、思考の範囲が一気に広がります。
ゴードン法とNM法の違いを理解し使い分ける
NM法と並んで知られる発想技法に「ゴードン法(Gordon Method)」があります。両者は一見似ていますが、発想のアプローチと心理的効果が異なります。
ゴードン法とは
ゴードン法は、アメリカの心理学者ウィリアム・ゴードンが提唱した発想法で、グループメンバーに課題の「本当のテーマ」を最初は知らせない状態でアイデアを出してもらう手法です。
目的は、固定観念や先入観を排除し、自由な連想を引き出すこと。ファシリテーターだけが本当のテーマを知り、メンバーは抽象的なヒントをもとに発想を進めます。
ゴードン法の例
たとえばテーマが「家庭用掃除機の新デザイン」だった場合、参加者には「“吸う”という行為をどう進化させられるか」とだけ伝えます。そこから「空気を浄化する」「吸わない掃除」「自動で動く」などの多様なアイデアが出るのです。
最終的にファシリテーターが本来のテーマを明かし、抽出したアイデアを再構築します。
NM法との違い
- ゴードン法:無意識的に発想の制約を外す「心理的アプローチ」
- NM法:意識的に異なる要素を結びつける「構造的アプローチ」
つまり、ゴードン法は“知らずに自由に考える”方法であり、NM法は“知ったうえで自由に結合する”方法です。NM法の方がビジネス現場で再現性が高く、個人作業にも向いています。
シネクティクス法との関係と違いを整理する
NM法のルーツをたどると、もう一つの重要な発想法「シネクティクス法(Synectics)」に行きつきます。これはアメリカのW.J.J.ゴードンとG.プリンスが開発した技法で、「異質なものを結びつけて新しい概念を生む」ことを目的としています。
シネクティクス法の特徴
シネクティクス(Synectics)は、ギリシャ語で「異なるものを結びつける」という意味です。主に以下の4つの類比(アナロジー)を使って発想を広げます。
- 直接類比:他分野の事例からヒントを得る
- 個人的類比:自分が対象物になったつもりで考える
- 象徴的類比:比喩やイメージを使って連想する
- 空想的類比:現実にない理想状態を思い描く
たとえば「快適な通勤」をテーマにした場合、直接類比では「水が流れるような動線」、個人的類比では「自分が風になったつもりで通勤する」、象徴的類比では「通勤=旅立ち」、空想的類比では「テレポートする出勤」などの発想が出ます。
NM法との関係
NM法も「異質な要素を結びつける」という点ではシネクティクス法の考え方を取り入れていますが、NM法はより実務的で簡潔です。
- シネクティクス法:心理的・哲学的アプローチ(発想訓練として強い)
- NM法:実務的・構造的アプローチ(会議や企画現場で使いやすい)
つまり、NM法は「ビジネスで使えるよう最適化されたシネクティクス法」と言っても過言ではありません。
類比法・チェックリスト法との組み合わせで発想を拡張する
NM法は単体でも効果的ですが、他の創造技法と組み合わせることで、さらに発想の幅を広げられます。特に相性が良いのが「類比法」と「チェックリスト法」です。
類比法との併用
類比法(アナロジー法)は、「似ている構造」や「異分野の共通点」から発想を得る方法です。たとえば「新しい交通システムを考える」という課題で、「血液の流れ」「データ通信」「水道管」などを参考にすると、効率的なルート設計やネットワーク化のヒントが得られます。
NM法で無関係な要素を取り込み、その後に類比法で関連性を整理するという順番で使うと、思考の飛躍と構造化の両立が可能になります。
チェックリスト法との併用
チェックリスト法は、既存のアイデアをさまざまな視点から見直す手法です。代表的な項目には「転用できないか」「拡大・縮小できないか」「順序を変えられないか」などがあります。
NM法で生まれた発想をチェックリストで検証することで、実現可能性が高まり、実際の提案や企画書に落とし込みやすくなります。
NM法を会議やチームで活かす実践ステップ
- テーマを1文で共有する
- 全員で要素を洗い出す(5分)
- ランダムな刺激語を出す(カード・新聞など)
- 結合して連想を書く(各自5案以上)
- 共有→深掘り→実用化へ絞り込み
ポイントは、「正解を探さないこと」と「異質な意見を歓迎すること」です。NM法は“違和感を出す”ことが成功のサインです。
NM法が活用されている企業・分野の事例
- 製品開発:家電メーカーが既存機能に“異業種の発想”を加える際に使用
- 広告業界:キャッチコピーやコンセプト作成時のブレスト補助
- 教育現場:中学・高校の授業でも創造教育として導入
- デザイン思考との融合:ワークショップでの発想ステップに活用
NM法を使いこなすための3つのコツ
- “無関係”を恐れない
異質な要素ほど新しさを生みます。 - 時間を区切る
制限時間がある方が集中力と自由度が上がります。 - 否定しない場をつくる
最初から評価せず、すべてのアイデアを一度受け止めるのが鉄則です。
まとめ|NM法は「ズラして考える力」を鍛える実践的発想法
NM法は、「New Method=新しい考え方を生み出す方法」として、ブレストの限界を超える創造技法です。ゴードン法やシネクティクス法のように心理的要素を取り入れながらも、現場で使いやすく構造化されているのが魅力です。
発想が煮詰まったときこそ、無関係なものを掛け合わせるNM法を試してみてください。ビジネス会議でも、個人のアイデア整理でも、「思考の壁」を破るきっかけになりますよ。