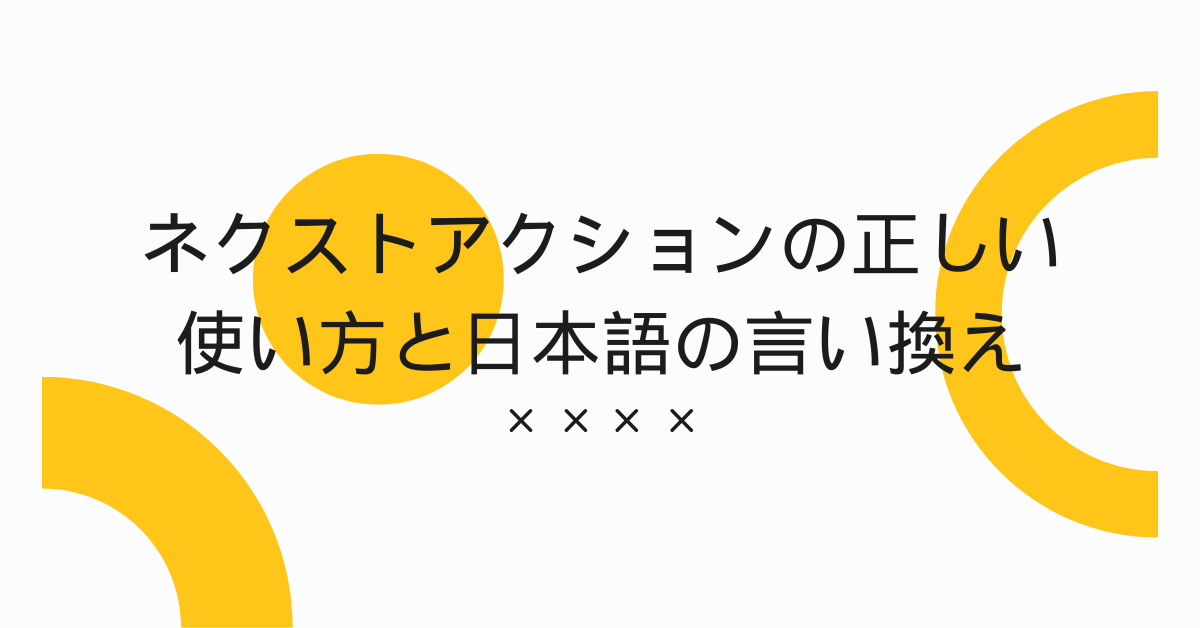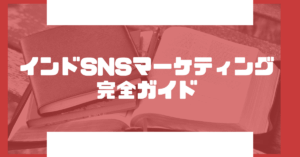ビジネスの現場で「ネクストアクションを共有してください」「次のNA(ネクストアクション)を設定しましょう」といった表現を耳にしたことはありませんか?
一見すると外資的で格好いい言葉ですが、正しく使いこなせている人は意外と少ないです。
この記事では、「ネクストアクション」と「ToDo(やるべきこと)」の違い、日本語での自然な言い換え方、そしてビジネスで活かせる使い方を実践的に解説します。
読後には、あなたの会議・報告・タスク管理の精度が確実に上がりますよ。
ネクストアクションとは何かを理解する
ネクストアクションの意味と由来
「ネクストアクション(Next Action)」とは、直訳すると「次の行動」です。
ビジネスシーンでは、今後具体的に何をするかを明確にする行動項目を指します。
特に、会議やプロジェクト進行中に「次に誰が、いつまでに、何をするのか」を共有するときに使われます。
たとえば商談の打ち合わせ後に「ネクストアクションは、提案資料を金曜までに送付」と言えば、次の動きが誰の頭の中にも明確になります。
つまり「ネクストアクション」とは、**会議で終わらせないための“実行の橋渡し”**なのです。
ネクストアクションがビジネスで重要な理由
ビジネスの現場では、「いい会議だったね」で終わる打ち合わせほど非効率なものはありません。
重要なのは、話し合いの結果を“行動”に変えること。
ネクストアクションが設定されていないと、進捗が止まり、責任の所在も曖昧になります。
反対に、明確なネクストアクションがあれば次のようなメリットがあります。
- チームの動きが整理され、無駄な確認が減る
- 各自の役割と期限が明確になる
- プロジェクトの停滞リスクを防げる
- 会議や商談の成果が“結果”として残る
つまり、ネクストアクションとは単なるタスクではなく、**次の一手を具体化する“進行の指針”**なのです。
ネクストアクションとToDoの違いを明確にする
ToDoは「やること」、ネクストアクションは「動き出す一歩」
「ToDo」と「ネクストアクション」は似ているようで本質が異なります。
ToDoは「やるべきこと」の一覧であり、計画全体を俯瞰するリストです。
一方、ネクストアクションはその中の**“今すぐ取りかかれる行動”**を指します。
たとえば次のように考えると違いが明確です。
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ToDo | 新製品のキャンペーン企画を立てる | ゴールを示す項目(抽象的) |
| ネクストアクション | 広告代理店に打ち合わせ依頼のメールを送る | 実行に直結する行動(具体的) |
ToDoが“計画の箱”だとすれば、ネクストアクションはその“最初のスイッチ”です。
つまり、「やることリストを動かすための具体的アクション」がネクストアクションなのです。
ネクストアクションを明確にする3つの質問
会議やタスク整理の際、「これからどうすればいい?」と迷う場面がありますよね。
そんな時は次の3つの質問を自分に投げかけてみましょう。
- 誰が実行するのか?(担当者を明確にする)
- いつまでに完了させるのか?(期限を設定する)
- 何を具体的に行うのか?(行動を分解する)
これに答えられれば、すでにネクストアクションが定義されています。
反対に、誰が・いつ・何をが曖昧なままでは、ToDoのまま止まってしまうのです。
ネクストアクションの日本語表現とビジネスでの言い換え
ネクストアクションの日本語での自然な言い換え
「ネクストアクション」という外来語は便利な一方で、社内によっては伝わりにくいこともあります。
特に、外資系文化になじみのない部署や取引先では「具体的に何のこと?」と思われるケースも少なくありません。
そんなときに使える日本語の自然な言い換えとしては、次のような表現があります。
- 次の行動
- 今後の対応
- 次のステップ
- 今後の進め方
- 次のタスク
- 実施項目
- 取り組み内容
たとえば、会議議事録に「ネクストアクション:A社に見積もり送付」と書く代わりに、「今後の対応:A社へ見積もり送付」と表現すれば、誰にでも伝わる文章になります。
ビジネスシーンでの使い分け方
外資系企業やスタートアップでは「ネクストアクション」や「NA」という略語が自然に使われています。
一方で、官公庁や老舗企業などの伝統的組織では、「次の対応」「今後の進め方」といった日本語の方が柔らかく受け入れられます。
使い分けのポイントは次のとおりです。
- 社内文化に合わせる:カタカナ語が多い企業なら「NA」、日本企業なら「次の対応」
- 相手に合わせる:上司・顧客・外部パートナーの理解度を意識する
- 資料・議事録では日本語、会話ではカタカナ語:読み手の混乱を防ぐ
「相手に伝わる表現を選ぶ」というのは、ネクストアクションの本質にも通じます。
どんなに正しい指示でも、相手が理解していなければ“次の行動”にはつながらないのです。
ネクストアクションを設定する具体的な方法
ステップ1:目的を明確にする
ネクストアクションを考えるとき、まずは「何のために行動するのか」を明確にします。
たとえば、営業会議の後に「提案資料を作る」ではなく、「商談を進めるために提案資料を作る」と目的を加えることで、行動の方向性がブレません。
目的を含めて表現することで、チーム全体が“なぜそれをやるのか”を共有できます。
結果として、タスクに優先順位がつけやすくなります。
ステップ2:小さな行動単位に分解する
「次にやるべきこと」を設定するときは、抽象的な目標を1つのアクションに分解しましょう。
たとえば「顧客対応を改善する」では漠然としすぎています。
これを次のように具体化します。
- クレーム対応履歴を整理する
- 対応マニュアルを共有する
- 改善案を週末までに上司に提案する
このように行動を「誰でも今日から動けるレベル」にまで落とし込むことで、ネクストアクションが機能します。
ステップ3:期限と責任者を設定する
ネクストアクションの効果を最大化するには、「期限」と「担当者」を必ず明確にします。
「○○をやる予定」ではなく、「○○さんが金曜までに完了」とするだけで進捗スピードは大きく変わります。
もしチーム内で共有する場合は、タスク管理ツールやスプレッドシートなどに見える化しておくと、誰がどこまで進んでいるのか一目で分かります。
ネクストアクションを効果的に運用するコツ
チームで共有することを前提に考える
ネクストアクションは個人だけでなく、チームで共有するための仕組みです。
会議やSlack、Teamsなどで決定したアクションを全員が把握していないと、認識のずれが起きてしまいます。
そのため、「共有できる形」で記録することが大切です。
議事録やタスクボードに書く際は、次の3点を意識しましょう。
- 行動内容(何をするのか)
- 担当者(誰が行うのか)
- 期限(いつまでに行うのか)
この3つがセットになっていることで、タスクの“次の一手”が明確になります。
定期的に見直して「次のNA」を更新する
プロジェクトが進むと、当初のネクストアクションが不要になったり、新しい課題が出てきたりします。
そのため、週次・月次などのタイミングで「次のNA」を見直す習慣を持つと良いです。
例えばチームミーティングの締めで「次回のネクストアクションを確認しましょう」と言うだけで、会議の締まり方が変わります。
“終わる会議”ではなく、“動き出す会議”へと変わるのです。
ネクストアクションを正しく伝えるコミュニケーション例
メールで伝える場合
メールやチャットでは、「ネクストアクションを明確に伝える一文」を入れるだけで相手の理解度が格段に上がります。
例文:
【次の対応】
・A社に見積もり送付(担当:田中、期限:3月8日)
・資料修正後、再共有予定(担当:鈴木、期限:3月10日)
また、外資系企業では「NA: Follow up with client by Friday.」のように“NA”を略して使うことも一般的です。
ただし、日本語環境では「NA」とだけ書くと伝わりにくい場合があるため、「NA(次の対応)」のように補足を加えると親切です。
会議で伝える場合
会議の締めでは、「次のアクションを確認して終わりましょう」と声かけすることで、自然にネクストアクションが共有されます。
特にプロジェクトマネージャーやチームリーダーは、“結論よりも次の行動”を残す姿勢を意識すると良いでしょう。
まとめ|ネクストアクションを意識すれば会議も仕事も止まらない
ネクストアクションは、「やること」を整理するだけでなく、「どう動くか」を明確にするための思考ツールです。
ToDoとの違いを理解し、行動レベルまで落とし込むことで、チームのスピードと精度が大きく変わります。
- ToDoは「やることの全体像」
- ネクストアクションは「今すぐ動ける一手」
- ビジネスでは「次の対応」「今後の進め方」など日本語言い換えも活用する
- 期限と責任者を明確にし、チーム全員で共有する
「次に何をするか」を明確にする力こそ、ビジネスを前に進める原動力です。
今日の会議から、あなたのチームでも“ネクストアクション思考”を取り入れてみてください。