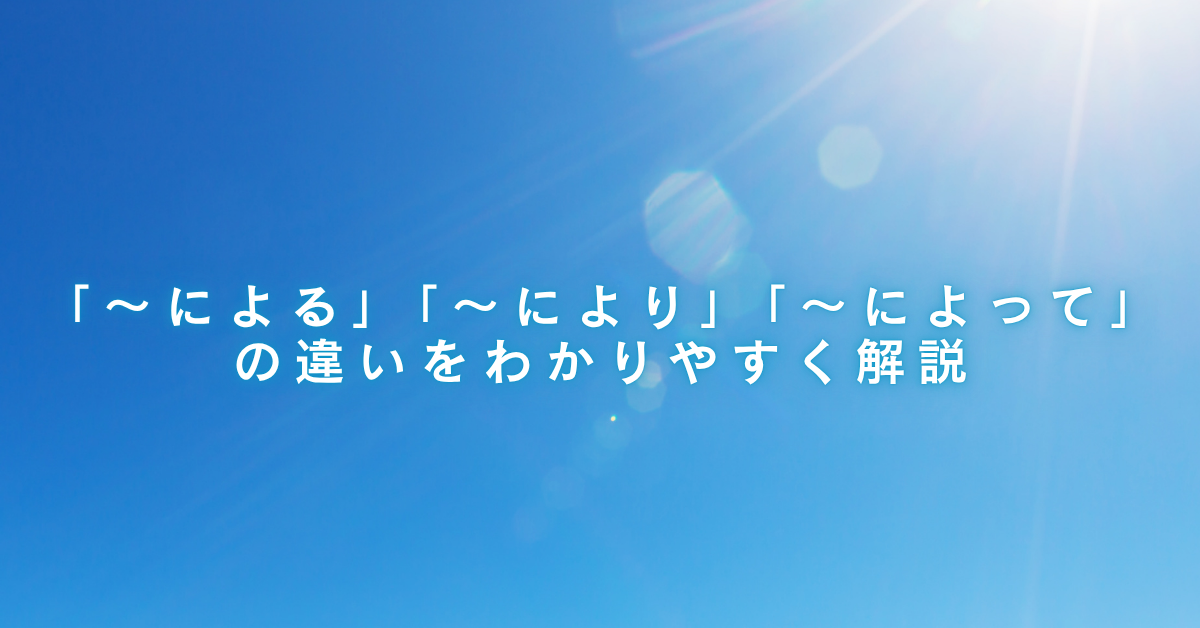ビジネス文書や報告書、英文メールを書くときに、「〜による」「〜により」「〜によって」など似たような表現に迷った経験はありませんか?
どれも原因や手段を表す表現ですが、使う場面や文の響きによって印象が微妙に変わります。この記事では、それぞれの違いを日本語文法の観点から丁寧に解説し、英語ではどのように言い換えるのか、実際の例文を交えて紹介します。読み終わるころには、社内メールや英文レポートで「どの表現を選ぶか」迷わなくなるはずです。
「〜による」「〜により」「〜によって」の基本的な違いを理解する
ビジネス文書では、どの表現を使うかで印象が変わることがあります。たとえば「システム障害による遅延」と「システム障害により遅延が発生しました」では、文末の流れが異なり、読み手に与える印象も微妙に違います。まずは、それぞれの使い方の基本を整理しましょう。
「〜による」は名詞を修飾する
「〜による」は名詞を説明・修飾するときに使われます。つまり「どんな〜なのか」を説明する働きをします。
例文:
・台風による被害が拡大しています。
・システム障害による遅延が発生しました。
・取引先の要望による仕様変更を行いました。
このように、「〜による」は名詞(被害・遅延・変更など)の前に置くことで、原因や理由を名詞と一緒にまとめて説明できます。
ビジネスの報告書や通知文では「〜による影響」「〜による停止」「〜による対応」など、名詞の連結に自然になじむ表現です。
英語ではどう表す?
英語で「〜による」は主に “due to” や “caused by” が対応します。
- Damage caused by the typhoon
- Delay due to system trouble
どちらも自然な表現ですが、「caused by」は原因を明確に示す直接的な言い方、「due to」はフォーマルでビジネス文書に向いています。
「〜により」は文語的でフォーマルな表現
「〜により」は「〜によって」とほぼ同じ意味ですが、より書き言葉に近く、ビジネス文書や公式な通知で好まれる傾向があります。
報告書・契約書・謝罪文・プレスリリースなどでよく見られる表現です。
例文:
・大雪により電車が運休しました。
・設定ミスによりデータが削除されました。
・法改正により手続きが変更されます。
特に日本語のビジネス文では、報告や謝罪のトーンを落ち着かせたいときに「〜により」が多用されます。
口語で使うとやや硬く感じられるため、会話やメール文では注意が必要です。
英語での言い換え:
・The train service was suspended due to heavy snow.
・The data was deleted as a result of a configuration error.
「due to」「as a result of」はどちらもフォーマルな表現で、ビジネス報告や契約書などに向いています。
「〜によって」は文末に置いて動作主や手段を説明する
「〜によって」は、動作主や手段・方法を表すときに使われます。
たとえば「山田さんによって書かれた報告書」「AIによって分析されたデータ」のように、何かを“行った人や手段”を示すのが特徴です。
例文:
・新しい制度は政府によって導入されました。
・本書は著者によって執筆されました。
・調査は専門機関によって実施されました。
このように、「〜によって」は“by someone”や“by means of”に近い働きを持ちます。
「〜による」が名詞を修飾するのに対し、「〜によって」は文全体で動作の手段や主語を補足します。
英語での対応表現:
・The new system was introduced by the government.
・The report was written by the author.
・The survey was conducted by a specialized agency.
つまり「〜によって」は受け身文(be動詞+過去分詞)と相性が良く、「誰によって行われたのか」を自然に説明できます。
違いを整理するとこうなる
| 表現 | 主な使い方 | 文の構造 | 英語の対応 |
|---|---|---|---|
| 〜による | 名詞を修飾する(原因・理由) | 被害による遅延 | due to / caused by |
| 〜により | 文語的・フォーマル(理由・手段) | 雨により試合が中止 | due to / as a result of |
| 〜によって | 手段・行為者・方法 | 政府によって発表された | by / through / with |
どれも似ていますが、「による」は名詞と組み合わせ、「により」は硬い書き方、「によって」は動作主や手段を示すと覚えると整理しやすいですよ。
「による」「により」「によって」をビジネス文書で正しく使い分ける方法
では、実際に業務でどのように使い分ければよいのでしょうか。ここでは社内報告やお知らせ文、クレーム対応メールなどで迷いやすいパターンを取り上げ、適切な表現に言い換える方法を紹介します。
「〜による」:原因や理由を明確にしたいときに使う
報告書やお知らせでは、「〜による」を使うことで“原因と結果”をスムーズにつなげられます。
例文:
・サーバー障害による一時的な停止についてお知らせします。
・大雨による交通遅延のため、会議開始時刻を変更いたします。
このように、「何が原因で」「どんな結果になったのか」を名詞同士で結びつけるのがポイントです。
ただし、1文中で何度も「〜による」を繰り返すと読みにくくなるため、適度に「〜が原因で」「〜の影響で」などと混ぜて使うと自然になります。
悪い例:
・台風による停電によるシステム障害が発生しました。
→「台風の影響で停電し、その結果システム障害が発生しました」と言い換えるとすっきりします。
英語での対応:
・System outage caused by a power failure due to the typhoon.
ここでも“caused by”を2回重ねるのではなく、前半を“due to”に置き換えることで自然な英文になります。
「〜により」:報告文・通知文でフォーマルにまとめたいとき
「〜により」は公的な文書に向いており、客観的で冷静な印象を与えます。
社外への通知やプレスリリース、公式発表などでよく使われます。
例文:
・メンテナンス作業によりサービスを一時停止いたします。
・設定変更により一部データが閲覧できなくなりました。
この表現は、文全体をフォーマルに引き締める効果があります。
ただし、社内チャットやカジュアルなメールで多用すると堅苦しい印象を与えることもあります。
使い分けのコツ:
- 「〜による」は“修飾”(名詞とセット)
- 「〜により」は“報告”(文末まで含む)
- 「〜によって」は“行為者”(受け身文など)
これを意識するだけで、使い分けの迷いがぐっと減ります。
英語での例:
・The service will be temporarily suspended due to maintenance work.
・Some data became unavailable as a result of configuration changes.
「due to」は多くのビジネスメールで使える万能表現ですが、よりフォーマルにしたいときは「as a result of」もおすすめです。
「〜によって」:行為者や手段を強調したいとき
社内の報告文や技術ドキュメントでは、「〜によって」は“誰が・どの手段で行ったか”を明確にするときに使います。
受け身構文と相性がよく、客観的な文体を作りやすいのが特徴です。
例文:
・調査は外部コンサルタントによって実施されました。
・分析はAIツールによって自動化されました。
・プロジェクトは営業部によってリードされました。
このように、「〜によって」はbyやthroughと対応します。
また「手段」を強調したい場合は、「by using」「through」などの英語表現に置き換え可能です。
英語での例:
・The survey was conducted by an external consultant.
・The analysis was automated through an AI tool.
・The project was led by the sales department.
「によって」は主体を明確にできる便利な表現ですが、同じ文中で何度も使うとリズムが重くなるので、1文に1回程度が目安です。
「による」「により」「によって」の連続使用で文章が読みにくくなる理由と修正法
ビジネスメールや報告書でよく見かけるのが、「〜による〜により〜によって…」と似た表現が連続して使われるケースです。
一見正しいように見えますが、読み手にとってはどこが原因でどこが結果なのか分かりにくくなってしまいます。
読みにくい例と改善例を比較する
悪い例:
・システム障害による通信エラーによりデータの遅延が発生し、復旧作業によって一時停止しました。
一見ビジネス文として正しそうですが、実際には同じ構文が3回も重なっていて、原因と結果が整理されていません。
改善例:
・システム障害が原因で通信エラーが発生し、その影響でデータ処理が遅延しました。復旧作業のため、一時的にシステムを停止しました。
修正後の文章では、「原因→影響→対応」という流れが明確になり、読み手が状況をスムーズに理解できます。
修正のコツ:原因・結果・対応を分けて書く
「〜による」などを連続して使わないためには、文の構造を意識することが大切です。
次の3ステップで整理すると、簡潔で伝わりやすい文章になります。
- **原因(なぜ起きたか)**を明示する
- **結果(何が起きたか)**を別文に分ける
- **対応(何をしたか)**を動詞で表す
例:
・停電によるトラブルにより会議が中止されました。
→「停電が原因でトラブルが発生し、その結果、会議を中止しました。」に修正。
こうすることで「による」「により」を連続させず、文がスッキリと読みやすくなります。
英文でも同様に整理する
英語でも「due to」「because of」「as a result of」を立て続けに使うと不自然になります。
そのため、原因・結果・対応を分けて構成するのが基本です。
悪い例:
The meeting was canceled due to a problem caused by a power failure.
→原因が二重に出てくるため読みにくい。
改善例:
The meeting was canceled because a power failure caused a system problem.
原因と結果を1つの文で整理し、より自然な英文になります。
「によるもの」の使い方とビジネス文での注意点
「〜によるものです」という表現は、報告書・社内メール・お詫び文などで頻繁に登場します。
丁寧で便利な言い回しですが、使いすぎると曖昧な印象を与えることもあります。
「〜によるものです」は原因や理由を和らげる表現
この表現は、「〜が原因です」と言い切るよりも柔らかい響きを持ちます。
特に、相手に責任を追及されたくない場面や、クレーム対応文でよく使われます。
例文:
・今回の不具合は設定ミスによるものです。
・遅延はサーバー負荷の増大によるものです。
・データ破損は一時的な通信障害によるものです。
このように、「〜によるものです」は「〜が原因です」と同義ですが、語感がやわらかく、ビジネス上のトーンを調整するのに役立ちます。
曖昧さに注意し、具体的な原因を補う
一方で、「によるものです」だけで終えると、「具体的に何が問題だったのか」が伝わらないことがあります。
報告書やお客様への説明では、原因をもう一歩踏み込んで説明することが大切です。
悪い例:
・エラーは設定の不備**によるものです。
(どの設定が?どのように?が分からない)
改善例:
・エラーはサーバーのIP設定に誤りがあったこと**によるものです。
(原因が具体的になり、相手に安心感を与える)
英語での対応表現
「〜によるものです」は、英語では “is caused by” や “is due to” で表せます。
- The issue was caused by a configuration error.
- The delay was due to increased traffic.
フォーマルな報告文では “due to” が使いやすく、口頭説明では “caused by” のほうが自然です。
「による」などに使われる漢字の意味と由来を押さえておこう
「による」「により」「によって」はいずれも“寄る”という動詞から来ています。
「寄る」は「近づく」「もとにする」「原因に基づく」といった意味を持ち、文法的には格助詞「に」と結びついて使われます。
「寄る」がもつ3つの基本的な意味
- 依存・原因:「AによるB」は“Aに依存してBが起きた”を意味する
- 手段・方法:「によって」は“その方法で行う”という意味
- 基準・根拠:「により」は“それに基づいて”というニュアンス
たとえば「法律により禁止されている」という文は、「法律を根拠にして」という意味をもっています。
漢字の理解でニュアンスがつかみやすくなる
文法的な説明よりも、“寄る=もとになる・基づく”とイメージすると理解しやすいです。
「〜による」はその“もと”を説明し、「〜によって」はその“働きかけ”を強調します。
こうした日本語の構造を理解しておくと、英語で「because」「by」「due to」などを使い分けるときにも役立ちます。
英文メールで「〜による」を自然に伝えるフレーズ集
ビジネス英語では、「〜による」「〜により」「〜によって」に対応する表現が複数あります。
直訳ではなく、文の目的(原因を伝えるのか、手段を述べるのか)によって適切な単語を選ぶことが大切です。
原因・理由を表す英語表現
- due to:フォーマルで最も多用される。書面・ビジネスメール向け。
- because of:口語的で自然。会話・プレゼンに向く。
- as a result of:結果として〜になった、という意味でフォーマル。
例文:
・The delay was due to a system error.
・The event was canceled because of heavy rain.
・The data loss occurred as a result of maintenance work.
手段・方法を表す英語表現
- by:誰が行ったか、どの手段で行ったかを示す。
- through:過程や仕組みを強調する。
- with:道具や手段を示す柔らかい表現。
例文:
・The survey was conducted by an external agency.
・The issue was resolved through collaboration.
・The data was processed with AI technology.
ビジネスメールでの自然な文例
・We apologize for the delay caused by the system maintenance.
(システムメンテナンスによる遅延についてお詫び申し上げます。)
・Some data became unavailable due to a temporary server issue.
(一時的なサーバー障害により、一部データが利用できなくなりました。)
・The project was completed through joint efforts.
(共同の取り組みによって、プロジェクトが完了しました。)
英語では原因を明確に伝えることが重視されるため、「by」や「due to」などを繰り返しても違和感はありません。
ただし、“caused by” を多用しすぎると硬く聞こえるため、“due to”“because of”と組み合わせて使うのがコツです。
まとめ:「による」「により」「によって」を使いこなして伝わる文章に
似ているようで微妙に使い方が異なる「による」「により」「によって」。
ポイントを整理すると次のようになります。
- 「による」:名詞を修飾し、原因や理由を明示する
- 「により」:フォーマルな書き言葉で、手段や理由を表す
- 「によって」:動作主・方法・影響を説明する
そして、英文では以下の対応を覚えておくと便利です。
- による → due to / caused by
- により → as a result of / due to
- によって → by / through
これらの違いを理解して使い分けることで、ビジネス文書の正確さと信頼感が格段に向上します。
社内報告、顧客対応、海外とのやり取り、いずれの場面でも「言葉の選び方」が伝わり方を左右します。
文章を整えることは、相手への敬意を示すことでもあります。次に文書を書くときは、ぜひ「による」「により」「によって」を意識的に選んでみてください。