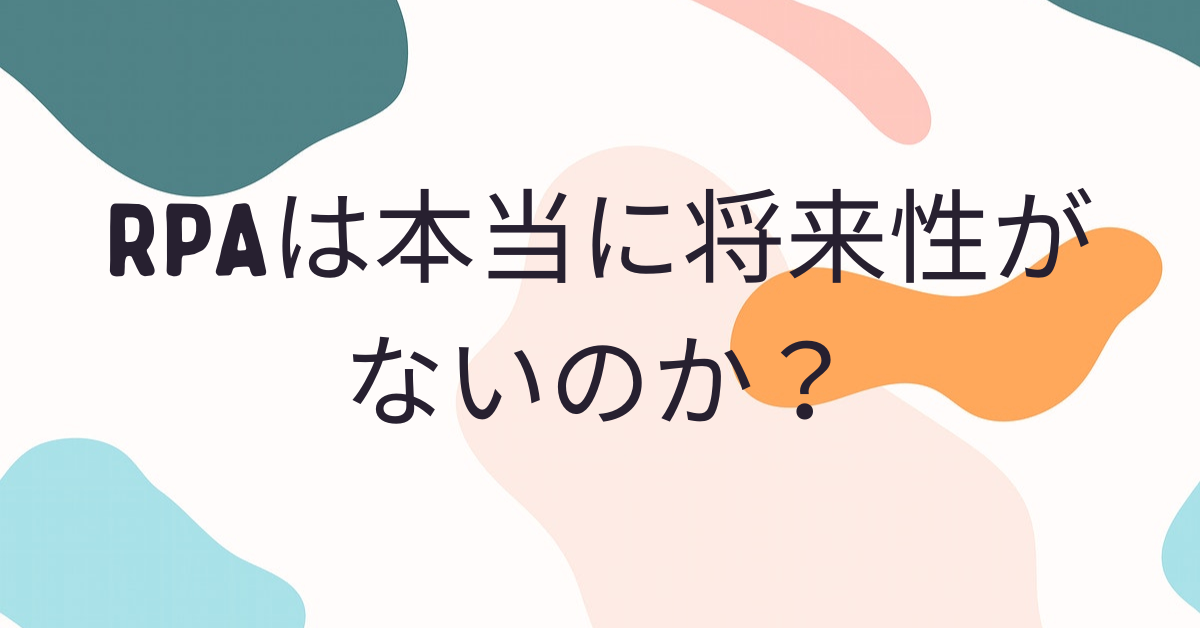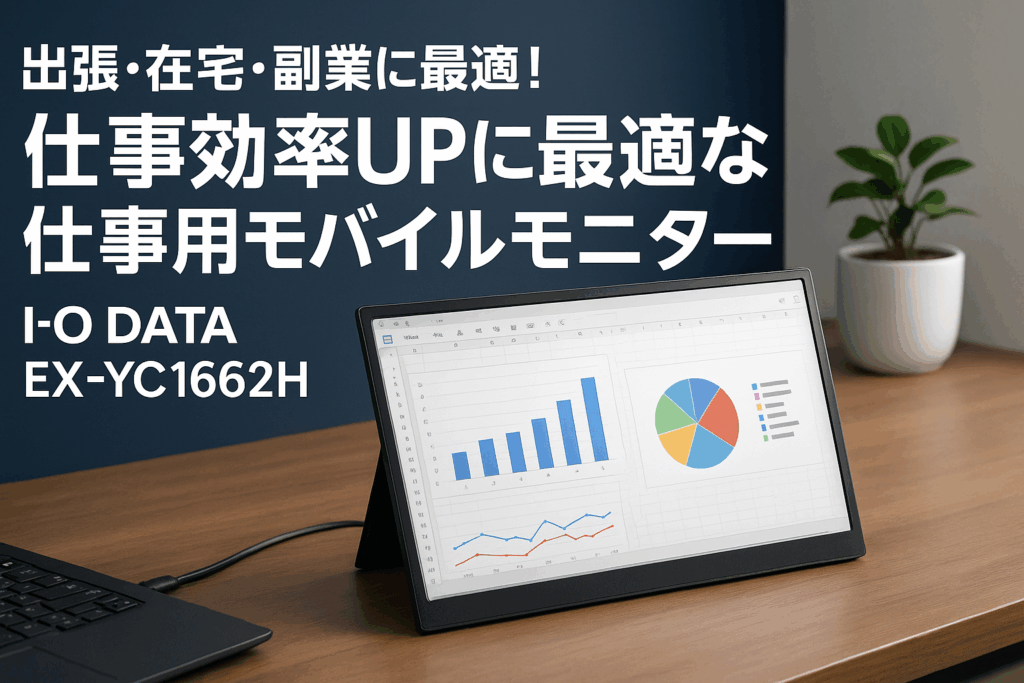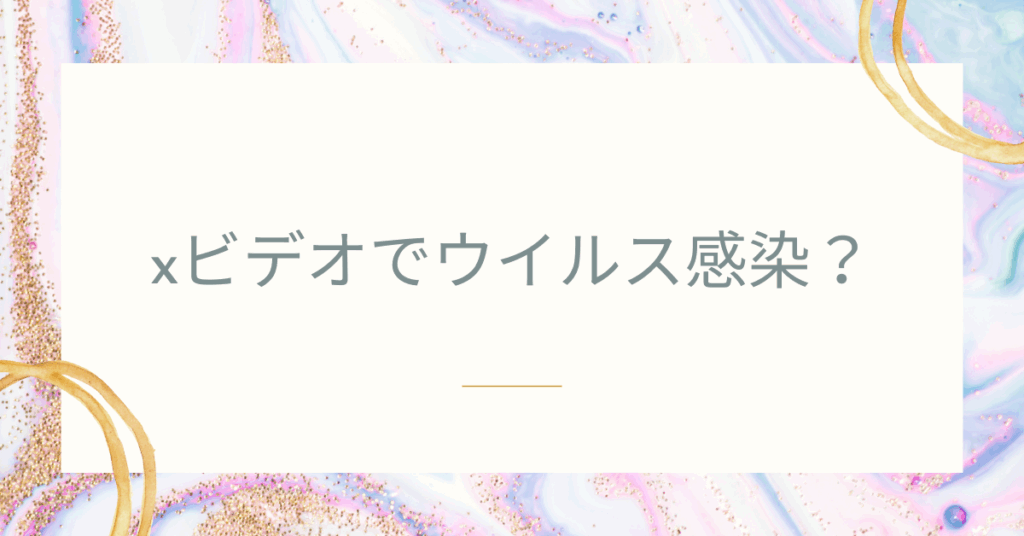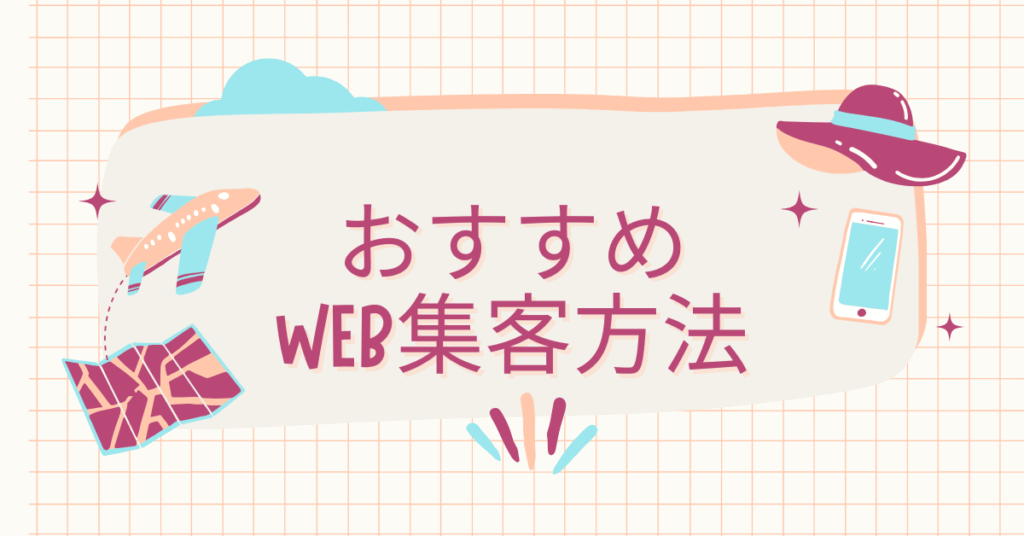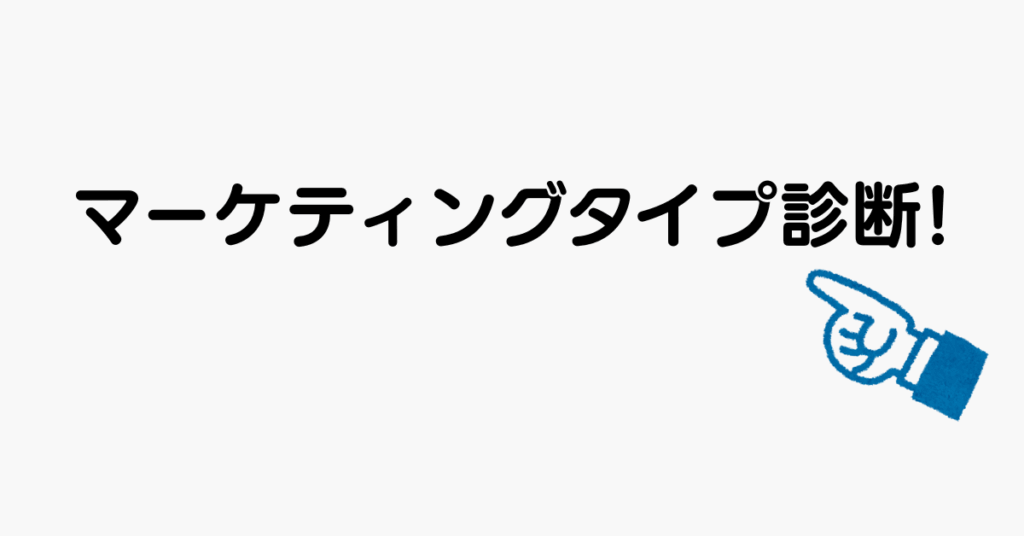RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、一時期「業務効率化の切り札」として多くの企業が導入しました。
しかし近年、「RPAはもう終わった」「RPAに将来性はない」という声を耳にすることも増えています。
果たしてそれは本当なのでしょうか?それとも誤解なのでしょうか?
この記事では、RPAブームの背景や日本だけの課題、RPAエンジニアの現実、そしてAIとの融合による新たな自動化の未来までを、実例とともにわかりやすく解説します。
読み終えた頃には、「RPAは終わった」の意味が“変わる”かもしれません。
RPAとは何かを改めて理解する
まず、「RPAとは?」という基本から整理しておきましょう。
RPAは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、コンピューター上の定型作業をソフトウェアロボットが自動で行う仕組みを指します。
例えば、経理部門での請求書処理、営業部門での見積書作成、人事部門での勤怠データ入力など、「人間が毎日同じ手順で行う仕事」を自動化できます。
Excelのマクロやスクリプトよりも柔軟で、複数のアプリケーションをまたいだ操作が可能なのがRPAの特徴です。
代表的なRPAツールには以下のようなものがあります。
- UiPath(ユーアイパス)
- Automation Anywhere
- Blue Prism
- WinActor(日本製)
これらはGUI操作で簡単にロボットを作れるため、非エンジニア職でも導入しやすいという利点がありました。
この「誰でも使える」という手軽さが、2017〜2020年頃のRPAブームを生み出したのです。
RPAブーム終焉と言われる理由とその真相
しかし近年、「RPAブームは終わった」と言われるようになりました。
ではなぜそう言われるようになったのでしょうか。
表面的に「RPAが古い」と切り捨てるのではなく、背景にある要因を見てみましょう。
1. 現場任せの導入で“定着しなかった”企業が多い
RPA導入当初、企業の多くは「とりあえず導入してみよう」と現場に任せる形でプロジェクトを進めました。
しかし、明確な目的設定や運用ルールがないまま導入すると、すぐにエラーやメンテナンス負荷が発生します。
「動かなくなった」「担当者が異動して誰も修正できない」などのトラブルで、結果的に放置されたRPAも少なくありませんでした。
2. 対象業務が限定的だった
RPAは「ルールが明確」「例外が少ない」業務には強いものの、判断や変化を伴う業務には対応できません。
AIや自然言語処理がまだ発展途上だった当時、RPAは“手作業の自動化ツール”の域を出なかったため、活用の幅が限定されていました。
そのため「思ったより効果が出ない」「運用コストが高い」と感じる企業も増えていったのです。
3. AI・ChatGPTの登場で注目が移った
2023年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIが登場し、
「もうAIで自動化できるのでは?」という流れが強まりました。
この結果、RPAが“古い技術”のように扱われ、「RPAはオワコン」という印象を持たれたのです。
しかし、実際にはAIとRPAは対立する存在ではなく、補完関係にあります。
RPAが得意な定型処理をAIが理解し、判断部分をAIが担うことで、より高度な自動化が可能になります。
RPAオワコン説は本当か?日本だけが遅れている理由
「RPA オワコン説は本当か?」という問いに対し、結論から言えば**“誇張された誤解”**です。
確かにブームのような熱狂は落ち着きましたが、世界的にはRPAは今も進化を続けています。
むしろ、日本市場が「RPA 日本だけ遅れている」と言われる理由を理解すると、今後の可能性が見えてきます。
海外では「ハイパーオートメーション」へ進化
米国や欧州では、RPAを中核にAIやBPM(ビジネスプロセスマネジメント)を統合した「ハイパーオートメーション」が注目されています。
これはRPA単体ではなく、AIによる判断・分析と連携する自動化の仕組みです。
たとえば、請求書の内容をAIで読み取り、その情報をRPAで会計システムに入力する、といった組み合わせが一般的になっています。
日本だけが“属人的な運用”にとどまっている
一方、日本ではRPA導入を「現場の手作業を減らすツール」として使う企業が多く、経営層レベルでのデジタル戦略に結びついていないケースが目立ちます。
つまり、RPAを**“業務改革”ではなく“便利ツール”扱い**してしまったのです。
この「部分最適」にとどまる姿勢が、海外との差を広げる要因になっています。
RPAの真価は「自動化の基盤技術」にある
RPAは確かに成熟期に入りましたが、
それは「終わり」ではなく「標準化」の段階です。
AI・チャットボット・クラウドサービスなどと連携する前提技術として、RPAはこれからも重要な役割を担います。
実際に多くの企業では、ChatGPTとRPAを連携させて社内業務の自動化を進めるケースが増えています。
RPAエンジニアはやめとけ?将来性と実情を冷静に分析
「RPAエンジニア やめとけ」というフレーズを見たことがある方も多いでしょう。
しかし、これは単にネガティブな意見というよりも、RPAエンジニアの“立ち位置の誤解”から生まれた声です。
実際のところ、RPAエンジニアには明確な将来性があります。
ただし、そのままでは生き残れないのも事実です。
RPAエンジニアの仕事内容とは
RPAエンジニアの主な仕事は、業務プロセスを分析し、自動化のロボットを設計・開発・運用することです。
プログラミングスキルがなくても始められますが、現場での運用やトラブル対応には技術知識が欠かせません。
具体的な業務内容には次のようなものがあります。
- 自動化対象業務のヒアリングとフロー整理
- RPAツール(UiPathなど)を使ったロボット開発
- 実運用後のメンテナンスや修正
- 社内展開や教育支援
RPAエンジニアが「やめとけ」と言われる理由
- 単純作業化しやすいポジション
RPAツールのテンプレート化が進み、「誰でも開発できる」環境が整ったため、スキル差が出にくい職種になりました。 - キャリアパスが曖昧
RPAだけに特化すると、AIやシステム統合との連携スキルが不足し、将来的な成長が止まりやすくなります。 - メンテナンス負担が大きい
現場の仕様変更や環境依存が多く、「きつい」と感じる現場もあるのは事実です。
しかし、これらの課題は「RPAしかできない」状態にとどまることで生じます。
逆に言えば、AI・データ連携・クラウド構築スキルを磨けば、RPAエンジニアは自動化戦略の中心人材になれるのです。
RPAエンジニアの将来性と年収のリアル
RPAエンジニアの将来性は「広げ方次第」で大きく変わります。
単にロボットを作るだけの作業者ではなく、企業の業務効率化を設計できる“プロセスデザイナー”へ進化することで、需要はむしろ高まります。
現在のRPAエンジニアの年収目安
- 初級(開発経験1年未満):350〜450万円
- 中級(運用・設計経験2〜3年):450〜600万円
- 上級(チームリーダー・自動化コンサル):700万円以上
特にAI連携やクラウド構築スキルを持つエンジニアは、年収800万円を超えるケースも珍しくありません。
また、RPAベンダーやコンサルティング会社に転職すると、プロジェクトマネージャーとしてのキャリアパスも開けます。
将来性の鍵は“AI×RPA”の統合スキル
生成AIが広まる今、RPAはAIと共存する段階に入りました。
ChatGPT APIを組み込んで自然言語の指示を自動化したり、OCR(文字認識)で書類データを自動処理したりと、連携の幅が広がっています。
この領域を理解できる人材は非常に少なく、企業からのニーズも高まっています。
RPAは本当に終わったのか?今後の進化と新しい役割
RPAブームが過ぎ去ったように見えても、実はその下で静かに進化が続いています。
2025年以降、RPAは「AIと共に働くインフラ」として再評価されつつあります。
AI連携による次世代RPAの姿
RPA単体では難しかった“判断”や“理解”の部分を、生成AIが補完する時代になりました。
たとえば、AIがメール内容を読み取り、RPAが適切な処理を実行するという流れです。
このようなハイブリッド型自動化が、次世代RPAの中心になります。
ノーコードから「プロセス設計力」へ
ツール操作よりも重要なのは、「どの業務を自動化するか」を見極める力です。
単なる操作員ではなく、業務全体を設計できる人材が求められています。
これこそ、RPAエンジニアが“業務改善のプロ”として成長できる道です。
RPAの未来は「終わり」ではなく「進化」
RPAはオワコンではありません。
むしろ、AIとの統合によって新たなステージに入ったと言えます。
「人の判断を奪う」技術ではなく、「人の時間を取り戻す」技術へ。
この考え方こそが、これからの自動化時代を生き抜くカギになります。
まとめ
RPAは確かに一時的なブームを終えましたが、それは「終焉」ではなく「成熟」です。
RPAブームの中で生まれた課題を乗り越え、今はAIと連携した新しい自動化の形へと進化しています。
RPAエンジニアの将来性も、“自動化の全体設計ができる人”として広がり続けています。
単純な作業自動化ではなく、業務の仕組みそのものを変える視点を持てる人にこそ、RPA時代の次の波が訪れます。
「RPAはもう古い」と言われる今だからこそ、本質を理解し、AIと共に自動化を設計できる人が最も求められているのです。
RPAは“終わった技術”ではなく、“新しい働き方の基盤”として、これからも企業の成長を支え続けていくでしょう。