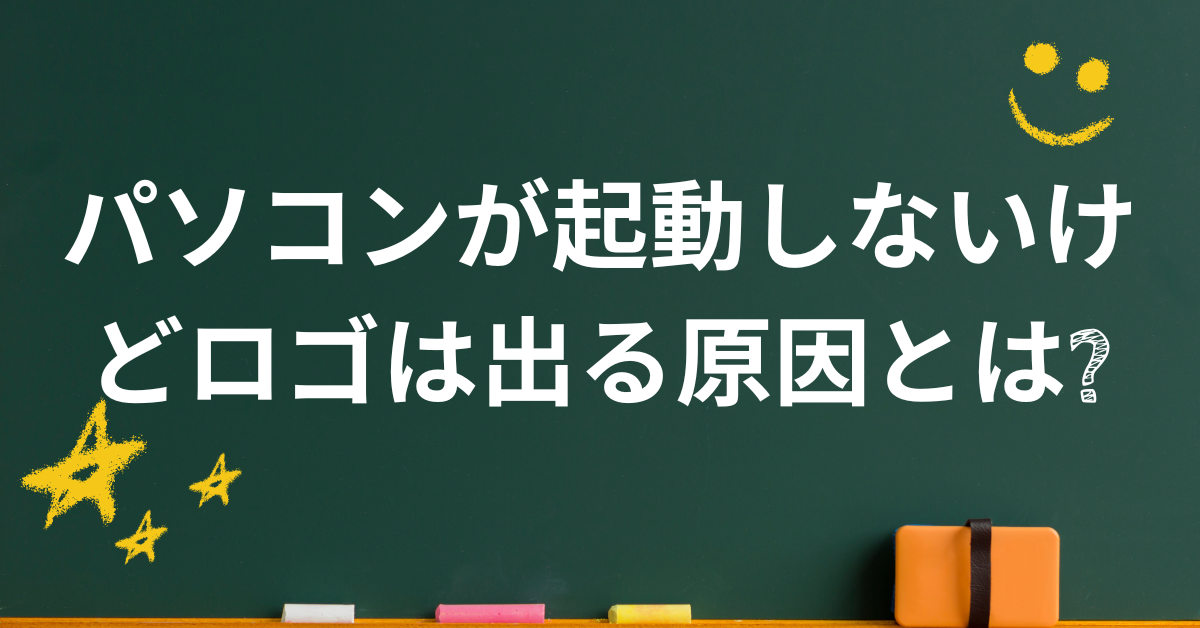パソコンの電源を入れるとメーカーのロゴは表示されるのに、そこから先に進まずフリーズしたような状態になる──。このような症状は、Windowsユーザーの間で非常に多く見られるトラブルの一つです。
この記事では、「ロゴは出るのに起動しない」状態に対して、原因の切り分けから、Lenovo・ASUS・富士通・Dell・ガレリアなどのメーカー別対処法、さらに個人と法人がとるべき行動指針まで、実践的に解説します。
目次
ロゴは出るけど起動しない状態とは?その基本構造
よくある症状
- ロゴ表示後に「くるくる」が永遠に続く
- ロゴは出るが黒画面で停止
- OSのログイン画面まで進まず再起動を繰り返す
起動プロセスの流れと停止しやすいポイント
- 電源投入 → BIOS(UEFI)起動
- ストレージ認識 → ブートローダー実行
- OSの読み込み開始
ロゴ表示まで進んでいる=BIOSまでは正常動作しているが、そこから先のOS読み込みで何かしらのエラーが発生している可能性があります。
考えられる主な原因と優先順位
1. 周辺機器の接続不具合
- USBメモリや外付けHDDがあるとブートの妨げになるケースあり
2. BIOSの設定不整合
- セキュアブートや起動順が原因で止まっていることも
3. Windowsアップデート後の不具合
- 一部の更新が正しく反映されず、再起動ループになる例も
4. SSD/HDDの物理的故障
- ストレージの読み込みに失敗し、OSが起動できない状態
対処法①:まずは共通のチェックポイントを確認
ケーブルと周辺機器の取り外し
- 外部ディスプレイ、USB周辺機器をすべて取り外し
- バッテリーがある機種は一度外して放電
BIOS画面に入って設定を確認
- 電源投入時に[F2]または[DEL]キーでBIOSにアクセス
- 起動順やセキュアブートを確認
- ストレージ(HDD/SSD)が認識されているか確認
スタートアップ修復を試す
- 電源ON→ロゴ表示→強制OFFを3回繰り返すと修復モードに入る
- 「トラブルシューティング」→「スタートアップ修復」へ進む
メーカー別の特徴と対処のコツ
Lenovoの特徴と対処法
- 「Novoボタン」搭載モデルが多く、これを使うことで回復オプションに直接アクセス可能
- TPM設定やセキュアブートの切り替えで改善するケースあり
ASUSの特徴と対処法
- 高性能なゲーミングモデルが多く、メモリ増設やSSD交換時の不具合が多い
- BIOSが旧バージョンだと互換性問題が起きやすいため、BIOSアップデートが効果的
Dellの特徴と対処法
- デル製PCは**診断機能(ePSA)**が強力
- 電源ON時に[F12]→診断を実行→ハード異常があれば表示される
富士通の特徴と対処法
- Windowsのリカバリ領域に簡単にアクセスできる機種が多い
- 起動時[F12]や「Fujitsu Recovery」を活用して初期化も可能
ガレリア(ドスパラ)の特徴と対処法
- ゲーミングPCでBTO構成が多いため、パーツ相性による不具合が起きやすい
- 初心者は保証サポートに早めに連絡を
症状別の対応フローまとめ
黒い画面で止まる場合
- モニター接続の問題を含め、HDMIケーブルの再接続や別モニターで確認
- グラフィックドライバー破損の可能性 → セーフモード起動を試す
ロゴのあと「くるくる」が止まらない
- スタートアップ修復、システムの復元を優先
- 一度セーフモードで立ち上げてから通常起動へ戻すと成功することも
ロゴ表示→勝手に再起動が繰り返される
- Windowsブートマネージャーの破損が疑われる
- コマンドプロンプトから
bootrec /fixbootやchkdskを試す
ノートパソコン特有の注意点
- バッテリー劣化や静電気によるロックが原因となることも
- 一度バッテリーを外し、電源ボタン長押しで放電処理を行う
- 放電後にACアダプタのみで起動を試すと回復する例あり
最終手段:OSの再インストールとデータ救出
- 別PCで**Windowsインストールメディア(USB)**を作成
- BIOSでUSBブート設定→Windowsを再インストール
- データを救出するには、Live USBでLinuxを起動してバックアップ取得がおすすめ
法人利用者向けのポイントとリスク管理
- 複数台で同様の症状が発生した場合、Windows Updateやウイルス配布の可能性を視野に
- セキュリティソフトやグループポリシーによる競合が原因となる場合あり
- 定期的なバックアップと、スタンドアロン型の復元ツール整備が重要
まとめ:ロゴが出るのに起動しないなら、原因は絞り込める
「ロゴは出るけど起動しない」トラブルは、見た目の派手さに反してBIOSとストレージ・OSの境界で発生することが多いです。
- 周辺機器の確認やBIOS設定の見直しで改善することも多い
- メーカーごとの機能(Novoボタン、診断ツールなど)を活用する
- 放電やセーフモードなどの“定番対処”も一度は試す価値あり
起動しない状況でも、冷静に一つずつ原因を潰していけば、多くのケースは自己対応で回避できます。特に業務用PCの場合は、復旧後の再発防止まで視野に入れて運用を見直すことが求められます。