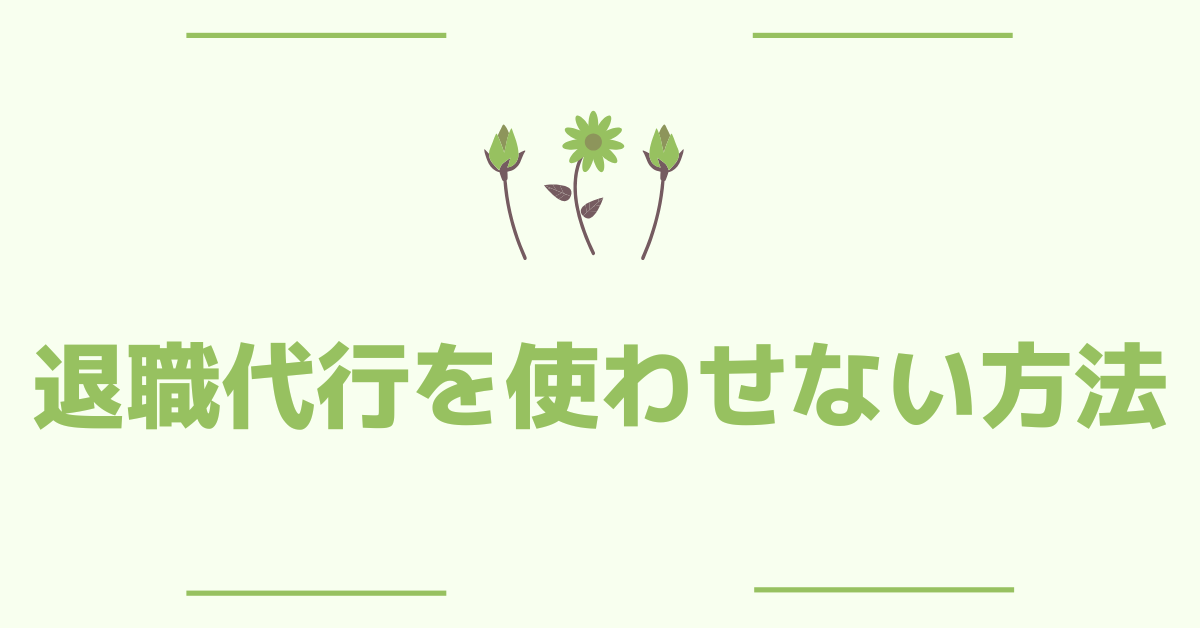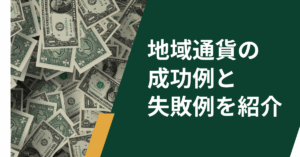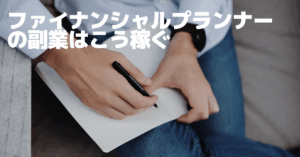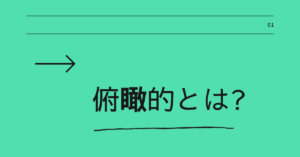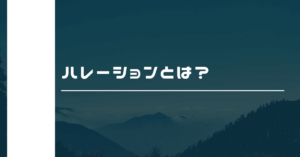社員から突然「退職代行を通じて辞めます」と連絡が入った――。
そんな事態が続くと、企業側としては「どう防げばいいのか」「契約で制限できないのか」と悩みますよね。
本記事では、退職代行を使わせないために企業がとるべき施策と、法的なリスク、そして現実的な予防策を人事・経営の視点で解説します。
退職代行とは?企業に与えるインパクト
退職代行サービスの概要
退職代行とは、本人に代わって第三者(業者や弁護士など)が会社に退職の意思を伝えるサービスです。
連絡の煩わしさや心理的なストレスを避けたいという理由から、利用者は年々増加傾向にあります。
企業側に起こる問題とは?
- 業務の引き継ぎができない
- 社内の士気が下がる
- 突然の退職により人員計画が狂う
- SNSで「ブラック企業」とレッテルを貼られるリスク
退職代行を使われる理由とは?
社員が退職代行を選ぶ心理的背景
- 直属の上司が怖くて言い出せない
- 引き止めが強引で、前にも辞められなかった
- 精神的に限界で、会話すら避けたい
- 言っても無視される、聞き入れてもらえない
会社側が気づいていない問題も多い
「突然辞めた」と感じるかもしれませんが、実は何度かSOSが出ていた可能性もあります。
退職代行は、その“最後の手段”として選ばれるケースが多いのです。
退職代行を使わせないための現実的な方法
1. 「退職が言い出せる風土」をつくる
- 月1の1on1面談でキャリアの悩みも聞く
- 上司が退職を受け止める姿勢を持つ
- 辞めることを“裏切り”扱いしない社風
2. 退職引き止め文化をやめる
- 本人が辞意を伝えたら、粛々と手続きに入る
- 「あと○ヶ月いてくれ」などの強要はNG
- 結果として、退職代行の使用率が下がる
3. メンタルケアと早期対応の強化
- ストレスチェックの実施と人事面談の定期化
- 体調不良が見られたら業務調整や休養提案
- 外部の相談窓口(EAP)を設ける
契約書や就業規則で退職代行を制限できる?
法的には「制限できない」のが現実
結論:退職代行を契約書や就業規則で「禁止する」ことは、法的に無効になる可能性が極めて高いです。
民法の規定に基づく退職の自由
- 期間の定めのない雇用契約は、労働者からいつでも退職できる(民法627条)
- 退職の意思は、代理人を通して伝えても有効とされている
判例上も“代理による退職”は認められている
「退職は本人が直接出社して申し出ること」と定めても、法律上は拘束力なし。
契約書・就業規則に書ける「現実的な表現例」
以下のような文言であれば、法的リスクを避けつつ、手続きの明確化に繋がります。
原則として、退職の意思表示は直属の上司または人事担当者に対して口頭もしくは書面により行うものとする。代理人を通じて行う場合には、本人の委任状など、正当な代理権を証明する書類の提出を求めることがある。
この表現であれば、禁止にはならず、一定の抑止力を持たせることが可能です。
契約書をつかった制限の注意点
結論から言うと、
退職代行の「使用を制限する契約書・誓約書」は法的に無効になる可能性が非常に高いです。
🔍理由①:労働者の「退職の自由」は強く保護されている
民法第627条で、期間の定めがない雇用契約はいつでも解約できるとされています。
また、代理人(退職代行業者など)を通じての意思表示も有効です。
つまり…
- 本人が言わなくても、正規の代理権を持った退職代行が伝えた時点で【退職の意思表示】は成立。
- 就業規則や誓約書で「本人からしか退職できない」と定めても、民法・判例上は否定される。
🔍理由②:「業者利用禁止」は私的自治の限界を超える
会社と従業員の契約で「退職代行を使うな」という取り決めをしても、
- 使用者による過度な拘束(憲法の職業選択・契約自由の制限)とされ、
- 実効性はほぼゼロ。仮に裁判になっても、会社側が不利になる可能性が高い。
❌やってはいけないこと
- 「退職代行を使ったら損害賠償」などの条項 → 威圧的で、不法行為に該当するリスクあり
- 「退職は書面で本人が出社して申し出ること」→ 一見正当でも、強制的に出社させるのは違法行為に近い
✅現実的な対応策
法的な制限ではなく、**「社内ルールとして望ましい手続きを明示」**しておくことは可能です。
たとえば:
退職の意思表示は、原則として直属の上司または人事部門への口頭・書面にて行うことを推奨します。やむを得ず代理人を立てる場合は、正当な委任関係を証明する書面(委任状等)の提出をお願いすることがあります。
これは「禁止」ではなく、手続きを明文化しているだけなので、トラブル回避に一定の抑止力があります。
✅補足:退職代行を使われた後の会社の正しい対応
- 無視しない(無視は違法リスク)
- 本人確認を求めるのはOK(ただし柔らかく)
- 離職票・源泉徴収票などは速やかに処理しないと労基署案件になる
法的に縛るのではなく、“代行を使わないほうがスムーズ”と思わせる社内体制がベストです。
退職代行を使われた時、企業側のNG対応
やってはいけない行為一覧
- 「退職を許可しない」と伝える
- 無視して出勤扱いにする
- 「代行なんて無効だ」と突っぱねる
- 会社備品の返却を強制して脅す
これらは違法・パワハラ認定される可能性があり、労基署や訴訟リスクを高めます。
法的リスクを抑えつつ退職代行を減らす「裏技的対応」
1. 匿名相談チャットの設置(Slack・LINE WORKSなど)
- 社員が不満や退職希望を事前に伝えやすくなる
- 人事が早期に兆候を察知できる
2. 外部キャリア面談の導入
- キャリアコーチや産業カウンセラーと連携
- 社内では言えない本音が引き出せる
3. 評価制度・教育制度の透明化
- 退職理由の一部に「評価が不透明」がある
- 将来像が描けない会社に社員は残らない
退職代行を「使わせない組織」にするために重要な視点と退職代行を「使われない職場」にする具体策
- 「使う人が悪い」のではなく「使われる背景」に目を向ける
- 会社側の意識改革こそが最強の予防策
- 退職は自然なキャリア選択の一つ。“出戻りOK”の文化がある会社ほど人が辞めにくい
退職代行を「使われない職場」にする具体策
① 退職希望を“言いやすい雰囲気”をつくる
- 月1回の1on1やキャリア面談で、「退職」も話題に出せる風土をつくる。
- 上司との信頼関係が薄いと、退職も言い出しにくくなる。
- 「辞める=裏切り」と捉える上司がいると、社員は黙って代行を使う。
② 引き止めないスタンスを明示する
- 「辞める人を引き止めない方針です」と入社時に伝えておく。
- これがあるだけで退職代行を使う理由の大半が消える。
③ 就業規則で「退職の申出方法」を明記する
- 退職代行からの連絡でも正式な手続きになるように整備はしておくべき。
- ただし、「本人が直接言わないと無効」などのルールは**無効(違法扱いになる可能性あり)**なので注意。
④ メンタル不調の兆しに早期介入する
- 精神的に追い詰められてから退職代行を使うパターンが多いため、早期に面談や業務調整を行う。
- 産業医や外部相談窓口の案内も重要。
⑤ 入社時に「退職も選択肢である」と伝える
- 「いつでも辞めていい」くらいのスタンスを示すと、かえって定着率が上がるケースも。
❌ NG対応(退職代行を加速させる)
- 「辞めるなら訴えるぞ」と脅す
- 「今辞めたら迷惑」と圧をかける
- 「次の人が見つかるまでダメ」などのルール押し付け
これらは逆効果で、むしろ労基署案件になるリスクすらあります。
💡裏テク(やや攻めた対策)
- 退職面談をプロに任せる:外部の第三者が中立に退職者と面談し、離職理由・職場改善ポイントを吸い上げる。
- SlackやLINEで匿名相談窓口を設ける:言い出せない不満を事前に拾うチャネルを用意。
退職代行を“防ぐ”のではなく、「使う必要がない」と感じてもらえる会社であることが最大の予防策です。
まとめ:契約書で退職代行は制限できない。されない職場を設計せよ
退職代行を禁止する契約書や就業規則は、法的には無効になりやすく現実的ではありません。
重要なのは、「使わせない仕組み」ではなく「使う必要がないと思われる職場環境」をつくることです。
- 信頼できる上司
- 引き止められない退職風土
- メンタル不調を早期察知できる仕組み
こうした“人と人との関係性”が整っていれば、退職代行は自然と減っていきます。