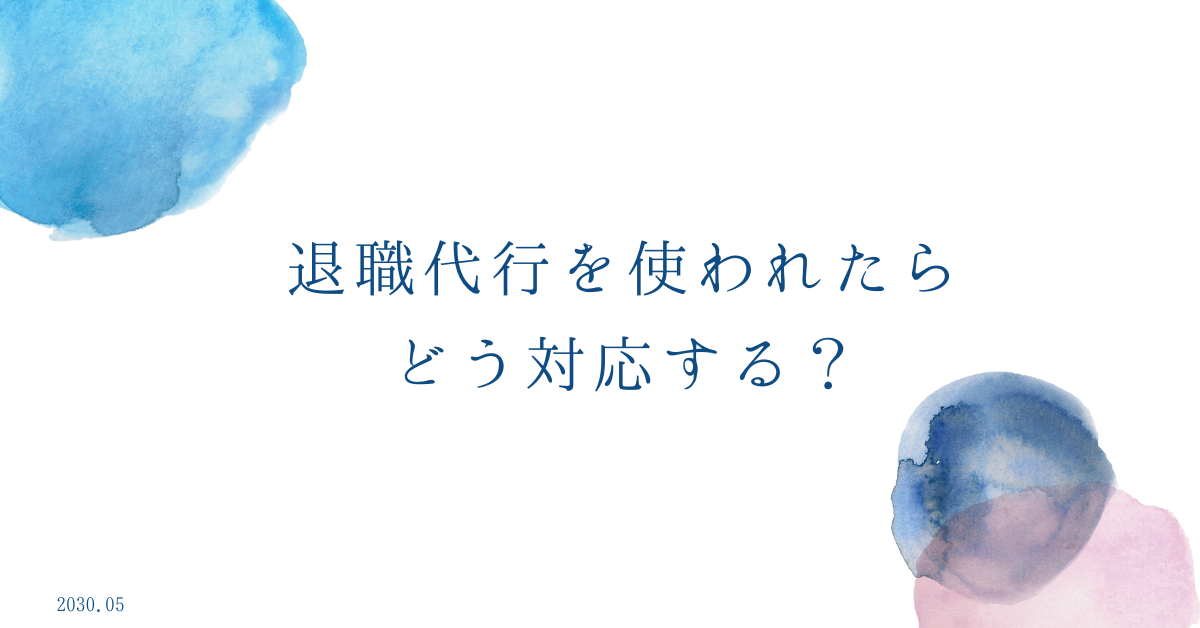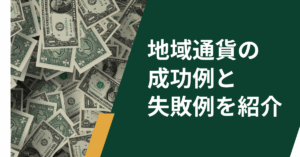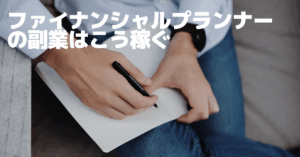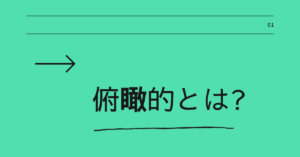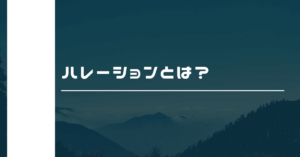突然、社員本人ではなく“退職代行業者”から「退職の連絡」が届いたら、企業としてどう対応すればいいのか。
感情的になったり、法的にグレーな対応をとってしまうと、訴訟リスクや企業イメージの悪化にもつながりかねません。
本記事では、退職代行を使われた際に会社が取るべき対応、やってはいけないNG行動、さらに防止のための体制整備まで網羅的に解説します。
退職代行を使われた企業が最初に確認すべきこと
本人の退職意思が明確かを確認する
退職代行を通じて連絡があった場合でも、退職の意思が本人によるものであれば原則として法的に有効です。
民法627条では「雇用契約は、期間の定めがない場合、2週間の予告で解約できる」とされており、本人の意思表示が明確であれば退職を拒むことはできません。
※キーワード対策:「退職代行 法的リスク」「退職代行 使わせない」
代理人の正当性を確認する
退職代行業者が弁護士でない場合、代理交渉(有給の取得交渉や損害賠償など)には法的権限がないため、
あくまで「本人の伝言係」に過ぎないケースが多いです。
ただし、伝えられた退職の意思が本人のものであれば、会社側が拒否することはできません。
退職代行への対応で絶対にやってはいけないNG行動
1. 無視する・放置する
退職代行の連絡を「ふざけてる」「無視しておけば戻ってくる」と考えて放置するのは危険です。
- 労働基準法違反とみなされる可能性
- 社会保険・給与の手続き遅延によるトラブル
- SNSや口コミで企業名が広まり炎上するリスク
2. 「本人が来なければ無効」と言う
退職はあくまで意思表示です。出社の有無は関係ありません。
「退職は本人が直接申し出ないと無効」とする対応は、違法対応にあたる可能性があります。
※キーワード対策:「退職代行 NG対応」
3. 引き止め・脅迫・損害賠償請求を持ち出す
たとえ急な退職で業務に支障が出るとしても、社員に責任を問う姿勢は逆効果です。
- 「訴えるぞ」「損害賠償を請求する」などの発言はパワハラ認定リスク
- SNSやメディアに拡散されやすく、企業ブランドに致命傷を与えることも
退職代行への正しい対応フロー【実務編】
ステップ①:業者からの連絡内容を記録
- 送信元(業者名、連絡先)
- 本人の名前、退職希望日
- 委任状や代理権の有無(弁護士名義か否か)
記録を残すことで、万が一トラブルが発生した場合の法的証拠になります。
ステップ②:必要書類を整備し、郵送で対応
- 離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などを本人住所に送付
- 貸与物の返却依頼は丁寧に文書で行う(脅迫口調NG)
ステップ③:就業規則に基づいた手続き処理
退職日を就業規則に従って設定し、勤怠・社会保険・給与処理を行います。
無断欠勤ではなく「退職」として正規処理するのが基本です。
【制度整備編】退職代行を“使わせない”ための職場づくり
本質は「制度」ではなく「信頼関係」
退職代行が使われる背景には、上司への不信感・職場の閉鎖性・パワハラ気質などが影響しています。
- 定期的な1on1面談の導入
- 引き止め文化を見直す
- 退職の申し出ができる心理的安全性の確保
※キーワード対策:「退職代行 使わせない」
「退職の意思表示」に関する社内ガイドラインを整備
禁止はできなくても、手続きを明確化することで抑止効果は見込めます。
就業規則例文:
「退職を希望する場合は、原則として直属の上司または人事担当者へ、口頭または書面にて通知するものとする。代理人を通じる場合は、本人の意思であることを証明する書面の提出を求めることがある。」
※キーワード対策:「退職代行 就業規則」「退職代行 禁止 契約書」
退職代行が続出する企業に共通する“組織課題”
1. コミュニケーション不足
- 上司との会話がなく、辞意を伝えにくい
- ミスを責められる職場環境
- 人間関係の悪化を放置している
2. キャリア不透明性
- 評価制度がブラックボックス化
- 将来像が描けない
- 成果と報酬が一致しない
法的に抑えておくべき注意点まとめ
| 観点 | 会社側の対応ルール |
|---|---|
| 退職の意思表示 | 本人の代理人からでも法的に有効(民法627条) |
| 無視・拒否 | 違法リスクあり。速やかな対応が求められる |
| 退職日は? | 基本的に申し出から2週間後(または就業規則に基づく) |
| 書類の返送 | 本人宛に速やかに郵送。返送拒否はNG |
| 有給取得 | 弁護士でない業者による請求は断っても問題なし |
まとめ|退職代行は「排除」ではなく「予防」へ
退職代行の使用は、単なる離職手段ではなく組織との信頼が崩れた結果とも言えます。
だからこそ、企業側がやるべきは排除ではなく、「使う必要のない職場環境づくり」です。
- 感情的な対応はリスクを拡大するだけ
- 就業規則の整備は「明文化」で抑止に
- 普段の関係性・心理的安全性の確保が最大の対策
経営者・人事の方は、目の前の1件の対応をこなすだけでなく、「なぜ使われたのか」に目を向けて、根本的な改善を進めていくことが求められます。