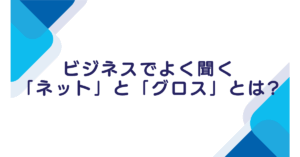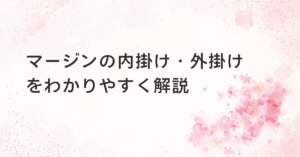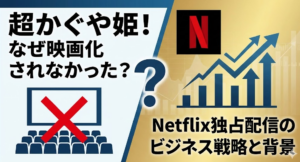「庭師の仕事に興味があるけれど、収入が少ないって本当?」「実際にどれくらい稼げるの?」そんな疑問を抱える方は少なくありません。伝統技術と自然との共存を体現する庭師という職業は、近年では芸術性やライフスタイルの観点からも再評価されています。一方で、収入の不透明さや業界の体質から“やめとけ”とさえ言われることもあるのが実情です。本記事では、庭師・造園業界の年収実態から、1000万円以上を目指すためのキャリア戦略まで、具体的かつ現実的な視点で掘り下げていきます。
庭師の平均年収の実態と業種ごとの違い
一般的な統計によると、庭師の平均年収はおよそ300万〜400万円台にとどまっています。しかしこれは、全国平均として幅広い年齢・経験層を含めた数字であり、都市部と地方、雇用か自営かでも大きく変動します。
たとえば、造園会社に勤務している場合、新卒で月給20万円前後が一般的です。そこから年数を重ねて経験を積んでも、昇給は緩やかで、10年働いても月給30万円前後というケースも多く見られます。一方、住宅地を中心に個人宅の定期管理を請け負う自営業者は、案件の数と単価によって年収が大きく上下します。都市部でリピーターを抱える職人の中には、月に60万円以上を安定的に稼ぐ人もいます。
また、公共事業に強い造園会社や、ゴルフ場・ホテル・寺社の専属契約を持つ事業者では、年収が500〜700万円台に届くこともあります。つまり、「庭師は稼げない」という声は一部の環境に限定されたものであり、業種・働き方・地域性を総合的に見る必要があるのです。
なぜ「造園業はやめとけ」と言われるのか?その理由と現実
インターネット上では「造園業 やめとけ」というネガティブな検索キーワードが目立ちます。こうした意見の背景には、過酷な労働環境と報酬のアンバランスが挙げられます。
たとえば、夏の猛暑や冬の極寒の中での作業、蚊や蜂との戦い、腰をかがめたままの長時間作業といった身体的な負荷があります。また、現場ごとの時間の制約や納期のプレッシャー、繁忙期と閑散期の落差の大きさも精神的に厳しい要因です。
それに対して、給与は経験に比してなかなか上がらず、福利厚生が手薄な小規模事業者も多いことから、待遇に不満を抱く若手が離職していく傾向があります。こうした構造的な問題が、「造園業は続かない」「やめとけ」と言われる要因となっています。
しかし一方で、それを上回るやりがいや自由度の高さに魅力を感じて長年続けている人も多く存在します。特に独立後の働き方や、デザイン性・アート性を重視した空間作りに価値を見出す職人は、造園を「天職」として捉えているのです。向き不向きがはっきりしている分、マッチすれば長く活躍できる仕事でもあります。
年収1000万の壁を越える庭師の働き方とは
一般的な庭師の年収から見ると、「1000万円を超える」ことは非常に高いハードルに思えるかもしれません。しかし、いくつかの条件をクリアできれば十分に現実的な数字です。
まず、自分のブランディングを確立し、指名制で仕事を受注できる立場になることが必要です。SNSやブログで実績を公開し、ビフォーアフターの写真やお客様の声を発信していくことで、口コミと紹介の連鎖が起きやすくなります。
さらに、単価の高い案件を中心に受けること。一般的な庭木の剪定では1件あたり1〜3万円程度ですが、庭園設計や特殊な施工管理、年間契約のメンテナンスなどでは10万〜100万円規模の受注が可能です。こうした仕事を月に2〜3本こなすだけでも、年間1000万円のラインが見えてきます。
加えて、スタッフや外注を活用して「時間と収入の分離」を図ることも大切です。完全な一人親方だと稼働時間の限界=収入の上限になってしまいますが、施工管理や現場ディレクションに回ることで、より多くの現場を同時に動かすことが可能になります。
庭師で2000万円以上を稼ぐには何が違うのか?
年収1000万を越えるだけでも十分に高収入ですが、それをさらに上回る2000万円となると、経営者としての感覚が強く問われます。ここで重要なのは「スケールと仕組み」です。
具体的には、法人化しスタッフを雇い、年間契約で複数の施設管理やプロジェクトベースのデザイン施工を請け負うモデルが考えられます。さらに、造園資材の販売や、庭づくりに関する講演・講座・ワークショップといった副収入の仕組みを整えることで、収入の柱を複数持つ形が理想です。
また、設計+施工の一体型サービスや、インバウンド向けの体験型庭園プログラムなど、単価の高いジャンルにチャレンジしている庭師も存在します。こうした新規事業は収入だけでなく、業界全体の価値向上にもつながっており、自治体とのコラボや海外案件にも発展することがあります。
つまり、2000万円プレイヤーになるには「庭を作る」ことから一歩踏み出し、「価値をプロデュースする」視点が必要不可欠なのです。
独立・自営と会社員、収入面でどちらが得か?
庭師として働く上で「自営と会社勤め、どちらが得か?」というのは永遠のテーマです。収入だけに限れば、自営のほうが上限は大きく、稼げる可能性は高くなります。しかしリスクも増えます。
会社員の場合、月給制で安定した収入と社会保険・労災が完備されており、長期的な生活設計がしやすいというメリットがあります。一方、自営業者はすべての責任を自分で負う代わりに、自由な価格設定やスケジューリングが可能となり、売上の全てが自分の判断次第で伸びていきます。
実際には「3年勤めて独立」「一度フリーになったが会社に戻る」など、キャリアの中で立場を変える人も多くいます。どちらにも良し悪しがあるため、最終的にはライフスタイル・家族構成・経済的目標などによって最適解は変わってきます。
自営で成功するには、技術と営業、計画性、数字への強さが不可欠です。逆にこれらを苦手とする人は、良い職場を選んで長く勤める道を選んだ方が安定するでしょう。
求人の探し方とキャリアアップの現実的ルート
未経験から庭師になるには、まずは求人探しが第一歩となります。現在では、ハローワーク、求人サイト、地域の造園組合、公園管理会社など、さまざまな媒体に求人が出ています。
注意すべきは「何が学べる職場か」「将来的に独立を視野に入れられる環境か」を見極めることです。若手を使い捨てにする現場ではなく、丁寧な指導や現場管理、顧客対応まで経験させてくれる現場を選ぶと、その後の成長スピードがまるで違ってきます。
また、転職時には「造園技能士」「造園施工管理技士」といった資格が強力な武器になります。資格取得支援をしてくれる職場や、社外講習に参加できる体制があるかもチェックポイントです。求人票だけで判断せず、必ず職場見学や面談を通じて現場の雰囲気を確認するようにしましょう。
造園業に向いている人と、適性がない人の違い
向き・不向きがはっきりしている仕事として知られる庭師。どのようなタイプがこの業界に向いているのでしょうか。
まず間違いなく必要なのが「自然を好きになれる感性」です。雑草も害虫も天候も、すべてが仕事の一部であり、そこに愛情や興味を持てないと長続きしません。また、「体を動かすのが苦でない」「早起きや暑さ寒さへの適応力がある」など、肉体的な耐性も重要です。
さらに近年では、「お客様と接する力」「SNS発信力」「プレゼン力」も高く評価される要素です。現場だけではなく、人との接点をどう活かすかが、受注や信頼につながる時代になっています。
逆に、日々の気温変化に弱い人、繰り返し作業が苦手な人、即成果を求めがちな人には向いていません。結果が出るまでには地道な経験と実績が必要な世界であることを、あらかじめ理解しておくべきです。
まとめ:庭師は夢のある仕事。収入もキャリアも自分で切り開ける
庭師は「稼げない」「きつい」と言われがちな仕事ですが、それは一面に過ぎません。適性があり、努力を重ね、情報発信やブランディングを行えば、年収1000万円以上も実現できる、実は可能性に満ちた仕事です。
キャリア戦略を持って動く人と、なんとなく続けている人とでは、5年後10年後に大きな差がつきます。資格取得、経験値の積み上げ、顧客対応の丁寧さ、SNS発信など、小さな積み重ねが高収入へと繋がっていくのです。
「庭づくり」で人の暮らしを豊かにしながら、自分自身の人生設計もデザインしていける職業。それが庭師です。今の収入に疑問を感じている方も、これから目指す方も、ぜひ自分なりの戦略を描いて、収入と誇りを両立できる庭師のキャリアを築いていってください。