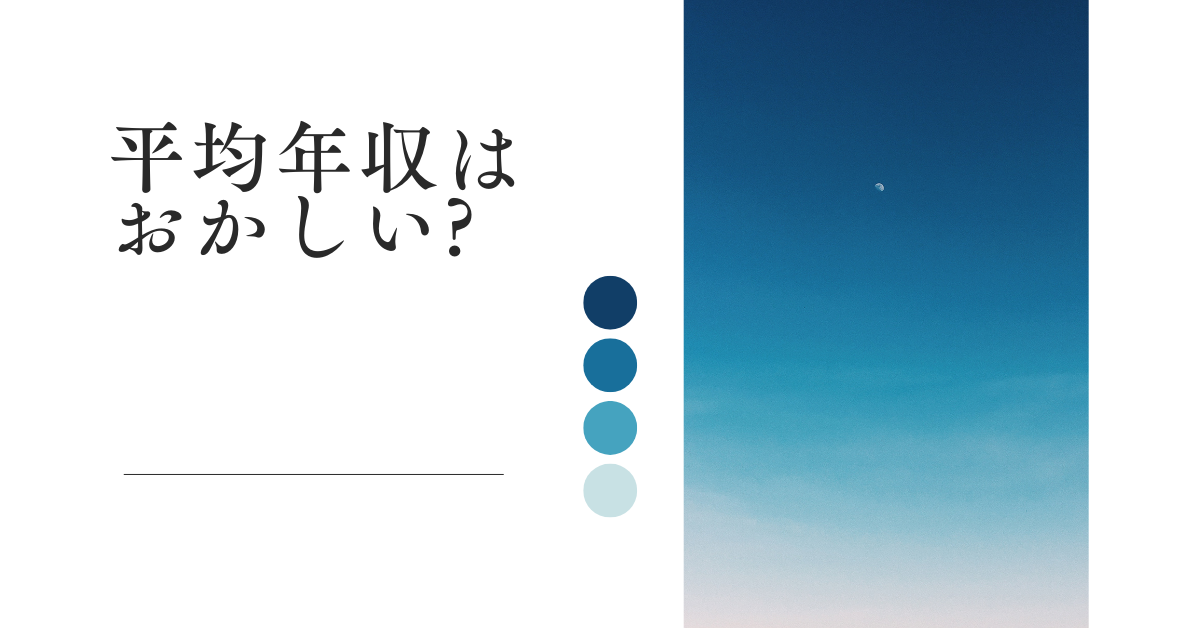「自分の年収は平均より低いのでは?」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか。
ところが、この“平均年収”という数字は、私たちが思っているよりもずっと“現実とかけ離れた指標”なのです。
平均値と中央値の違いを知らないままニュースやSNSの数字を信じてしまうと、実際よりも「自分が低い」と錯覚する人が続出します。
この記事では、「平均年収はおかしい」と言われる理由をデータと構造から紐解き、あなたの年収感覚を正しくアップデートする方法を詳しく解説します。
平均年収がおかしいと感じるのはなぜか
「平均年収ってどうもおかしくない?」——SNSや知恵袋でもそんな声をよく見かけます。
たとえば「平均年収は460万円」と報じられても、「そんなにもらっている人、周りにいない」と違和感を覚える人がほとんどです。
このズレの正体は、“平均値”という数字の構造そのものにあります。
平均値は「一部の高所得者」に大きく引っ張られる
平均年収は、すべての人の年収を合計して人数で割った数字です。
たとえば100人のうち99人が年収400万円で、1人だけが1億円の場合、平均年収は約500万円を超えてしまいます。
つまり、少数の高所得者が全体の数字を底上げしてしまうのです。
この構造があるため、「平均年収」は一般的な感覚より高く出やすく、実際の“多くの人の収入感”を反映していません。
そのため「平均年収 低すぎ」や「平均年収 高すぎる」という真逆の議論がネット上で飛び交うのです。
平均値だけで語られる“格差の錯覚”
もう一つの問題は、メディアやSNSが“平均値のみ”を切り取って報じていることです。
ニュースで「日本人の平均年収は458万円」と聞くと、誰もが「自分の年収と比較」してしまいます。
しかし、その比較基準がそもそも正しくない。
同世代や同業種の中央値を知らないまま平均値を見れば、ほとんどの人が「自分は下」と錯覚してしまうのは当然です。
こうした数字の構造的な誤解が、「平均年収はおかしい」という感覚を生み出しているのです。
平均年収と中央値の違いを正しく理解する
平均年収のズレを理解するうえで欠かせないのが、「中央値(ちゅうおうち)」という概念です。
これは年収を高い順・低い順に並べたときの“真ん中の人の年収”を指します。
平均と違って、極端な高収入者の影響を受けにくいのが特徴です。
中央値こそ“リアルな年収水準”を示す
実際、国税庁が毎年公表している「民間給与実態統計調査」では、平均年収と中央値に明確な差があります。
例えば令和5年(2023年)のデータでは次の通りです。
- 平均年収:約458万円
- 中央値:約373万円
なんと、約85万円もの差があります。
つまり、平均だけを見て「みんな500万円近くもらっている」と思い込むと、現実より1割以上ズレた感覚になってしまうのです。
また、同調査によると30代の中央値は以下の通り。
- 30代男性の年収中央値:約430万円前後
- 30代女性の年収中央値:約320万円前後
SNSで「平均年収500万」と聞いて落ち込む必要はありません。
実際には、多くの人が“中央値”付近の年収帯にいます。
これが、「平均年収はおかしい」と言われる最大の理由なのです。
年代別で見る中央値の現実
中央値は世代によっても異なります。年齢を重ねても右肩上がりとは限りません。
| 年代 | 平均年収 | 中央値年収 |
|---|---|---|
| 20代 | 約350万円 | 約300万円 |
| 30代 | 約450万円 | 約370万円 |
| 40代 | 約520万円 | 約430万円 |
| 50代 | 約580万円 | 約470万円 |
このように、どの年代でも中央値は平均値より一段低い位置にあります。
つまり「平均より低い」人が多数派であり、「平均付近に届かない=負け組」では決してないのです。
平均年収の“おかしさ”を生む3つの構造的な理由
平均年収の数字が実態とズレている背景には、統計の取り方や社会構造の変化が関係しています。
ここでは特に重要な3つの要因を整理します。
1. 高所得者層の影響が強すぎる
企業経営者や上場企業の役員、外資系エリートなど、上位1%の高所得者が全体の平均を大きく引き上げています。
たとえば、年収1億円の人が100人のうち1人混ざるだけで、平均は数十万円上がってしまいます。
日本では所得分布が二極化しているため、この影響が顕著です。
2. 非正規雇用が含まれている
国税庁の調査では、パート・アルバイト・契約社員も「給与所得者」として集計されています。
そのため、正社員の平均よりも大きく下がる傾向があります。
一方で、一部の高所得者が全体を引き上げるため、結果として“中間層の実感とかけ離れた数値”になるのです。
3. 業種・地域差が大きい
同じ年代でも、業界によって年収水準は驚くほど違います。
たとえば、金融・IT・製薬業界では600万円台が当たり前の一方、介護・小売・飲食では300万円台が一般的です。
地方と都市部の格差も大きく、東京と地方都市では同じ職種でも年収差が100万円以上あることも珍しくありません。
このように、平均年収の“おかしさ”は単なる数字の誤差ではなく、社会構造の歪みが生み出しているのです。
「平均年収 低すぎ」「高すぎる」と感じる心理の正体
ネット上では「日本の平均年収、低すぎ!」という声と、「この数字、高すぎるだろ!」という声が同時に上がります。
一見、真逆の意見のように見えますが、どちらも“感覚のズレ”が原因です。
平均年収を「低すぎ」と感じる人の特徴
- 海外の給与水準と比較している
- 都市部の物価や生活費を基準にしている
- 物価上昇に対して賃金が上がっていない
たとえば、アメリカの平均年収(中央値)は約600万円、日本は約370万円。
数字だけを見ると「日本は低すぎ」と思えますが、社会保障や物価、勤務時間の違いを考慮すると単純比較はできません。
平均年収を「高すぎる」と感じる人の特徴
- 自分や周囲の年収が中央値以下
- 非正規雇用や地方勤務が多い
- SNSで“高収入層”ばかりが可視化されている
特に「平均年収 おかしい 知恵袋」などで検索される意見には、「そんなに貰っている人いない」「自分の周りと違いすぎる」といった声が多く見られます。
これは平均値が“上位層に引っ張られた数字”だからこそ起きる自然な現象です。
大卒の平均年収はおかしい?学歴よりも職種格差が深刻
「大卒の平均年収は500万円」といった情報を見て、「そんなにもらえない」と感じたことはありませんか?
実はこの違和感も、職種や働き方の違いが原因です。
学歴別よりも“職種別”の差が大きい
文部科学省や厚労省のデータによると、大卒の平均年収はおよそ480〜520万円。
しかしこの数字には、上場企業や専門職が多く含まれています。
実際の中央値で見ると、大卒全体の年収は約420万円前後に落ち着きます。
一方、高卒でも技能職や営業職で500万円以上稼ぐ人もいます。
つまり「学歴=年収の差」よりも、「業界・職種・地域」の影響の方がはるかに大きいのです。
平均年収だけを信じると、キャリア選択を誤る
たとえば「IT業界の平均年収600万円」と聞いて転職したとしても、実際には新人や事務職では400万円前後が現実。
平均値は“中堅〜管理職”を含んだ数字なので、実際のスタート地点とはズレがあるのです。
このように、平均値を基準にキャリアを選ぶと「思っていたより稼げない」というギャップに陥る危険があります。
数字の裏側を理解することが、納得のいく働き方を選ぶ第一歩です。
平均年収の数字に惑わされず、自分の市場価値を把握する方法
「平均年収」ではなく、「自分の市場価値」を基準に考えることが大切です。
年収の比較ではなく、“どうすれば上げられるか”に視点を移すことで、数字の意味が変わります。
自分の市場価値を知る3つの方法
- 転職サイトの年収診断を使う
職種・スキル・地域を入力するだけで、あなたと同条件の人の年収中央値が分かります。 - 同業種の給与レンジを調べる
求人サイトで同職種・同経験年数の求人を見比べると、相場が明確になります。 - 社外評価を受ける
副業・業務委託など社外案件を試すと、自分のスキルが市場でどれほどの価値を持つかが実感できます。
こうした“市場基準”を知ることで、「平均年収」という曖昧な数字に振り回されなくなります。
大切なのは、“平均”ではなく“自分の基準”を持つことなのです。
まとめ:平均年収の数字は錯覚にすぎない。見るべきは「中央値」と「自分の成長軸」
「平均年収はおかしい」と感じるのは自然なことです。
なぜなら、その数字は現実よりも上振れした“幻想的な指標”だから。
実際の生活水準を反映しているのは“中央値”であり、あなたの実感が間違っているわけではありません。
これからの時代、重要なのは「平均と比べてどうか」ではなく、「自分がどれだけ成長し、安定した収入を得られているか」です。
年収という数字は、あなたの価値を決める絶対的なものではありません。
数字に惑わされず、自分の軸を持ってキャリアを積み上げていくことが、最も確実な“格差から自由になる方法”です。