「JAを通して出荷しているけど、思ったより手元にお金が残らない……」
そんな声を、多くの農家の方から耳にします。JA(農業協同組合)は流通の効率化や販売ルートの確保といった面で農業を支えてきた存在ですが、収益面で“中抜き”が問題視されることも。この記事では、農協経由の販売でどれほど利益が削られるのか、その仕組みと背景をわかりやすく解説します。また、JAを通さずに販路を確保する方法についても紹介します。
JA(農業協同組合)とは何か
農協の役割と成り立ち
農協(JA:Japan Agricultural Cooperatives)は、農家が個別に行うには難しい販売・仕入れ・金融・保険などの業務を、共同で支援する仕組みです。戦後の食料事情や農業政策の中で、農家を守るためのインフラとして構築されました。
- 出荷先の確保(市場や小売との取引)
- 肥料・農薬・資材の一括仕入れ
- 農業融資や共済(保険)の提供
などを担い、特に高齢化が進む農業現場にとっては“面倒なことを任せられる存在”として重宝されています。
全国組織でありながらローカル単位で運営される構造
JAは全国組織(JA全中、JA全農など)ではありますが、実際の運営は地域単位。各地域JAごとに手数料体系や支援内容、販路も異なるため、「どれくらい儲からないか」は地域によって差があります。
JAを通すとどれくらい“中抜き”されるのか?
手数料の内訳と収益構造の実態
JAを通して農産物を販売すると、以下のような手数料が差し引かれます。
| 項目 | 概要 | 割合の目安 |
|---|---|---|
| 販売手数料 | 出荷物の販売代行に対する手数料 | 約10〜15% |
| 共同選果・包装料 | 共選施設での仕分け・パッキング | 約5〜10% |
| 出荷手数料 | 出荷時にかかる運送・流通コスト | 約5%前後 |
例:100万円分の出荷をした場合
👉 手数料合計で約20〜30万円が差し引かれ、農家の手取りは70〜80万円前後
※JA全農の公開資料や実際の農業簿記データ(※1)をもとに再構成
エビデンス出典
なぜ手数料が高いのか?JAの論理と現実
JAが提供する“代行サービス”のコスト構造
JAは単なる販売窓口ではなく、「流通」「選果」「請求管理」「未収回収」などの機能を担っています。そのため、「自分でやるには難しい業務」の代行費用として手数料が発生するのは当然の側面もあります。
職員の人件費・施設維持費が手数料に含まれる
JA職員の給料や選果場・集荷場の光熱費も、農家からの手数料によって賄われています。いわば、農家が“JAという組織そのもの”を支えている形です。
農協を通さずに農家が直接販売する方法とそのメリット
直販(直売所・マルシェ・ネット販売)
JAを通さずに販売する「直販」は、農家自身が価格を設定できるため、手取り率が大幅に上がります。
メリット
- 手数料がかからず、利益率が高い
- 消費者と直接つながれる
- リピーターやファンがつきやすい
デメリット
- 梱包・発送・販売促進などの手間がかかる
- 在庫・返品リスクの管理が必要
飲食店・加工業者との直接取引
飲食店や地元の加工業者との契約販売も選択肢のひとつ。大量出荷が見込めるため、安定収益につながりやすい。
実例:北海道の小規模農家が、Instagram経由で地元レストランと契約し、JA経由の2倍の単価で野菜を出荷(※農業総合研究所レポート)
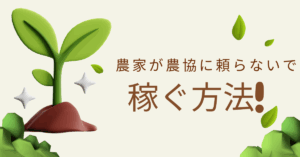
JA離れが進む背景と新たな農業マーケティング
若手農家を中心に「JA依存からの脱却」傾向
SNS活用や自社ECサイト開設によって、自分で販路を築く若手農家が増えています。特に「規格外品でも価値をつけられる」直販ルートは魅力的。
クラウドファンディング・サブスク型農業も登場
- CAMPFIREなどを活用して、農作物の先行予約販売
- 「定期便」モデルでファンに毎月出荷
こうした仕組みはJAでは提供できないため、独自販路の構築と差別化に役立ちます。
それでもJAを使うべき理由はある?
高齢者や規模の大きい農家にとっての利便性
- 集荷・請求管理・販売代行まで一気通貫
- 規模の大きい農家はJA経由の安定出荷で計画的に経営しやすい
また、JAは台風など災害時の保険対応や共済制度の窓口としても有用です。
JAを通すメリットとデメリット
JAを通して出荷・販売することで「手数料が引かれて儲からない」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、その仕組みや背景を正しく理解すれば、JAを使うべきケースも見えてきます。ここでは、JAを通すことで得られるメリットと、逆に注意すべきデメリットを詳しく見ていきましょう。
JAを通すメリット
1. 安定した販売ルートの確保
JAには既に確立された販路(市場・小売店・卸業者など)があるため、農家が営業活動を行わなくても販売が成立します。特に出荷量が多い農家にとっては、安定供給できる仕組みは大きな利点です。
2. 集荷・選果・出荷作業を一括で任せられる
JAでは、農産物を一括で集荷し、選果場で等級分け、パッケージング、発送まで行ってくれます。個人では手間のかかる作業を効率化できるため、「農作業に集中できる」という安心感があります。
3. 売上の請求・入金管理を代行してくれる
代金回収、未収金の督促、月次の入金処理など、販売に付随するバックオフィス業務をJAが代行してくれます。農業経営において「売ることに専念できる」のは大きなポイントです。
4. 資材購入や金融支援との連携がスムーズ
JAを利用する農家は、農業資材の共同購入や、JAバンクからの融資、共済(保険)などもスムーズに利用できます。これにより、資金繰りやリスクヘッジの面でも恩恵があります。
5. 災害時・病害虫発生時のサポートが受けられる
JAは行政や農業改良普及センターとも連携しており、自然災害や病害虫被害への対応支援、再建のための助言や支援制度の案内など、農家を守るインフラ的な役割も果たしています。
JAを通すデメリット
1. 高い販売手数料が利益を圧迫
販売手数料や共選手数料、出荷手数料などを含めると、売上の20〜30%が差し引かれるケースもあります。例えば100万円の売上でも、実際の手取りは70〜80万円程度になることも少なくありません。
2. 市場価格に連動するため単価が安定しない
JAは市場流通が主な販路となるため、農産物の価格は相場(需給バランス)に強く左右されます。時期によっては採算が取れないほど安値で買い取られることもあります。
3. 等級や出荷規格が厳しい
「形が悪い」「大きさが揃っていない」といった理由で、せっかく育てた作物がB品やC品として低価格で扱われることがあります。規格外品の扱いが厳しく、ロス率が高くなる傾向があります。
4. 決済タイミングが遅いケースがある
JA経由での売上入金は、月末締め・翌月払いなど、タイムラグが生じることがあります。キャッシュフローに余裕がない農家にとっては、資金繰りに注意が必要です。
5. 自由な価格設定・ブランディングができない
JA経由の販売では、商品単価は市場価格やJAの決定価格に従うため、ブランド農産物としての付加価値をつけにくい面があります。「◯◯さんが作った野菜」ではなく、「農協ブランド」として流通するため、個人のファンや直販力は育ちにくいという側面もあります。
結論:儲かるかどうかは「販路戦略」と「自分のリソース次第」
農協を通すことで得られる安心・効率もあれば、手数料という“コスト”の代償もある。
一方、JAを通さずに販路を開拓するには、マーケティング力やITリテラシーが求められます。
👉 選択肢は一つではなく、「JA×直販のハイブリッド戦略」が現代農業の現実解といえるかもしれません。
































