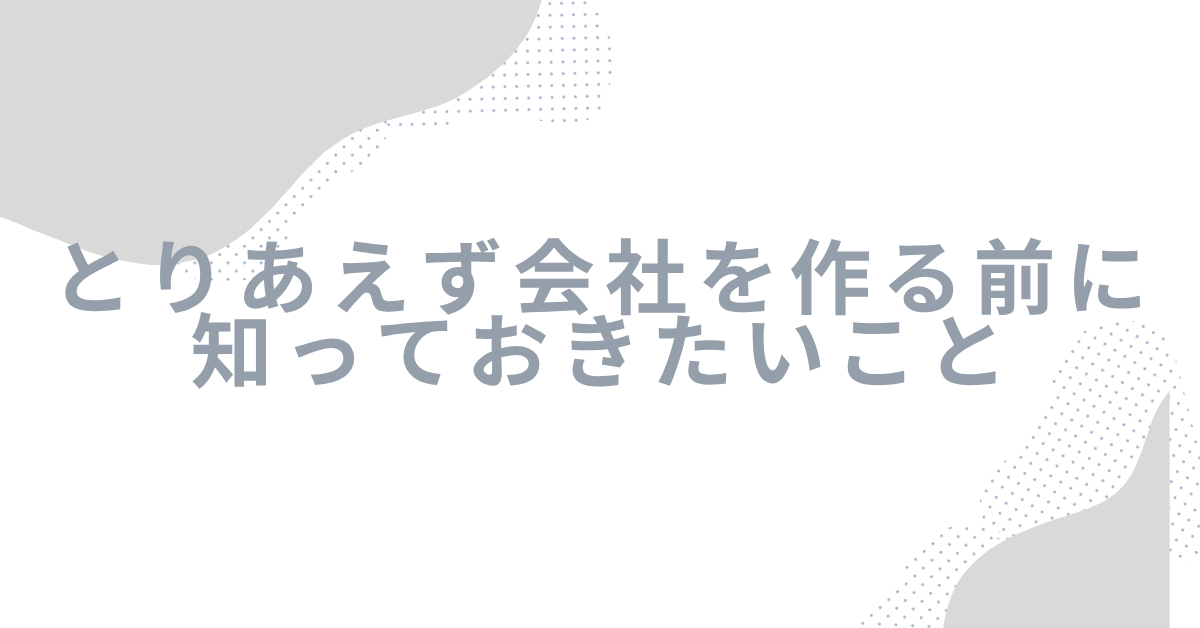「とりあえず会社を作れば節税できる」「法人にすれば社会的信用が上がる」──そんな話を一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
確かに、法人化はビジネスの信頼を高めたり、経費計上の幅を広げたりと、多くのメリットがあります。
しかし、目的や準備をせずに“とりあえず会社を作る”のは、節税どころかリスクになることもあるのです。
この記事では、「なんの会社を作るか」決まっていない状態で法人化を考えている人に向けて、設立前に押さえるべき注意点・節税の現実・放置した場合のリスク・一人法人の具体的な手順まで、実例を交えて徹底解説します。
読めば、会社を作るタイミングと目的が明確になり、後悔のない判断ができるはずです。
なぜ「とりあえず会社を作る人」が増えているのか
SNS時代が後押しした「とりあえず法人化」ブーム
ここ数年、Twitter(現X)やYouTubeなどで「節税したいなら法人化」「年収800万円超えたら会社を作れ」といった情報が拡散されています。
これに刺激されて、事業が安定していない段階でも**“とりあえず法人を作っておこう”という流れ**が生まれました。
また、マネーフォワードやfreeeのようなクラウド会計ソフトが普及し、登記から経理までワンストップでできる環境が整ったことも大きな要因です。
法務局に出向かなくてもオンラインで定款を作成でき、実質10万円程度で誰でも会社を設立できる時代になりました。
一方で、「設立は簡単でも維持が難しい」という現実を知らずに登記してしまい、後悔するケースも増えています。
たとえば、税理士なしで放置した結果、申告漏れや延滞金が発生して数十万円の損失になったり、休眠会社として強制解散になったりする例も少なくありません。
「なんの会社を作るか」が曖昧なままでは失敗しやすい
「なんの会社を作るか」を決めずに登記するのは、家を建てる前に土地だけ買って放置しているようなものです。
実際、法人設立後に次のような後悔をする人が多いです。
- 「物販をやるつもりだったけど、コンサルも始めたくなった。定款を変更するのに費用がかかった」
- 「登記したのに全然事業が動かせず、毎年7万円の法人住民税だけ払っている」
- 「仕事がない状態で会社を放置したら、休眠手続きが必要だと後から知った」
会社を作るという行為は“スタート”ではなく“責任の始まり”でもあります。
定款(会社の基本ルール)には事業内容を明記する必要があり、「とりあえず」で設立すると、後で変更手続きが面倒になります。
とりあえず会社を作ると得する?節税のリアルな実態
法人化で節税になるのは「年収800万円を超えた人」から
多くの人が「法人にしたら税金が減る」と考えていますが、それは半分正解で、半分間違いです。
節税効果が出るかどうかは、年間所得・経費・家族構成・社会保険の有無によって変わります。
たとえば、個人事業主として年収1000万円、経費が200万円なら、課税所得は800万円。
所得税・住民税を合わせると約250万円の税負担です。
一方で、これを法人化し、役員報酬600万円+会社利益200万円に分けると、
法人税+所得税を合わせても約180万円前後に抑えられるケースがあります。
つまり、80万円前後の節税効果が期待できるのです。
このように、法人化が有利になるのは年収800万円を超えたあたりから。
それ以下の所得の場合、社会保険料や顧問料の負担が増え、結果的にトータルコストが上がることもあります。
節税目的だけで会社を作るのは危険
節税目的だけで会社を作ると、次のようなリスクがあります。
- 顧問税理士費用(月2〜3万円)がかかる
- 決算申告のたびに10万円前後の費用が発生する
- 社会保険料が強制加入となり、個人より負担が増える
- 事業がないのに毎年7万円の法人住民税が発生する
特に「会社設立 仕事 ない」状態で放置すると、税金だけが積み重なっていきます。
税理士が関与していないと、“無申告”扱いで青色申告の取り消しや延滞金発生に至ることもあります。
節税は確かに魅力的ですが、「事業を継続できる前提」で初めて意味を持つものです。
逆に言えば、まだ売上が安定していないうちは、個人事業のまま経費管理を最適化する方が安全です。
一人で会社を作る方法と実際の手順
一人で会社を作るにはどんな準備が必要か
「一人で会社を作る 手順 知恵袋」と検索する人が多いように、
いまや法人設立は行政書士や司法書士に頼まなくても、自力でできます。
ここでは一人で株式会社または合同会社を設立する流れを紹介します。
ステップ1:会社の形態を決める
- 信用を重視するなら「株式会社」
- 費用を抑えたいなら「合同会社」
合同会社は印紙代不要・設立費用6万円前後、株式会社は約20万円前後です。
ステップ2:会社名と所在地を決定
自宅住所でも登記は可能ですが、信用を意識するならレンタルオフィスやバーチャルオフィスも検討しましょう。
ステップ3:定款作成
定款には「事業目的」を明記します。
たとえば「コンサルティング業」「輸出入業」「広告代理業」など、将来的に拡大する可能性を踏まえ、幅広く書くのがポイントです。
ステップ4:資本金の入金
資本金は最低1円から可能ですが、現実的には50万円〜100万円程度あると信頼を得やすいです。
銀行口座や取引先に提出する際、「資本金1円」だと不信感を持たれる場合があります。
ステップ5:登記申請
法務局に申請後、1〜2週間で登記が完了します。
その後、「登記事項証明書」「印鑑証明書」を取得すれば、会社名義の口座開設が可能になります。
一人で会社を作るメリットとデメリット
【メリット】
- 経費計上の範囲が広がる(家賃・通信費・車両費など)
- 取引先からの信用が増す
- 法人カードや融資が受けやすくなる
- 将来的な事業拡大がしやすい
【デメリット】
- 会計・申告が複雑になる
- 社会保険料が強制加入になる(年50万円以上の負担)
- 毎年法人住民税7万円が発生
- 仕事がなくても申告義務がある
つまり、「経営を始める覚悟がある人」にとってはチャンスですが、
「様子を見たいだけの人」にとっては、維持コストの重荷になりかねません。
会社を作って放置したらどうなるのか
登記後に放置した場合の実際のリスク
「会社を作って放置しても問題ない」と思っている人は要注意です。
会社を登記した時点で、あなたは“法人代表”として以下の義務を負います。
- 毎年の決算・税務申告
- 法人住民税(赤字でも7万円)
- 会社名義の社会保険・年金の届出
- 法務局への登記事項変更
もし申告をせず放置すると、税務署は「非申告法人」として監視対象にします。
数年後、突然「督促状」や「延滞金通知」が届くこともあります。
また、長期間登記を放置すると、法務局によって職権解散されることがあります。
再登記には裁判所の許可が必要で、数ヶ月と数万円単位のコストがかかります。
合同会社を放置した場合の結末
「合同会社 放置 どうなる」と検索する人も多いですが、
合同会社であっても放置は危険です。
12年以上登記が更新されないと「休眠会社」として解散登記されるほか、
銀行口座も自動的に凍結されるケースがあります。
また、税務署の法人番号システム上も「解散済み」扱いになり、再利用が困難です。
たとえば、ネットショップをやろうと考えて合同会社を設立し、何もせず放置した場合、
数年後に「新たに事業を始めたい」と思っても、その法人では再利用できず、新会社を立ち上げ直す羽目になるのです。
仕事がない状態で会社を維持する方法
「仕事がない=何もできない」ではない
設立直後に仕事がなくても、法人を動かす方法はあります。
たとえば、以下のような行動は「事業準備活動」として経費にできます。
- 取引先探し・営業活動・HP制作
- 名刺・ドメイン・広報費用
- 補助金・助成金申請の準備
つまり、「まだ売上がない=経営が止まっている」ではなく、
**「次の収益化のために動いている状態」**を作ることが大切です。
売上ゼロでも発生する義務と注意点
たとえ赤字でも、以下の手続きは毎年必須です。
- 法人税・県民税・市民税の申告
- 法人住民税(均等割)7万円の納付
- 決算書の作成(税務署提出用)
- 社会保険の届出(該当者がいなくても)
これを怠ると、青色申告が取り消され、翌年以降の節税メリットが失われます。
税理士をつけるのが難しい場合でも、クラウド会計ソフトで最低限の管理はしておきましょう。
「なんの会社を作るか」で決まる未来
「なんの会社を作るか」という問いは、会社経営の根幹です。
コンサル会社なのか、物販会社なのか、IT開発会社なのか──
目的を曖昧にしたまま設立すると、定款の事業目的がチグハグになり、
銀行口座開設や融資審査で落とされることもあります。
たとえば、
「通販サイトをやる予定だったが、実際は飲食コンサル中心になった」
という場合、事業内容の整合性が取れず、税務署や銀行が不信感を抱くのです。
会社の目的を言語化することは、自分のビジネスを整理すること。
法人化を考える前に、まずは「自分が誰に何を提供したいか」を明確にしましょう。
まとめ|会社を作るのはゴールではなくスタートライン
会社を作ること自体は、いまの時代とても簡単です。
ですが、その後の運営を継続できるかどうかで「成功する法人」か「負債になる法人」かが分かれます。
- 節税目的なら、利益が出てからでも遅くない
- 信用を得たいなら、目的を明確にして登記する
- 放置は「休眠」ではなく「リスクの先送り」
- 一人法人でも、責任は個人と同じように重い
「とりあえず会社を作る」こと自体は悪ではありません。
ただし、それをどう活かすかを考えずに登記してしまうと、税金・登記・保険といった維持コストに追われて終わります。
もし今、「作ろうか迷っている」段階なら、まずは3つの質問を自分に投げかけてください。
- なぜ会社を作りたいのか?
- 1年後にどうなっていたいのか?
- 維持に必要なコストを理解しているか?
この3つに明確に答えられた時こそ、法人設立のベストタイミングです。
勢いで作る会社ではなく、目的を持って動く会社を作れば、たとえ一人でも必ず軌道に乗せられます。