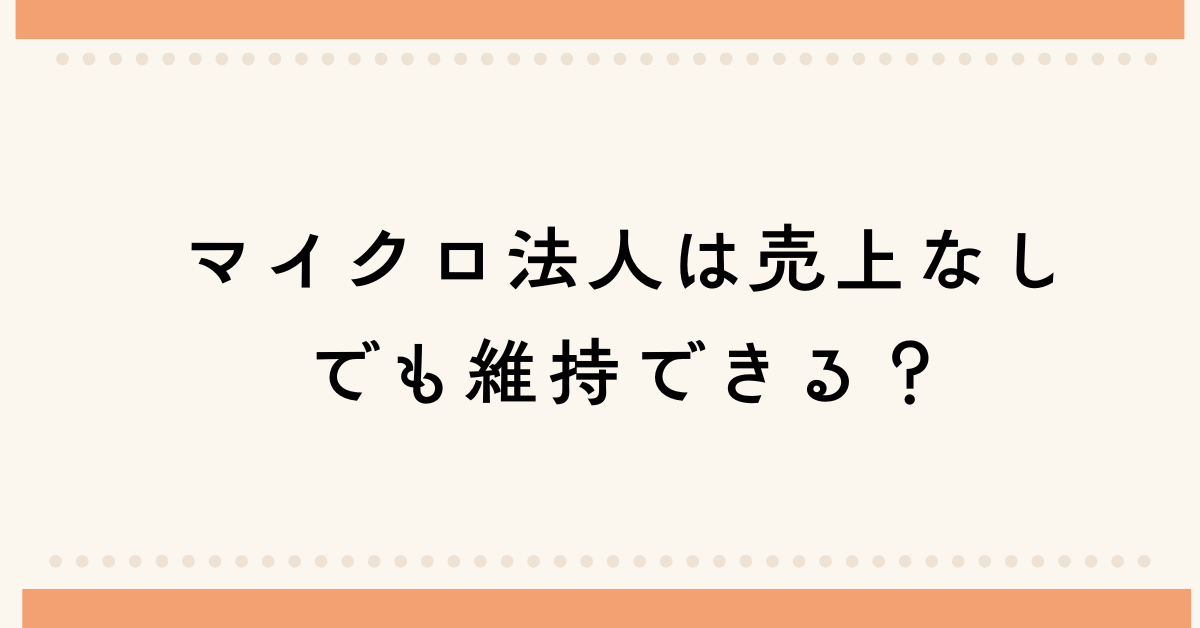マイクロ法人は売上なしでも維持できる?節税・社会保険・税務のリアルを徹底解説
「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えましたよね。個人事業主や副業をしている人の間では、節税や社会保険対策の手段として注目されています。
しかし一方で、「売上なしでも維持できるの?」「違法にならない?」「税金はどうなる?」といった疑問を抱く人も多いのが現実です。
この記事では、マイクロ法人を“売上なし”で運営しても大丈夫なのかを中心に、節税・社会保険・税務リスク・おすすめ事業モデルまで、実務レベルで詳しく解説します。
会社を作ってから後悔しないために、制度の“現実”を知っておきましょう。
マイクロ法人とは何か?小さな会社を作る意味
まず前提として、マイクロ法人とは「社員1〜2名で構成される小規模な株式会社または合同会社」のことを指します。
一般的に、代表取締役1名+形式的な役員1名(配偶者や家族)で設立されるケースが多く、事業規模よりも税務・社会保険上のメリットを目的に作られることが特徴です。
マイクロ法人が注目される背景には、次のような理由があります。
- 社会保険料の負担を最小限に抑えられる
- 所得を法人と個人に分けて節税できる
- 事業資金を会社名義で管理しやすい
- 個人の信用力(法人名義の口座や契約)を高められる
つまり、マイクロ法人は「実際の売上が小さくても、税金と社会保険を効率化できる仕組み」なんですね。
売上なしのマイクロ法人は維持できるのか?
売上ゼロでも法人を維持することは可能
結論から言えば、売上がゼロでもマイクロ法人を維持することは可能です。
日本の会社法では「活動していない会社を解散しなければならない」という規定はなく、登記・税務申告をきちんと行っていれば問題ありません。
ただし、「放置」と「維持」は全く違います。
売上がなくても、次のような最低限の義務は必ず発生します。
- 年1回の決算・法人税申告(売上ゼロでも必須)
- 県税・市民税(均等割)
- 社会保険や役員報酬の処理
特に法人住民税の**均等割(年7万円前後)**は赤字でも必ず発生します。
そのため、「売上なし=税金ゼロ」ではない点に注意が必要です。
放置するとどうなる?売上なし法人のリスク
「法人を作ったまま放置している」という人も少なくありませんが、これは非常に危険です。
放置状態のまま数年経過すると、次のようなリスクが生じます。
- 税務署から「申告していない法人」として調査対象になる
- 登記の更新が行われず「みなし解散」になる
- 銀行口座が凍結される、信用情報に傷がつく
- 将来的な補助金・助成金の申請資格を失う
実際に、マイクロ法人を設立したが「特に使っていない」人の中には、登記抹消や強制解散を経験したケースもあります。
つまり、「売上がなくても運営の手間はかかる」点を甘く見てはいけません。
売上なしでも社会保険には加入できるのか?
マイクロ法人と社会保険の関係を整理する
マイクロ法人を作る理由の一つに、「社会保険を安くするため」という考え方があります。
会社員と違い、法人代表者(役員)は報酬額を自由に設定できるため、たとえば年60万円(月5万円)とすれば、社会保険料も最低限に抑えられるのです。
ただし、ここで誤解されやすいのが「売上がなくても社会保険に入れるのか?」という点。
結論は、「入れるが条件次第」です。
法人を設立すると、自動的に社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所になります。
そのため、実際に報酬を支払っている場合は、たとえ売上がゼロでも加入義務が発生します。
売上なし+報酬ゼロの場合は加入義務なし
もしマイクロ法人が「売上なし・役員報酬なし」の状態であれば、
社会保険の加入義務はありません。
ただし、これは“暫定的な状態”として扱われるため、長期間続くと税務署から「実体のない法人では?」と疑われる可能性もあります。
たとえば、社会保険料を回避するためだけに形式的に法人を作った場合、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。
役員報酬の設定は“月5万円〜”が現実的ライン
マイクロ法人で売上がほとんどない場合でも、役員報酬は「ゼロ」ではなく、月5万円程度を設定するのが一般的です。
その理由は以下の通りです。
- 報酬を出さないと、法人としての経費処理ができない
- 社会保険に加入しないと「節税効果」が得られない
- 税務上「法人の実体がある」と認められにくい
実務的には、**「役員報酬5万円+売上ゼロでも最低限の維持が可能」**というケースが多いです。
もちろんその場合でも、法人税・住民税の均等割(年7万円前後)は支払う必要があります。
売上なしのマイクロ法人が後悔する理由
節税になると思っていたが、コストが上回る
「節税のためにマイクロ法人を作ったのに、かえって損をした」という声は非常に多いです。
その理由の大半は、法人維持にかかる固定コストを見誤ったことにあります。
たとえば、年間コストを具体的に見ると以下の通りです。
- 法人住民税(均等割):7万円
- 税理士報酬(決算申告):10〜15万円
- 社会保険料(最低ライン):年間約40〜50万円
- 登記関連費・通信費など:数万円
合計で年間60〜80万円の固定費が発生します。
これに対して売上がゼロ、または10万円程度しかないと、節税どころか赤字運営になるのです。
売上なし法人は「違法」と見なされることも
税法上、法人は「営利を目的として活動する団体」であることが前提です。
そのため、売上を出す意思もなく節税目的だけで法人を設立すると、違法または脱法とみなされるおそれがあります。
特に注意すべきは、次のようなケースです。
- 会社を作っても事業実態がない(取引先・契約・請求なし)
- 役員報酬を経費にして個人の税負担だけ下げている
- 社会保険料を不正に軽減する目的が明白
こうした運用は、税務署や年金事務所の調査対象になりやすいです。
実際に、「節税スキームとしてマイクロ法人を使った結果、追徴課税を受けた」例もあります。
売上なしでも合法的に運営するためのコツ
「おすすめ事業」を設定して事業実体を作る
マイクロ法人を安全に維持するには、売上が少なくても“事業の実態”を持たせることが重要です。
たとえば、次のような事業を設定しておくと、維持が容易になります。
- フリーランスの請負業(Web制作・デザイン・ライティングなど)
- コンサルティング・講師業
- 物販・EC運営
- YouTube・コンテンツ制作
- 不動産賃貸・管理業
これらは初期投資が少なく、在庫を持たないため、**「売上が少なくても事業継続が可能」**という点でマイクロ法人に向いています。
年に数万円でも“売上”を立てるのが安全
完全に売上ゼロだと、「実体がない」と見なされるリスクが高まります。
そのため、年に1回でも取引を発生させるように意識しましょう。
たとえば以下のようなケースでも十分です。
- 知人の依頼で請負作業を行い、報酬を得る
- 自社名義で小規模ECを運営し、少額販売を行う
- 登録型業務委託(クラウドワークスなど)で単発受注をする
このように、わずかな売上でも「事業として動いている」ことを示すことで、合法的かつ節税効果を維持しながら継続運営が可能になります。
売上なしマイクロ法人の確定申告と税金
売上ゼロでも決算申告は必須
売上がないからといって、決算をサボることはできません。
法人は「毎事業年度ごとに税務申告を行う」義務があるため、売上ゼロでも確定申告が必要です。
この場合、申告内容は「赤字決算」または「休眠扱い」として提出します。
申告を怠ると、青色申告の承認が取り消されたり、ペナルティとして延滞税が課される可能性もあります。
税理士を使わない場合の注意点
マイクロ法人の場合、「売上がないから自分で申告できる」と思いがちですが、法人税の申告書は非常に複雑です。
会計ソフト(freee法人会計・弥生会計など)を使っても、勘定科目の設定を誤ると後で修正が必要になります。
税務署は「売上ゼロ法人=節税目的」と見なして厳しく見る傾向があるため、
最低限、決算書作成だけは税理士に依頼することをおすすめします。
まとめ|売上なしのマイクロ法人は「維持できるが慎重に」
マイクロ法人は、節税や社会保険料削減の面で確かに魅力的です。
しかし、売上なしのまま放置すると“節税どころかコスト増・違法リスク”に繋がるという現実があります。
この記事の要点を整理します。
- 売上ゼロでも法人は維持可能(ただし申告・税金は必要)
- 役員報酬を月5万円前後に設定すれば最低限の運営ができる
- 売上ゼロ期間が長いと「実体なし法人」と見なされるリスクがある
- 年間60〜80万円の維持コストが発生する
- わずかでも“売上のある実態”を持たせることが安全
つまり、「節税のためだけの会社」は長く続かないということです。
マイクロ法人を活用するなら、少額でも収益が出る事業を用意し、
“法人としての信頼を育てていく”意識が大切ですよ。