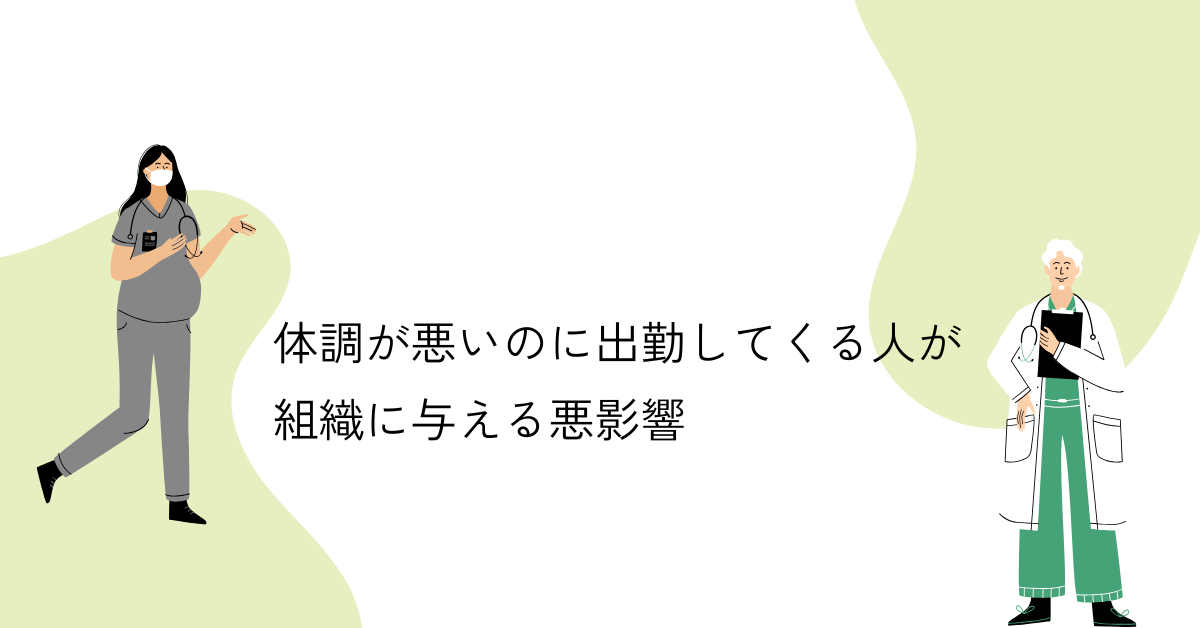働き方改革が叫ばれる中でも、「体調が悪いのに出勤してくる人」は少なくありません。一見すると責任感が強く、頑張り屋に見えるかもしれませんが、実はそれが組織にとって大きなマイナスとなることも。本記事では、体調不良で無理して出勤する人が抱えるリスクと、その行動が職場に与える悪影響について解説します。また、出勤圧の背景にある“隠れハラスメント”の構造や、健康的な職場づくりのヒントも紹介します。
なぜ体調が悪くても出勤するのか?
まずは、体調が悪くても出社してしまう人の背景を探ってみましょう。
無理してでも出勤する理由とは
- 「自分がいないと回らない」という過度な責任感
- 上司や同僚からの無言の圧力
- 有給が取りづらい雰囲気、制度的なハードル
- 出社しないと評価が下がるという誤解
体調不良を訴えにくい空気
特に日本の職場では「頑張っている姿勢」が評価されがちで、体調不良を正直に申告すると「甘え」と受け取られる風潮があります。
体調不良で出勤する“プレゼンティーズム”の弊害
出勤はしているけれどパフォーマンスが落ちている状態、いわゆる“プレゼンティーズム(Presenteeism)”。これが組織全体に深刻な影響を与えることがあります。
生産性の低下
体調不良のまま業務を行っても、集中力や判断力が鈍り、結果的にミスが増えたり、成果物の質が下がることに。
周囲への感染リスク
特に風邪やインフルエンザ、コロナなどの感染症にかかっている場合、出勤することで他の社員にもリスクを広げてしまいます。
職場全体の空気が悪くなる
「無理してでも来ている人」がいると、それを見た他の社員にもプレッシャーがかかり、職場全体が“休めない空気”になります。
「体調不良でも出勤」はハラスメントになりうる
実は、体調が悪くても出勤せざるを得ない状況は、“隠れハラスメント”の温床でもあります。
体調悪いのに出勤してくる人 ハラスメントの構造
- 無理して出勤する人が「他人も出るべき」と無言の圧をかける
- 上司が「そのくらいなら出社できるよね」と軽視する
- 同調圧力により、休む選択肢が消される
職場の雰囲気が連鎖的に悪化
結果的に、「体調不良 休まない人 迷惑」「体調悪いのに休まない人 コロナ」といった状態を招き、従業員の不信や離職率の増加にもつながります。
体調不良時の“出社美徳”はもう古い
コロナ禍で価値観が変わった
「体調不良 無理して出勤 コロナ」のように、パンデミック以降は出勤=責任感という考えはリスクとして認識されるようになりました。
休むべきときは休む文化づくり
- 体調不良時にリモートワークや有給取得を推奨する
- 「休む勇気」を評価する仕組みづくり
- 症状が軽くても休んだ人を責めない職場の風土
知恵袋でよく見る「体調悪いのに出勤してくる人」への悩み
掲示板サイトなどでは、以下のような声がよく見られます。
「明らかに風邪引いてるのに出勤してきて、マスクもせず咳してる同僚…正直迷惑」
「隣の席の人がインフル明けで出勤してきたけど、まだ調子悪そう。帰ってほしい…」
「体調悪いアピールしてくるのに出勤してくる人、かまってほしいの?」
これらは、「体調悪い 仕事 乗り切る」ための方法ではなく、他人への不安や不満として現れています。
健康的な職場のためにマネジメントができること
1. 勤怠制度の見直し
- 有給取得しやすい仕組みを整える
- 病気休暇や特別休暇制度の導入
2. 評価制度の改革
- 出社率や稼働時間でなく、成果ベースで評価する
- 「無理をして出勤する=頑張っている」という誤解を払拭
3. 上司・リーダーの意識改革
- 部下の健康状態に気を配る
- 休みを取ることの価値をチームに浸透させる
まとめ|休めない空気が一番の“病原体”
「体調悪いのに出勤してくる人」は、本人の責任感だけでなく、職場文化や人事制度にも原因があります。一見“頑張っている”ように見えて、実は職場全体を疲弊させる要因にもなり得るのです。健康的で生産性の高い職場づくりのためには、個人ではなく組織として“休める空気”を整えることが求められます。