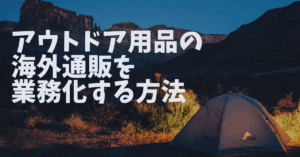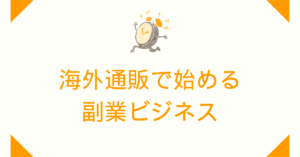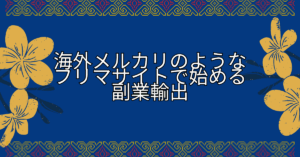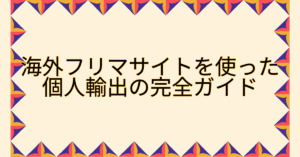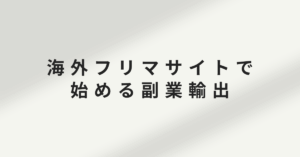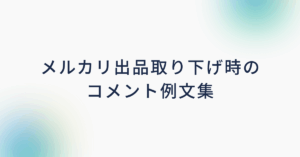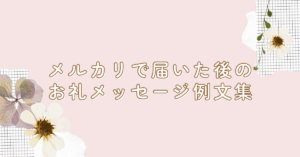古着転売は、低資金で始められる副業として注目されています。しかし、SNSやブログを見ていると「古着転売はやめとけ」「もう儲からない」といった否定的な声が目立つのも事実です。実際に始めた人の中には、数ヶ月で撤退してしまうケースも少なくありません。この記事では、なぜ古着転売がうまくいかないのか、どんな人が続けられるのか、そして失敗しやすいポイントと対策について、ビジネス視点から詳しく解説していきます。
古着転売が「やめとけ」と言われる背景
古着転売が「やめとけ」と言われる理由にはいくつかの現実的な背景があります。第一に、古着市場は参入障壁が低く、未経験者でも簡単に始められる一方で、競争が非常に激しい点が挙げられます。メルカリやラクマなどのフリマアプリを使えば、誰でも商品を出品できますが、それはつまり「ライバルが無限にいる」ということでもあります。
また、古着転売には多くの工程があり、単なる「不用品販売」とはまったく異なります。リサーチ、仕入れ、検品、クリーニング、撮影、出品作業、発送、顧客対応…これらをすべて一人で行う必要があるため、思っているよりも時間と体力が必要です。
さらに、フリマアプリの規約変更や手数料の見直しによって、利益率が徐々に下がっている現状もあります。特に送料の高騰は深刻で、小型商品であっても送料負担が大きくなり、「売ってもほとんど利益が出ない」というケースが増えています。
精神的にも、商品が売れない、クレームが来る、悪い評価がつくなど、想像以上のストレスを感じて辞めてしまう人も少なくありません。
メルカリで古着が売れない本当の理由
古着転売を始める人の多くが、まず出品先に選ぶのがメルカリです。しかし、「なかなか売れない」「売れても利益が少ない」という悩みを抱えて、数ヶ月で撤退する人も多くいます。なぜ古着が思うように売れないのか、その理由は一つではありません。
まず、競合が多すぎるという問題があります。メルカリのアクティブユーザー数は日本国内で数千万人とも言われており、出品数も膨大です。その中で自分の商品を目立たせるには、ただ出品するだけでは不十分で、写真の撮り方、タイトルの付け方、説明文の丁寧さなど、細かな工夫が求められます。
また、商品選びに問題があることも。たとえば、ノーブランドで状態があまりよくない商品は、いくら安くても売れづらく、仮に売れたとしても利益は薄いです。買い手は「同じ価格なら有名ブランドのほうが安心」と感じるため、仕入れの段階から戦略が必要です。
加えて、メルカリ独自の検索ロジックや「新着重視」の表示仕様も関係しています。時間が経った商品は埋もれてしまうため、こまめな再出品や価格調整、プロフの工夫など、アルゴリズムに合わせた対応も求められます。
ユーザーの間では「メルカリ 古着屋 うざい」というネガティブな声も見かけます。これは、大量出品やテンプレ化された説明文による不信感が背景にあります。ユーザー視点を忘れた出品方法は、ブランド価値を下げ、逆に売れにくくなる原因となります。
古着屋は儲からない?オンラインと実店舗の違い
「古着屋は儲からない。絶対に開業するな。」といった見出しの記事や動画が話題になることがあります。確かに、実店舗型の古着屋は初期投資が大きく、家賃、人件費、光熱費、内装費、什器購入など、経営にかかるコストが高いのが現実です。
加えて、実店舗は立地の影響を強く受けるため、集客に苦戦するケースも少なくありません。仕入れや在庫管理に失敗すれば、売れ残った在庫が利益を圧迫し、閉店に追い込まれるリスクもあります。
一方で、オンライン古着屋であれば、初期費用をぐっと抑えることができ、副業としても始めやすい環境が整っています。とはいえ、オンラインだからといって簡単に儲かるわけではありません。ネット上では写真と文章だけで商品の魅力を伝える必要があり、ブランディングやSNS運用、SEO知識などが必要とされる場面も増えてきています。
成功しているオンライン古着屋は、ニッチなジャンルに特化したり、配送スピードや梱包品質などに強みを持っていたりします。単なる「古着の寄せ集め」ではなく、「選ばれた品を届ける」という意識が必要です。
古着転売の仕入れ先とリスクの見極め方
古着転売の成否を大きく左右するのが「仕入れ先」です。どこから仕入れるかによって、商品の質や価格、そして利益率が決まります。主な仕入れ先としては以下が挙げられます。
リサイクルショップ(セカンドストリートやトレジャーファクトリーなど)は、実際に商品を手に取って状態を確認できるメリットがありますが、価格はやや高めで仕入れとしては難易度が高いです。
一方、古着卸業者は単価が安く、まとまった仕入れが可能ですが、状態の良し悪しが混在していたり、希望と異なるテイストの商品が届くリスクがあります。初心者には「運任せ」と感じる場面もあるかもしれません。
また、フリマアプリでの仕入れは、価格交渉が可能で意外な掘り出し物を見つけられる一方、転売を見越した価格設定がされている場合も多く、利益を出すには高い目利き力が求められます。
どの仕入れ先にも共通して言えるのは、「在庫リスク」と「目利きの力」が必要ということです。買ってから「売れない」となっては意味がないため、事前の市場調査や販売履歴の確認、トレンド分析などを怠ってはいけません。
古着転売のコツを知らずに始めると失敗する
古着転売を成功させるには、いくつかのコツを意識的に実践する必要があります。まず大切なのは「売れ筋商品の把握」です。どのブランド、どのカテゴリ、どの季節の商品が売れやすいのかをリサーチし、トレンドを先読みする力が必要です。
また、商品説明やタイトルの付け方にも工夫が必要です。単に「Tシャツ メンズ Mサイズ」ではなく、「ユナイテッドアローズ 半袖Tシャツ メンズM 美品 ブラック 夏物」など、検索にかかりやすく、購入意欲を刺激するような言葉選びが大切です。
写真の質も重要です。床置きのシワだらけの写真よりも、ハンガーにかけて撮ったり、背景を白で統一したりするだけで、印象が大きく変わります。スマホでも十分きれいに撮れるので、撮影環境を工夫するだけでも売れ行きが変わります。
出品後の対応も見落としがちですが、コメント返信や発送の迅速さなども評価に直結します。悪い評価がついてしまうと、その後の販売に影響するため、顧客対応は丁寧に行うべきです。
副業として古着屋経営は本当に可能か?
副業として古着屋を運営することは、十分に可能です。ただし、やみくもに始めるのではなく、明確な戦略とルールを決めておくことが重要です。特に本業がある人にとっては、「どれだけの時間を副業に割けるか」が現実的な課題になります。
副業で成功している人の多くは、ルーティンを仕組み化しています。たとえば、週末にまとめて仕入れ・撮影・出品作業を行い、平日は発送と顧客対応のみにするなど、時間の使い方に工夫があります。作業時間をあらかじめスケジューリングしないと、生活リズムに支障をきたしてしまい、長く続けることが難しくなります。
また、家庭の理解も重要です。古着の在庫が部屋に溢れる、週末に仕入れで家を空ける、といったことがストレスになるケースもあります。始める前にパートナーと話し合っておくことで、継続しやすい環境を整えることができます。
副業であるからこそ、収益よりも「学び」や「経験」を重視してスタートするのも一つの手です。初月から大きく稼げなくても、継続することで利益を上げられる体質に変えていくことが可能です。
続けられる人と辞めてしまう人の違い
古着転売を続けられる人と、すぐに辞めてしまう人。その違いは、決して「能力」や「知識」ではありません。最も大きな差は「継続への意志」と「改善力」にあります。
辞めてしまう人の多くは、「最初から儲かると思っていた」「手軽に稼げる副業だと思った」といった期待値の高さが原因で、現実とのギャップに耐えられなくなる傾向があります。また、仕入れた商品が売れなかったときに、その理由を分析せずに諦めてしまう人も多いです。
一方、続けられている人は、売れなかった理由を探し、改善を繰り返します。たとえば、出品時間帯を変えてみたり、タイトルや価格を見直したり、写真を撮り直したりと、細かい工夫を積み重ねています。
また、仕入れにおいても「なんとなく」で選ばずに、リサーチに時間をかけ、データを元に判断する傾向があります。経験と感覚だけでなく、数字に基づいた意思決定ができる人ほど、着実に結果を出しています。
まとめ:やめとけと言われる理由は現実、でも工夫と覚悟があれば続けられる
古着転売は、確かに簡単ではありません。「やめとけ」と言われる理由には、多くの初心者がぶつかる壁があるからこそです。商品が売れない、利益が出ない、作業が思った以上に大変、という事実は、実際に多くの人が経験しています。
しかしその一方で、継続して成果を出している人もいます。その違いは「やり方」ではなく、「取り組み方」にあります。楽して稼げると思わず、売れない理由を分析し、改善しながら継続できる人は、着実に成長しています。
副業として古着転売を始めるなら、最初から完璧を求めず、小さな成功体験を積み上げていく姿勢が何より大切です。自分のペースで試行錯誤しながら、ビジネスとして確立していく覚悟があれば、「やめとけ」と言われる世界の中でも、自分なりの活路を見出せるでしょう。