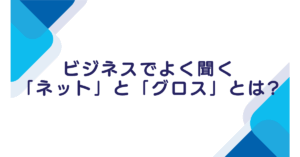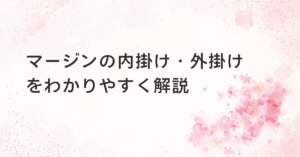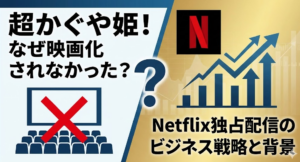「育休は取るだけ取って、育児はしない」。そんな実態を指して広まりつつあるのが「とるだけ育休」という言葉です。制度だけ整えても、企業にとっても家庭にとっても価値を生まない使われ方が問題視されています。本記事では、上司・人事が理解すべき「とるだけ育休」の定義と現場課題、さらに企業としての対策・制度設計、実践的なフォローアップの手法までを、現場目線で詳しく解説していきます。
とるだけ育休とは何か
「とるだけ育休」とは、男性が育児休業を形式的に取得する一方で、実際の育児にほとんど参加しない、または全くしない状態を指す言葉です。言い換えれば、「育休」という制度を利用しながら、その目的である“育児参加”の実態が伴っていない状態です。
本来の育休の目的と社会的背景
育児休業の目的は、育児における家庭内の役割分担を柔軟にし、ワークライフバランスを実現することにあります。とくに男性の育休取得促進は、政府の政策でも推進されており、厚生労働省も積極的な活用を後押ししています。
しかし、制度の導入や法的整備が進む一方で、運用の実態とのギャップが表面化しているのが現状です。
データで見るとるだけ育休の実態
とるだけ育休が社会問題として認識されるようになった背景には、実際の「育休取得者の行動」と「家庭内での役割」の乖離が大きく関係しています。
育休取得男性の中での割合と傾向
厚生労働省の調査によれば、男性の育休取得率は年々上昇していますが、その中で「育児にほとんど関与しない」人の存在も明らかになっています。とるだけ育休の割合に関する明確な統計は存在しませんが、SNSや現場の声から読み取れるのは、取得者全体の一部が“育児放棄状態”にあるという懸念です。
また、論文や実態調査の中でも「妻の負担は変わらなかった」「夫は育休中に旅行や趣味に没頭していた」などの声も報告されています。
実際に起きた“とるだけ育休”の事例
家族の不満が噴出するケース
SNSでは「取るだけ育休旦那に鉄槌を下した結果」といった投稿が拡散されることもありました。内容としては、夫が“育休”の名のもとに毎日趣味に出かけていたため、妻が激怒し、家庭内の信頼関係が崩れたというものです。
これは一例ですが、こうした「制度の形骸化」は、夫婦関係にも職場環境にも悪影響を及ぼします。
旅行や帰省に使われるケースも
育休期間中に長期旅行に出かけた、実家へ帰省してリフレッシュしていた、という話も見受けられます。もちろん一部の休息は必要ですが、それが主目的となると、本来の育児支援からは外れた行動となり、「形だけ取って中身がない」と批判されても仕方がありません。
とるだけ育休が職場にもたらす影響
チームへの負担と感情的な摩擦
育休による人員不足に対応していたメンバーが、「実際には育児してないらしい」と知ったとき、業務へのやる気や信頼感が一気に低下することがあります。これは業務効率の低下だけでなく、職場のモチベーション管理にも大きく影響します。
制度導入の信頼性にも影響
企業として男性育休を推進しているのに、形骸化した育休取得者が出てしまうと、制度全体の信頼性が損なわれます。次の取得希望者が周囲を気にして躊躇したり、人事評価がゆがんだりする懸念も生じます。
上司・人事が知っておくべき対応策
とるだけ育休を防ぐためには、制度そのものの設計以上に、「取得前後のコミュニケーション」が極めて重要です。
育休前のオリエンテーションを徹底する
取得希望者には、育休の目的・期待される行動・育児参加の重要性などを面談形式でしっかり共有しましょう。これは“注意喚起”ではなく、“当事者意識”を持ってもらうための重要なステップです。
配偶者との確認の場を設ける
可能であれば、配偶者との育休計画書の提出を求める、あるいは配偶者同席での説明会を実施することで、育児への協働姿勢を可視化できます。これは形式ではなく「使い方の質」を担保する仕組みとなります。
フォローアップと制度運用の工夫
育休中の定期的な連絡
育休中も一定の頻度で職場との連絡を取り、本人の様子を把握するようにしましょう。これは監視目的ではなく、復職のタイミングでスムーズに戻れるようにするための土台づくりです。
また、雑談ベースの連絡を推奨することで、職場への心理的な距離を保つ効果も期待できます。
復職後の育児共有のフィードバック
復職時には「育児を通して得た学び」「時間管理の工夫」などを本人に共有してもらうことで、単なる制度利用ではなく、本人の成長や周囲の意識変革にもつなげることができます。
この取り組みは、他のメンバーにも良い影響を与え、今後の制度運用にもプラスに働きます。
厚生労働省の動向と企業の責任
制度は整ったが“使い方”は企業次第
厚生労働省は育休促進の一環として、男性育休の取得義務化や「産後パパ育休」制度を導入しています。しかし、制度の本質を理解し、企業がどう運用していくかは現場の裁量に委ねられているのが現状です。
企業側が「形だけ取得」のリスクを意識し、内部で対応策を講じなければ、制度そのものが機能しなくなります。
まとめ:制度を“活かす”ためのマネジメントへ
とるだけ育休という言葉の裏側には、「形骸化した制度」「目的を見失った運用」「現場の不信」が見え隠れします。制度は企業にとっても社員にとっても可能性を広げるツールであるべきです。
人事部門やマネジメント層は、「育休=取らせて終わり」ではなく、「どう育児と向き合ってもらうか」まで設計し、実行することが求められています。フォローアップまで含めた“実効性ある運用”が、組織の信頼と働きやすさを支える土台になります。