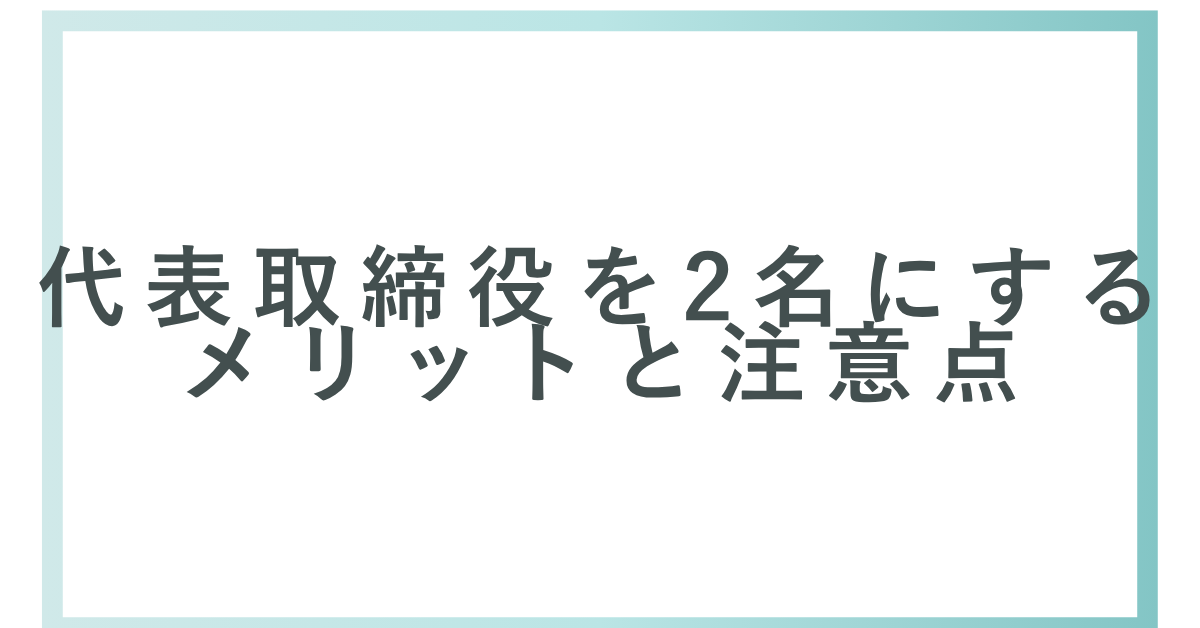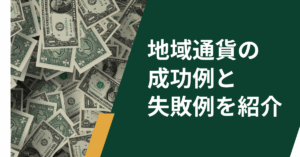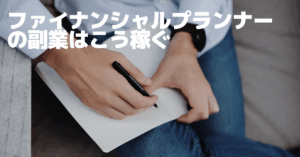会社経営をしていると、「代表取締役を2人にした方がいいのでは?」という局面に出会うことがあります。
急成長に伴い意思決定を分担したい場合、複数の事業を同時に進めたい場合など、代表取締役を2名体制にする企業は少なくありません。
しかし、登記や定款、銀行取引、代表権の扱いなど、実務的な注意点を理解していないと、トラブルや手続きの遅れを招くおそれもあります。
この記事では、代表取締役を2名にする際の仕組み、登記・定款の書き方、代表権の付与方法、銀行対応の流れ、そしてデメリットや辞任時の対処法まで、実務者が迷わず対応できるように徹底的に解説します。
経営者や総務・法務担当者の方はもちろん、会社設立を検討している方にも役立つ内容ですよ。
代表取締役を2人にできる仕組みと法律上の位置づけ
まず前提として、「代表取締役を2人にすることは可能なのか?」という疑問から整理しましょう。
結論から言えば、会社法では代表取締役を複数人置くことが認められています。
複数代表取締役の基本構造
株式会社の最高意思決定機関である取締役会では、通常、複数の取締役が存在し、その中から1名以上を代表取締役として選定します。
つまり、代表取締役は取締役の中から選ばれる存在であり、2名でも3名でも問題はありません。
複数の代表取締役を置く理由としては、次のようなケースが多いです。
- 経営責任を分散し、意思決定をスピーディに行いたい
- 事業分野ごとに代表を分けたい(例:技術部門と営業部門)
- 創業者同士で平等に経営権を持ちたい
- 海外支社や複数拠点の代表権を明確に分けたい
複数代表取締役制は、企業の成長段階で柔軟な経営を実現する手段の一つです。
ただし、その分、登記・定款・銀行取引などの「手続き上の整備」が必要になるため、実務的な理解が欠かせません。
代表権とは何かを明確に理解しておこう
ここで重要なのが「代表権(だいひょうけん)」という言葉です。
代表権とは、会社を代表して契約や取引などの法律行為を行う権限のことです。
たとえば、代表取締役が会社名義で契約書に署名・押印した場合、それは会社全体の意思として有効になります。
代表取締役が2人いる場合、
- 両者がそれぞれ代表権を持つ「各自代表」
- 二人で共同して代表する「共同代表」
の2パターンがあります。
この違いを理解しないまま進めると、後に「契約の効力が無効」となる可能性もあるため、慎重に判断しましょう。
代表取締役2人の代表権の与え方と実務上の注意点
代表取締役が2人いる場合、会社法ではどちらにも自動的に代表権が与えられるわけではありません。
代表権をどのように設定するかによって、実務の流れが大きく変わります。
各自代表と共同代表の違い
複数代表制を採用する際は、「各自代表」か「共同代表」かを定款または取締役会の決議で定めます。
各自代表の場合
それぞれの代表取締役が、単独で会社を代表して契約・取引が可能です。
たとえば、営業部門の代表が単独で取引契約を結んでも有効です。
スピード感はありますが、社内での意思統一が取れないとリスクもあります。
共同代表の場合
代表取締役AとBの双方が署名・押印しない限り、契約は成立しません。
意思決定に時間がかかる一方で、暴走や不正を防ぎやすいというメリットがあります。
どちらの方式を採用するかは、会社の規模や経営方針によって異なります。
スタートアップや小規模法人では「各自代表」、大企業やグループ経営では「共同代表」を選ぶ傾向があります。
代表権の範囲を限定することも可能
定款で「特定の取引に限り代表権を持つ」と定めることも可能です。
たとえば、「Aは国内取引の代表権を持つ」「Bは海外取引に限り代表権を行使できる」といった具合です。
このような限定代表権を設けると、業務分担が明確になり、責任の所在もはっきりします。
ただし、外部の取引先にその内容を周知しておかなければ、契約トラブルにつながる可能性があります。
取引先には登記簿謄本を提示するなどして、代表権の範囲を明確に伝えることが大切ですよ。
実務上の注意点:代表印と契約書
代表取締役が2人いる場合、それぞれに「代表印」を登録できるかどうかは、実務上の混乱ポイントです。
法的には、代表印は1つである必要はなく、複数登録も可能です。
ただし、銀行や法務局によっては「どちらか一方のみ有効」とする運用があるため、事前に確認しましょう。
また、契約書に押す際も、どの代表印を使用したかが後の証明に関わります。
契約管理台帳や電子署名サービスを導入して、押印者を明確化しておくと安心です。
代表取締役2人の登記と定款の書き方・変更手続き
代表取締役を2人にする場合、法務局への登記が必要です。
定款における代表取締役の定め方、登記申請書の作成、議事録の添付など、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
定款に記載する代表取締役の規定例
定款とは、会社の憲法のようなものです。代表取締役を複数にする場合は、次のような定めを入れる必要があります。
例文:各自代表の場合
「当会社の代表取締役は2名とし、各自会社を代表する。」
例文:共同代表の場合
「当会社の代表取締役は2名とし、2名共同して会社を代表する。」
この文言を定款に記載し、取締役会や株主総会の議事録にも反映します。
定款変更を伴う場合は、公証人の認証も必要になります。
登記申請書に必要な記載事項
登記を行う際には、「代表取締役2名登記申請書」を作成します。
申請書には、代表取締役の氏名・住所・生年月日・就任年月日を記載し、以下の添付書類を添えます。
- 取締役会議事録(または株主総会議事録)
- 定款の写し
- 代表取締役の就任承諾書
- 印鑑届出書(法務局所定様式)
申請手続き後、法務局の審査を経て登記簿謄本に2名の代表取締役が記載されます。
議事録の書き方とポイント
代表取締役を2名にする場合の議事録には、次の要素を明確に書きます。
- 開催日時・場所
- 出席取締役の氏名
- 議題(代表取締役選定の件)
- 決議結果(賛成・反対)
- 議長および署名人の署名押印
たとえば、議題部分では次のように書きます。
「当会社において、取締役Aおよび取締役Bを代表取締役に選定し、それぞれ会社を代表することとした。」
この文面を誤ると、法務局で補正を求められるケースがあります。
議事録作成後は、代表印を押印し、登記書類に添付しましょう。
代表取締役が複数いる場合の銀行取引と印鑑登録の扱い
代表取締役が複数いるとき、銀行との取引実務にも影響が出ます。
特に「口座開設」「融資契約」「送金承認」などでは、代表権の扱い方を明確にしておくことが欠かせません。
銀行が確認するポイント
銀行は、新規口座開設や融資契約時に、登記簿謄本を必ず確認します。
代表取締役が2人の場合、各自代表なのか共同代表なのかによって審査の進め方が異なります。
- 各自代表:どちらか一方の署名・押印で取引可能
- 共同代表:2名の署名・押印が揃わないと取引不可
また、共同代表制では、ネットバンキングでの承認設定も2人分必要になるため、事務手続きが煩雑になります。
銀行によっては「どちらか一方に限り代表権を行使できる」とする内部ルールを求められることもあります。
銀行印と代表印の使い分け
銀行口座に登録する印鑑(銀行印)は、登記上の代表印とは別に設定できます。
ただし、代表取締役が2人の場合、どちらの印鑑を登録するかを明確に決めておかないと、資金移動や支払処理で混乱します。
実務的には、次のような方法が多いです。
- 経理担当の指示系統を明確にし、代表印の使用ルールを決める
- 振込権限をネットバンキング上で役職ごとに分ける
- 印鑑登録証明書を定期的に更新し、代表者変更を銀行へ即報告する
これにより、経理や財務業務が止まるリスクを防ぐことができます。
代表取締役2人制のデメリットと意思決定を円滑にするコツ
代表取締役を複数にすることにはメリットも多いですが、同時に運営面での課題もあります。
よくあるデメリット
- 意思決定に時間がかかる
- 責任の所在が曖昧になりやすい
- 社員が「どちらの指示を優先すべきか」迷う
- 銀行や取引先への説明が煩雑になる
特に、経営方針に対する意見が分かれると、業務が停滞することもあります。
このような問題を防ぐためには、あらかじめ「業務分担表」や「決裁ルール」を明文化しておくことが重要です。
意思決定をスムーズにするための実務ルール
- 各代表取締役の担当領域を明確化する(営業・財務など)
- 重要事項は必ず会議録として残す
- 代表印の使用権限を文書で定め、社員に共有する
- 定期的に両代表で経営会議を行い、方針をすり合わせる
こうした仕組みを整えておくことで、複数代表制でも混乱なく運営できます。
代表取締役2名のうち1名が辞任する場合の手続きと登記変更
代表取締役が2名いるうちの1名が辞任した場合、残る代表取締役の登記を必ず変更する必要があります。
辞任時に必要な手続き
- 辞任届の提出(会社宛て)
- 取締役会または株主総会で辞任承認
- 登記変更申請書の提出
- 印鑑届の廃止および変更手続き
登記申請には、辞任した代表取締役の辞任届と、残る代表取締役の承認議事録を添付します。
この手続きが完了するまでの間、法的には辞任した代表者にも責任が残ることがあるため、迅速な対応が求められます。
まとめ|複数代表制は仕組みを整えれば大きな武器になる
代表取締役を2名にすることは、経営を柔軟にし、責任を分散できる一方で、手続きや運用面の工夫が不可欠です。
定款や登記、議事録、銀行手続きなどをきちんと整備すれば、複数代表制は大きな経営の武器になります。
「代表取締役 2人 登記」や「代表取締役 2人 代表権」で検索して不安を感じていた方も、まずは自社に最適な形を検討し、必要な文書を整えておくことから始めてみてください。
複数代表制を“トラブルの火種”ではなく“成長の仕組み”として活かせるかどうかは、準備と運用次第ですよ。