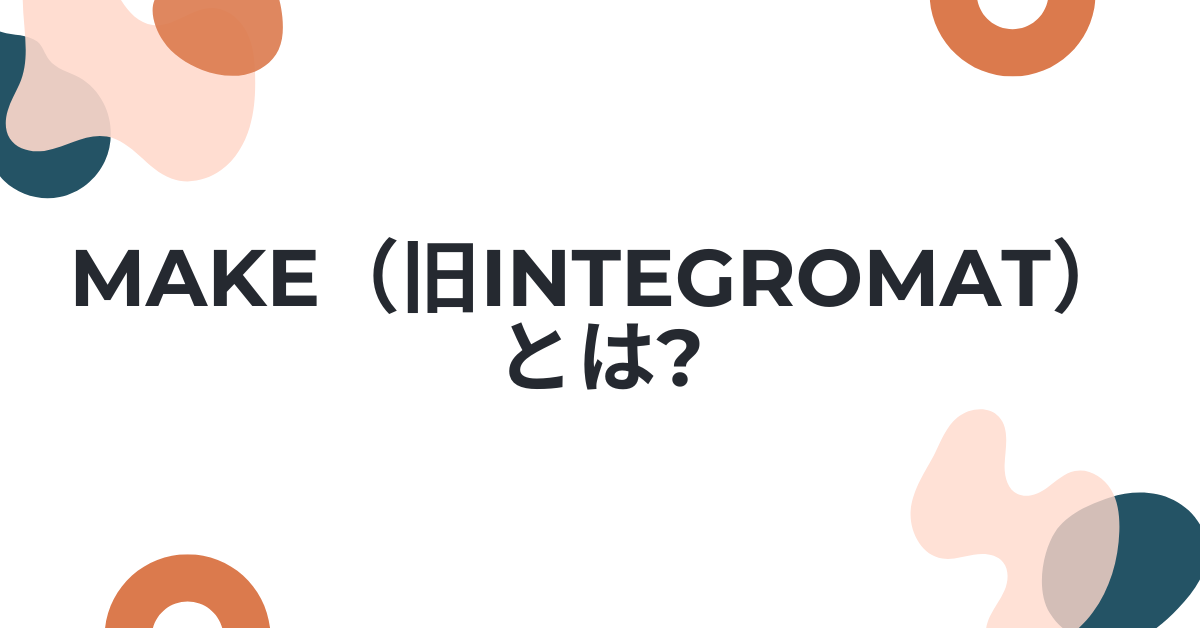もしあなたが「毎日のルーチン作業に時間を取られている」「人手不足でも業務を効率化したい」と感じているなら、**Make(旧Integromat)**が強い味方になります。
Makeは、プログラミング不要で業務を自動化できる“ノーコード自動化ツール”です。メール送信からデータ集計、Slack通知、ChatGPT連携まで、アイデア次第でほとんどの業務を自動化できます。
この記事では、Makeの仕組みから料金、できること、導入事例、そして「右クリック→名前を付けて画像を保存」のようなショートカットの作り方まで、実務で役立つ情報を網羅的に解説します。
Make(旧Integromat)とは?ノーコード自動化ツールの基本をわかりやすく解説
まずは、Makeというツールがどんな仕組みなのかを理解しておきましょう。
Makeは、かつて「Integromat(インテグロマット)」という名前で提供されていたサービスの進化版です。2022年にブランド名が「Make」に変更され、UI(ユーザーインターフェース)や自動化機能が大幅に改善されました。
Make(旧Integromat)の基本機能とは
Makeは、「複数のアプリやWebサービスをつなぎ、条件に応じて自動的に処理を行う」ためのツールです。
プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップ操作だけでワークフロー(=自動処理の流れ)を作成できます。
たとえば次のような自動化が可能です。
- Gmailで届いた請求書を自動でGoogle Driveに保存し、Slackで通知
- ECサイトの受注情報をスプレッドシートに記録し、ChatGPTに要約を依頼
- カレンダーに予定が入ると自動でメールを送信
- 新しいブログ記事が公開されたらTwitterで自動投稿
このようにMakeは、人が手動で行っていた繰り返し作業を、24時間休まずに自動で実行してくれるツールです。
Zapierとの違いと選ばれる理由
Makeとよく比較されるのが、同じくノーコード自動化ツールの「Zapier(ザピアー)」です。
Zapierはシンプルで分かりやすい反面、複雑な処理を作るのは苦手です。
一方、Makeは「条件分岐」「ループ」「データ変換」など、より高度な自動化が可能。
エンジニアでなくても、**“業務プロセスを丸ごと自動化”**できる点が評価されています。
特に日本企業では、スプレッドシートやSlack、ChatGPTなどとの連携でMakeを導入するケースが増えています。
Make ノーコードでできること|自動化の実例と活用アイデア
Makeの最大の魅力は、プログラミング不要で“人間の代わりに作業をしてくれる”こと。
ここでは、実際に「Make ノーコードでできること」をビジネスの現場に即して紹介します。
社内業務の自動化に使えるシナリオ例
Makeで作成するワークフローは「シナリオ」と呼ばれます。
たとえば、営業、バックオフィス、マーケティングなどの現場でよく使われるシナリオは次の通りです。
- 営業部門向け:フォーム送信内容を自動でスプレッドシートにまとめ、営業担当にSlack通知
- 経理・管理部門向け:経費精算のメールを受け取ると自動でDriveに格納し、承認者へリマインド送信
- マーケティング部門向け:ChatGPTと連携してSNS投稿文を自動生成・投稿
- 人事・採用部門向け:応募フォームのデータをまとめて採用管理シートに転記
これらの自動化を、すべてノーコード(=プログラミング不要)で構築できます。
ボタンを押すだけで業務が進むので、作業効率が劇的に向上します。
ChatGPTと連携して“考える業務”も自動化する
最近注目されているのが、「Make × ChatGPT」の連携です。
MakeにはOpenAI APIを接続できるため、ChatGPTの出力結果を自動的に取得・加工できます。
たとえば、以下のような使い方が可能です。
- 新着のお問い合わせ内容をChatGPTで要約し、Slackに送信
- 週報をChatGPTに要約させ、メールでチームに共有
- 生成されたキャッチコピーや商品説明をスプレッドシートに自動保存
これにより、単なる“作業の自動化”から“思考の自動化”へと一歩進んだ業務効率化が可能になります。
AIとの組み合わせこそ、Makeがビジネスの現場で評価される理由の一つです。
Make ノーコードの料金プランと費用感|無料プランでもどこまでできる?
業務効率化ツールを導入する際に、やはり気になるのはコストです。
Make ノーコードの料金体系は非常にシンプルで、無料プランから本格的な企業向けプランまで段階的に用意されています。
無料プラン(Free Plan)
個人利用や小規模チームのテスト用途にぴったりです。
月に1,000回の操作(=オペレーション)が無料で使えます。
基本的な自動化構築は可能ですが、同時実行数や処理速度に制限があります。
- 月1,000オペレーションまで無料
- 同時実行数は1
- シナリオの実行間隔:15分ごと
小規模のルーチン業務なら、この無料プランだけでも十分運用可能です。
有料プラン(Core/Pro/Teams/Enterprise)
有料プランは、月額9ドルから利用できます(2025年時点)。
上位プランに行くほど、オペレーション数や実行速度が上がり、大規模運用に対応します。
| プラン | 月額料金(目安) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Core | 約9ドル | 小規模チーム向け。処理速度・接続アプリを拡張可能。 |
| Pro | 約16ドル | 並列実行や条件分岐を多用するシナリオに最適。 |
| Teams | 約29ドル | チーム共有・共同編集が可能。管理者権限付き。 |
| Enterprise | 要相談 | 大企業・高度なセキュリティが必要な場合に対応。 |
Makeの料金はZapierよりもコストパフォーマンスが高く、
「処理量あたりの価格が安い」ことが導入理由の一つとされています。
中小企業でも導入しやすいのが嬉しいポイントです。
料金の目安と導入判断のポイント
「どのプランを選べばいいかわからない」という方は、以下を目安にすると良いでしょう。
- 試験的に使いたい:無料プラン
- 日常業務を自動化したい:CoreまたはProプラン
- チーム全体で使いたい:Teamsプラン
最初は無料で試して、成果が出たら上位プランに切り替えるのがおすすめです。
なお、料金は米ドル建てなので、円安時期は多少変動する可能性があります。
Make ノーコードの使い方|ログインから自動化までのステップ
ここからは、実際にMakeを使い始める手順を紹介します。
難しそうに感じるかもしれませんが、慣れれば数分で自動化が完成しますよ。
アカウント作成とログイン方法
- Makeの公式サイト(make.com)にアクセス
- Googleアカウントまたはメールアドレスでサインアップ
- 登録後に「Dashboard(ダッシュボード)」へログイン
Make ノーコード ログインは非常にシンプルで、数十秒で完了します。
もしチーム利用を想定している場合は、メンバー招待機能を活用しましょう。
自動化(シナリオ)の作り方
- 「Create a new scenario」をクリック
- 接続したいアプリを選択(例:Gmail、Google Sheets、Slackなど)
- 条件とアクションを設定(例:メールが届いたら→スプレッドシートに記録)
- テスト実行し、問題なければ「オン」に設定
これで、あなたの業務が自動で回り始めます。
複雑な設定は不要で、すべてアイコンベースで操作できる点が魅力です。
「右クリック→名前を付けて画像を保存」のショートカットについて
Makeの操作画面で生成したワークフロー画像などを保存したい場合、
ブラウザに標準のショートカットキーは存在しません。
ただし、Chrome拡張機能「GoFullPage」などを使えば、
画面全体をキャプチャして保存することが可能です。
もしどうしてもショートカットを作りたい場合は、
AutoHotkey(Windows用自動化ソフト)などを使って
「右クリック→名前を付けて保存」操作を自動化するスクリプトを設定する方法もあります。
このように、Make自体は“Web上での自動化”を得意としますが、
PC上の物理操作も工夫次第で自動化できるのです。
Make ノーコードで自動化できる業務の具体例と実践事例
「どんな業務を自動化できるの?」という疑問は、多くのビジネスパーソンが抱くポイントです。
ここでは、実際の企業導入事例や職種別の自動化パターンを交えながら、Make ノーコードの活用シーンを紹介します。
営業職の業務を効率化するMakeの使い方
営業担当者の時間の多くは、「データ整理」や「報告書作成」といった非営業活動に割かれています。
Makeを使えば、これらの作業を自動化し、顧客対応や提案活動に集中できます。
たとえば次のような活用事例があります。
- フォーム送信内容を自動でスプレッドシートに記録
GoogleフォームやTypeformで受け取ったリード情報を、自動的にスプレッドシートへ転記します。
さらにSlack通知も同時に送ることで、チーム全体で即時共有が可能になります。 - 営業日報をChatGPTに要約させる
営業報告をフォーム入力するだけで、ChatGPTが内容を要約し、上司宛にSlackまたはメールで送信。
上司はAIがまとめた要点を読むだけで進捗が把握できます。 - 顧客フォローの自動リマインド
スプレッドシートの「最終連絡日」から一定期間経過すると、Slackで自動通知。
抜け漏れのないフォロー体制を作れます。
営業現場では“入力と通知”の2工程が最も時間を取ります。
Makeで自動化することで、「1件の問い合わせを数秒で処理する仕組み」が構築できます。
マーケティング業務での自動化事例
マーケティング部門では、SNS運用・データ集計・広告レポートなど、日々大量の情報を扱います。
Make ノーコードは、こうした反復作業をまとめて自動化できます。
- SNS投稿の自動化
スプレッドシートに投稿内容と日時を入力しておけば、指定時刻に自動でX(旧Twitter)やLinkedInへ投稿。
ChatGPTと連携すれば、投稿文を自動生成することもできます。 - Google Analyticsレポートの自動化
日次アクセスデータを取得し、Slackで共有。Excelを開かなくてもKPIを確認できます。 - 広告レポート統合
Facebook広告・Google広告・X広告のデータを自動で集約し、スプレッドシートにまとめる。
レポート作成の時間を毎週数時間削減できます。
マーケターにとって、Makeは「データを動かすための自動秘書」のような存在です。
繰り返し作業をAIに任せることで、戦略設計や分析により多くの時間を使えます。
バックオフィス業務の自動化で“属人化”を防ぐ
バックオフィス業務(経理・人事・総務)は、手作業が多く、人によって処理のばらつきが起きやすい領域です。
Makeを導入することで、属人化を防ぎ、安定したオペレーションを構築できます。
- 経費精算の受付と管理
社員が提出した領収書メールを自動でDriveに保存し、担当者にSlack通知。
必要項目をスプレッドシートに転記して集計まで完了。 - 勤怠管理・打刻通知
打刻漏れを自動検知して本人と上司に通知。
定期的なリマインドも自動化できるため、管理コストが減ります。 - 入退社手続きの自動化
新入社員がフォーム入力した情報をもとに、アカウント発行依頼メールを自動送信。
手続きの抜け漏れを防止できます。
バックオフィスは「正確さ」と「スピード」が求められる領域です。
Makeを導入すれば、人的ミスを減らしながら作業効率を上げることができます。
Make ノーコードとChatGPTの連携方法|AIと自動化の最強タッグ
2024年以降、MakeとChatGPTの連携は業務自動化の中心トレンドになっています。
「AIが考え、Makeが動かす」仕組みを構築すれば、単純な自動化を超えた“思考業務の自動処理”が実現します。
ChatGPT連携の基本構成
Makeでは「HTTPモジュール」や「OpenAI連携テンプレート」を使ってChatGPTと接続します。
設定は非常にシンプルで、次のステップで行えます。
- OpenAIアカウントでAPIキーを取得
- MakeのHTTPモジュールでAPIキーを入力
- ChatGPTモデル(GPT-4など)を指定
- プロンプト(命令文)を入力し、出力結果を別アプリに渡す設定を追加
この連携によって、ChatGPTに「メール文を要約」「レポートを生成」「文章を修正」などの指示を自動で送り、
その結果をスプレッドシートやSlackに反映できます。
ChatGPT × Makeの実用シナリオ
- 問い合わせメールの自動返信
受信メールをChatGPTが解析し、テンプレート返信を自動生成→送信。 - 週報の自動作成
スプレッドシートにある業務記録をChatGPTが要約し、見出し付きで整形してSlackに投稿。 - 顧客レビュー分析
顧客のレビュー文をChatGPTが感情分類し、ポジティブ・ネガティブの比率を自動算出。
AIを「使う」から「組み込む」時代へ。
Makeを活用すれば、ChatGPTの知的処理を既存業務の中に溶け込ませることができます。
Make ノーコードの導入事例|中小企業から大手までの活用パターン
「本当に現場で使われているの?」という疑問に答えるため、実際の導入事例を紹介します。
Makeはすでに世界で数百万人が利用しており、日本国内でも導入企業が急増中です。
事例①:中小IT企業での見積もり業務を自動化
あるIT開発会社では、営業担当が都度メールで見積もり依頼を受け取り、
手作業でExcel入力・見積書作成を行っていました。
Makeを導入したことで、フォーム入力内容を自動でスプレッドシートにまとめ、
ChatGPTが見積もり文を生成。担当者は内容を確認して送るだけに。
結果、1件あたり30分かかっていた作業が3分に短縮。
年間では約200時間の工数削減に成功しました。
事例②:スタートアップ企業でのSNS運用を自動化
マーケティング担当1名の小規模チームでは、SNS運用が追いつかず更新が止まりがちでした。
Makeを導入し、スプレッドシートに入力した投稿内容をX(旧Twitter)・LinkedIn・Instagramへ自動投稿。
ChatGPTが投稿文を整える仕組みも導入し、**“自動でつぶやく企業アカウント”**を実現。
結果、投稿頻度が週2回から毎日に増加。フォロワー数も3か月で1.5倍に伸びました。
事例③:製造業での受注データ整理を自動化
製造業では、受注データがFAX・メール・フォームなど複数チャネルから届くことがあります。
Makeでそれらのデータを自動統合し、ERPシステムに一元登録。
担当者の手入力作業がなくなり、入力ミスが激減しました。
**「現場を止めない自動化」**を実現した代表例といえます。
Make ノーコードの導入で失敗しないコツ
便利なMakeですが、「自動化しすぎて混乱した」「想定外の処理が動いてしまった」という失敗例も少なくありません。
導入時に注意しておくべきポイントを整理しておきましょう。
小さく始めて徐々に拡張する
最初から複雑な自動化を設計すると、トラブル対応が難しくなります。
まずは「1アクション=1結果」の単純なフロー(例:メール→スプレッドシート保存)から始めましょう。
うまく動いたら徐々に条件分岐や複数処理を追加していくのがコツです。
手動テストを必ず行う
シナリオを保存したら、実行前に「テストモード」で動作確認を行います。
想定外のデータ送信や削除を防ぐために、ダミーアカウントを使うのもおすすめです。
自動化の「責任者」を明確にする
チーム利用では、「誰が作ったシナリオか分からない」問題が起きがちです。
Makeにはシナリオごとに作成者情報を表示する機能があります。
運用体制として、責任者と管理者を決めておくとトラブルが少なくなります。
Make ノーコードと他ツールの違い|ZapierやPower Automateとの比較
Makeは多くの自動化ツールの中でも高い自由度を持っています。
他ツールとの違いを理解しておくと、選定時の判断がしやすくなります。
| 項目 | Make(旧Integromat) | Zapier | Power Automate |
|---|---|---|---|
| 操作性 | ビジュアル操作で直感的 | シンプルだが構造が固定的 | Microsoft製品との連携が強い |
| 柔軟性 | 条件分岐・ループ処理に強い | 基本的な自動化に限定 | 業務フローの設計自由度は中程度 |
| 料金 | 無料〜月9ドルから | 無料〜月20ドル前後 | Microsoft365契約内で利用可 |
| 主な利用者層 | 中小企業・マーケター・開発職 | 個人・フリーランス | 企業の情シス部門 |
Makeは、**「非エンジニアでも高度な処理を設計できる」**点が特徴です。
特に、スプレッドシートやSlackなどのGoogle・クラウド連携を多用する企業に向いています。
まとめ|Makeで“働かない仕組み”を作ることが最強の業務改善
Make(旧Integromat)は、ノーコードでありながらプロレベルの自動化を実現できるツールです。
料金は手頃で、無料から始められるのも大きな魅力。
ChatGPTやGoogleアプリとの連携を活用すれば、単純作業を削減するだけでなく、
AIと連携した“思考型の自動化”も可能になります。
一度自動化の仕組みを作れば、翌日から時間の使い方が変わります。
メール返信、報告書作成、データ整理……それらをMakeがすべて代わりにやってくれる。
「自動化は難しそう」と思っていた方こそ、まずは無料プランで1つの業務を置き換えてみてください。
その瞬間から、あなたの仕事の“常識”が変わるはずです。