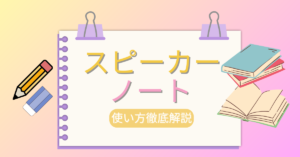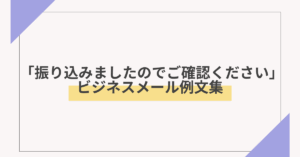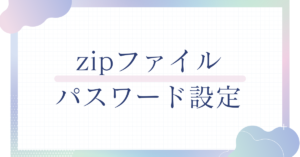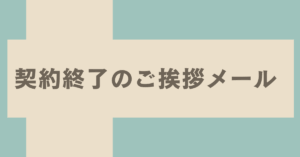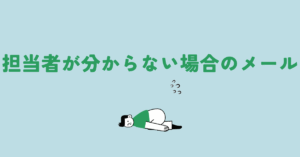突然スマホにかかってくる「非通知設定」の電話。ビジネス中や夜間、しかも相手がわからない状態では、不安やストレスを感じる方も多いはずです。本記事では、非通知電話がかかってくる理由、誰からの着信かを見分ける方法、リスクの見極め方まで、実務で役立つ対応法を解説します。業務効率を妨げないための着信管理術として、ぜひ参考にしてください。
非通知は誰からの電話なのか調べる方法

結論から言うと
非通知電話の発信者を「確実に特定する方法」は基本的にありません。
ただし
✔ ある程度見極める方法
✔ ブロック・対策する方法
✔ 危険なケースの対処法
は存在するため、その方法について解説をさせていただきます。
着信履歴からわかるケースはある?
非通知番号の場合、端末の履歴には「非通知」や「不明な番号」としか表示されず、通常の方法では相手を特定できません。
しかし、以下のような手段で手がかりを得られる可能性があります。
- 留守番電話の内容を確認する
- 着信時間帯と文脈を照合する(例:通院先、役所、取引先など)
- SMSやメールで連絡が来ていないか確認する
- 電話会社のサービスで通話履歴を確認する(法人契約の場合)
非通知の電話を調べるサービス
個人向けには以下のようなサービスがあります
- 通話録音アプリ(Whoscall、Truecaller など)
- キャリア提供の着信通知・迷惑電話対策サービス(docomo「あんしんナンバーチェック」など)
法人の場合は、PBXやクラウド電話システムに着信履歴を記録する機能を持たせておくと、非通知もある程度トレースが可能です。
非通知の先を調べるやり方

STEP1:着信状況の記録
| チェック項目 | 記入例 |
|---|---|
| 着信日時 | 2025/05/18 14:32 |
| 着信端末 | 営業部社用スマホ(iPhone) |
| 着信回数 | 同日2回(14:32、14:38) |
| 通話内容 | 出たが無言で切れた/自動音声だった/要件不明 など |
| 留守電あり/なし | 留守電なし(サイレント切断) |
記録は端末の通話履歴/ログ出力がある場合は必ずスクショ・保存
法人用クラウド電話を使っている場合は管理画面でログ確認(PBX等)
STEP2:関連性の高い発信元候補をリストアップ
次の情報をもとに、発信者の可能性を高める情報を絞り込みます。
① 着信の時間帯と業務の関連性
- 平日日中 → 公共機関・業務委託先の可能性あり
- 夜間・休日 → 私的・迷惑系・海外発信の可能性大
② 直近のやり取りや申込・手続き状況の確認
- 行政手続き(例:税務署、役所、ハローワークなど)
- 医療・教育・予約サービス(病院・検診など)
- 海外ツールやクラウドサービス(海外IP発信のケース)
該当の部署や関係者と「〇〇時ごろに非通知で電話しましたか?」と確認する
STEP3:音声・留守電の解析
留守電にメッセージがある場合のチェック項目
| 内容項目 | 判断指標 |
|---|---|
| 発信者の名乗りあり | ○(信頼度高) |
| 自動音声(日本語が不自然) | △(詐欺・海外業者の可能性) |
| 折返し依頼あり(番号提示) | ×(詐欺・営業リスク) |
| 緊急を装って不安を煽る | ×(スパムの特徴) |
音声内容が不明瞭な場合でも録音は削除せず保存(証拠保持)
STEP4:番号ブロック or 記録保持判断
| パターン | 推奨対応 |
|---|---|
| 正規取引先・社内関係の可能性あり | 一時保留、再着信待ち(メール・チャット確認) |
| 公共機関・病院などが濃厚 | 同日内に再連絡 or 担当窓口に確認 |
| 留守電なし・複数回の無言着信 | 着信拒否設定(スマホ・MDM)+記録保管 |
| 「番号教えて折返して」パターン | ブロック+情報共有(迷惑電話データベース登録推奨) |
STEP5:番号通知リクエスト(電話会社経由)
法人契約している場合、電話会社経由で以下の対応が可能なケースがあります。
- 着信番号の開示申請(契約者本人に限る)
- 着信元の事業者名開示(悪質事例に限る)
- 通話履歴データ(要申請・書面)
NTTドコモ/KDDI/SoftBankそれぞれで申請フォームが異なります
悪質な迷惑行為が疑われる場合は「警察への相談」+「電話会社への開示依頼」が有効
おすすめツール(法人対応向け)

| ツール名 | 主な用途 |
|---|---|
| Whoscall/Truecaller | 着信番号解析・発信元特定(海外非通知にも対応) |
| クラウドPBX(BIZTEL、MiiTelなど) | 通話履歴・録音・発信元管理 |
| MDM管理ツール(Jamf、Intuneなど) | 社用スマホの着信制御・遠隔管理 |
| 電話代行・IVRサービス | 業務時間外・非通知対策用の窓口設計に有効 |
非通知で電話がかかってくる理由と仕組みは?

まずは「なぜ非通知で電話がかかってくるのか」を理解しておくと安心です。非通知は相手が自分の番号を表示させない設定にしているだけで、特別な技術が使われているわけではありません。
非通知になる仕組み
電話をかける際に「184」を番号の前につけると、発信者番号が相手に表示されなくなります。これは日本の電話サービスで共通の仕組みです。逆に「186」をつけてかければ、必ず番号が通知されます。つまり非通知とは「発信者が意図的に番号を隠している」ということなのです。
非通知でかかってくる典型的なケース
- 営業や勧誘の電話
企業によっては顧客に直接番号を知られないように非通知で発信することがあります。 - 病院や役所などの公的機関
担当部署から折り返し電話をするときに、回線共有の都合で非通知になるケースがあります。 - 個人がプライバシー保護のために利用
友人や知人が番号を知られたくない場合に「184」を利用することもあります。
非通知にするのはどんな人・目的があるのか?
非通知設定での着信には、いくつかのパターンがあります。
- 公的機関(警察・市役所・病院など)の発信
- 企業の調査・アンケート業務
- 個人のプライバシー保護目的
- セールス・勧誘・迷惑電話
- イタズラ・嫌がらせ目的
公的機関や一部企業では発信番号が固定されない内線システムを使っているため、「非通知」になることがあります。
夜中に非通知でかかってくる電話の正体
夜間の非通知着信は、多くの場合以下のような背景が考えられます。
- 病院や介護施設からの緊急連絡
- 間違い電話(国際電話含む)
- イタズラやストーカー行為
- 自動発信システムによる着信試験
このような時間帯での非通知電話は、業務用スマホでも私用でも、心身への負担となるケースが多く、対応のルール化が重要です。
iPhoneで非通知番号を知る方法

iPhoneを使っている方は「非通知 誰からかわかる方法 iPhone」や「非通知 番号 知る方法 iPhone」と検索することが多いでしょう。iPhoneには標準機能やキャリアサービスを組み合わせることで、非通知対策が可能です。
iPhoneの標準設定でできること
iPhoneの設定から「おやすみモード」や「着信拒否」を活用することで、非通知からの着信を受けないようにできます。例えば「知らない番号からの着信を消音」に設定すれば、非通知からの電話が直接鳴らずに履歴に残るだけになります。これで誤って出てしまうリスクを減らせます。
キャリアサービスと組み合わせる
iPhone単体では非通知の番号を表示させることはできませんが、ドコモやauのナンバーリクエストを利用すれば相手に通知を促すことができます。つまりiPhoneの機能とキャリアのサービスを組み合わせることが、現実的な「非通知 誰からかわかる方法 iPhone」になるのです。
非通知に出てしまった場合の注意
「非通知電話 出てしまった」という悩みも多いですが、慌てる必要はありません。もし営業や勧誘なら丁寧に断れば問題ありませんし、怪しい電話だと感じたら即座に切りましょう。個人情報を不用意に答えないことが最も大切です。
非通知を着信拒否する方法

「非通知からの電話は不安だから出たくない」という人も多いですよね。実はスマホやキャリアサービスを使えば、非通知着信を自動的にブロックすることができます。ここでは具体的な方法を紹介します。
iPhoneで非通知を拒否する方法
iPhoneの場合
- 設定アプリを開く
- 電話 →「不明な発信者を消音」にチェック
- 連絡帳にない番号からの着信を自動で留守電に送る
iPhoneには「知らない番号を消音」という機能があります。設定アプリから「電話」→「不明な発信者を消音」をオンにすると、非通知の電話は着信音が鳴らずに履歴だけ残ります。これなら不用意に出てしまう心配がありません。さらにキャリアのナンバーリクエストと組み合わせれば、非通知からの電話自体が接続されなくなるので安心です。
Androidで非通知を拒否する方法
Androidの場合
- 電話アプリを開く
- 設定 →「ブロック番号」→「非通知をブロック」ON
※機種によって表記が異なる場合があります。
Androidスマホの場合、メーカーや機種によって手順は異なりますが、多くのモデルには「非通知着信を拒否」という設定が用意されています。電話アプリの設定画面から「通話拒否設定」や「ブロック設定」を探して有効化すればOKです。機種によっては「非通知着信は受け付けません」と自動でアナウンスしてくれることもありますよ。
キャリアサービスを利用する方法
- ドコモの「ナンバー・リクエスト」
非通知でかかってきた場合、自動音声で「186をつけてかけ直してください」と伝えてくれます。 - auの「番号通知お願いサービス」
非通知のままでは着信できず、相手に通知を促す仕組みです。 - ソフトバンクの「ナンバーブロック」
迷惑電話や非通知着信を自動で遮断し、履歴にも残さないことができます。
非通知 着信拒否をしたいなら、端末設定とキャリアサービスの両方を組み合わせるのがおすすめです。特に仕事やプライベートで電話を多く使う人は、安心感が大きく変わります。
業務用スマホでの着信制限管理
MDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入している企業では、社用スマホに一括で着信制限をかけることも可能です。
営業妨害・サイバー攻撃・なりすまし対策の一環として、非通知着信の拒否は有効です。
非通知電話に出てしまった場合のリスクと対策
出てしまったからといって必ず危険ではない
非通知電話だからといって、すべてが危険というわけではありません。
ただし、以下のようなケースでは警戒が必要です。
- 無言のまま切れる
- 名前や個人情報を聞かれる
- 折り返し電話を強く促される
- 不審な商品・サービスを勧誘される
対応を誤るとどうなる?
- 個人情報を悪用される
- 業務時間の浪費
- メンタル的ストレスによるパフォーマンス低下
こうした影響を避けるには、非通知からの着信に一貫したルールを設けることが重要です。
非通知に出るべき?判断の基準と対応のポイント
非通知に出るかどうかの判断軸
| 状況 | 出るべきか? | 理由 |
|---|---|---|
| 営業時間中・不在着信が続いている | △ | 他部署・取引先の可能性あり |
| 深夜・休日・複数回の無言電話 | × | 高確率で迷惑・嫌がらせ |
| 公共機関の手続き中 | ○ | 区役所や病院の連絡の可能性 |
まとめ|非通知電話には目的がある、判断軸とルールを持とう
非通知着信は、誰からかわからない不安や恐怖を伴うものですが、正しい知識と設定、そしてアプリなどのツールを活用することで、そのリスクを大幅に減らすことができます。自分自身のプライバシーと安全を守るためには、「非通知の電話には出ない」というシンプルなルールを徹底し、必要に応じて警察や弁護士などの専門家の力を借りることが大切です。