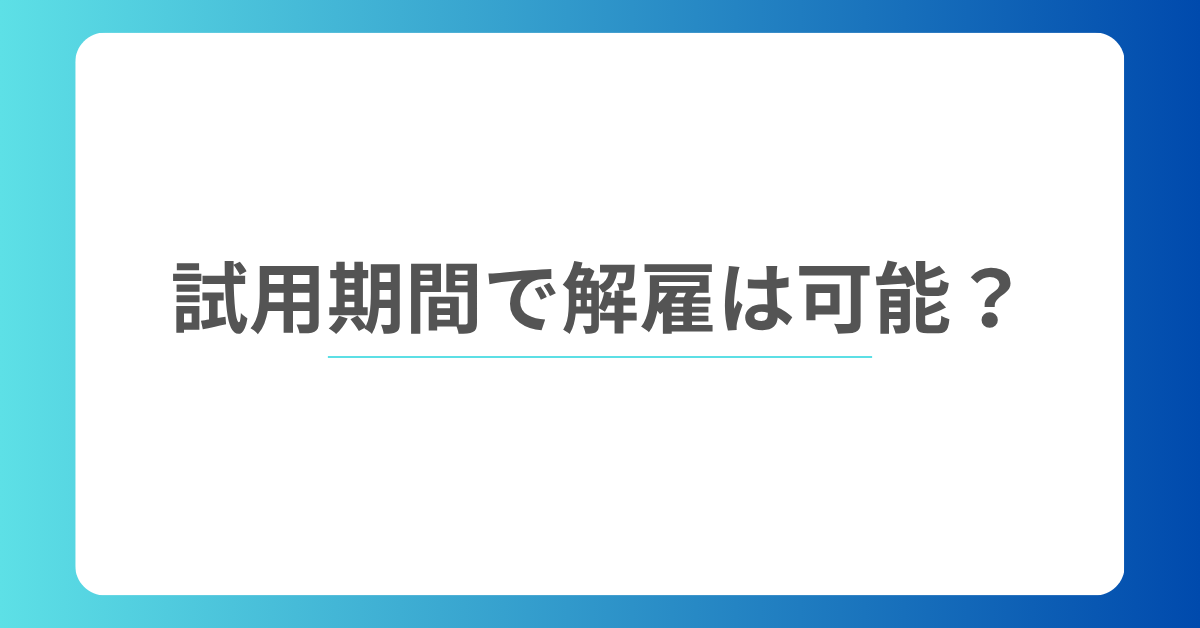仕事を始めてまだ数か月、慣れない職場でようやくペースをつかみかけたころに「試用期間中で終了にしたい」と告げられる——。そんな話を聞くと、不安になりますよね。
一方で、採用側から見ても「思っていた働きぶりと違った」「指導しても改善が見られない」と感じる場面もあるでしょう。
この記事では、試用期間中に解雇が認められる条件や手続き、能力不足や勤務態度を理由にする際の注意点、さらに“クビになる人の特徴”や転職時の影響までを、具体的な事例を交えて解説します。
人事担当者にも働く本人にも役立つよう、法律・現場・心理の3つの視点から整理しました。
試用期間中でも解雇はできるのか?法律上の位置づけを理解しよう
まず大前提として知っておきたいのが、「試用期間中でも労働契約はすでに成立している」ということです。
つまり、正社員と同じ労働契約が締結されており、“本採用前だから自由にクビにできる”というわけではありません。
試用期間の法的な意味
試用期間とは、会社が社員の適性や能力を見極める「評価期間」のこと。
法律上は「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、採用を取り消す可能性を残しつつ働いてもらう仕組みです。
しかし、労働基準法第21条により、試用期間中でも労働者には解雇予告制度が適用されます。
つまり、次の2つが原則です。
- 14日を超えて勤務している場合、30日前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払う
- 解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められる
このため、「ちょっと合わないから」「雰囲気が違うから」という曖昧な理由では認められません。
能力不足を理由に試用期間中の解雇が認められるケース
「能力不足」は最も多い解雇理由のひとつですが、裁判例では非常に慎重に判断されます。
なぜなら、“教育や指導によって改善できる余地”があるとされるからです。
認められる代表的なケース
以下のような場合、能力不足による試用期間中の解雇が認められやすくなります。
- 明らかに基本的な職務が遂行できない(例:営業職で顧客対応の報告を全くしない)
- 指導・注意を繰り返しても改善が見られない
- 面接時に虚偽の経歴やスキルを申告していた
- チーム業務に著しい支障をきたすほど協調性が欠けている
ただし、これらも教育体制や評価記録が残っているかが大切です。
「感覚的にダメだと思った」ではなく、客観的な証拠(指導記録、業務報告、考課シートなど)が必要になります。
能力不足を理由にできないケース
逆に、以下のような場合は違法とされやすいです。
- 業務マニュアルや指導体制が十分でない
- まだ教育期間中で、成果を求める段階にない
- 他の社員と比べて極端に不公平な評価
- 性格・印象など、業務に直接関係しない主観的な理由
試用期間は「会社も教育責任を負う段階」です。
育てる努力を怠ったうえでの解雇は、裁判で無効になる可能性が高いとされています。
勤務態度を理由にした試用期間中の解雇はどこまで許される?
勤務態度の悪さも「評価不適格」とされる要因の一つです。
しかし、ここでもやはり“程度”と“改善のチャンス”が重視されます。
勤務態度による解雇が認められる例
- 無断欠勤や遅刻・早退が繰り返されている
- 上司の指示に対して明確な拒否や反抗的態度をとる
- ハラスメントや社内トラブルを頻発させる
- チームワークを著しく損なう行動(協調性の欠如)
このような場合、職場秩序を乱す行為として「業務適格性の欠如」と判断されることがあります。
ただし、1〜2回の軽微な遅刻や意見の食い違いなどは該当しません。
注意すべきポイント
- 注意・警告を行った履歴(メール・面談記録など)を残す
- 「本人が改善する意思を示したか」を確認する
- 一貫した評価基準を設け、感情的な判断を避ける
人事側の評価が主観的だと、裁判になった際に「不当解雇」とされるリスクがあります。
逆に従業員側も、評価を受け入れる姿勢や改善行動を見せることで、信頼を得やすくなります。
試用期間でクビになる人の特徴と上司が見ているポイント
試用期間は、単に「仕事ができるか」だけでなく、「組織に馴染めるか」も重要な評価項目です。
ここでは、実際の企業人事が挙げる“クビになりやすい人の特徴”をまとめます。
よくある特徴
- 報連相が遅く、問題が大きくなってから報告する
- 指摘を受けても素直に受け止めず、言い訳が多い
- チームよりも個人プレーを優先する
- 周囲とのコミュニケーションを避ける
- ミスを他人のせいにする
企業は「成果」よりも「伸びしろ」を見ています。
たとえスキルが未熟でも、“学ぶ姿勢”がある人は残されやすいのが現実です。
よっぽどのことがない限りクビにはならない?
SNSなどで「試用期間中にクビになるのはよっぽど」と言われますが、実際は業界や企業風土によります。
たとえば、専門職や外資系企業ではパフォーマンス重視の傾向が強く、
結果を出せない場合は3か月以内に契約終了となるケースもあります。
一方で、国内の大手企業や公的機関では教育期間が長く、短期間で解雇するのは極めてまれです。
つまり、「業界×企業文化×上司の裁量」でリスクの度合いが変わります。
試用期間中の解雇は会社都合扱いになる?雇用保険・失業保険の扱い
ここで気になるのが、「試用期間で解雇された場合、失業保険はもらえるのか?」という点です。
能力不足や勤務態度による解雇の場合
原則として、会社都合による退職扱いになります。
ただし、本人に重大な責任がある場合(暴力行為・無断欠勤の長期化など)は「自己都合退職」に分類されることもあります。
そのため、ハローワークでの申請時には「離職票の離職理由」をしっかり確認してください。
間違って“自己都合”として処理されている場合、申立てによって修正が可能です。
受給までの期間と注意点
- 会社都合:待機期間7日後からすぐ支給開始
- 自己都合:3か月の給付制限あり
また、試用期間中に短期離職した場合でも、雇用保険の加入期間が6か月以上あれば受給資格が発生します。
勤務期間が短いと「日額が少なくなる」点には注意が必要です。
試用期間で解雇された後の転職は不利になるのか?
実は、「試用期間中に解雇された=転職が不利」ではありません。
重要なのは、「なぜそうなったのか」を整理し、次の職場にどう活かすかです。
採用担当が見ているポイント
- 自己分析ができているか
- 反省点や改善点を具体的に説明できるか
- 環境や価値観のミスマッチを冷静に話せるか
面接では「前職ではどんな仕事をしていましたか?」と聞かれたときに、
“試用期間で終了した理由”を前向きな形で説明できるかどうかが鍵です。
たとえば、
「業務スピードが求められる職場で自分の得意分野と合わず、
改善の努力を続けましたが結果が出せませんでした。
ただ、その経験で自分には○○分野が向いていると気づき、
今はその方向で挑戦しています。」
という言い方なら、誠実さと学習姿勢が伝わります。
試用期間の解雇を回避するためにできる行動
解雇は最終手段ですが、避けられるケースも多いです。
現場での印象や信頼関係づくりを意識するだけでも、大きく変わります。
今すぐ実践できる行動例
- 指導された内容はメモし、翌日には改善して見せる
- 朝礼やミーティングで積極的に発言する
- 分からないことは早めに質問する
- 業務終了時に上司へ報告し、安心感を与える
- 同僚や他部署とも挨拶・雑談で関係を作る
これらはどれも「信頼を積み重ねる行為」です。
スキル不足よりも、“態度”で評価が変わるのが試用期間の特徴といえます。
まとめ:試用期間の解雇は慎重に。記録とコミュニケーションが鍵
試用期間中の解雇は、企業にとっても従業員にとっても大きな決断です。
ポイントを整理すると、次のようになります。
- 試用期間でも法律上の保護があり、自由に解雇できるわけではない
- 能力不足・勤務態度の不良でも、改善の余地がある限り解雇は難しい
- 解雇する側は記録・説明責任を、される側は誠実な姿勢と学習意欲を持つ
- 解雇後も転職や再就職に前向きに活かせる
「試用期間=不安な時間」と思うかもしれませんが、見方を変えれば自分を知り、成長するためのチェック期間でもあります。
焦らず、一つひとつ信頼を積み上げていくことが、最良の結果につながりますよ。