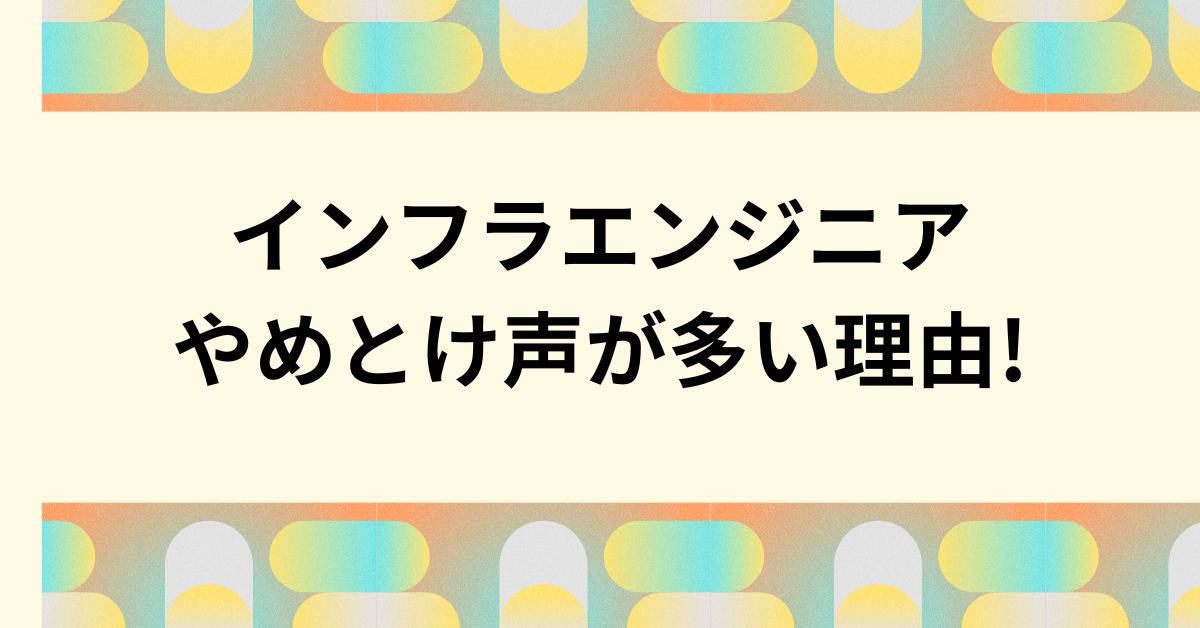「インフラエンジニアはやめとけ」──そんな言葉をネットで見かけて不安になった方も多いのではないでしょうか。実際に2chやSNSでは「きつい」「成長できない」「底辺扱いされる」といったネガティブな意見が散見されます。一方で、「最強の職種」「安定して働ける」と称賛する声もあるのが現実です。
本記事では、こうしたギャップの理由や、後悔しやすい人の共通点、向いている人の特徴、そして今後のキャリア戦略まで、ビジネス目線で深掘りします。
なぜ「インフラエンジニアはやめとけ」と言われるのか?
業務の性質が合わないと“地味でつまらない”と感じる
インフラエンジニアの主な業務は、サーバーやネットワークなど「IT基盤」を支える裏方的なポジションです。可視化されづらく、成果も目に見えにくいため、「つまらない」「やりがいが感じにくい」と感じる人が一定数います。
開発のように新しい機能を作る創造性よりも、安定性・信頼性・手順通りの対応が求められるため、向き不向きが出やすい職種ともいえます。
夜間対応・障害対応の負荷が高い現場もある
特にオンプレミス運用の企業や古いシステムを扱う現場では、「24時間365日監視」や「障害時の深夜対応」が求められることも少なくありません。このようなワークスタイルがライフバランスを崩す要因となり、離職や転職を決断する人もいます。
2chなどで語られる“やめとけ”のリアルな声
ネット掲示板やSNSでは、「インフラエンジニア やめとけ」と検索すると、多くの匿名の本音が出てきます。
- 「開発と比べてスキルアップ感がない」
- 「障害対応ばかりで心が削られる」
- 「クラウド化で将来性が不安」
こうした声が目立つのは、「成長実感が得られにくい環境」で働いているケースが多いからです。逆に、クラウド環境に精通したインフラエンジニアであれば、今後も需要は右肩上がりです。
インフラエンジニアが「楽すぎ」と言われる一面も
一部では「インフラは楽すぎて逆に不安になる」といった声も見受けられます。自動化が進んだ環境や、障害の少ない現場では、確かにルーチン業務のみで日々が過ぎていくケースもあります。
こうした職場では「定時で帰れる」「何も起きなければ仕事が終わる」など、働きやすさはある一方、やりがいを求める人にとっては「退屈」と感じやすいのも事実です。
女性がインフラエンジニアをやめたくなる理由とは
女性がインフラエンジニアの職場において悩むのは、技術の問題よりも職場環境と物理的な負荷が大きいケースが多いです。
- 夜勤や休日対応が家庭と両立しづらい
- 機器搬入などフィジカル面でハードな現場もある
- 男性社会での孤独感
これらが「やめたい」という心理に繋がりやすく、特に出産・育児といったライフイベントとの両立に壁を感じやすい構造があります。ただし、近年ではクラウドインフラやフルリモート型の働き方も増え、女性にも柔軟なキャリアの選択肢が広がってきています。
インフラエンジニアが「底辺」と揶揄される構造的要因
「底辺」という過激な表現が出る背景には、以下のような職種イメージがあります。
- コーディングが不要 → 技術者っぽくない
- 手順書通りに動くだけ → 誰でもできる仕事?
- 下流工程が多い → 上流との関わりが薄い
しかし、これは偏見に近く、現代のインフラエンジニアはむしろクラウドアーキテクチャ設計や**IaC(Infrastructure as Code)**など高度な知識が求められます。定型業務のみのイメージにとらわれると、キャリアを誤解されやすいので要注意です。
実際に「後悔」してしまう人の特徴とは?
インフラエンジニアで後悔してしまう人には、以下のような傾向があります。
- 自分の成果が見えないとモチベーションが下がるタイプ
- 状況変化や障害対応がストレスになるタイプ
- 新しい技術に関心がない人(変化に対応しづらい)
このような方は、開発職や企画・マーケティングなど、成果が可視化されやすい職種の方がマッチしやすいでしょう。逆に「安定志向」「サポート好き」「縁の下タイプ」であれば、インフラの魅力を感じやすいです。
向いている人の特徴とスキル資産化の方法
向いている人の特徴
- トラブル対応を冷静に処理できる
- マニュアルや手順書を着実にこなせる
- 安定した稼働・運用に価値を感じられる
- 周囲のサポートや裏方的貢献が好き
- 地味な作業でもコツコツ継続できる
向き不向きが激しい職種であるからこそ、自分の性格や価値観を見極めることが重要です。
スキル資産化の具体策
- AWSやAzureなどのクラウド資格取得
- Python・Shellスクリプトなどによる自動化スキル習得
- セキュリティやネットワーク知識の横展開
- SREやDevOps分野へのステップアップ
「最強」と言われる側面とその根拠
安定的なインフラは、すべてのITサービスの土台です。そのため、一定のスキルがあるインフラエンジニアは、
- 不況でも需要が高い
- クラウド転換期における重要な存在
- 運用スキルがあることでプロジェクト全体を理解できる
といった理由で「最強職種」として評価されることもあります。特にSRE(Site Reliability Engineering)やクラウド設計に関わるエンジニアは、今後さらに報酬・地位ともに高まっていく見込みです。
インフラエンジニアとして後悔しない働き方戦略
- 属人的な環境から脱却する
ドキュメント整備や自動化によって、自分だけがわかる仕事から脱する。 - クラウドスキルに移行する
オンプレ専属では将来的に市場価値が下がる可能性がある。AWSやGCP、Terraform等の知識を積極的に吸収していくことが重要です。 - チーム内の“潤滑油”になる
技術だけでなく、調整・対話・支援といった“ソフトスキル”がキャリア持続において武器になる。
まとめ|「やめとけ」ではなく、自分に合っているかどうか
インフラエンジニアという職種に対しては、「やめとけ」「楽すぎる」「底辺」といった極端な評価が並ぶ一方で、「最強」「安定」「必要不可欠」というポジティブな見方も存在します。大事なのは、周囲の声に流されるのではなく、自分の価値観とマッチしているかどうかを見極めることです。
向いていれば、地味な仕事の中にもやりがいを見つけ、クラウド時代にも活躍できる武器になります。逆に、合わない場合は早めに方向転換するのも一つの戦略です。
「やめとけ」の声を鵜呑みにせず、自分らしいキャリア設計を描いていきましょう。