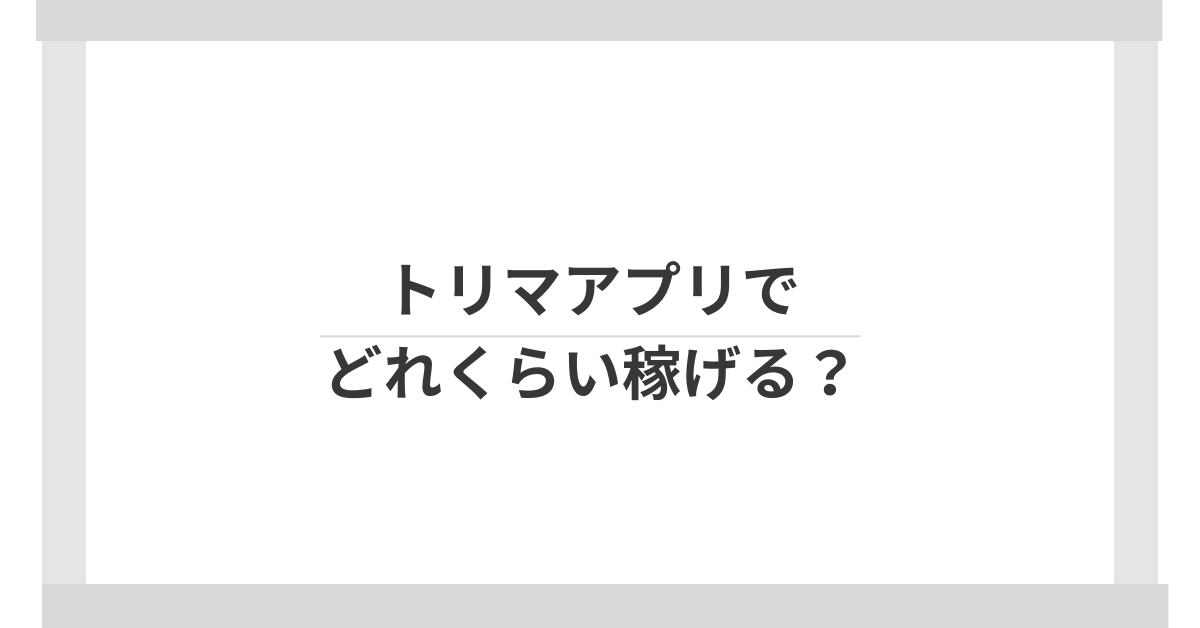スマホを持ち歩くだけでポイントが貯まる「トリマアプリ」。移動や歩数に応じて報酬がもらえるという仕組みで、多くの人が“スキマ時間で稼げる副業アプリ”として注目しました。ところが、実際に使ってみると「思ったより稼げない」「危険性があると聞いた」「位置情報を常に取られているのが不安」といった声も目立ちます。この記事では、トリマアプリがどれくらい稼げるのかを現実的なデータで検証し、副業として成り立たない理由や安全性の真実、そして知恵袋で話題になっている“危険性”の正体をビジネス目線で解説します。業務効率や情報管理の観点からも、利用の判断材料になるはずです。
トリマアプリとは?歩くだけでポイントが貯まる仕組み
トリマ(TRIMA)は、移動距離や歩数をもとに「マイル」というポイントを付与する無料アプリです。貯めたマイルは、Amazonギフト券やdポイント、Google Playギフトなどに交換できます。運営元は日本の株式会社インクリメントPで、地図情報で有名なゼンリンのグループ企業です。そのため、「トリマアプリはどこの国が運営しているの?」という疑問に対しては、“日本国内企業による開発”と明言できます。
トリマアプリの基本的な仕組み
アプリをインストールし、GPSをオンにすることで移動距離を自動計測します。
歩数や移動距離に応じてマイルが貯まり、動画広告を視聴すると追加報酬が得られる仕組みです。
この「広告を見るほどポイントが増える」という構造が、ビジネスモデル上の肝になっています。
トリマは「広告を出したい企業」と「移動情報を提供するユーザー」とをつなぐ仲介役であり、言い換えれば“移動データをマネタイズしているアプリ”ともいえます。
なぜトリマアプリが人気を集めたのか
トリマの人気は、2021年以降のポイ活ブームの中で急速に拡大しました。
背景には次のような要因があります。
- 通勤・通学の移動を「お金に変えたい」というニーズ
- 健康管理アプリとしても使える二面性
- 「歩くだけで稼げる」というキャッチコピーのわかりやすさ
- コロナ禍で外出機会が減り、“運動+報酬”の仕組みが再評価された
こうしたポジティブなイメージが拡散されたことで、多くの人が“副業感覚”で始めました。
しかし、そこには“見えないコスト”も潜んでいます。
トリマアプリでどれくらい稼げる?実際の収益と時間効率
もっとも多い質問が「トリマアプリはどれくらい稼げるの?」というものです。
広告では「毎日歩くだけでお小遣い稼ぎ」と言われますが、現実的には副業レベルの収益は見込めません。ここでは、実際のシミュレーションを通して具体的に見ていきましょう。
平均的な月収は数百円から千円台
一般的な通勤・買い物・ウォーキングユーザーの場合、1日あたりの獲得マイルは数十〜数百マイル程度。
1マイル=約0.001円前後の換算となるため、月間にしておよそ300〜1,000円ほどが相場です。
SNSや知恵袋でも、「1か月で500円前後しか稼げない」との声が多数見られます。
また、営業職やデリバリー業などで一日中移動する人でも、月に2,000〜3,000円程度が限界。
「トリマアプリ どれくらい 稼げる」と検索する人の多くが、“副業として成立するかどうか”を期待していますが、実際のところ「お小遣いレベル」です。
広告視聴による時間単価は10円未満
ポイントを増やすには動画広告を頻繁に見る必要があります。
広告1本につき15〜30秒で、得られるのは数マイル。
これを時給換算すると、1時間に約5〜10円ほど。
つまり、稼ぐための時間を増やすほど“時間対効果(ROI)が悪化”します。
ビジネスパーソンの平均的な時給を考えれば、これは“労働”ではなく“暇つぶし”に近い水準です。
稼ぐよりも健康維持・モチベーション管理ツールとして割り切る
本気で副業収益を目指すより、「運動のきっかけ」「移動のモチベーション維持」として使う方が現実的です。
たとえば、在宅ワークが中心の人が「毎日1万歩を目指すための仕掛け」として活用するのは良い方法です。
このように“行動の習慣化を支えるツール”として割り切れば、ストレスなく続けられます。
トリマアプリの危険性は本当?知恵袋でも話題のリスクを検証
「トリマアプリ 危険性 知恵袋」という検索が多いように、実際に利用した人から不安の声が上がっています。
結論からいえば、トリマアプリ自体が違法・詐欺というわけではありませんが、利用の仕方によっては“情報リスク”や“セキュリティ上の脆弱性”が生じる可能性があります。
常時位置情報ONによるプライバシーリスク
トリマのポイント付与はGPS情報に依存しているため、アプリを起動していなくても位置情報を取得します。
この常時追跡が「怖い」と感じるユーザーも多く、知恵袋でも以下のような書き込みが見られます。
- 「勤務先や自宅の位置が特定されそうで不安」
- 「どこの国に情報が送られているのか分からない」
- 「企業スマホには入れない方がいいと思う」
運営は日本企業ですが、広告配信や分析に海外サーバーを利用するケースがあり、厳密には“完全に国内データで完結している”とは言い切れません。
そのため、ビジネス用途のスマホでの利用は避けた方が無難です。
通信量とバッテリーの大量消費
GPSを常に稼働させるため、通信量と電池の消耗が激しくなります。
特に広告視聴を頻繁に行うと、1日で数百MB〜1GBに達することも。
「スマホが熱くなる」「充電がもたない」「仕事の通話中に電池が切れた」などの声も多く、これも“見えないコスト”のひとつです。
アカウント停止やエラー報告も多数
一部ユーザーからは「マイルが付与されない」「広告が表示されない」「突然アカウント停止になった」といった報告もあります。
こうしたトラブルが“トリマ ひどい”“トリマ やめた”といった口コミにつながっています。
サポート対応が遅いという指摘もあり、信頼性の面では課題が残ります。
トリマアプリの安全性を保つための設定と使い方
危険性があると聞くと不安になりますが、正しい設定と使い方をすれば安全に楽しむことも可能です。ここでは、業務端末でもトラブルを避けるための安全対策を紹介します。
位置情報の権限を「使用中のみ」に制限する
Android・iPhoneの設定から「位置情報を常に許可」ではなく「使用中のみ」に変更することで、アプリを開いていない間の追跡を防げます。
トリマを起動したときだけGPSを有効にする運用なら、情報漏えいリスクは大幅に減ります。
定期的にキャッシュと広告履歴を削除する
アプリ内に蓄積される広告データや閲覧履歴を削除すると、動作の安定性とセキュリティが向上します。
1週間に1度程度、「アプリ情報」からキャッシュをクリアする習慣をつけるのがおすすめです。
ビジネススマホにはインストールしない
業務端末でトリマを利用するのは避けましょう。
移動履歴が勤務先や顧客ルートを示すデータとなる可能性があり、企業情報保護の観点からリスクが高いです。
あくまで個人の私物スマホで楽しむ範囲に留めるのが賢明です。
トリマアプリのデメリットとやめた人の共通点
トリマアプリを利用している人の中には、「最初は楽しかったけど、だんだん面倒になった」「やめた」と感じる層も多く存在します。
彼らが離脱した理由を分析すると、“時間効率”と“報酬の限界”が大きな要因として浮かび上がります。
動画広告のストレスが積み重なる
広告を見ることでマイルが増える仕組みは、一見お得に思えます。
しかし、1日に何十本も見続けると、ストレスが溜まりやすくなります。
「広告を見るのが義務みたいで疲れた」「稼ぐために見てるのに時間を取られる」といった声が多く、心理的な疲弊が離脱の原因です。
報酬が頭打ちになる
トリマはある程度使うと「マイル効率が落ちる」と感じる時期がきます。
動画広告の上限やボーナスミッションの制限があるため、長期利用者ほど収益が減る傾向にあります。
結果、「最初は楽しかったけどもう稼げない」という感想につながるのです。
データ通信費が収益を上回る
広告再生や通信の頻度が増えると、月々のデータ通信量が上がります。
格安SIMユーザーにとっては、追加料金が発生することも。
これでは“実質マイナス収益”になってしまい、やめた人が続出するのも当然です。
トリマアプリ終了の噂は本当?今後の展望を読み解く
一時期SNSで「トリマアプリ終了」という噂が拡散しました。
実際のところ、2025年現在もトリマはサービスを継続していますが、背景にはいくつかの変化がありました。
終了の噂が出た理由
- 広告単価の下落による報酬減少
- アプリのアップデート頻度が減った
- 利用者離れでランキング順位が下がった
これらの状況が重なり、「もう終わるのでは?」という憶測が広まりました。
しかし運営会社は、ユーザー層の維持と新機能開発に引き続き取り組んでおり、完全終了ではありません。
今後の課題と方向性
トリマのような“データ提供型ポイ活”は、プライバシー保護規制が強化される中で厳しい局面を迎えています。
今後の課題は次の3点です。
- 位置情報データの匿名化と透明性向上
- 報酬体系の見直しによる継続利用率の改善
- 健康・フィットネス分野への機能拡張
もし運営がこれらを実現できれば、“健康×マネー”の新市場を再びリードする可能性もあります。
ビジネス視点で見るトリマアプリの価値と限界
企業やフリーランスの間では、トリマのようなアプリを「データマーケティングの教材」として分析する動きもあります。
なぜなら、ユーザーの移動データがリアルな生活導線を示すからです。
トリマが示す“無料アプリの経済構造”
トリマを通じて学べるのは、「無料サービスの裏にはデータ提供がある」という基本構造です。
ユーザーは“歩数”や“位置情報”を提供し、その見返りにマイルを受け取る。
つまり、目に見えない対価として「行動データ」を支払っているのです。
これは多くの無料アプリにも共通する構造であり、ビジネスパーソンにとっては“情報リテラシー教材”としても価値があります。
業務効率の観点からの評価
業務時間中にアプリ広告を再生したり、報酬を確認する行為は生産性を下げる要因にもなります。
また、移動データを業務と混在させると、セキュリティポリシー違反につながる恐れがあります。
したがって、仕事用スマホでは利用を避け、私生活の範囲で完結させるのが理想です。
トリマアプリの代替サービスと比較
トリマの“稼げなさ”や“危険性”が話題になる一方で、他にも似た仕組みのアプリが存在します。代表的なのが「Miles」「スギサポWalk」「aruku&」などです。
- Miles(マイルズ):移動手段を自動判別する海外発アプリ。報酬は少ないが提携店舗が多い。
- スギサポWalk:スギ薬局系列が提供する歩数連動アプリ。健康管理要素が強い。
- aruku&:位置情報ゲーム要素を取り入れた日本発の歩数アプリ。地域連携イベントが多い。
いずれも「健康+インセンティブ」を軸にしていますが、収益性よりも“続けやすさ”や“安全性”が重視されています。
トリマはその中で“広告マネタイズ型”に偏りすぎたことが、今の不信感を招いたともいえるでしょう。
トリマアプリを安全に使いこなすためのまとめ
ここまで解説してきたように、トリマアプリは“危険”と断定できるものではありませんが、正しい理解とリスク管理が欠かせません。最後に、安全に使いこなすためのポイントを整理します。
- 運営は日本企業(インクリメントP)で、基本的には信頼できる
- 位置情報の設定は「使用中のみ」にして常時追跡を防ぐ
- ビジネススマホでは使用しない
- 通信量・バッテリー負担を考え、使いすぎない
- 副業目的ではなく、健康管理やモチベーション維持ツールとして使う
このように利用スタンスを見直せば、トリマアプリは安全かつストレスなく活用できます。
まとめ:トリマは“稼ぐアプリ”ではなく“データ経済の教材”
トリマアプリで稼げる金額は、月に数百円〜数千円が限界です。
危険性の大部分は、位置情報の扱い方や広告視聴の頻度に起因しています。
安全に楽しみたいなら、設定を見直し、「歩くついでにポイントが貯まる程度」と割り切ることが大切です。
ビジネスの視点で見れば、トリマは“データ経済の縮図”でもあります。