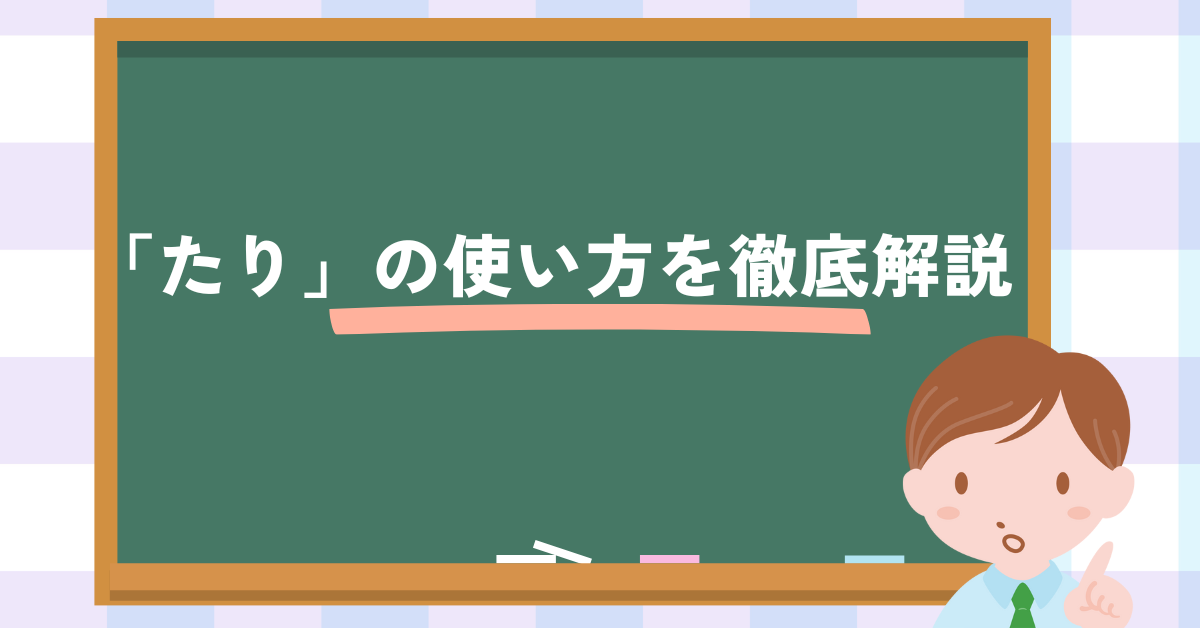日常会話やビジネスメール、論文でもよく使われる「たり」。一見すると簡単に思えるこの表現ですが、実は正しい使い方を知らないまま使っている人も少なくありません。「1回だけでも使っていいのか?」「書き言葉として適切か?」「言い換えるならどうする?」といった疑問に答える形で、本記事では「たり」の文法的な基本からビジネスでの実用例、論文での注意点までを詳しく解説します。
「たり」の意味と基本的な文法構造
「たり」は、日本語において並列する複数の動作や状態を挙げるために使われる接続助詞の一つです。たとえば「食べたり、寝たりする」というように、いくつかの行動を並べるときに用います。ここでのポイントは、すべての行動を列挙するのではなく、“代表例”を挙げる形式であるという点です。
この文法の特徴は、単なる列挙とは異なり、動作の一部を象徴的に提示することで、全体的な傾向や様子を示すという点にあります。「たり〜たり」は、少なくとも2つ以上の動作や状態をバランスよく並べるのが基本的なルールとされています。接続される動詞や形容詞の活用形にも注意が必要で、連用形に「たり」をつけ、最後は「する」や「している」で締めるのが自然な形です。
また、「たり」は文末に使うと、文章にやわらかさや余韻を与える効果もあり、会話では気軽に使われています。たとえば「泣いたりして……」という言い方は、感情の含みを持たせる表現として定着していますが、このような表現はカジュアルな場面に限るべきです。文法的に使いこなすには、形式の正確さと表現の目的を明確に意識する必要があります。
「たり」を1回だけ使うのは正しいのか
「たり」の使い方においてよくある誤解が、「1回だけ使ってよいのか?」という疑問です。文法的な観点では、「たり」は複数の事例を並列に並べる働きを持っているため、最低2回以上の使用が基本となります。
たとえば「泣いたり。」だけで終わる文は、本来ならばもう一つ別の行動が並ぶべきで、「泣いたり、笑ったりした」のように、対になる動作が必要です。とはいえ、会話表現ではあえて一つの動作だけを挙げて含みを持たせる「省略的表現」として成立することもあります。「最近は忙しかったり……」というように、文末を曖昧にぼかす言い回しも、話し手の意図や感情が背景にあるため、自然な表現として認識されています。
しかし、ビジネス文書や論文ではこのような表現は適しません。あいまいさや文の不完全さは、読み手に誤解を与える原因になります。正確な意図を伝えるためには、必ず「たり」を2回以上使い、文章全体を完結させることを心がけましょう。
「たり〜たり」は何回まで使っていいのか
「たり〜たり」は、基本的には2つの動作や状態を挙げる構文ですが、3回以上繰り返すことも可能です。たとえば「走ったり、泳いだり、飛んだりして遊びました。」というような文も文法的には問題ありません。
とはいえ、3つ以上の「たり」を使う場合は、文が冗長になったり、リズムが悪くなることもあります。特に論文やビジネス文書では、明快で簡潔な文章が好まれるため、必要以上に「たり」を多用するのは避けた方が良いでしょう。
また、3回以上使う場合は、動作に一定の共通性やテーマ性があるかを意識することが重要です。たとえば、「資料を印刷したり、配布したり、説明したりした」は、業務の流れが一貫しているため自然ですが、「掃除したり、会議したり、飲みに行ったりした」では、活動の性質がばらばらで違和感を覚える可能性があります。
文章を読みやすく保つには、2つの「たり」で収めるのが理想ですが、文脈によっては3回以上使うこともあり得ます。その際は、行動の整合性とリズムを意識しながら、必要に応じて別の接続表現に切り替える柔軟さも大切です。
「たり〜たり」の文法的な注意点
「たり〜たり」構文を使用する際には、文法的な整合性に十分注意を払う必要があります。まず、並列される動詞や形容詞は、文法上の形式を一致させることが原則です。たとえば、「読んだり、書いたりする」は正しいですが、「読んだり、資料作成」では動詞と名詞が並んでしまい、文のバランスが崩れます。
さらに、「たり」は必ず動詞の連用形(〜た)に付くものであるため、「走るたり」や「見るたり」は誤用になります。正しくは「走ったり」「見たり」となり、そこから「〜した」といった終止形に結びつけるのが基本構造です。
もうひとつ注意したいのは、「たり」を使う文の終わり方です。文末を「〜している」「〜した」とすることで、並べた動作をひとつの意味にまとめあげることができます。これが抜けると、文章として未完の印象を与え、読み手に違和感を残す結果となります。
つまり、「たり〜たり」は単なる装飾的な並列表現ではなく、意味のまとまりや文全体の構成を左右する重要な役割を果たしているのです。正しく使うためには、動詞の活用形、文末表現、論理的な関係性に注意を払うことが不可欠です。
書き言葉としての「たり」の適切な使い方
「たり」は柔らかく、曖昧さを含んだニュアンスを持つため、書き言葉では使いどころに配慮が必要です。特にビジネス文書では、意図を明確に伝えることが重要なため、「〜したり、〜したりしました」といった表現が繰り返されると、読み手に稚拙な印象を与えるリスクがあります。
書き言葉として「たり」を使う際は、「列挙する必要があるのか」「簡潔に書き直せないか」といった視点で文章を見直すことが大切です。たとえば、「説明したり、質問に答えたりしました」という文は、「説明と質疑応答を行いました」と置き換えることで、より端的で洗練された印象になります。
また、社外文書や論文では、「たり〜たり」はカジュアルに見える場合があるため、「〜や〜を行いました」「〜を含む業務を実施しました」といった、より客観的で定型的な言い換えが推奨されます。文章の目的と相手に応じて、表現のレベルを調整することが、信頼性のある書き手としての第一歩です。
論文での「たり〜たり」の使い方と言い換え例
論文や研究報告においては、「たり〜たり」は基本的に避けた方がよい表現とされています。理由は、文章が口語的・あいまいな印象を与える可能性があるからです。学術的な文章では、簡潔で厳密な表現が求められるため、動作や内容は明示的に書く必要があります。
たとえば、「観察したり、インタビューしたりした」という表現は、「観察およびインタビューを実施した」と書き換えることで、論文としてふさわしい堅実な文体になります。また、「検討したり、分析したりした結果」は、「検討と分析を経た結果」と要約することで、文章が簡潔で伝わりやすくなります。
言い換えには以下のような形式が使えます:
- 「〜したり、〜したりする」→「〜および〜を実施する」
- 「〜に参加したり、〜を確認したりした」→「〜と〜を行った」
このように、論文では「たり」の代わりにより正確な名詞化・動詞化の表現を使うことで、文章の信頼性と整合性が高まります。文体の一貫性が求められるアカデミックな場面では、特に注意すべきポイントです。
ビジネスで「たり」を使うときの言い換えテクニック
ビジネス文書でも「たり〜たり」は便利に使える表現ですが、ややくだけた印象を与えることがあるため、状況に応じて言い換える工夫が必要です。特に外部の取引先や上司に送るメール、報告書などでは、端的で丁寧な表現が求められます。
たとえば、「連絡したり、対応したりしました」は「連絡と対応を行いました」と置き換えると、すっきりとした印象になります。また、「説明したり、確認したりして対応しました」は「説明と確認を通じて対応しました」にすると、文章の品位が高まります。
このような言い換えは、文章をビジネス用途に適したものへと昇華させる技術でもあります。「たり〜たり」は便利な一方で、使いすぎると冗長になりがちです。読み手の立場や書く目的に応じて、「たり」を活用するか、他の表現に切り替えるかを判断する視点を持つことが大切です。
「たり」の例文で理解を深める
最後に、実際の使用例を通して「たり」の使い方を確認してみましょう。具体例に触れることで、文脈に応じた適切な使い方のイメージが明確になります。
【ビジネスメールでの例】 「本日は資料作成を行ったり、クライアント対応をしたりしておりました。」 → よりフォーマルにするなら「本日は資料作成およびクライアント対応を実施しておりました。」
【社内報告書の文面】 「週明けは商談に出たり、社内会議に参加したりと多忙な日々でした。」 → 報告書向けには「週明けは商談と会議が重なり、多忙な日々となりました。」が適切
【論文での事例】 「本調査では、観察を行ったり、ヒアリングを実施したりした。」 → 書き換え例:「本調査では、観察およびヒアリングを実施した」
まとめ:適切な「たり」の使い方が信頼をつくる
「たり」は便利な接続表現でありながら、使い方を誤ると曖昧さや冗長さを生み、文章の質を落としてしまうリスクもあります。特にビジネス文書や論文のように、正確で論理的な文章が求められる場面では、「たり」の多用や一回だけの使用は避けるべきです。
本記事では、「たり」の文法的基本から、一回だけの使い方、3回以上繰り返す場合の注意点、書き言葉としての適切な使い方、論文・ビジネスでの言い換えテクニック、そして例文による実践的な使い方まで、幅広く解説してきました。
まずは、日常業務のメールや報告書の中で、「たり」を使った表現を見直してみてください。そして、場面に応じた最適な表現に言い換える意識を持つことで、文章全体の印象がぐっと洗練されます。伝わる文章には、細部への配慮が宿ります。「たり」という小さな接続詞も、読み手の印象を大きく左右する重要なパーツであることを忘れないようにしましょう。