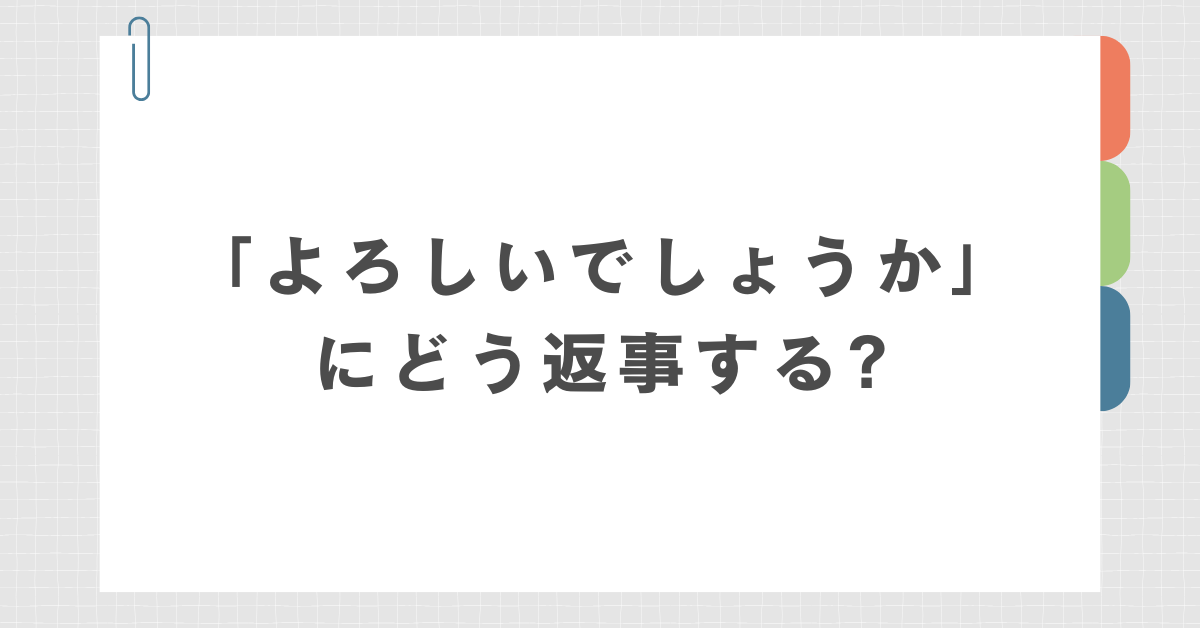ビジネスメールややり取りの中で「よろしいでしょうか」と尋ねられたとき、どう返事すればいいのか迷った経験はありませんか。承諾なのか、確認中なのか、あるいは訂正が必要なのかによって、適切な返信は変わります。この記事では、ビジネスシーンで失礼にならない「よろしいでしょうか」への返答方法を、具体例を交えながら解説します。読み終えるころには、あらゆる場面で自然に使えるフレーズが身につきますよ。
「よろしいでしょうか」に対する基本的な返事の仕方
「よろしいでしょうか」とは、相手が承諾や確認を求める際に用いる丁寧な表現です。そのため、返事の基本は「了承する」「保留する」「訂正する」の三つに分けられます。状況に合わせて正しく返すことで、信頼関係やスムーズな業務進行につながります。
承諾を伝える場合の返答例
相手の依頼や確認に同意する場合は、前向きかつ簡潔な返答が求められます。「大丈夫です」だけではややカジュアルなので、ビジネスメールでは以下のような表現が適しています。
- 「承知いたしました」
- 「問題ございません」
- 「その認識で相違ございません」
例えば、資料送付のスケジュール確認に対して「承知いたしました。予定どおり進めていただければ幸いです」と返せば、丁寧で安心感を与えられます。
保留や調整を伝える場合の返答例
すぐに返答できないときに「大丈夫です」と答えてしまうと、あとで訂正が必要になるリスクがあります。そうした場面では一度確認を挟む表現が適切です。
- 「確認のうえ、改めてご連絡いたします」
- 「社内で調整し、後ほどご回答申し上げます」
たとえば、会議日程を提案されたときに「一度社内で調整し、改めてご返信申し上げます」と返せば誠実な対応になります。
訂正を伝える場合の返答例
相手の認識や理解が誤っている場合には、やんわりと正しい内容を伝える必要があります。
- 「恐れ入りますが、〇〇の点については△△となります」
- 「ご提示いただいた内容につきまして、一部訂正させていただきます」
例えば「資料の締め切りは15日でよろしいでしょうか」と聞かれた際に「恐れ入りますが、締め切りは20日でございます」と返せば、角を立てずに修正が可能です。
「よろしいでしょうか」返事のビジネスメール例文
実際のビジネスメールでは、承諾・保留・訂正の三つを状況に応じて使い分ける必要があります。ここでは具体的なメール文例を紹介します。
承諾を伝えるメール例文
件名:資料送付の件について
本文:
株式会社〇〇
△△様
いつもお世話になっております。
ご確認いただきました件、承知いたしました。
ご提示いただいた内容で進めていただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
□□株式会社
営業部 山田
このように「承知いたしました」「進めていただければ幸いです」と添えることで、安心感のあるやり取りが実現します。
保留を伝えるメール例文
件名:会議日程の件
本文:
株式会社〇〇
△△様
お世話になっております。
会議日程の件につきまして、ご提案ありがとうございます。
ただいま社内で調整を行っており、改めてご連絡いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
□□株式会社
総務部 佐藤
このように「改めてご連絡いたします」と書けば、すぐに返事できない状況でも丁寧に伝えられます。
訂正を伝えるメール例文
件名:納期の確認について
本文:
株式会社〇〇
△△様
お世話になっております。
ご確認いただいた件につきまして、恐れ入りますが納期は15日ではなく20日でございます。
ご認識を改めていただけますと幸いです。
引き続きよろしくお願いいたします。
□□株式会社
生産管理部 田中
このように「恐れ入りますが」と前置きすることで、相手に不快感を与えずに修正が可能です。
「よろしいでしょうか」返事の敬語の使い分け方
ビジネスメールでは、相手との関係性に応じた敬語の使い分けも大切です。上司や取引先に対しては特に注意が必要です。
上司への返答の仕方
上司から「よろしいでしょうか」と尋ねられた場合、カジュアルすぎる返答は避けたほうが無難です。
- 「承知いたしました」
- 「かしこまりました」
- 「そのようにいたします」
「大丈夫です」とだけ答えると軽い印象を与えてしまうので、目上の人には控えましょう。
取引先への返答の仕方
取引先や顧客に対しては、さらに一歩丁寧さを加えると信頼関係につながります。
- 「ご指示いただいた内容で進めてまいります」
- 「ご認識のとおりでございます」
- 「問題なく対応可能でございます」
こうした表現を選ぶと、プロフェッショナルな印象を与えられます。
「よろしいでしょうか」返事で使えるフレーズとNG表現
最後に、実務でよく使うフレーズと避けたほうがいい表現を整理します。
使えるフレーズ
- 「承知しました」
- 「問題ございません」
- 「その認識で相違ございません」
- 「確認のうえご連絡いたします」
- 「恐れ入りますが、△△となります」
これらは状況に応じてそのまま使える便利なフレーズです。
避けるべき表現
- 「大丈夫です」
- 「OKです」
- 「いいですよ」
これらはカジュアルすぎて、ビジネスメールには不向きです。気心の知れた同僚であれば問題ありませんが、上司や取引先には避けましょう。
「認識でよろしいでしょうか」への返事例
ビジネスメールでは「この認識でよろしいでしょうか」と確認を求められることがよくあります。これは「私の理解が正しいかどうか確認したい」という意味であり、丁寧に答える必要があります。
認識が正しい場合の返事例
- 「ご認識のとおりでございます」
- 「そのご理解で問題ございません」
- 「記載の内容に相違ございません」
例えば、契約内容の条項確認に対して「ご認識のとおりでございます。引き続きよろしくお願いいたします」と返すと、相手に安心感を与えられます。
認識が一部誤っている場合の返事例
- 「ご認識いただいた点のうち、納期は20日ではなく25日となります」
- 「恐れ入りますが、一部内容が異なりますので訂正させていただきます」
このとき「違います」とだけ答えるのは不親切なので、どこが正しく、どこを修正すべきかを具体的に伝えることが大切です。
「理解でよろしいでしょうか」への返答方法
「理解でよろしいでしょうか」は、相手が説明を受けたあとに「この理解で正しいですか」と確認している表現です。適切に答えることで、誤解を防ぎ、業務を円滑に進められます。
理解が正しい場合
- 「そのご理解で差し支えございません」
- 「はい、その通りでございます」
- 「ご理解いただいた内容で問題ございません」
例えば「本件は来週までに対応すればよろしいという理解でよろしいでしょうか」と聞かれた場合に、「はい、その通りです。来週中のご対応をお願いいたします」と返すとスムーズです。
理解が誤っている場合
- 「恐れ入りますが、その点については誤解がございます」
- 「一部異なりますので、改めてご説明いたします」
- 「正しくは〇〇でございます」
このときは必ず代替の正しい情報を提示することが重要です。ただ「違います」では相手を戸惑わせてしまうため、修正と説明をセットで伝えるようにしましょう。
「お待ちいただいてもよろしいでしょうか」への返事例
「お待ちいただいてもよろしいでしょうか」は、相手から猶予をお願いされるフレーズです。返答は「待てる」「待てない」の二択に分かれますが、どちらにせよ丁寧に伝える必要があります。
待てる場合
- 「承知いたしました。お待ちいたします」
- 「問題ございませんので、ご準備が整いましたらご連絡ください」
- 「かしこまりました。対応完了までお待ち申し上げます」
例えば、資料作成に時間がかかると言われた場合に「承知いたしました。ご準備が整い次第ご連絡いただければ幸いです」と返せば安心してもらえます。
待てない場合
- 「大変恐れ入りますが、〇日までにご対応いただけますでしょうか」
- 「恐縮ですが、急ぎで必要なため、本日中にお願いできますでしょうか」
待てない場合でも、強い言葉ではなく「恐れ入りますが」「恐縮ですが」といったクッション言葉を添えることで、相手への配慮を示せます。
「よろしいでしょうか」のカジュアルな場面での返答(メルカリなど)
ビジネス以外の場面では、「よろしいでしょうか」に対する返答はもっと柔らかく、カジュアルで構いません。フリマアプリや日常会話では、堅苦しい敬語を避けて自然に答えると良いです。
カジュアルな返答例
- 「はい、大丈夫です」
- 「問題ないですよ」
- 「よろしくお願いします」
例えばメルカリで「こちらのお値段でよろしいでしょうか」と聞かれたときは、「はい、大丈夫です。よろしくお願いします」と返せば十分です。
注意点
ビジネスと異なり、あまりに堅苦しいと不自然になってしまいます。取引相手が個人の場合は、適度に柔らかい言葉を選んだほうが好印象です。ただし、最低限の丁寧さは保つことが信頼につながります。
まとめ
「よろしいでしょうか」という問いかけに対する返事は、状況や相手との関係性によって最適な表現が異なります。
- 承諾なら「承知いたしました」「問題ございません」
- 認識・理解が正しい場合は「そのとおりでございます」
- 間違いがあるときは「恐れ入りますが〜」と訂正を添える
- 待つ場合は「承知いたしました」、待てない場合は「恐縮ですが〜」
- カジュアルな取引では「大丈夫です」「よろしくお願いします」
このように柔軟に使い分けることで、相手に安心感と信頼を与えられますよ。ビジネスメールから日常のやり取りまで、「よろしいでしょうか」に対する返事の引き出しを持っておくと、今後のコミュニケーションがぐっとスムーズになるはずです。