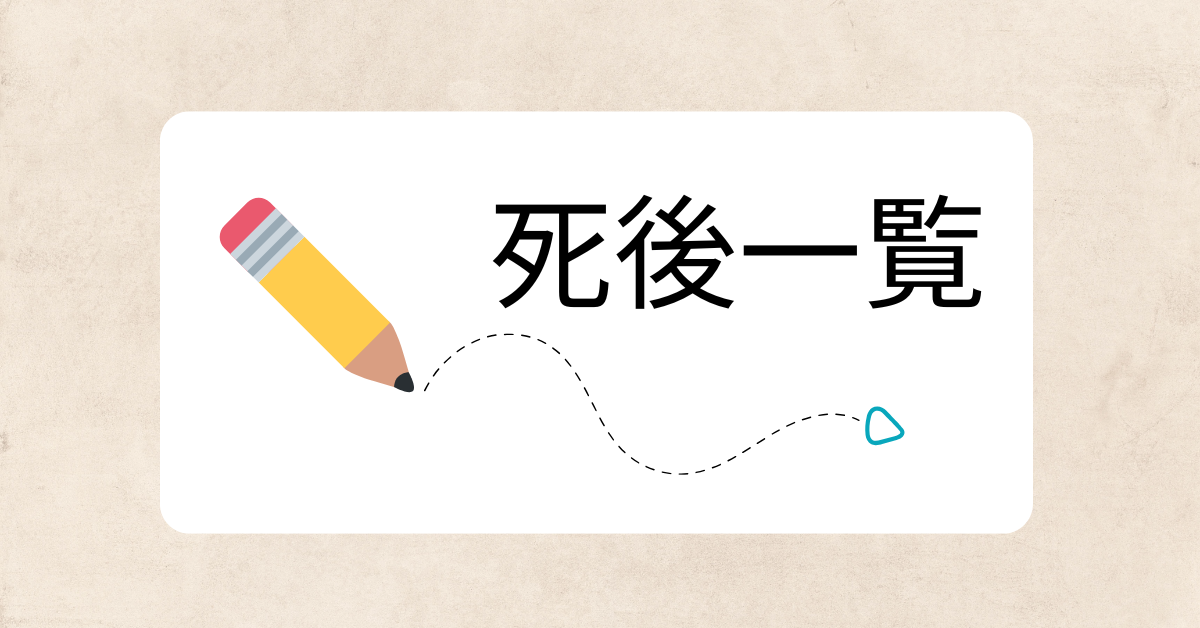日々変化する日本語の中で、かつては当たり前のように使われていた言葉が、時代の流れとともに“死語”として扱われるようになってきました。特にビジネスの場面では、無意識のうちに使っている古い表現が、若手社員に通じなかったり、思わぬ誤解を生んだりすることもあります。この記事では、現在あまり使われなくなった死語の一覧とその背景を紹介しながら、現代に適した表現への置き換え方を解説します。
死語とは何か?意味とビジネスでの影響
“死語”とは、かつて一般的に使われていたものの、現在ではほとんど使われなくなった言葉を指します。言語の進化とともに言い回しや価値観が変わり、時代遅れとなった単語は自然と使われなくなります。
ビジネスシーンでの影響は特に大きく、世代間の感覚差がある場面では、死語が「古臭い」「通じない」「空気が読めていない」といった印象を与えることも。特に営業や広報など対人コミュニケーションが多い職種では、言葉のアップデートが欠かせません。
今では使われなくなった死語一覧とその背景
以下は、SNSや若年層に通じにくくなった代表的な死語の一覧です。ビジネスで不用意に使っていないか、チェックしてみましょう。
昭和・平成を象徴する死語一覧表
- グロッキー:体調が悪い状態。元はボクシング用語。今では「ダウン気味」「体調不良」と表現することが多い。
- マブダチ:特に親しい友人の意味。現在は「親友」「地元の友達」「リア友」などに置き換えられています。
- ナウい:今風・流行していること。今では「トレンド」「最新」「イマドキ」が一般的です。
- イケてる:魅力的、かっこいいという意味。今なら「垢抜けてる」「オシャレ」などが使われます。
- もち:「もちろん」の略。略語文化としては残っているが、現在はあまり使われません。「当然」「OKです」などが適切です。
- しごでき:「仕事ができる」の略称。ビジネススラングとして一時期使われたが、若手にはかえって不自然で自己主張が強いと受け取られることも。今は「有能」「段取り上手」「頼れる人」などの文脈で表現される。
これらは昭和~平成初期に多用された言葉であり、若手には通じないどころか、冗談のように受け取られる可能性もあります。
死語ランキング:ビジネスで使ってしまいがちな表現とは?
ビジネスシーンで実際に“使ってしまう死語”をランキング形式で紹介し、その代替表現も合わせて提示します。
- 了解しました(目上には不適切) → 「承知しました」「かしこまりました」
- ガラケー(前提がすでに死語) → 「フィーチャーフォン」「従来型携帯」など、必要なら説明付きで使用
- チョベリバ/チョベリグ → 全く通じない。感情表現は「最悪」「最高」などでシンプルに
- KY(空気読めない) → 今では「鈍感」や「言葉を選ばない」といった直接的な表現が主流
- イミフ → 意味不明の略だが、Z世代には逆に古い印象を与えるため避けるのが無難
これらの表現は、本人は“軽いノリ”のつもりでも、受け手によっては不快や違和感につながる恐れがあります。
死語を使うとどうなる?世代間ギャップと印象への影響
社内コミュニケーションで死語を使った場合、以下のような課題が発生する可能性があります:
- 若手社員に通じず、説明の手間が増える
- 無理に若者言葉を使っているように見え、違和感を与える
- 顧客との会話で相手の年代とズレることで空気を壊す
特に「それな」といった一見若者っぽい言葉であっても、Z世代からは“古い”とされ始めている例もあります。「それな 死語 代わり」で検索される背景には、最新の言い回しを模索するビジネスパーソンのニーズも伺えます。
「それな」の代わりに使える表現
- 「共感しかない」
- 「まさにそれ」
- 「完全に同意です」
TPOに応じて言葉のチョイスを変えることで、柔軟でスマートな印象を持たれるようになります。
死語を現代風に言い換えるポイント
では、死語を避けながら、現代的な言葉に置き換えるにはどうすればよいのでしょうか?以下の視点が重要です。
ポイント①:単語の“目的”を明確にする
死語の多くは、「軽い冗談」「親しみ」「略語」などの目的で使われていました。これを現代に置き換える際には、伝えたい意図をシンプルな言葉に分解してから選ぶことがコツです。
ポイント②:相手世代の使う言葉を観察する
Z世代がよく使うチャット、SNS、YouTubeのコメントなどに注目すると、言葉のトレンドや文脈が見えてきます。特に「略語ではなく丁寧な言葉回し」がビジネスでは好まれる傾向にあります。
ポイント③:敬語とカジュアルのバランスを調整する
死語を回避するだけでなく、硬すぎず柔らかすぎず、適度な距離感のある言葉を選ぶことが重要です。たとえば「よろしくでーす」は砕けすぎですが、「よろしくお願いいたします」では堅すぎる場面も。「よろしくお願いします(^^)」のようなニュアンス調整も選択肢の一つです。
ビジネスで“伝わる言葉”を選ぶ意味
業務効率の向上や円滑な人間関係づくりのためには、伝わる言葉を選ぶことが不可欠です。伝わらない言葉は、単に意味が通じないだけでなく、相手との信頼関係にも影響を与えます。
特に社内・社外のチャットツールやプレゼン、営業メールなどの文章表現においては、“言葉選び=配慮の現れ”ととらえられることも少なくありません。死語の使用は、相手の世代・文脈・文化に対する理解の欠如と見なされてしまうこともあるのです。
まとめ:死語をアップデートするだけで、あなたの印象は変わる
「昔ながらの言い回しが安心する」という人も多いかもしれませんが、それが時代に合わなくなっているのであれば、コミュニケーションの妨げになりかねません。死語をアップデートすることは、単なる言葉の置き換えではなく、“伝える力”の質を上げる行動です。
ビジネスシーンでの印象を良くし、業務の効率を高めるためにも、自分が無意識に使っている言葉を見直してみることをおすすめします。世代や業種を越えて「通じる表現」を選ぶ力こそが、今後のビジネスコミュニケーションに求められるスキルとなるでしょう。