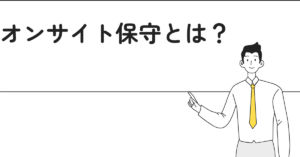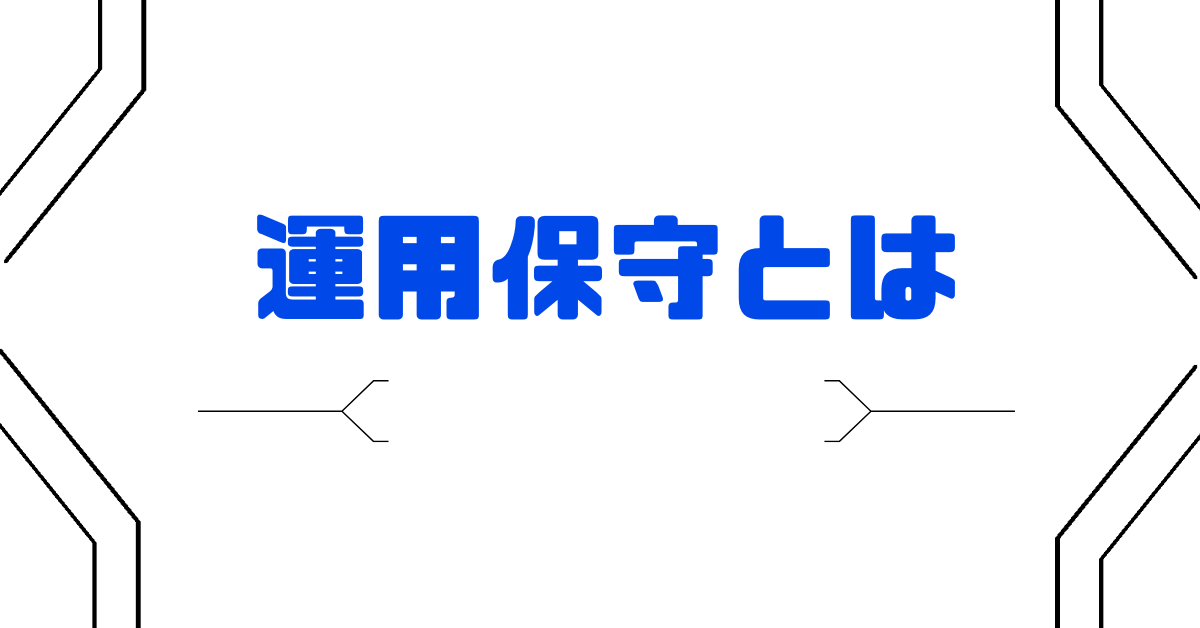「運用保守って地味だし、将来性もなさそう…」そんなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか? しかし、ITインフラの根幹を支える運用保守は、実は非常に重要かつ専門性の高い業務です。 本記事では、運用保守の仕事内容や相場金額、開発との違い、さらに「やめとけ」「底辺」「きつい」と言われる理由を掘り下げながら、リアルなキャリアの選び方について解説していきます。
運用保守とは?IT業界における役割と定義
運用保守とは、ITシステムやアプリケーションを安定して動かし続けるために、日々の監視・障害対応・アップデートなどを行う業務です。 IT業界の中でも、”縁の下の力持ち”的な存在として重要視されています。
運用とは
- サーバー・ネットワークの監視
- 定期的なバージョンアップ対応
- セキュリティパッチの適用
- 業務システムの稼働チェック
保守とは
- 障害発生時の対応と復旧
- 不具合調査・修正
- 問い合わせ対応(ユーザーサポート)
- 機器・ソフトの入れ替え対応
この2つを総称して「運用保守」と呼びます。
運用保守の仕事内容をもっと詳しく
主な業務内容
- 監視ツールを使った24時間体制のモニタリング
- システム障害発生時のエスカレーション対応
- ITILに基づいた変更管理・インシデント管理
- 定型業務(ログ取得、バッチ実行)
- 手順書やマニュアルの整備・更新
現場による差異も大きい
現場によっては、手順書に沿ったオペレーション業務中心の場所もあれば、コードに手を加えるような高度な対応が求められることも。 そのため「仕事が単調」「やりがいがない」と感じるか、「重要な役割だ」と感じるかは職場環境次第です。
保守運用で依頼できる範囲
インフラ系:サーバー・ネットワーク保守運用
依頼できる内容
- サーバー・ネットワークの死活監視(Zabbixなどを使用)
- パフォーマンスモニタリング(CPU・メモリ・ディスク使用率など)
- セキュリティパッチ適用・OSアップデート
- バックアップ設計と運用・リストア対応
- ハードウェア障害時の代替機手配・ベンダー調整
- 障害時のログ解析・原因調査・再発防止策立案
アプリケーション保守運用
依頼できる内容
- エラー監視(例:500系エラー、API障害など)
- バグ修正(軽微なロジック不具合や表示崩れなど)
- アップデートに伴うテスト・動作確認
- リリース後の保守対応(ログ確認・不具合一次対応)
- UI/UXレベルの小修正(HTML/CSSレベル)
※コード改修が必要な場合は、保守契約内か開発案件化するかを事前に要確認
セキュリティ・アカウント管理
依頼できる内容
- アクセス制御(Active Directory管理など)
- 権限管理ポリシーの運用
- 不正アクセス監視・通知対応
- SSL証明書の期限監視・更新
- セキュリティログのレビューとレポート作成
ヘルプデスク・ユーザーサポート
依頼できる内容
- 社内ITサポート(PC設定・アカウント管理など)
- ユーザーからの問い合わせ1次受け
- トラブル時のエスカレーション対応
- FAQ更新・手順書作成・マニュアル整備
定期運用タスク・自動化支援
依頼できる内容
- バッチ処理・定型レポート出力
- 業務日次・月次スケジュールの実行管理
- 運用手順書の見直し・標準化
- 自動化スクリプトの改善・簡易的な作成(Shell, PowerShell, Pythonなど)
- RPA導入支援(WinActor, UiPath等)
レポート・改善提案
依頼できる内容
- 稼働状況の月次・四半期レポート作成
- MTTR(平均修復時間)や稼働率の可視化
- 継続的な改善提案(効率化、コストダウン、障害低減)
- キャパシティプランニング(リソース増強提案など)
SLA(サービスレベル契約)に基づく依頼
大規模システムや高信頼性が求められるケースでは、以下のような明確な運用体制を保守契約で取り決めます。
- 24時間365日対応(NOC/BPO連携)
- 障害対応の初動時間(例:15分以内対応)
- リカバリー時間(例:1時間以内復旧)
- 定期報告会・レビュー対応
開発との違いとは?保守運用とどっちがいい?
開発との違い
| 比較項目 | 運用保守 | 開発 |
|---|---|---|
| 役割 | システムの安定運用を支える | システムを新規構築する |
| 主なスキル | 問題解決力、インフラ知識 | プログラミング、設計力 |
| 働き方 | シフト制も多く24時間体制もある | 比較的裁量労働が多い |
| キャリアパス | ITインフラ、セキュリティなど | エンジニア→PM、CTOなど |
保守運用・運用保守の違い
言葉の違いに過ぎない場合もありますが、
- 「運用保守」=運用がメイン、保守が従属的
- 「保守運用」=保守を中心に、運用業務も含む という文脈で使われることがあります。求人票などでよく確認しましょう。
運用保守はやめとけ?底辺?そう言われる理由と実態
よくあるネガティブな声
- スキルが身につかない
- 年収が上がりにくい
- 開発のような成果が見えづらい
- 単調な仕事が多い
でも、それ本当?
確かに「手順通りの作業だけ」ならスキルは伸びづらいですが、
- 複雑な障害対応
- セキュリティ対策
- 自動化や効率化提案 などに取り組める職場では、十分に専門性が高まります。
また、インフラやクラウドの知見がある運用保守エンジニアは、むしろ需要が高いのが実情です。
システム運用保守はきつい?現場のリアルと向いている人
どこが「きつい」と言われるのか?
- 夜勤やシフト制(特に監視業務)
- 障害発生時のプレッシャー
- 休日・深夜の緊急呼び出し
向いている人の特徴
- 地道な作業を丁寧にできる
- 危機管理能力が高い
- 状況に応じて冷静な判断ができる
- チームプレーが得意
相場金額・年収はどれくらい?
平均年収の目安
| 経験年数 | 年収の目安 |
| 未経験〜2年 | 300〜400万円 |
| 3〜5年 | 400〜500万円 |
| 5年以上 | 500〜650万円以上も可 |
ただし、夜勤手当や深夜割増、保守対応手当などで年収にバラつきが出る場合もあります。
案件単価の例(SES)
- 監視・オペレーション:月40〜60万円
- インフラ運用:月60〜80万円
- クラウド保守:月80万円以上も
運用保守は英語で何と言う?
ビジネス文脈では以下のように表現されます:
- IT Operations and Maintenance
- System Operation and Support
- Application Maintenance
グローバル案件や外資系企業では、英語での職種説明が必要になることもあります。
まとめ:運用保守は「支える力」。地味だけど、ITの要。
運用保守は確かに派手な仕事ではありませんが、ITシステムの安定稼働を支える大切なポジションです。
「やめとけ」「底辺」などの声に惑わされることなく、現場の中でスキルアップを目指せば、将来的にはクラウド、セキュリティ、ITコンサルなどへのキャリア展開も可能です。
仕事内容の理解を深め、自分に向いているかどうかをしっかり見極めながら、長期的な目線でキャリアを考えていきましょう。