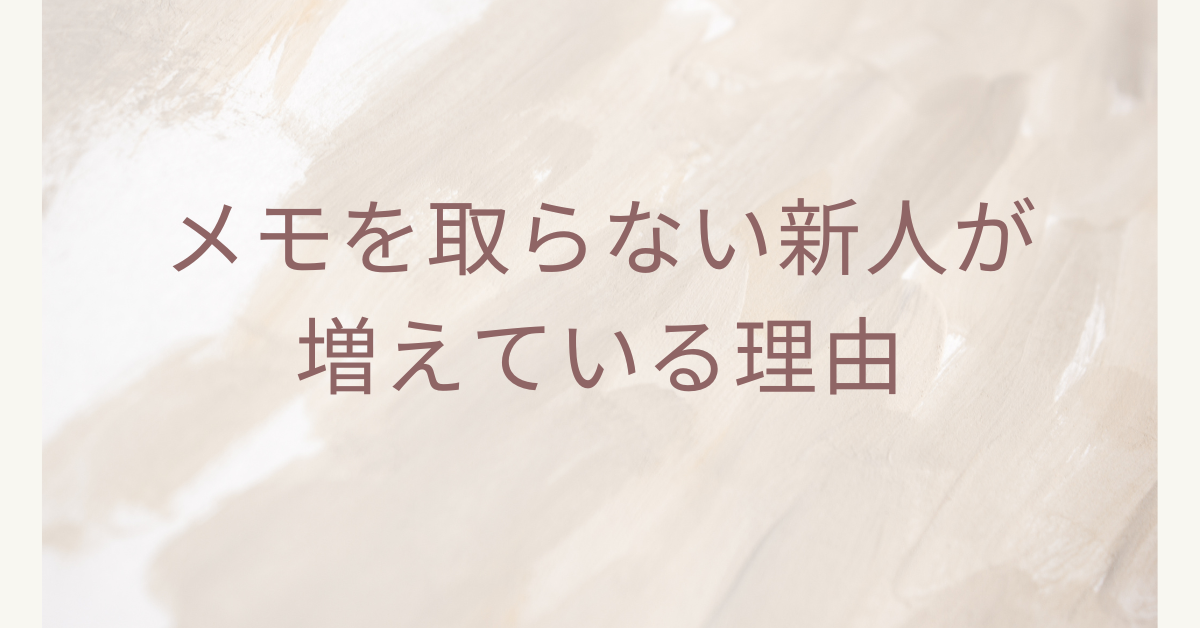近年、「メモを取らない新人が増えた」と感じる管理職や教育担当者が増えています。何度も同じことを聞いてくる、注意しても記録を取らない、指示をすぐ忘れる──そんな状況に頭を抱える人も多いのではないでしょうか。この記事では、「なぜメモを取らない人が増えているのか」「それは本当に怠慢なのか」「どう指導すれば育つのか」を心理・時代背景・教育法の観点から徹底的に解説します。新人教育に悩む上司や先輩にとって、明日から現場で使える“伝わるマネジメント術”がわかる内容です。
メモを取らない人が増えている時代の背景を読み解く
デジタル化が「記録=手書き」の概念を変えた
「メモを取らない新人が増えた」と感じる背景には、社会全体のデジタル化があります。
かつては紙とペンが主流でしたが、今はスマホやPCで記録を残すのが当たり前の世代です。メモ帳よりもLINEの下書きやスマホのカメラ、チャットツールの履歴を“メモ代わり”にしている人も多くいます。
つまり、彼らの中では「メモ=ノートに書く」ではなく、「デジタルで保存して検索できる状態をつくる」という認識に変わっているのです。これを知らずに「なんでノートに書かないの?」と叱ってしまうと、価値観のズレから信頼関係が崩れてしまうこともあります。
「すぐ聞ける」環境が記憶力を弱めている
もう一つの要因は、“情報の即時アクセス”です。スマホやチャットで何でもすぐ聞けるため、「とりあえず聞けばいい」という思考が身についています。
例えば、上司に「この資料どこにありますか?」と何度も聞く新人。本人は悪気がなく、「聞いたほうが早い」と思っているだけ。記録を取る習慣が薄れているというより、“覚えるより聞くほうが効率的”という発想に慣れてしまっているのです。
この「メモ取らない 時代」は、怠慢ではなく“学び方の多様化”と捉える必要があります。管理職側が「なぜメモを取らないのか」だけでなく、「どうすれば覚えられる仕組みを作れるか」という視点を持つことが重要です。
「メモを取らない=仕事ができない」は昔の常識
「メモを取らない人 仕事 できない」という言葉は、いまだ多くの職場で聞かれます。
しかし近年では、「メモを取らない=非効率」ではなく、「メモを取る必要がない環境をつくる力がある」と評価されるケースも出てきました。
例えば、タスク管理ツールやクラウド共有を活用し、チーム全員が同じ情報を見られる仕組みを作る人は、手書きのメモを取らなくても仕事を回せます。
つまり、**“メモを取る行為”よりも、“情報を整理し活用できるかどうか”**が、今の仕事力の指標になっているのです。
メモを取らない新人の特徴と心理背景を理解する
メモを取らない人の特徴を整理する
「メモを取らない人 特徴」を分析すると、次のような共通点が見えてきます。
- 記憶力に自信がある、または“すぐ調べられる”と思っている
- 注意力が分散しやすく、同時処理が苦手
- 言語よりも映像・感覚で覚えるタイプ(いわゆる右脳型)
- 書くより話す・聞く方が得意で、行動して覚える傾向がある
- そもそも「メモを取る意味」を教わっていない
新人の多くは、学生時代に“授業ノートを取る”経験はあっても、“業務メモを整理して活用する”訓練を受けていません。
つまり、彼らは「メモを取らない」のではなく、「メモの取り方を知らない」だけなのです。
「メモを取らない=集中していない」ではない
会議中にメモを取らない新人を見ると、「話を聞いていない」と感じる人も多いでしょう。
しかし、最近の若い世代は“目で覚える”“動画で学ぶ”スタイルが中心。相手の話に集中している間は、手を止めているだけのこともあります。
特にオンライン会議では、PC画面上にメモアプリを開きながら同時進行で整理しているケースも多く、一見して「何もしていないように見える」だけの可能性もあります。
上司側の思い込みで判断せず、「どんな方法で情報を整理しているのか」を確認する対話が欠かせません。
メモを取らない人は病気なのか? ADHDとの関連
検索トレンドでは「メモを取らない人 病気」というキーワードも目立ちます。
確かに、ADHD(注意欠如・多動症)やLD(学習障害)など、集中力や記憶保持が難しい特性を持つ人が一定数存在します。
ただし、それを「病気だから仕方ない」と決めつけるのは危険です。
多くの場合は、環境や指導方法のミスマッチが原因。例えば、口頭で大量の情報を与えるより、タスクを分割し、視覚的に示す方が理解しやすいケースが多いです。
つまり、“メモを取らない=怠けている”ではなく、**「人によって記録方法が違う」**と捉えることが、現代のマネジメントには必要です。
メモを取らない新人に何度も同じことを聞かれるときの対処法
「何度も聞く」新人を叱るより“仕組み”を変える
「メモを取らない 何度も聞く」新人に悩む上司は少なくありません。
しかし、何度言っても改善しないのは、本人の意識よりも“環境”の問題であることが多いです。
例えば、マニュアルが存在しない、共有フォルダが複雑、上司が指示をその場で変える──そんな職場では、どれだけメモを取っても再現性が低くなります。
指導側が「同じ質問をされない仕組み」を整えることが、根本的な解決になります。
- 業務手順をテンプレート化する
- チャットツールで質問履歴を残す
- チーム全員で共有できるQ&Aドキュメントを作る
これにより、「聞く」よりも「調べる」文化が自然と根づきます。
メモを取らない新人に“書かせる”より“話させる”
新人教育では、「書け」よりも「説明してみて」と伝える方が効果的です。
教えた内容を本人の言葉で説明させると、理解の浅い部分が可視化され、記憶の定着にもつながります。
メモを取らない新人の多くは、“受け身の記録”が苦手な一方で、“対話による学習”には強い傾向があります。
上司や先輩は「これどう理解した?」「どんな手順でやってみる?」と問いかけることで、自然と要点を整理させられます。
電子化教育で「メモを取らない世代」に合わせる
「電子化教育」という考え方も広がっています。
デジタル世代には、アナログのノートよりも“オンライン資料+チャットサポート”の方が学習効果が高い傾向があります。
- Googleドキュメントで手順を共有し、リアルタイムでコメントできるようにする
- 動画マニュアルで「見て覚える」方法を導入する
- Slackなどで「質問チャネル」を設け、同じ疑問が繰り返されないようにする
こうしたツールを活用すれば、個々の“メモ力”に依存しないチーム体制を作れます。
結果として、「何度も聞かれる」ストレスが減り、教育効率も飛躍的に上がります。
メモを取らない人に見える“天才型”の特徴と扱い方
「メモを取らない 天才」と呼ばれる人の実態
中には、メモを取らないのに仕事が早く、正確な人もいます。
こうした人は、情報を“構造化して記憶する力”が高く、脳内で整理できるタイプ。
メモを取らなくても、要点を瞬時に掴み、再現できるのが特徴です。
ただし、このタイプは再現性が低く、チームプレーに弱い傾向があります。
本人は覚えていても、他人に共有できないため、結果的に「属人化」や「ブラックボックス化」を招くリスクがあります。
上司としては、彼らの能力を活かしつつ、知識を見える化する役割を担わせると効果的です。
たとえば、「他のメンバーが理解できる形で手順書をまとめてみて」と依頼すれば、自分の思考を整理するトレーニングにもなります。
メモを取らないおばさん・上司のケース
一方で、「メモを取らないおばさん」や「上司」も問題視されるケースがあります。
これは経験値の高さから、「自分は覚えている」「今さら書かなくても大丈夫」という思い込みが原因です。
しかし、情報量が増えた今の時代、ベテランでも記録を怠るとミスや伝達漏れが起きやすくなります。
世代に関係なく、**“個人の記憶ではなくチームの仕組みで支える”**という意識転換が求められています。
メモを取らない新人を育てるマネジメントの実践ステップ
1. 書かせる前に「なぜ記録が必要か」を伝える
「とにかくメモを取れ」と命令しても効果はありません。
まず、「メモは自分を助けるツール」という意味を理解させることが先決です。
「上司のためではなく、自分のために書く」──この視点を与えるだけで、新人の行動が変わります。
実際、心理学的にも「目的を理解して行動する方が、継続率が高い」とされています。
2. メモを“取る”から“使う”へ意識を変える
メモは取って終わりではなく、使って初めて意味があります。
新人が取ったメモをそのままにしている場合は、「明日の朝、昨日のメモを読み返してから動いてみて」と促すだけで行動が変わります。
上司がフィードバック時に「そのメモ見せて」と声をかけると、**“活用される前提でメモを取る習慣”**が根づきやすくなります。
3. デジタルメモの導入で時代に合わせる
紙のノートが苦手な新人には、電子メモやノートアプリを導入しましょう。
Notion、Google Keep、Microsoft OneNoteなど、同期や共有ができるツールを使えば、スマホでもPCでも同じ情報を閲覧できます。
これにより、「メモを取らない」という問題ではなく、「どのように情報を残すか」という“手段の自由”を与えられます。
まとめ:メモを取らない新人を責めず、仕組みと対話で育てる
メモを取らない新人は、怠けているのではなく、“時代に合った学び方”をしているだけです。
彼らの特性を理解し、記録方法の多様化を受け入れることで、指導は格段にスムーズになります。
大切なのは、叱ることでも強制することでもなく、**「メモを取らなくても成果を出せる仕組み」**を整えること。
それが、電子化教育が進む今の時代における“新しいマネジメント力”です。
メモを取らない新人に戸惑うのではなく、彼らの学習スタイルを活かした教育へ。
記録する力ではなく、**“活かす力”**を育てることが、現代の組織が成長するための鍵になるでしょう。