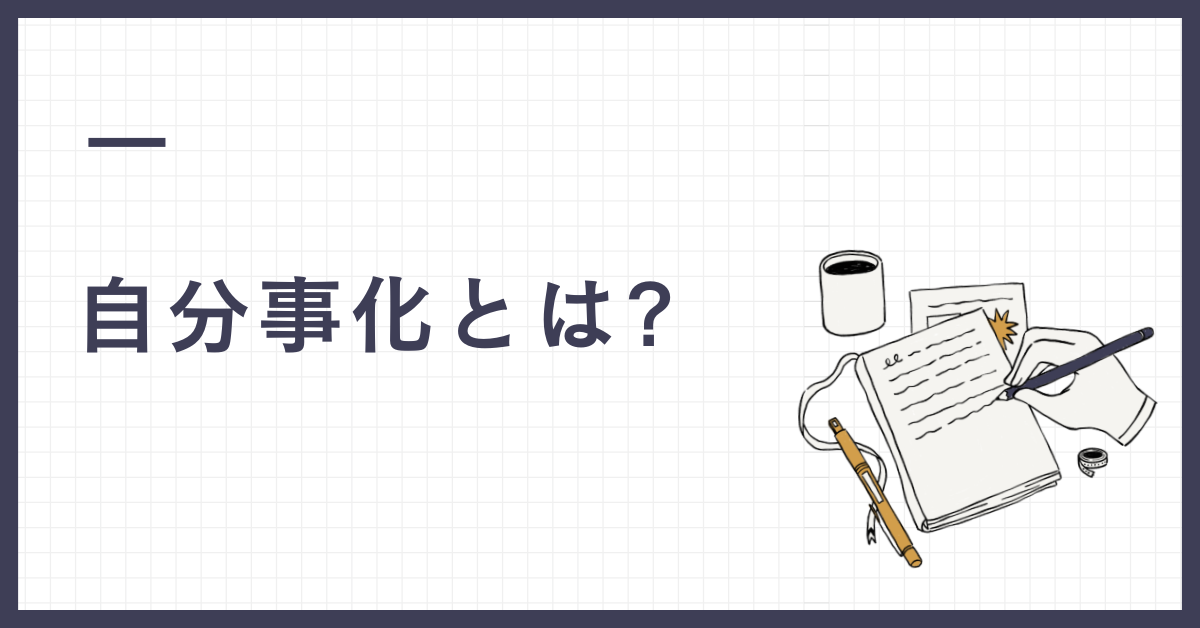ビジネスの現場では、いかに社員が「当事者意識」を持って行動できるかが成果を左右します。しかし「自分事化」がうまく進まないと、他人事として課題を放置してしまうケースも少なくありません。本記事では、ビジネスにおける「自分事化」の本質や読み方、使い方、さらには企業における導入事例や誤解されがちなネガティブな印象についても丁寧に解説していきます。マネジメント層から現場社員まで、組織を変える第一歩として「共感と思考」をどう育てていくかを考えるヒントにしてください。
自分事化とは何か
ビジネスにおける定義と意味
「自分事化」とは、目の前の出来事や課題、プロジェクトを“他人事”ではなく“自分の問題”として捉える思考や行動のことを指します。読み方は「じぶんごと・か」。本来、当事者でなくても、その物事に対して「自分に関係がある」と認識し、主体的に動こうとする心構えです。近年では、企業のマネジメントや人材育成、マーケティングの現場でも頻繁に使われるようになっています。
自分事化と当事者意識の違い
「当事者意識」は責任を持って業務を遂行する態度を指すことが多いのに対し、「自分事化」は物事を“自分の問題”として捉える認識の段階から始まります。つまり、当事者意識は行動、そして自分事化は思考の出発点といえるでしょう。
自分事化がなぜ重要なのか
組織の自走力を高めるための鍵
社員が上からの指示を待つだけでなく、自発的に課題を拾い、改善策を考える文化が組織に根付けば、それは大きな競争優位につながります。特にスタートアップや中小企業など、全員が多くの役割を担う現場では、この「自分事化」の有無が成果の差を生み出します。
自分事化できない社員が増える背景
「自分事化 できない」と感じる社員が増えている背景には、業務が細分化されすぎて自分の仕事が全体にどう影響しているかが見えづらい環境や、心理的安全性が確保されていない組織風土などが挙げられます。そのため、自分が口を出す立場にないと感じてしまい、意見も行動も止まってしまうのです。
自分事化とマーケティング
マーケティングにおいても「自分事化」は極めて重要な概念です。顧客が商品やサービスを「自分に関係のあること」として認識することで、初めて購入や利用のアクションにつながります。
例えば、BtoB商材の提案において、「御社の課題に効きます」という一般的な訴求ではなく、「まさに自分の部署の状況だ」と共感を生むストーリー設計が、自分事化を促す鍵になります。
自分事化の実践ステップ
ステップ1:共感の入口をつくる
人は自分に似た境遇や悩みを抱える他者には共感しやすくなります。そのためには、感情や背景にアプローチする導入が効果的です。
ステップ2:情報を“解像度高く”共有する
「何が起きているのか」「誰にどう影響しているのか」を伝える情報が曖昧だと、自分事にはなりにくくなります。具体性とストーリー性が重要です。
ステップ3:意見や感情を引き出す場づくり
自分の意見を言える環境が整っていなければ、行動も変わりません。心理的安全性の担保と、対話の習慣化が求められます。
自分事化が気持ち悪いと感じられる理由
一方で、「自分事化 気持ち悪い」と検索される背景には、あまりに押し付けがましい啓発や、自己責任を過剰に求める風潮への違和感があります。「なんでも自己責任」という圧力では、むしろ思考停止や無関心を生む結果にもなりかねません。重要なのは「共感」と「尊重」による自発的な変化を促すことであり、押し付けない導きが求められます。
自分事化の英語表現とグローバルでの捉え方
英語では “Ownership” や “Sense of responsibility” に近い概念として扱われることが多いです。ただし、「感情移入」や「共感による参加意識」という点では “Empathy-driven engagement” といった言い方も文脈によっては有効です。
自分事化の言い換え表現
職場での会話や資料において、少し柔らかい表現としては「当事者意識」「共感思考」「主体的関与」「ユーザー目線」などが代用されることもあります。相手の理解度に合わせて選ぶことで、伝わりやすくなります。
自分事化の例文
社内報や企画書で使える例文をいくつか紹介します。
・この施策を、全員が自分事化できるようストーリーを再設計しましょう。
・ユーザーの声を共有することで、自分事として開発に向き合える環境を整えたい。
・プロジェクトメンバー全員が、自分事として捉えて動けているかを可視化します。
自分ごと化が浸透した企業の事例
あるIT企業では、カスタマーサクセス部門がユーザーの「クレーム」を単なる対応業務としてではなく、自分たちの事業改善の“ヒント”と捉える文化を醸成しています。定例会議では、実際のユーザーの感情がこもった声を読み上げる時間を設けることで、感情移入が生まれ、全員が“自分の仕事に関係している”と認識し始めました。この取り組みによって、解約率は約30%改善したそうです。
自分事化を組織でどう育てるか
共感的なストーリーテリング、情報のオープン化、成果ではなく行動を評価するカルチャーなど、長期的な仕組みとして自分事化を育てる組織文化づくりが欠かせません。単発的な研修では根づかないため、リーダーシップと現場が一体となった運用設計が求められます。
組織全体に自分事化を根づかせる方法
マネージャーが果たすべき役割
部下やメンバーに「自分事化」を促す鍵は、マネージャー自身が当事者意識のある言動を示すことです。課題共有の際に「これは私も自分事だと感じている」という姿勢を伝えることで、彼らも同じ視点を持ちやすくなります。
また、定例会議などの中で「何が自分の関係する業務なのか」「どう考えて行動すべきか」を一緒に言語化し、対話する機会を設けることが極めて重要です。
成果ではなく行動を評価する仕組み
自分事化を育てるには、「成績」や「売上」などの結果ばかりを評価する文化ではなく、「課題発見」「巻き込み方」「共感の生み方」といった行動プロセスも見える化・評価対象にすることが不可欠です。たとえば、提案書に「ユーザー視点を反映した構成になっているか」を評価項目に組み込むことなどが具体策です。
情報のオープン化とアクセスしやすさ
組織内で重要情報が限られた人しか知らない状態では、自分事化は難しくなります。業務進捗、課題、顧客の声などを全員が閲覧できる状態を作ることで、「自分の仕事が全体にどう影響しているか」が見えるようになります。これが主体的な関与の第一歩となります。
若手社員と中堅層、それぞれに応じた育成アプローチ
若手に対しての自分事化支援
若手は経験の浅さから目の前の業務で迷いやすく、「自分事化できない」と悩むことが多いです。若手には、仕事の意味・目的を繰り返し伝え、行動の背景を可視化すると自分の貢献がわかりやすくなります。また、短期的な成功体験(顧客と関係を築けた、提案が通った)を定期的に振り返る機会をつくると、自信と共感意識が育まれます。
中堅層への働きかけ方
中堅層は既に成果を求められる立場ですが、自分事化を忘れがちです。定量目標だけでなく、部下育成や部門課題への巻き込みといった「影響領域の拡大」に自分事意識を持ってもらう必要があります。そのために、プロジェクト内で他部署と共同して課題解決に取り組む機会を用意し、自分以外の視点を持つ体験を設計しましょう。
教育現場における「自分ごと化」と社会人との違い
学校など教育現場でも「自分ごと化」(自分事化と同義)が課題になっています。たとえば、道徳教育や地域活動では「自分の行動が社会にどうつながるか」を考えさせる指導が行われます。
社会人とは異なり、学校では「教育者が主導して問いを投げかける」形式が多いため、自分事の内在化には工夫が必要です。ただ、その体験が社会人になる際の共感力や主体性のベースになることは間違いなく、組織での研修設計への示唆も含まれます。
心理学の視点:自分事化と内発的動機付けの関係
心理学では「内発的動機付け(intrinsic motivation)」が自分で行動する際の原動力になります。この概念と自分事化は非常に近く関係しています。
たとえば、自分の成長や他者貢献という価値に気づいたとき、人は「やりたい」と思います。そのような感情が芽生える組織では、自分事化が自然と進みやすくなります。具体的には、自己選択と達成感を得られるタスクを配置する仕組みが有効です。
テレワーク時代の自分事化の課題と解決策
課題:距離感がモチベーションを薄める
離れて働くことで「自分の仕事がチームや全体につながっている感覚」が希薄になり、自分事化しづらくなります。たとえばミーティングや共有ファイルを通じた情報がチーム内で閉じてしまうと、それを他の社員が“自分とは関係ない事項“だと捉えてしまうことがあります。
解決策:非同期コミュニケーション・感情共有
週1回の全社またはチーム定例で、各自が学んだことや課題感を共有する “5分のリフレクション時間” を設けることで、共感機会を増やすことができます。ビデオ共有やチャットによる感情の投げかけを通じて、「自分たちの話だ」と感じさせることが重要です。
未来の働き方における共感 × 自分事化の可能性
働き方がプロジェクト単位、多様なチーム構成で進む未来では、自らの役割を自覚し、「共感と思考」で動ける人材が中心的な存在となります。共感と自分事化がある組織は、柔軟で変化に強く、創造的な協働が可能になります。