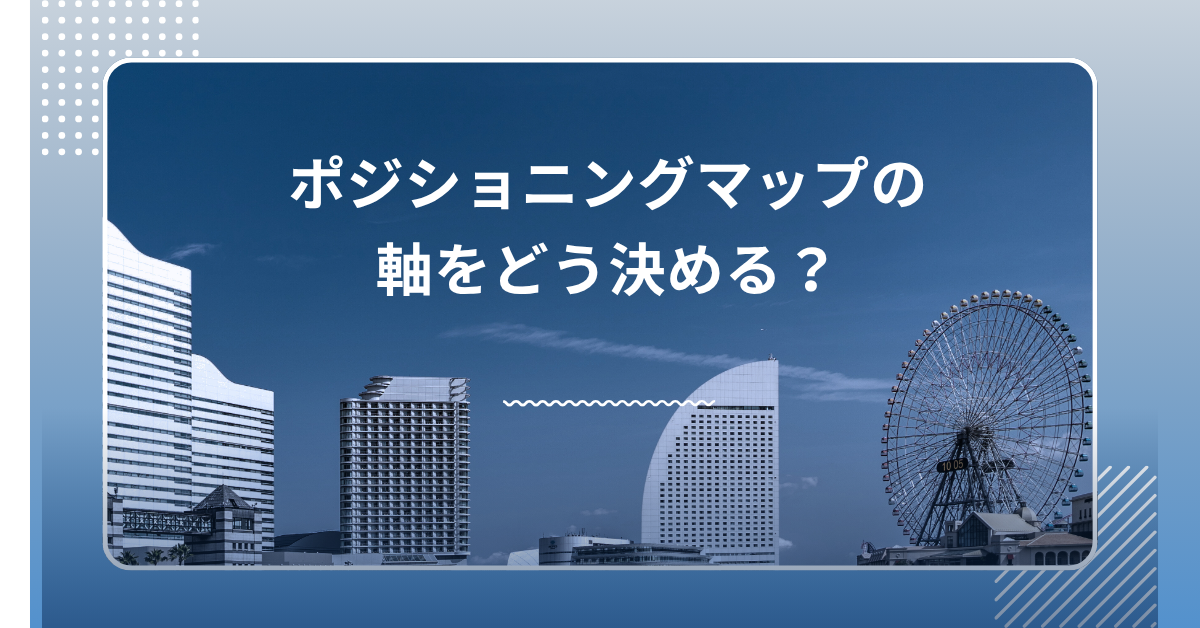競争が激しい市場で、自社の「立ち位置」を明確に示すことは欠かせません。
しかし、「ポジショニングマップを作ってみたけど軸の決め方がわからない」「他社と差別化できる切り口が思いつかない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、マーケティング理論の基礎であるコトラーの競争地位別戦略をベースに、リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャーそれぞれの立場に合ったポジショニングマップの軸の決め方を徹底解説します。
読むことで、「自社がどの戦略を取るべきか」「どの軸で差を出せるか」が明確になり、実践的なマーケティング戦略を自信を持って描けるようになります。
ポジショニングマップとは何かと軸を決める重要性
まずは基本となるポジショニングマップの考え方を整理しておきましょう。
ポジショニングマップとは、市場における自社と競合の“位置関係”を視覚的に整理した図です。
横軸と縦軸に異なる評価基準を置き、商品・ブランド・サービスを配置することで「どのポジションが空いているか」や「どこで勝負できるか」を把握できます。
ポジショニングマップの目的を理解する
ポジショニングマップの目的は単なる“図作り”ではありません。
企業が自分たちの強みを明確にし、顧客に「なぜ選ばれるのか」を示すための戦略ツールです。
軸をどう設定するかで、戦略の方向性はまったく変わってしまいます。
たとえば「価格」と「品質」を軸にすると、
- 高品質・高価格ゾーン=プレミアムブランド(リーダー戦略に多い)
- 低価格・中品質ゾーン=コスト優位型(フォロワー戦略が得意)
- 独自性・デザイン性を軸にすると、チャレンジャーやニッチャー企業が輝きやすい
というように、軸そのものがどの地位の企業に向いているかを決める要素にもなるのです。
軸の決め方でありがちな失敗
多くの企業がやりがちな失敗が、「自社に都合のいい軸を選ぶ」ことです。
例えば、業界内で価格が中程度の企業が「安さ」を強調しても、リーダーやチャレンジャーとの比較で埋もれてしまいます。
また、「品質」や「信頼」など抽象的すぎる軸も避けるべきです。
顧客の目線で“具体的に比較できる基準”を設定しなければ、マップの意味が薄れてしまいます。
コトラーの競争地位別戦略を理解して軸を選ぶ
ポジショニングマップの軸を決めるには、まず自社の立ち位置=「競争地位」を明確にする必要があります。
マーケティングの巨匠フィリップ・コトラーは、市場での企業の位置づけを次の4つに分類しました。
- リーダー戦略
- チャレンジャー戦略
- フォロワー戦略
- ニッチャー戦略
それぞれの立場によって、選ぶべき軸や戦略設計の考え方が大きく異なります。
リーダー戦略に合うポジショニング軸の決め方
リーダー企業とは、業界の中で最も高い市場シェアを持つ存在です。
たとえば自動車業界のトヨタ、検索エンジンのGoogle、ファーストフードのマクドナルドなどが代表例です。
リーダー戦略では、「市場全体を拡大し、自社の優位を維持する」ことが目的です。
そのため、軸の選び方も業界の基準を作る視点が重要になります。
軸の例としては、以下のようなものが効果的です。
- 品質 × 価格
- 機能性 × ブランド信頼度
- 利便性 × サービス網
リーダーは「業界の指標」を作る存在です。
したがって、あえて広い軸を設定し、“中心軸でバランスを取る”ことが多いです。
ただし、油断は禁物。市場の細分化が進む現代では、「リーダー=安全地帯」ではありません。
新しい価値軸で挑んでくるチャレンジャーに対して、常に次の軸を模索する柔軟性が求められます。
チャレンジャー戦略に適したポジショニングマップの軸設計
チャレンジャー企業とは、リーダー企業を追い抜こうとする挑戦者の立場です。
市場シェアでは2位または3位のポジションに位置しながらも、革新や差別化でリーダーに挑む存在です。
ソフトバンクやダイソン、Netflixなどは、典型的なチャレンジャー企業の事例といえるでしょう。
チャレンジャー戦略の本質は「異なる土俵で勝つ」こと
チャレンジャー企業が勝つためには、リーダーと同じ軸では戦えません。
なぜなら、リーダーが既に“基準”を作っているため、その軸上では圧倒的に不利だからです。
そのため、ポジショニングマップの軸を決める際には「リーダーが軽視している価値」を探すことがポイントになります。
たとえば、リーダーが「スピード×価格」を重視しているなら、
チャレンジャーは「カスタマイズ性×ユーザー体験」など異なる評価軸を選ぶのが有効です。
チャレンジャー戦略の実践的な軸設定例
- 機能性 × デザイン性
Appleがパソコン市場で成功したのは、この軸を明確にしたからです。
IBMが「スペック重視」だった時代に、「デザイン性と直感操作」で新しい土俵を作りました。 - 価格 × サービス品質
格安航空会社(LCC)は、「安いけれど安全・快適」というポジションを打ち出しました。
ANAやJALというリーダーが取らない価格帯を狙う“側面攻撃”の好例です。 - 専門性 × 顧客密着度
大手が網羅できない専門分野で、ユーザーと直接つながる仕組みを作ることも有効です。
中小のコンサルティング会社やITベンダーは、この戦略で成功しているケースが多いです。
チャレンジャー戦略のポイントは、「小さく始めて大きく動かす」こと。
特定の市場に的を絞り、他社には真似できない価値軸を明確にすることが、結果的にリーダーを脅かす力になります。
フォロワー戦略の企業が軸を決めるときの考え方
フォロワー戦略は、リーダー企業の動きを観察し、模倣を通じてリスクを抑えながら安定した利益を得る戦略です。
「2番手でいい」「安全に成長したい」という企業に多く見られます。
ただし、単なるコピーでは長続きしません。軸の決め方次第で、フォロワーは“堅実な収益モデル”を構築できます。
フォロワー戦略の成功軸とは
フォロワーが取るべき軸は、「効率」「コスト」「利便性」といった実用的な価値です。
たとえば、リーダーが「プレミアム感×ブランド価値」で戦っている場合、
フォロワーは「手軽さ×価格」を軸に設定することで、別の層にリーチできます。
代表的な例として、家電業界のアイリスオーヤマが挙げられます。
大手メーカーの製品を分析しつつ、「必要十分な機能×低価格」で市場を拡大しました。
これは“リーダーを真似しながらも、あえて求められない部分を削る”戦略です。
フォロワー戦略の軸は、**「シンプルさ」と「安心感」**をキーワードに設定すると効果的です。
大企業が手を出さない「安価・簡便・即納対応」などの領域で信頼を積み上げると、長期的に安定したシェアを確保できます。
ニッチャー戦略の企業が選ぶべき軸の作り方
ニッチャー戦略とは、「小さくても独自の市場でNo.1を取る」戦略です。
大手が参入しづらい狭い領域に集中し、圧倒的な専門性を発揮することが目的です。
医療機器、クラフト食品、地域限定サービスなど、ニッチ市場では軸の選び方が勝敗を分けます。
ニッチャー戦略に適した軸の考え方
- 専門性 × 顧客ロイヤルティ
例:地元の顧客に愛される工務店や美容院。顧客との関係性が最重要。 - 独自技術 × 高価格
例:職人技や特許技術を活かした中小メーカー。少量でも高単価で勝負。 - 環境配慮 × デザイン性
例:サステナブル商品を展開するD2Cブランド。小さな市場でも共感で支持を得る。
ニッチャー戦略では「大手が真似できない強み」を軸にすることが鉄則です。
市場規模は小さくても、“深さ”で勝負するのが成功のポイントです。
チャレンジャー企業一覧とポジショニングマップの共通点
実際にチャレンジャー企業として成功している企業には、いくつか共通の特徴があります。
ここでは有名なチャレンジャー企業の例を挙げながら、ポジショニングマップ上でどんな軸を選んだのかを見ていきましょう。
| 企業名 | 業界 | 主な軸 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通信 | 技術革新 × ブランド体験 | iPhone販売でリーダーを超える価値を創出 |
| ダイソン | 家電 | 性能 × デザイン | 機能特化でプレミアム市場を独占 |
| Netflix | エンタメ | 手軽さ × コンテンツ量 | 新しい視聴体験を提案 |
| Zoom | IT | シンプル操作 × コスト効率 | リモート需要に迅速対応 |
| モスバーガー | 外食 | 品質 × 国産素材 | リーダーと真逆の価値を軸に設定 |
これらの企業はいずれも、「リーダーが取らない軸」を選び、自らの強みを可視化することで支持を獲得しました。
チャレンジャー戦略を成功させる鍵は、“誰も見ていない軸で勝負すること”です。
まとめ:ポジショニングマップの軸は「自社の強み×市場の穴」で決める
ポジショニングマップは、単なる図表ではなく“戦略を導く羅針盤”です。
軸の決め方を誤ると、自社の立ち位置がぼやけ、戦略の焦点もずれてしまいます。
最後に、軸を決める際のチェックポイントをまとめます。
- 顧客が明確に比較できる指標を選ぶ
- リーダー企業の軸をそのまま真似しない
- 自社の強みを活かせる評価軸を選ぶ
- 小さな市場でもNo.1になれる“深さ”を意識する
- 定期的に軸を見直し、市場変化に対応する
リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャー——
どの立場であっても、自社が勝てる場所を見極めて軸を設定することが、ポジショニングマップ最大の目的です。
今日からぜひ、自社のマップを見直してみてください。きっと、新しい戦い方のヒントが見えてくるはずですよ。