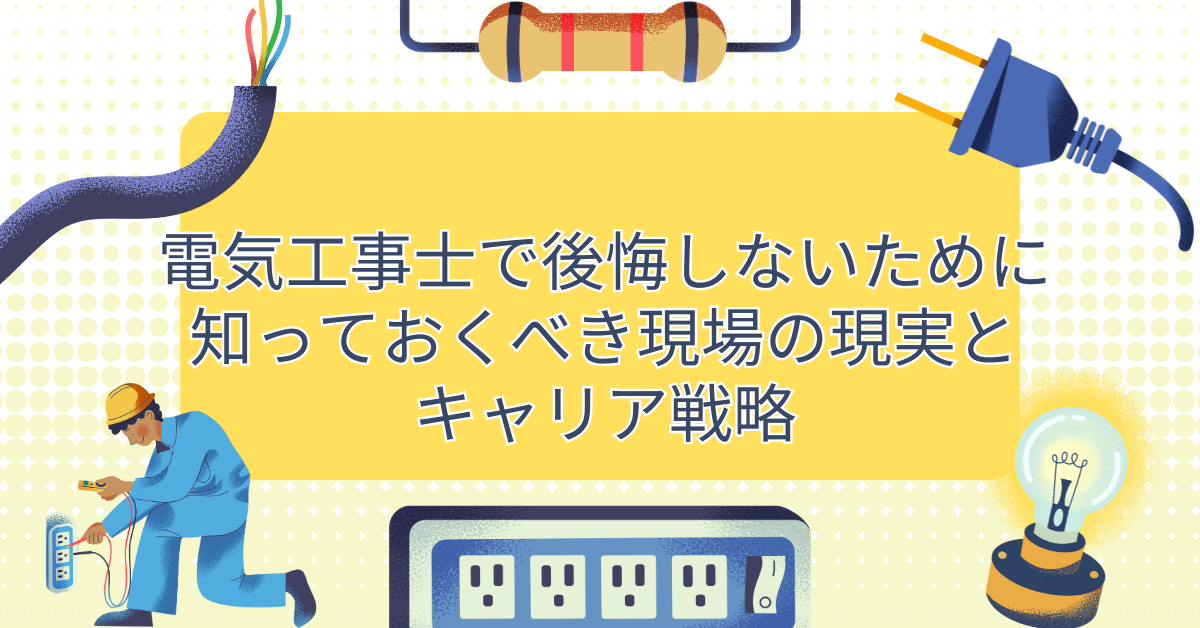「電気工事士になってみたいけれど、実際のところどうなの?」「ネットで“やめとけ”って書かれているのが不安」──そんな疑問や不安を抱く方は少なくありません。専門職としての安定性、求人の多さ、独立も視野に入るキャリアパスなど、電気工事士には多くの魅力がありますが、一方で業界特有の現実や厳しさがあるのも事実です。この記事では、電気工事士を目指す前に知っておくべき現場のリアルと、後悔しないためのキャリア戦略を、初心者にもわかりやすく解説していきます。
現場のリアル:なぜ「電気工事士はやめとけ」と言われるのか
インターネットで「電気工事士 やめとけ」「2ch」「知恵袋」などと検索すると、ネガティブな意見が目立つことがあります。これらの投稿には、過酷な労働環境、人間関係の難しさ、給与の伸び悩みといった課題が挙げられています。
特に若手の職人からは、「夏は炎天下、冬は極寒の中での作業がきつい」「残業が多い割に手取りが少ない」「職場の上下関係が体育会系すぎて合わなかった」といった声があり、そうした口コミが“やめとけ”という印象を広めているようです。さらに現場では高所作業や感電リスクなど、日常的に危険と隣り合わせの業務もあり、メンタル的なプレッシャーも無視できません。
ただし、これらは業種全体の実態というよりも、ブラックな職場環境や未整備な労働体制に起因することが多いです。電気工事士全体が過酷な職場というわけではなく、ホワイト企業も確実に存在します。福利厚生が充実し、残業管理も徹底されている企業では、労働環境は大きく異なります。現場のリアルをきちんと理解し、自分に合う働き方を選ぶことが何よりも重要です。
電気工事士の平均年収と将来性
厚生労働省や求人データによると、電気工事士の平均年収は約450万〜550万円程度とされており、日本の平均年収と比べてもやや高めの水準にあります。特に資格保有者や経験年数の多いベテランになると、年収600万〜800万円台も珍しくありません。
一方で、若手や未経験者は年収300万円台からスタートするケースも多く、経験とスキルの積み重ねが年収に直結する職業です。地方と都市部で差もあり、首都圏では民間工事の単価が高く、収入面でも優遇されやすい傾向があります。
将来性の面で言えば、インフラ整備や再生可能エネルギー関連の需要が高まる中、電気工事士の求人は今後も安定的に増えていくと見込まれています。EV充電設備、太陽光発電、スマートハウスなど技術革新とともに電気工事の分野も多様化しています。ビルや住宅の新築・改修だけでなく、これら新技術への対応力をつけることで、仕事の幅も収入も格段に広がるのがこの仕事の特徴です。
「電気工事士=金持ち」は本当か?収入アップの現実的ルート
「電気工事士は金持ちになれる」という声を聞くこともありますが、それは一部の成功者に限られた話です。たしかに、独立して法人化し、従業員を抱えて大規模な工事を請け負っているような事業者は、年収1000万円を超えるケースもあります。
収入を上げるためには、次のような段階的な戦略が必要です。まずは「第2種電気工事士(電気工事士2種)」を取得し、現場での実務経験を積みます。その後、より上位の「第1種電気工事士」や「電気工事施工管理技士」の資格を取得し、責任ある立場で工事を統括するポジションにステップアップしていくのが王道です。
さらに、元請け工事を受けられる立場を目指し、見積作成、顧客折衝、原価管理など“経営者目線”を身につけていくことが収入の壁を超えるために不可欠となります。実際に、フリーランスや法人化後に「案件単価は3倍以上」「下請けから元請けへと移行できた」という成功例も少なくありません。
また、補助金制度や省エネ設備のニーズに強い企業と組むことで、高単価案件の受注が可能になります。つまり「金持ち電気工事士」になるには、技術だけでなくビジネススキルも重要なカギとなるのです。
求人の選び方で後悔しない働き方が決まる
「電気工事士 求人」で検索すると、多くの募集が出てきますが、どこでもよいわけではありません。求人票だけでは見えにくい部分にこそ、職場の実情が隠れています。
たとえば、未経験歓迎と書いてあるのに実際は見習いに過酷な業務を丸投げするような職場や、資格取得支援をうたっていても実質的には時間も費用も自己負担というケースもあります。
ホワイトな企業を見分けるには、以下のようなポイントに注目しましょう。まず、労働時間や休日数が明示されているか。次に、研修制度や資格取得支援が制度として明文化されているか。そして、現場の若手定着率や先輩社員のキャリアモデルが提示されているかも大事な判断材料になります。
さらに、応募前に職場見学や実地体験ができる場合は積極的に参加すべきです。自分に合った企業風土か、将来のビジョンが描けるかは、現場の雰囲気を直に感じることで判断しやすくなります。求人選びは、キャリア全体を左右する非常に重要な第一歩です。
「ヤンキーが多い」って本当?業界のイメージと実際の職場環境
「電気工事士=ヤンキーが多い」というイメージを耳にすることがあります。これは一部の職人文化に根ざした偏見に過ぎません。たしかに過去には中卒や高卒後すぐに現場で働き始める人が多く、やや荒っぽい言葉遣いや上下関係の厳しさが見られたことは否定できません。
しかし現在は状況が大きく変わってきています。企業の採用方針も多様化し、大卒や異業種からの転職組、女性や外国人スタッフも増えており、現場の雰囲気は以前よりも格段に柔らかくなっています。安全管理の徹底、ハラスメント防止のガイドライン導入など、労働環境の整備が進んでいるのも追い風です。
とはいえ、体育会系の文化が完全に消えたわけではなく、口調が強かったり礼儀に厳しい先輩がいる職場も一部には存在します。そこに違和感を持つ人は、面接や職場見学時に社内の雰囲気をよく確認するようにしましょう。実際には丁寧に指導してくれる親方や、働きやすい環境を整える若手経営者も増えています。
電気工事士2種から始めるキャリア戦略
電気工事士としてのキャリアは、まず「電気工事士2種」の取得から始まります。この資格があれば、一般家庭や小規模事業所の電気配線工事が可能となり、就職先も広がります。
受験資格に制限がないことから、社会人になってから挑戦する人も多く、通信講座や職業訓練校を活用することで、働きながらでも取得を目指せます。試験の合格率はおおむね60〜70%前後で、対策をしっかりすれば初心者でも十分に狙える資格です。
実際に、2種を取得したことで「就職が決まった」「給与が月5万円アップした」「資格手当が毎月1万円ついた」といった声も多く見られます。この資格を足がかりに現場で実務経験を積み、次のステップとして「電気工事士1種」や「施工管理技士」などの上位資格へと進んでいくのが一般的なキャリアパスとなります。
さらに、資格を持つことで「電気工事の責任者」としての立場になれるため、施工における裁量権も広がり、より大きな仕事を任されやすくなります。これは将来的に独立や法人化を目指すうえでも大きな武器となるでしょう。
まとめ:電気工事士という仕事は「やめとけ」ではなく「選び方次第」
電気工事士に対するネガティブな声は、たしかにインターネット上には多く見られます。しかし、その多くは「職場環境のミスマッチ」や「情報不足」によるものです。職場の選び方次第で、過酷な現場と快適な職場とではまったく違う働き方が実現できます。
正しい知識をもってキャリアを選べば、電気工事士は高い専門性と安定した需要、そして努力次第で高収入も目指せる魅力的な職業です。電気工事士2種からスタートして、資格を増やし、経験を積み、顧客対応や経営スキルも磨いていけば、収入と働き方の自由度は大きく広がっていきます。
また、今後はスマートシティやEV関連インフラの整備が進むことで、電気工事士の仕事はさらに多様化し、より高度なスキルが求められるようになります。そうした流れにいち早く対応できれば、市場価値の高い存在として長期的に活躍することも可能です。
「やめとけ」という声に惑わされる前に、まずは自分に合う職場と働き方を見つけ、正しい一歩を踏み出してください。それこそが、後悔のないキャリアを築く第一歩なのです。