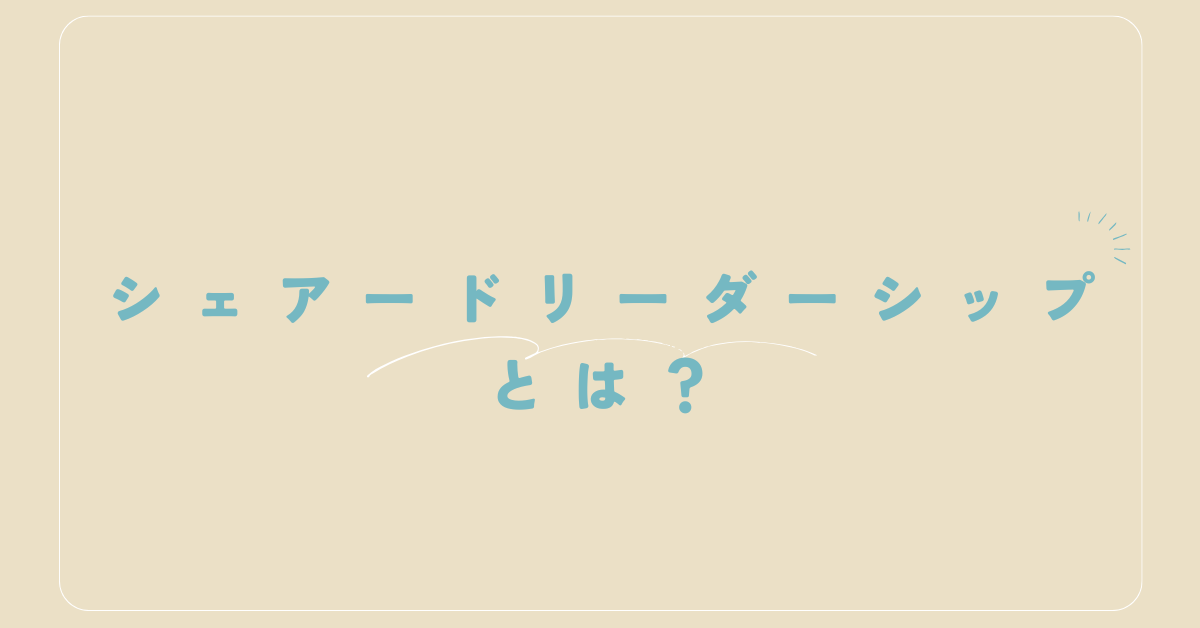上司の指示を待つのではなく、現場の一人ひとりが自ら考えて動く。そんな組織が実現できたら、マネジメントの負担も、業務の停滞も大きく減らせるはずです。近年注目される「シェアードリーダーシップ」は、そうした“現場主導”の働き方を可能にする組織モデルとして注目を集めています。本記事では、その概念から理論背景、実際の導入事例、そして導入時のリアルな課題までを、ビジネスの現場目線で解説します。
シェアードリーダーシップとは何か
権限を「共有」する組織スタイル
シェアードリーダーシップとは、リーダーシップを特定の上位者に集中させるのではなく、チーム内の複数人で分担・共有するという考え方です。従来のトップダウン型マネジメントでは、上司が指示を出し、部下がそれに従う構図が主流でしたが、変化の激しい現代においてはスピードと柔軟性が求められるため、現場の主体性がより重要視されるようになっています。
管理職がいなくなるわけではない
誤解されやすいのは、「リーダーがいらなくなる」という印象です。しかし実際は、管理職がリーダーシップを“手放す”のではなく、“分け与える”スタイルです。現場に判断権限を委ねながらも、組織の方向性はしっかりと管理層が握ることで、両者の役割分担が成立します。
理論と背景:なぜ今、注目されているのか
提唱者とその学術的ルーツ
シェアードリーダーシップは1990年代以降、米国を中心とした組織心理学や経営学で提唱されてきた理論です。中心となる研究者には、Craig L. PearceやJay A. Congerなどがいます。彼らは「リーダーシップは個人の資質ではなく、集団的な相互作用の中で生成される」と考え、これを体系的に研究しました。
日本での文脈と企業文化の転換
日本企業は長年、階層的な縦型組織が主流でした。しかし近年、変化のスピードが加速する中で、「自分で考えて動ける人材」へのニーズが高まり、形式的な肩書きよりも、実質的にリーダーとして機能する人の存在が注目されるようになりました。これがシェアードリーダーシップの日本的な土壌をつくり始めています。
トヨタの実践に見るシェアードリーダーシップの本質
現場力の強さは「分散型」の証
トヨタは現場の改善活動「カイゼン」で世界的に知られていますが、その根底にあるのは、現場社員の自律的な判断と行動です。各作業者が自分の仕事に責任と誇りを持ち、上司の命令を待つのではなく、自ら考えて改善に取り組む。この文化は、まさにシェアードリーダーシップの具現化といえます。
決して放任ではない「自律」の設計
トヨタでは、一定の訓練・知識・意識の醸成が前提として存在します。個人の力を引き出すには、適切な教育と信頼の蓄積が必要です。リーダーシップを共有するとはいえ、それが無秩序にならないよう、マネジメントとの連携設計が重要となるのです。
現場導入の成功事例と実践例
スタートアップにおける導入事例
あるIT系スタートアップでは、エンジニア・マーケター・デザイナーなど各職種がフラットに意見を出し合い、プロジェクトごとに自然発生的な“リーダー役”が生まれる仕組みを採用しています。役職に関係なく、最も知見が深い人が中心となり、他メンバーはその都度サポートに回る。この柔軟なリーダーシップ交代制が、スピードとイノベーションを生んでいます。
看護の現場での応用
医療業界、特に看護の分野では、患者対応の現場で素早い判断が求められます。そこで「シェアードリーダーシップ」を導入し、チーム内でリーダーシップを柔軟に分け合う体制が広まり始めています。状況に応じてリーダーが交代し、患者ごとのニーズや緊急性に対応することが、組織的なケアの質向上にもつながっているのです。
導入による効果と期待される組織変化
現場の主体性が高まる
従来のように「言われたことをやる」のではなく、「自分で考えて行動する」風土が醸成されることで、社員のエンゲージメントも向上します。ひとり一人が自分の業務を“自分ごと化”するため、イノベーションや改善提案が生まれやすくなります。
多様な視点からの意思決定が可能に
単一のリーダーだけが意思決定するのではなく、複数の視点から課題に取り組むことで、より多角的かつ実務的な判断が可能になります。このことで、組織全体の思考力が底上げされていきます。
導入の落とし穴とよくあるデメリット
全員リーダーで責任が曖昧になるリスク
「誰でもリーダーになれる」ことは裏を返せば、「誰も責任を取らない」構図につながりかねません。特に、明確な役割分担や目標設定がなければ、混乱やパフォーマンスの低下を招く恐れもあります。
組織文化と相性が合わないケース
年功序列が色濃く残る企業や、縦型の命令系統が根付いている組織では、シェアードリーダーシップの導入が反発を招くこともあります。導入前には、現場の温度感や人材の成熟度を見極め、必要であれば段階的な移行ステップを設計すべきです。
サーバントリーダーシップとの違いと共通点
上からの支援 vs 横からの共創
サーバントリーダーシップは「奉仕型の上司」を意味し、部下の成長を支援するスタンスに立つリーダー像です。一方、シェアードリーダーシップは「リーダー不在でも回るチーム」を目指すモデルであり、上下関係よりも“役割”に着目します。
共通するのは「信頼の土壌」
どちらのモデルも、最終的に成果を出すのは「信頼」によって結びついた人間関係です。メンバー全員が目的を共有し、対等な立場で貢献しあう関係性があってこそ、リーダーシップは真に共有されるものになります。
導入を成功させるためのステップ
教育・評価制度の再設計がカギ
個人が自律的に動くためには、信頼と権限だけでは不十分です。教育制度を刷新し、個々のリーダーシップ力を育てる育成施策が必要です。また、評価制度も成果だけではなく、「他者への影響力」や「協働姿勢」を見える化する設計が望まれます。
いきなり導入せず、試験導入から始める
中小企業や部署単位からテスト的に導入し、実際の反応や成果を検証することが有効です。フィードバックを重ねて文化に馴染ませていく段階的なアプローチが、長期的な成功を導きます。
まとめ:リーダーの数が組織力を決める時代へ
リーダーは「一人」ではなくていい。組織の全員が「場面ごとのリーダー」になれる柔軟な組織こそが、変化に強く、成長し続ける企業の条件です。シェアードリーダーシップは、そうした未来型組織のための“土台”となる思想と実践です。
もちろん、導入には準備と覚悟が必要です。責任の曖昧さや文化とのミスマッチなど、乗り越えるべき壁も存在します。しかし、それ以上に、全員が考え、動き、支え合う組織が生み出す力は、確実に次の時代の競争力となります。