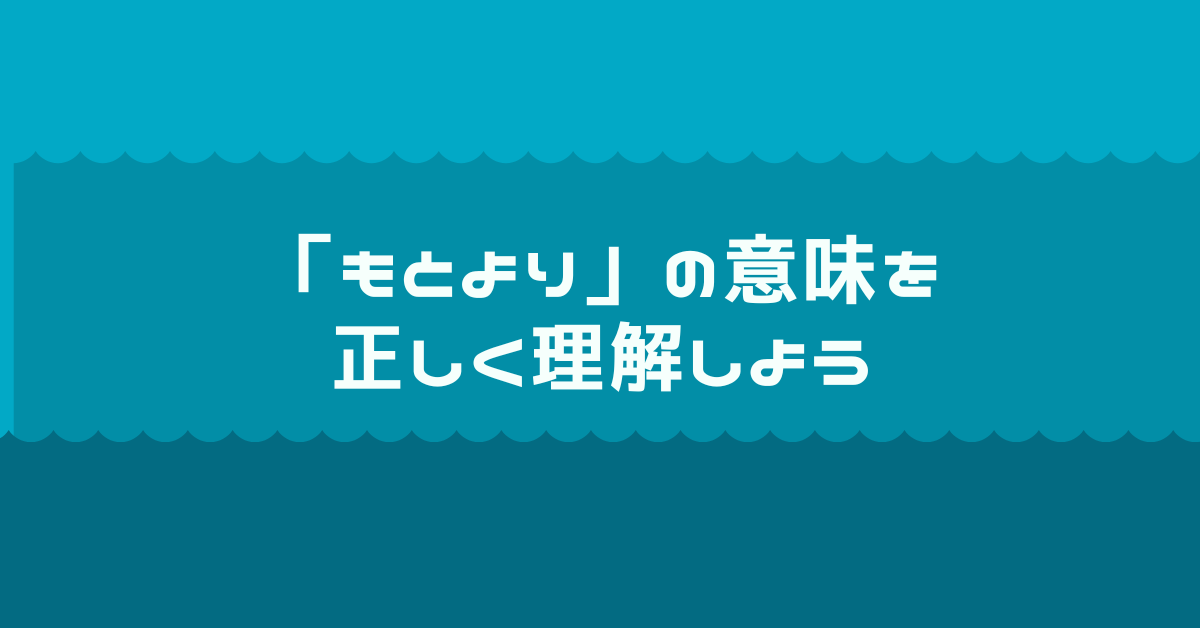日常でもよく耳にする「もとより」という言葉。しかし、いざビジネス文書や挨拶文に使おうとすると、「少しかしこまりすぎるかも」「そもそも意味をちゃんと理解できていないかも」と感じる方も多いのではないでしょうか。「もとより」は文語的な響きを持つ言葉でありながら、使い方次第で上品さや信頼感を与える表現です。本記事では、「もとより」の意味や正しい使い方、ビジネスシーンでの例文、さらに文学作品での使われ方まで丁寧に解説します。あなたの文章力を一段上げるヒントになりますよ。
「もとより」の意味を正確に理解して言葉の印象をつかむ
まずは、「もとより」という言葉の基本的な意味から整理しておきましょう。日常会話では何気なく使われる言葉ですが、意味を取り違えると文脈の印象が変わってしまうことがあります。
国語辞典における「もとより」の意味とニュアンス
国語辞典では「もとより」は次のように定義されています。
もとより(元より/本より)
① 初めから。以前から。
② 言うまでもなく。もちろん。
つまり、「もとより」には二つの意味があり、文脈によってどちらの意味にも使われます。
一つ目は「初めから」「以前から」という時間的な起点を表す意味。
二つ目は「当然」「言うまでもなく」といった強調・断定の意味です。
たとえば、
- 「彼はもとより努力家だった」→以前から(①)
- 「結果が出るのはもとより、過程も重要だ」→当然(②)
このように、同じ「もとより」でも意味が変化するため、文脈を読み取る力が大切になります。
「もとより」の漢字と語源の理解で誤用を防ぐ
「もとより」は漢字で書くと「元より」または「本より」です。どちらも誤りではありませんが、使う場面によって適した表記が異なります。
- 元より:もとの状態・起点を強調する場合(例:元より知っていた)
- 本より:原則・根本的な意味を強調する場合(例:本より当然のこと)
ただし、現代では多くの場合ひらがなで「もとより」と書かれるため、ビジネス文書でも無理に漢字にする必要はありません。ひらがな表記の方がやわらかく、フォーマルな文章でも読みやすくなります。
「もとより」の意味をビジネス的にまとめると
ビジネスシーンでは、「もとより」は主に次のように使われます。
- 当然・前提として(例:「お客様第一はもとより、社員の幸福も重視しています」)
- 以前から・そもそも(例:「当社はもとより地域社会との連携を大切にしてきました」)
つまり、「当たり前の前提を上品に表現する言葉」なのです。これが「もとより」を使う最大のメリットであり、同時に誤用が起きやすいポイントでもあります。
「もとより」の使い方とビジネスで自然に使うコツ
「もとより」の使い方を例文で理解する
「もとより 使い方」を正しく覚えるには、実際の例文で感覚をつかむのが近道です。
以下の例文で「当然」と「以前から」という2つの使い方を比較してみましょう。
①「当然・言うまでもなく」の意味で使う場合
- 「安全対策はもとより、社員教育にも力を入れています。」
- 「信頼はもとより、スピードも求められる時代です。」
- 「法令遵守はもとより、倫理的な行動も重視しています。」
このように、「〜はもとより、〜も/〜だけでなく〜も」と並列構文で使われることが多く、「Aは当然として、Bもそうだ」という流れを自然に作れます。
②「初めから・以前から」の意味で使う場合
- 「彼はもとより冷静な性格で、どんな場面でも動じない。」
- 「当社はもとより顧客志向を経営の軸としている。」
- 「彼女はもとより語学に強いが、交渉力にも長けている。」
この場合、「もとより」は“そもそもそうである”という意味を伝え、根拠や前提を補強する役割を果たします。
ビジネス文書での「もとより」の自然な言い回し
ビジネスシーンでは、次のような使い方が自然です。
- 「御社の信頼を得るのはもとより、長期的な関係構築を目指しております。」
- 「お客様満足度の向上はもとより、社員の働きやすさにも配慮しております。」
- 「利益追求はもとより、社会的責任を果たす企業でありたいと考えています。」
これらの例文では、「もとより」があることで、丁寧さと論理の流れを両立できます。
単に「当然」や「そもそも」と書くよりも、言葉の格が上がる印象を与えられますよ。
ビジネスシーンで誤用しやすいパターン
一方で、使い方を誤ると不自然に響くこともあります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 「私はもとより〜」と自己主張の強い文脈で使う
- 「〜するのはもとより」だけで文を終える
- 「もとより」を「もともと」や「そもそも」と混同する
たとえば、「私はもとよりこの企画に反対です」と書くと、「当然自分は反対」という押し付けがましい印象を与えます。
「もとより」は相手との共通認識や前提を述べる表現なので、自分の意見を強調したい場面には向きません。
正しく使うなら、「当初よりこの企画のリスクを懸念しておりました」と言い換えた方が自然です。
「もとより」の言い換え表現と使い分けで印象を変える
ビジネスでは同じ言葉を繰り返すよりも、文脈に合わせて適切な言い換えを使う方が洗練された印象になります。ここでは「もとより 言い換え」に使える自然な表現を紹介します。
「もとより」を「当然」と言い換える場合
「もとより」を「当然」「言うまでもなく」に置き換えると、よりストレートでわかりやすい文章になります。
- 「品質の安定は当然のこととして、価格競争力にも挑戦しています。」
- 「顧客満足の追求は言うまでもなく、従業員満足も経営課題です。」
ただし、「当然」は少しカジュアルで断定的に響くため、上司や顧客への文書では「もとより」の方がやわらかく丁寧です。
「もとより」を「そもそも」「当初から」と言い換える場合
「以前から」「初めから」の意味で使う場合は、次のような言い換えが自然です。
- 「当初からリスクを想定していました。」
- 「そもそもこのプロジェクトは顧客ニーズを重視しています。」
- 「もともと社内文化として定着しています。」
「そもそも」はやや会話的、「当初から」はフォーマル、「もともと」は中間的なトーンです。
文体や相手に応じて使い分けることで、文章全体の調和を保てます。
「もとより」を使わずに伝える上級表現
上級のビジネス文書では、「もとより」を使わなくても同様の意味を伝えられます。
- 「〜は前提として」
- 「〜は言うまでもなく」
- 「〜は周知の通り」
たとえば、「安全はもとより」と書かずに「安全は前提として」と言い換えると、論理的で実務的な印象になります。
相手に柔らかさよりも明確さを伝えたい場合は、このような言い回しの方が適しています。
「もとより 例文」で学ぶビジネスメールと会話の実践活用
ここでは、「もとより」を実際の業務シーンでどう使うかを例文で確認しましょう。ビジネスメール・プレゼン・会議の3つの場面を取り上げます。
ビジネスメールでの使い方
- 「この件につきましては、品質面はもとより、納期遵守も最優先と考えております。」
- 「新サービスの改善はもとより、サポート体制の強化にも努めてまいります。」
- 「安全確保はもとより、作業環境の改善にも取り組んでおります。」
フォーマルなメールで「もとより」を使うと、丁寧で落ち着いた印象を与えられます。
ただし、繰り返し使うと文章が重くなるため、文中1回程度がちょうどよいバランスです。
会議やプレゼンでの使い方
- 「品質の向上はもとより、コスト削減も今回のテーマの一つです。」
- 「信頼の獲得はもとより、スピード感のある対応も求められます。」
- 「お客様満足度の維持はもとより、ブランド価値の向上にも注力しています。」
口頭で使う場合、「もとより」は少しかしこまった印象になります。ビジネスの場では「もちろん」や「当然」と言い換える方が自然な場合もあります。
社内報告・文書での使い方
- 「法令遵守はもとより、職場内の倫理意識向上に努めております。」
- 「リスク管理はもとより、再発防止策を強化しました。」
- 「品質保証はもとより、顧客対応力の強化にも取り組んでいます。」
このように使うと、文書全体に落ち着いたトーンが生まれ、社内外問わず信頼感を高められます。
「もとより 意味 古文」から学ぶ日本語の背景
「もとより」は古くから使われてきた言葉で、古文では「初めから」「言うまでもなく」といった意味で登場します。
平安時代の文献や文学作品では、主に“起点”や“原理”を示す語として使われていました。
たとえば、『源氏物語』や『徒然草』の中では、「もとより」の語が“そもそもそのようなものである”という前提を表すために使われています。
古文における「もとより」は、人の性質や出来事の必然性を静かに強調する表現として位置づけられていたのです。
「もとより 意味 羅生門」「もとより 意味 こころ」に見る文学での使われ方
『羅生門』(芥川龍之介)における「もとより」
『羅生門』では、主人公の心理描写の中に「もとより」という言葉が登場します。
この場合、「当然ながら」や「言うまでもなく」といった意味で使われ、物語の前提や登場人物の心情の一貫性を表す役割を持っています。
文語的な響きを通じて、作品全体の緊張感や静けさを際立たせる効果があるのです。
『こころ』(夏目漱石)における「もとより」
一方、『こころ』に登場する「もとより」は、「以前から」「初めから」といった意味で使われています。
夏目漱石の文章では、登場人物の感情や思考を「もとより○○だった」と表すことで、心理の一貫性を描く技法が多く見られます。
つまり、「もとより」は文学の中で“人の本質”や“前提条件”を描くための重要な語として機能していたのです。
「もとより ビジネス」シーンで誤解されないための心得
ビジネス現場で「もとより」を使う際は、上品さと距離感のバランスが重要です。
次のポイントを押さえると、自然で信頼される表現ができます。
- フォーマルな文書に限定して使う(メール、企画書、挨拶文など)
- 相手と共有する前提を述べる場面で使う
- 口頭では控えめに、文書では積極的に使う
また、若手社員が上司や取引先に使う場合は、「当然」「当初から」と言い換える方が無難な場面もあります。
「もとより」は礼儀正しい言葉ですが、過剰に使うと堅苦しい印象になるため、使いどころを見極めることが大切です。
まとめ|「もとより」は言葉の品格を上げる便利な表現
「もとより」は、「初めから」「当然」といった意味を持つ上品で汎用性の高い日本語です。
その一方で、文脈によって意味が変わるため、誤用しやすい言葉でもあります。
覚えておくべきポイントは次のとおりです。
- 「もとより」は文語的な表現で、フォーマルな印象を与える
- 「当然」「以前から」という二つの意味がある
- ビジネスでは「AはもとよりBも」と並列で使うのが自然
- 言い換え表現として「当然」「そもそも」「当初から」などを使い分ける
- 古文・文学作品では“人の本質や前提”を表す重要な語として使われていた
正しく使えば、「もとより」は文章に信頼感と知性を与える言葉です。
ぜひ次にビジネスメールや報告書を書くときに、「もとより」を適切に使いこなしてみてください。きっと一段上の表現力を感じられますよ。