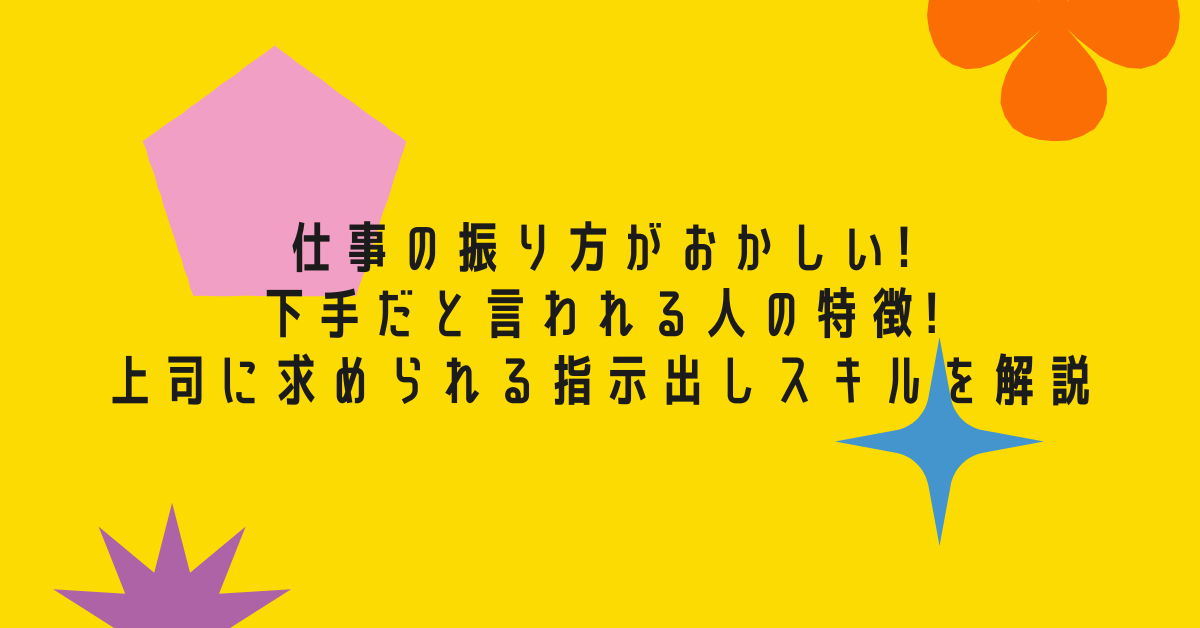仕事を円滑に進めるためには、適切なタイミングで適切な人に業務を任せる「仕事の振り方」が重要です。しかし、現場では「この人の仕事の振り方、おかしいな」と感じられてしまうケースも少なくありません。本記事では、仕事の振り方が下手だと評価されてしまう人の特徴を整理し、上司として求められる指示出しスキルや信頼を築くコミュニケーションの要点を、具体的な視点から解説していきます。
仕事の振り方に悩む人が増えている理由
指示出しが業務の一部になっていない
近年、働き方改革やリモートワークの浸透により、上司と部下の関係性がよりフラットになりつつあります。その中で、指示の出し方やタイミングを誤ると、「仕事の振り方がおかしい」といった不満を生む原因になります。上司側が「これくらいは言わなくても伝わるだろう」と思っていても、部下側は「何をどうすればいいのかわからない」と感じているケースが多いのです。
プレイヤーからマネージャーへの移行で躓く
プレイヤーとして優秀だった人が管理職になると、自身の業務スタイルをそのまま部下に押し付けてしまう傾向があります。その結果、「仕事を振るだけの人」になってしまい、具体的なサポートや意図の共有が抜け落ち、チームの不満や混乱を招いてしまうのです。
仕事の振り方が下手だと思われる人の特徴
タスクの背景や目的を伝えていない
仕事の振り方が下手だと感じられる一番の原因は、業務の「背景」と「目的」が共有されていないことです。たとえば、「これやっといて」とだけ言われても、なぜそれが必要なのか、どの程度の優先度なのかがわからないままでは、部下は行動しにくくなります。結果として成果物のクオリティが下がり、「仕事を振るのが苦手な上司」として評価されることになりかねません。
丸投げに見える振り方をしている
「これお願い」と言ってタスクだけを渡し、進捗管理もせずフォローもしないようなスタイルは、いわゆる「丸投げ型」です。本人には悪気がなくても、部下からすると「仕事を振るだけの人」であり、チームに対する責任感が薄いと映ってしまいます。
仕事量のバランスが取れていない
特定の部下にばかり仕事が偏っていたり、能力や経験に合わない仕事を無理に振ったりすると、不満が溜まりやすくなります。特に若手や未経験の部下に対しては、成長を促す視点と負荷のバランスが求められます。このバランス感覚が欠如していると、「仕事の振り方がおかしい」と言われてしまうのです。
上司に求められる仕事を振るスキルとは
目的・期待値・優先度を明確にする
業務を依頼する際には、「何のために行うのか」「どこまでを期待しているのか」「いつまでに必要なのか」をセットで伝えることが重要です。これは、ビジネスにおける基本的なコミュニケーションでありながら、実行できていない人が非常に多い部分でもあります。適切な情報共有こそが、仕事を振るスキルの根幹を支えます。
受け手のスキルと状況を見極める
人には得意不得意や成長ステージがあります。それを無視して一律に業務を振ってしまうと、「配慮が足りない」「理解してもらえていない」と不信感を抱かせる原因になります。状況に応じて、仕事の難易度や進め方を調整する姿勢が求められます。
振った後のフォローを丁寧に行う
仕事を振ったら終わりではなく、進捗の確認、壁にぶつかっていないかの対話、成果物のフィードバックまでがワンセットです。この一連の流れがあることで、部下は「自分の仕事が見守られている」と感じ、信頼関係が深まります。逆にフォローが一切ないと、「ただ振ってくるだけの人」「冷たい上司」と受け取られてしまいます。
なぜ「仕事を振るだけの人」になってしまうのか
忙しさにかまけて説明を省略している
多くの管理職が、「とにかく忙しい」状態にあるのが現実です。そのため、つい説明を省略し、短時間で済ませてしまう傾向があります。しかし、短期的には時短になっても、長期的にはミスや認識ズレによる手戻りが発生し、余計な時間がかかることになります。
「教えるのが面倒」という心理がある
特にプレイングマネージャーに多い傾向ですが、「自分でやった方が早い」「説明する時間がもったいない」と感じてしまい、仕事を振ることを敬遠する人もいます。その結果、無理に一部の業務だけを切り出して雑に渡し、部下からは「仕事の振り方が下手」と見られてしまうことになるのです。
信頼される上司になるための考え方
業務の意味を伝えられるリーダーになる
どんな小さな仕事でも、その意義を伝えることはできます。「これは会社全体の流れにどう関係しているのか」「このタスクがあなたのキャリアにどう影響するのか」など、意図を言葉にして伝える力は、信頼される上司に不可欠な資質です。
「仕事を振るのが失礼」と思わないことが大事
中には、「部下にお願いするのは気が引ける」と感じている人もいます。しかし、適切に仕事を任せることは、相手を信頼し、能力を評価している証拠でもあります。むしろ、任せないことの方が相手にとって失礼に映るケースもあるため、自信を持って任せる姿勢が大切です。
仕事の振り方を学ぶためのアプローチ
書籍や研修で体系的に学ぶ
「仕事の振り方 本」といったワードで検索すると、指示出しや業務分担に関する良書が多数見つかります。こうした書籍を活用し、理論と実例の両面から振り方の基本を学ぶのも有効です。また、社内外のマネジメント研修を受講することも、実践的なスキルを習得する近道となります。
振り返りとフィードバックを習慣にする
自分の振り方が適切だったかを定期的に振り返ること、部下からの意見を素直に受け取る姿勢を持つことも、上司として成長するうえで欠かせません。「仕事を振るのが苦手」だと感じている人ほど、小さな成功体験とフィードバックの積み重ねが自信に変わります。
まとめ:仕事の振り方は信頼構築の第一歩
「仕事の振り方がおかしい」「仕事の振り方が下手な上司」と言われる背景には、コミュニケーションの不足や、相手への配慮の欠如があります。一方で、仕事を適切に任せられる上司は、組織内で自然と信頼を集め、部下の成長を促進する存在となります。仕事を振るスキルは、単なる業務の割り振りではなく、組織運営の中核を担う重要な能力です。指示の出し方一つで、チームの成果もモチベーションも大きく変わります。今日から少しずつ、「任せ方の質」を見直していくことが、真に信頼されるリーダーへの第一歩となるでしょう。