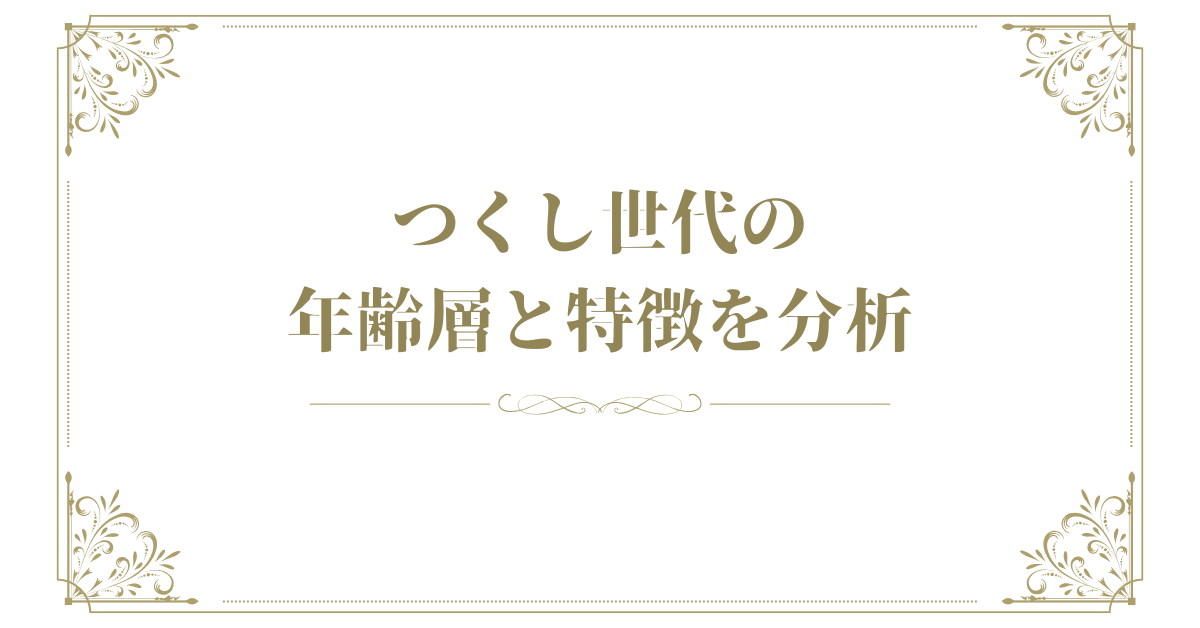近年、「つくし世代」という新しい言葉がメディアやビジネス現場で注目を集めています。ゆとり世代、さとり世代の次に登場したこの世代は、「尽くす」から名付けられたといわれ、他者に寄り添い、支え合う姿勢が特徴です。この記事では、つくし世代の年齢層や特徴、前後の世代との違いをわかりやすく整理しながら、企業や上司がこの世代とどう向き合えば良いのかを解説します。職場でのコミュニケーション改善やマネジメント力向上にも役立つ内容です。
つくし世代とは?ゆとり・さとりの次に現れた“支援型”の新世代
「つくし世代」という言葉の由来と背景
つくし世代とは、主に1996年〜2005年頃に生まれた若者層を指す言葉です。「尽くす」から転じて名付けられたこの言葉には、他者への思いやりや協調性を重んじる姿勢が込められています。
ゆとり世代が「個を尊重する世代」、さとり世代が「無理をせず現実を受け入れる世代」とされる一方で、つくし世代は「支援することに喜びを感じる世代」と言われています。
SNSやオンラインゲームなどを通じて他人とつながることが日常となった時代に育った彼らは、“誰かの役に立ちたい”という意識を自然に持つのが特徴です。
また、災害や感染症の流行など社会的に不安定な時期を経験してきたため、「一人では生きられない」「支え合いが大事」という価値観が強く根づいています。
つくし世代の年齢層と社会での立ち位置
2025年現在、つくし世代の中心層は20歳〜29歳前後。
つまり、大学生や社会人2〜7年目にあたる世代です。就職氷河期を知らず、比較的安定した教育環境で育った一方で、コロナ禍を境に急激な働き方の変化を体験しています。
そのため、彼らは「柔軟で適応力が高い反面、慎重でリスクを避ける傾向」があります。
職場では、「チームの和を乱さず、周囲を支える立ち回り」を好み、リーダーよりもサポーターとしての役割にやりがいを感じる人が多いのも特徴です。
「つくし世代の前」と「次の世代」の関係性
つくし世代の前には「さとり世代(1990年代前半生まれ)」が位置します。
さとり世代はバブル崩壊後の不況期に育ち、物質的豊かさよりも精神的安定を重視する傾向がありました。
一方で、つくし世代はスマホネイティブであり、社会との接点をデジタルで築くことが当たり前。**“現実的かつ共感的”**な姿勢が特徴的です。
つくし世代の次に続くのが、Z世代後半〜α世代。この層はAIや生成ツールを使いこなし、さらに「自己表現と多様性」を重視する方向へ進んでいます。
つまり、つくし世代は「他者との協調を重んじる最後のアナログ共感型世代」とも言えます。
つくし世代の特徴を詳しく解説|共感力・安定志向・個よりチームの価値観
つくし世代の特徴①:他者の感情を読み取る共感力が高い
つくし世代の最大の特徴は、**「共感力の高さ」**にあります。
SNSやオンライン環境で多様な価値観に触れてきた経験から、相手の感情を汲み取る力に長けています。
職場でも「誰かの気持ちを察して動く」「衝突を避ける」「和を保つ」という行動が自然にできる人が多いのです。
ただし、その反面「相手に気を使いすぎて意見が言えない」「感情を内にためやすい」という課題もあります。
上司や同僚が“話しやすい雰囲気”を作ってあげることで、彼らの本来の力が発揮されやすくなります。
つくし世代の特徴②:安定志向で、無理を嫌うバランス型
つくし世代は「挑戦より安定」を重視する傾向があります。
働き方においても、出世よりも**「心身のバランスを保ちながら長く働ける環境」**を求める傾向が強いです。
これは、コロナ禍を通じて在宅勤務・副業など多様な働き方を見てきた経験が影響しています。
彼らは“頑張ることが美徳”という旧来の価値観を持たず、「頑張りすぎる人をサポートする側」であることにやりがいを感じます。
一方で、指示待ち傾向が強く、自分でリスクを取って動くことを避けがちな面もあるため、リーダー層には「小さな成功体験を積ませる支援型マネジメント」が求められます。
つくし世代の特徴③:個人よりもチームを優先する“支援型マインド”
つくし世代は、組織の中で「主役」になるよりも、「縁の下の力持ち」として周囲を支えることに価値を見出します。
彼らにとっての成功は「自分が認められること」よりも、「チームがうまくいくこと」。
まさに「尽くす世代」という名前にふさわしい特性です。
この支援型マインドは、リーダーの右腕的存在としてチームを安定させる力になりますが、本人が評価されにくいという問題も生まれます。
企業側が「支える人を正当に評価する仕組み」を整えることが、つくし世代の定着率を高めるカギになります。
ゆとり世代・さとり世代・つくし世代の違いを比較して理解する
世代ごとの時代背景と価値観の変化
それぞれの世代を単に「性格の傾向」で区切るのではなく、「どんな時代に育ったか」を見ると特徴が明確になります。
| 世代 | 主な生まれ年 | 社会背景 | 主な価値観・特徴 |
|---|---|---|---|
| ゆとり世代 | 1987〜1995年頃 | 教育改革・個性尊重 | マイペース・自由・指示より対話 |
| さとり世代 | 1990〜1999年頃 | 就職氷河期後・安定志向 | 現実主義・欲が少ない・合理的 |
| つくし世代 | 1996〜2005年頃 | SNS普及・共感文化 | 支援型・協調・共感・無理をしない |
ゆとり世代が「自由と個性」を大切にし、さとり世代が「安定と自立」を重んじたのに対し、つくし世代は「共感とつながり」を軸に行動します。
つまり、「個からチームへ」価値観が移行した世代と言えます。
「さとり世代とは何か」を理解してこそ見える違い
「さとり世代とは」何かをもう少し掘り下げると、彼らは不況下で育ち、競争に疲れた社会を見て「欲を持つより平和でいたい」と考えるタイプです。
彼らはリスク回避的で現実的でしたが、一方で自分の感情にはあまり向き合わず、冷静さを重んじる傾向がありました。
つくし世代はその延長線上にありながら、感情に共鳴しながら行動する点が大きく異なります。
「冷静なさとり世代」と「温かい共感型のつくし世代」と表現すると分かりやすいでしょう。
つくし世代がビジネスにもたらす価値
つくし世代は、チーム内の関係性を重んじ、衝突を避けながら協働を進めます。
そのため、“人間関係の潤滑油”としての役割を果たすことができ、職場の離職率低下や心理的安全性の確保にも寄与します。
また、彼らは共感力と情報収集力に優れており、カスタマーサポートやコミュニティ運営など「人との距離感が大切な業務」に強みを発揮します。
企業にとっては、組織の安定化を担う重要な世代です。
まとめ:つくし世代は「支える力」で組織の未来をつくる
つくし世代は、ゆとり世代やさとり世代の流れを汲みながらも、「他者を支える」ことを軸に生きる新しい価値観を持つ世代です。
共感を大切にし、無理をせず、チームのために尽くす。その姿勢は、激変する時代において企業の“安定の礎”となるでしょう。
彼らを活かす鍵は、「競わせる」よりも「支える環境を作る」こと。
上司や企業が「支援型マインドを評価する文化」を築けば、つくし世代は組織を静かに、しかし確実に前進させていきます。
そしてその先にあるのは、「一人で頑張る時代」から「共に支え合う時代」へのシフト。
つくし世代は、その変化の象徴とも言える存在なのです。