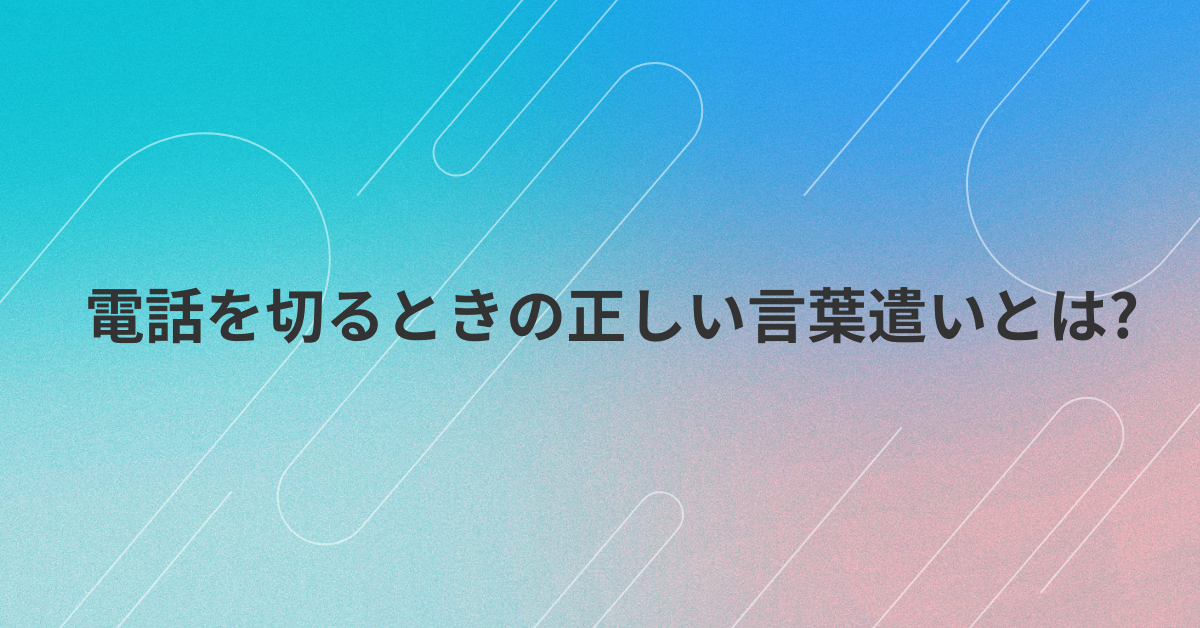仕事中の電話対応では、内容だけでなく「切るときのひと言」が相手に与える印象を大きく左右します。特にビジネスシーンでは、些細な言葉遣いの違いが「信頼」「礼儀」「マナー」すべてに関わります。今回は、電話を切る際の正しい言葉遣いについて、友達や恋人とのケースとの違い、トラブルを避けるための考え方、ビジネス現場で活かせる具体的な対応例まで解説します。
電話を切るときの基本マナー
なぜ「切るときの言葉」が重要なのか
電話のやりとりは、表情や身振りが伝わらない分、言葉の選び方やタイミングがすべてです。終話時の一言が丁寧であれば、相手は「きちんとした人」という印象を受けやすく、逆にぞんざいであれば無礼と感じられるリスクがあります。
一般的に適切とされるフレーズ
ビジネスシーンでは、「それでは失礼いたします」「本日はありがとうございました」など、敬語を用いた締めくくりが基本とされます。「失礼します」と「失礼いたします」の使い分けも重要で、目上の相手や取引先に対しては、より丁寧な後者を選ぶのが無難です。
「電話切るときの言葉」友達や恋人との違い
プライベートとビジネスでの使い分け
たとえば、友達同士では「じゃあねー」「はーい、またね」といった軽い表現も問題ありません。しかしビジネスでは、「はーい」だけで終話するのは稚拙な印象を与える場合があります。あくまでTPOを踏まえた使い分けが求められます。
好きな人との電話ではどうする?
恋愛関係にある相手との電話では、「切りたくない」「またすぐ話そうね」など、気持ちを込めた表現も珍しくありません。ただし、業務用スマホでこうした会話が漏れるリスクもあるため、プライベートと業務はきちんと分ける姿勢が大切です。
「電話を先に切るのはどっち?」問題の解釈
ビジネスマナー的な観点から
「どちらが電話を先に切るべきか」はしばしば議論になりますが、ビジネスマナー的には、基本的に「目下の者」が先に切らないようにするのが礼儀とされています。つまり、取引先が通話を終えたのを確認してから、静かに受話器を置くのが好印象を与えます。
実務上の対応ポイント
携帯電話などの通話ではタイムラグやノイズもあるため、「どうぞお切りください」「こちらから失礼します」といった“切る合図”を伝えるのも円滑なコミュニケーションの一部です。
「うまい電話の切り方」とは何か?
会話の流れを止めずに終話へ導く技術
突然「失礼します」と切ってしまうと、唐突に感じさせてしまいます。理想的なのは、会話の終わりに向かう流れを意識しながら、「それではこの件で進めさせていただきますね」「ご不明点があればまたご連絡ください」など、余韻を残しながら終話する方法です。
「電話切るとき 失礼します」は使い方次第
「失礼します」と「失礼いたします」の違い
「失礼します」は一般的な敬語ですが、上司や取引先などに対しては「失礼いたします」としたほうが丁寧です。細かな違いですが、こうした言葉遣いは企業の印象や担当者としての評価に直結することもあります。
相手の返事を待つべきか?
「失礼いたします」と言ったあとに、相手の「はい、失礼します」といった返答を待つのがベストです。ただし相手が無言だった場合、2秒ほど待って反応がなければ静かに電話を切って問題ありません。
「電話 失礼します 言わない人」にどう対応する?
社内マナーとして指導が必要な場合
社内で「失礼します」すら言わずに電話を切ってしまう人がいた場合、それが無意識であれば注意する必要があります。マナー研修やマニュアルの共有を通じて、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
社外の相手にはどう対応すべきか
社外の方がマナーに欠ける終話をした場合でも、こちらがきちんとした対応をすれば問題ありません。対応品質の高さが、逆に自社の印象アップにつながることもあります。
社内マナー向上のためのポイント
電話対応マニュアルの整備
社内で統一した電話応対を行うには、マニュアル化が有効です。「電話を切るときの言葉」も項目に含め、教育担当者が繰り返し指導できる環境を整えましょう。
フィードバック文化を定着させる
電話対応は“慣れ”の世界でもあるため、上司や同僚がフィードバックする文化を作ることも重要です。録音機能を活用した研修やロールプレイも有効です。
電話の切り方は小さな信頼の積み重ね
相手の見えない電話応対だからこそ、丁寧な言葉遣いと配慮のある対応が評価されます。電話を切るときの言葉ひとつで、信頼関係を深めることも壊すこともありえるのです。ビジネスで失礼にならない電話対応を目指すなら、まずは“終話の言葉”に注目してみましょう。