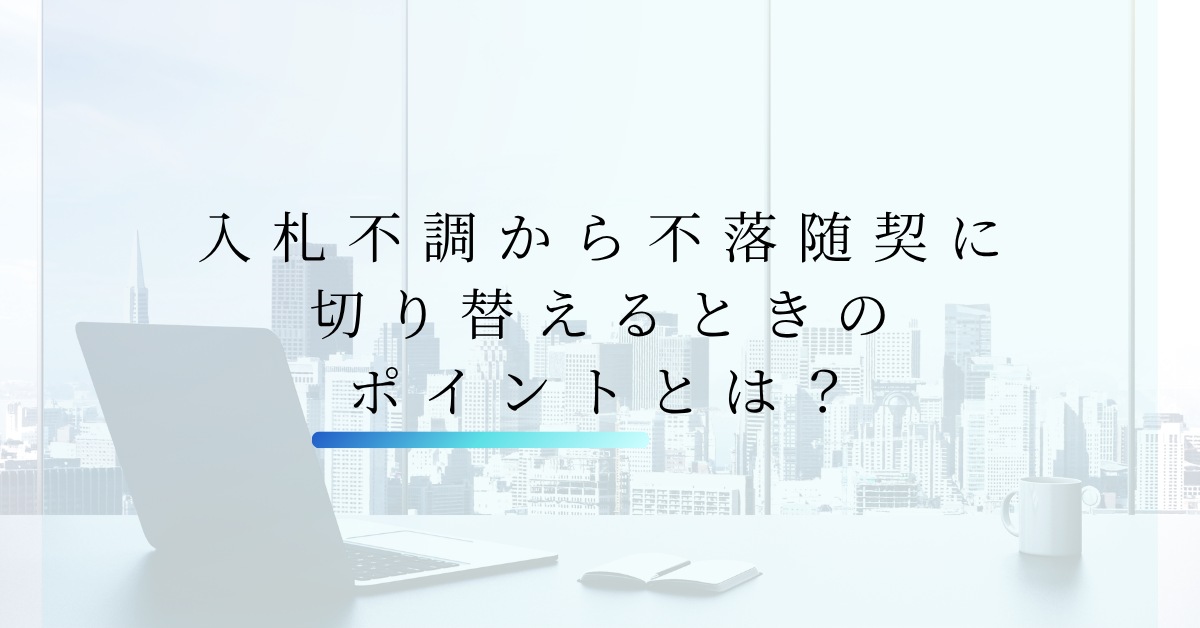公共調達の現場で、思うように入札が成立せず「不調」となってしまうケースは少なくありません。特に近年では、建設業界を中心に人手不足や資材高騰の影響で、予定価格と実勢価格の乖離が広がり、応札がゼロになるケースも増えています。こうした場面で活用されるのが「不落随契」という契約形態です。
この記事では、不落随契の基本的な意味から、導入にあたっての法的留意点、見積合せのポイント、予定価格との関係、交渉プロセス、さらに昨今の厳正化の流れまで、初心者にもわかりやすく、かつ実務に役立つ内容で丁寧に解説していきます。
入札不調とはなにか?背景と発生しやすい案件の特徴
入札不調とは、公告に基づいて入札を実施したものの、いずれの業者からも応札がなかった、または予定価格を超える高額な入札しかなく、落札者を決定できなかった状態を指します。代表的な原因としては以下のようなものがあります。
- 設計条件に対して予算が著しく低い(予定価格と実勢価格の乖離)
- 地方部での工事など、業者の確保自体が困難
- 工期が過密または繁忙期に集中している
- 契約条項が業者にとって不利すぎる
特に地方自治体では、少数の業者しかいない地域での公共工事においてこのような状況が頻発しています。事業自体は公共サービスの維持に直結しており、中止できない場合も多く、代替手段として不落随契の検討が行われるのです。
不落随契とは?基本的な考え方と法的な位置づけ
不落随契とは、一般競争入札や指名競争入札で契約の相手方が決まらなかった場合に、その入札に参加した者、またはそれ以外の業者と個別に契約を締結する方式を指します。正式には「随意契約の一形態」であり、公共工事などにおける例外的措置として位置付けられています。
そのため、不落随契はあくまでも競争入札による契約が成立しなかったことが前提であり、任意に選べる契約方法ではありません。行政手続法や地方自治法の契約制度に基づくものであり、導入には正当な理由と明確な手続きが必要です。
不落随契に切り替える際の条件と正当性の確保
不落随契の導入には、いくつかの厳格な条件があります。以下の要素を満たすことが基本とされています。
- 入札が1回以上実施され、成立しなかった事実があること
- 契約の緊急性、公共性が高く、再入札が困難または非現実的であること
- 契約締結に際して、公平性・透明性を保つための社内・第三者審査が行われていること
- 契約額が予定価格の範囲内であること、または合理的に見直された価格であること
たとえば、自治体が雪対策や災害復旧といった緊急性の高い工事を発注する場合、一度の不調で工期が大幅に遅延する恐れがあるため、不落随契が適用されることがあります。
見積合せの実施とその注意点
不落随契に切り替える場合、実務上必須とされるのが「見積合せ」の実施です。これは、複数の業者から相見積もりを取得し、契約価格の妥当性を担保するプロセスです。
ここで注意すべきなのは、単に価格を比較するだけでなく、以下のような観点も加味して評価する必要があるという点です。
- 技術力や過去の実績
- 業務遂行能力(人員確保、納期遵守)
- 契約履行にあたってのリスク管理体制
たとえば同価格の見積が複数あった場合、災害時の実績が豊富な業者を優先するという判断も正当化できます。このプロセスと判断基準をきちんと記録に残しておくことが、監査や住民監査請求においても重要になります。
不落随契と予定価格の関係性
不落随契における予定価格の役割は大きく、契約の上限価格を決定する基準となります。ここで抑えておきたいのが次の3点です。
予定価格は変更可能か?
入札不調後、不落随契に切り替える際には、当初の予定価格が実勢と乖離している可能性があります。この場合、価格調整のために「予定価格の再設定」が行われることがあります。ただし、見積や市場価格調査などに基づく客観的な裏付けがなければ、不適切な支出と判断されかねません。
公表済みの予定価格の扱い
「予定価格 公表」がされていた案件では、交渉余地が限定されることがあります。価格の天井がすでに公開されているため、それを基準に業者との交渉が難航することもあります。したがって、不落随契を想定する場合には、価格の公表方法についても戦略的に考える必要があります。
予定価格を超える契約は可能か?
原則として、予定価格を上回る契約はできません。ただし、仕様変更や特別な要件が加わった場合、価格変更に伴う再設定と再手続きを経て、上限額を見直すことが認められる場合もあります。
価格交渉の進め方と記録の重要性
「不落随契 価格交渉」は、業者との直接対話によって契約条件を決定するプロセスですが、その透明性が強く求められます。ポイントは以下の通りです。
- 価格だけでなく、契約条件(納期・仕様など)も同時に調整する
- 交渉プロセスは逐一議事録として記録し、社内で共有・承認を得る
- 決裁過程で金額妥当性や調達理由を文書で説明できるようにする
交渉内容が後日監査や情報開示請求の対象になる可能性を考慮し、形式的ではなく実態として妥当な交渉プロセスを心がける必要があります。
「不落随契の原則廃止等その厳正化について」とは
総務省や各自治体で注目されているのが「不落随契の原則廃止等その厳正化について」という指針です。これは、不落随契が本来の例外的措置であるにもかかわらず、常態化しているケースが一部で見られることに対する是正措置です。
具体的には次のような運用が推奨・指導されています。
- 不落随契を行う前に、2回以上の入札を実施する
- 必要性や価格妥当性について契約審査委員会の承認を得る
- 交渉・契約に至るまでの手順と文書をすべて保存し、必要に応じて公開
このようなガイドラインの背景には、随意契約を利用した不正・癒着への懸念があり、公共調達の透明性を確保する強い意図があります。
調達担当者が持つべき視点とリスク管理
不落随契を正しく運用するためには、単に形式を整えるだけでは不十分です。調達担当者として、以下のような視点を持って対応することが求められます。
- 契約の必要性と緊急性を客観的に説明できるか
- 市場価格や業者状況を把握し、契約額が妥当であるか検証しているか
- 自らの判断が後日の説明責任に耐えうるか
また、あらかじめ契約手続きや価格交渉における社内マニュアルを整備し、関係部門と共通認識を持っておくことが、業務の属人化を防ぐためにも有効です。
まとめ:不落随契の適切な運用が公共調達の信頼性を支える
不落随契は、入札不調という緊急事態に対応するための「例外的措置」であり、その導入には慎重な判断と手続きが必要です。見積合せによる価格妥当性の確保、予定価格との関係性、価格交渉の記録管理、さらに昨今の厳正化方針をふまえた制度設計まで、多くの要素をクリアしなければなりません。
調達担当者にとっては、業者との信頼関係や交渉力に加え、法的理解と説明責任の意識が求められる難易度の高い業務です。しかし、適切に運用できれば、行政としての信頼を保ちつつ、必要な事業を遅滞なく進めることが可能になります。
今後も制度の見直しやガイドラインの強化は続くと見られるため、常に最新情報を把握し、柔軟に対応できる体制づくりが重要です。