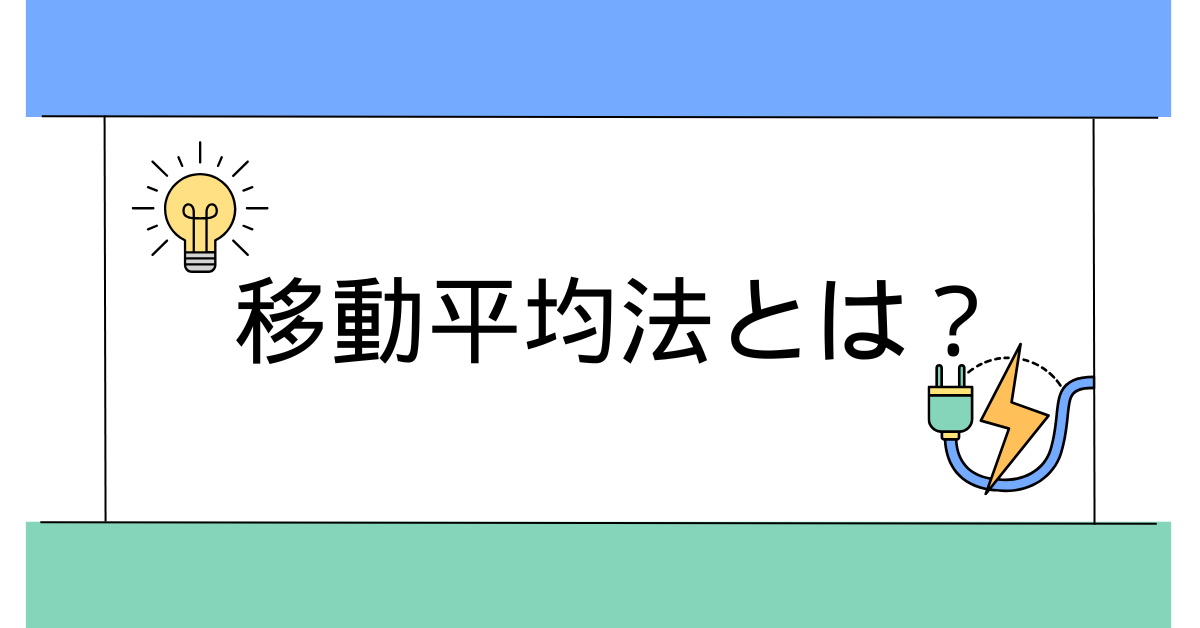在庫の管理や原価計算は、企業活動のなかで非常に重要な業務です。その中でも「移動平均法」は、日々の仕入れや出庫のたびに平均単価を更新しながら在庫評価を行う実務的な手法として広く用いられています。本記事では、移動平均法の基本から、総平均法・先入先出法との違い、簿記との関係、そして実務での活用例まで、初心者でもわかりやすく解説します。
移動平均法とは?
定義と特徴
移動平均法とは、商品の仕入れごとに平均単価を再計算し、その平均単価をもとに出庫分の原価を算出する方法です。仕入れのたびに「移動」するように平均を見直すため「移動平均法」と呼ばれています。
この方法は、在庫単価の変動をタイムリーに反映できるため、価格の変動が大きい商品を扱う業種にとっては特に有効です。たとえば、原材料価格が市場の影響で頻繁に変動する製造業などでは、移動平均法を採用することで、より実態に即した原価計算が可能となります。
また、移動平均法はリアルタイム性に優れている点でも注目されています。仕入れがあったその瞬間に平均単価を更新できるため、在庫情報が常に最新の状態に保たれます。これにより、経営判断のスピードや正確性も高まります。
移動平均法の計算式
基本的な計算方法
移動平均法の基本的な考え方は「加重平均」に近いものです。計算式は以下の通りです:
新平均単価 =(在庫数量×在庫単価 + 仕入数量×仕入単価) /(在庫数量+仕入数量)
この新しい平均単価を、次の出庫の単価として使用します。これを毎回の仕入れ後に更新することによって、在庫管理と原価計算を行っていきます。
具体的な数値例
たとえば、現在の在庫が10個で単価が100円だったとします。ここに新たに5個を単価120円で仕入れた場合、
新平均単価=(10×100+5×120)÷(10+5)=(1000+600)÷15=1600÷15=約106.67円
この新平均単価106.67円を用いて、次の出庫での売上原価を算出します。こうした処理を日々の業務で繰り返していくことで、より現実に即した在庫評価が実現できます。
さらに、この計算は手作業でも可能ですが、エクセルなどの表計算ソフトを使えば自動化も可能です。特に取扱商品が多い業種では、関数やマクロを組み合わせることで計算ミスを防ぎ、業務効率を飛躍的に向上させることができます。
簿記における移動平均法の扱い
試験対策としての重要性
簿記の学習においても、移動平均法は重要なトピックのひとつです。日商簿記2級や3級の試験範囲にも含まれており、在庫の評価や売上原価の算出方法として頻出しています。
簿記上では、帳簿に仕入れごとの数量と金額、そしてそれに応じた平均単価の記録が求められます。
仕訳の記入方法
仕入時は「仕入」勘定と「現金」または「買掛金」などの勘定を使い、在庫の単価を移動平均で更新します。出庫時には「売上原価」勘定と「商品」勘定を使って出庫数量×平均単価で売上原価を計上します。
この手法は、経理部門だけでなく、在庫を管理するロジスティクス部門や店舗運営でも理解しておくべき基礎知識です。実際の簿記試験でも、仕訳をもとに移動平均法による計算が問われることがあるため、実務と学習の両面で活用されています。
移動平均法と総平均法の違い
総平均法とは
総平均法は、一定期間内のすべての仕入れと在庫を一括して平均し、その平均単価を基に在庫評価や売上原価の計算を行う方法です。期間単位での平均単価を使用するため、期中に価格変動があっても一律の単価が使われるのが特徴です。
両者の違い
移動平均法は仕入れのたびに平均単価を更新しますが、総平均法は決算や月末などの一定のタイミングで平均を取る点で大きく異なります。
たとえば、頻繁な価格変動がある場合には、移動平均法のほうがより実態を反映した原価計算になります。一方で、総平均法は計算回数が少なく済むため、業務の簡素化というメリットがあります。
実務での使い分け
精緻な原価管理が求められる製造業などでは移動平均法が好まれる一方、取扱商品が多く、業務効率が重視される小売業や商社では総平均法が用いられることが一般的です。
たとえば、毎日数百〜数千種類の商品を仕入れ・販売するスーパーでは、移動平均法を運用するコストが高くなる可能性があります。こうした場合、一定期間まとめて計算できる総平均法がより適しています。
先入先出法との比較
先入先出法の特徴
先入先出法(FIFO)は、最も古い在庫から順に出庫していくという前提で原価を計算する方法です。物理的な出庫の順序に近いため、食品や消耗品などの回転が早い商材に向いています。
移動平均法との違い
移動平均法は平均をとることで原価の変動をならすのに対し、先入先出法は仕入れたタイミングによって原価がそのまま売上原価に反映されるため、価格が変動する市場では売上原価の数値も大きく変わります。
適用シーンの違い
たとえば、インフレ時には先入先出法のほうが古い安価な在庫が使われるため、売上原価が低く利益が大きくなる傾向があります。一方、移動平均法では平均が取られるため、利益のブレは抑えられます。
逆に、デフレの局面では新しい在庫の単価が低いため、先入先出法のほうが売上原価が高く計上されることになり、利益が減少する可能性があります。このように、経済状況や業種特性に応じて適切な手法を選ぶことが重要です。
移動平均法の実務活用と効率的なやり方
エクセルによる店舗別売上分析との連携
小売業などでは、移動平均法による在庫単価管理をエクセルで管理し、店舗ごとの売上や在庫評価と連動させる手法が多く見られます。具体的には、商品ごとに在庫表を作成し、仕入れ・販売ごとの数量と金額を入力することで、リアルタイムで在庫単価を把握できます。
この方法は「店舗別 売上 分析 エクセル」などのニーズに対応し、チェーン展開している企業にとっては非常に有効です。
データ分析ツールとの併用
クラウド型の在庫管理ソフトやBIツールと組み合わせることで、移動平均法の単価データをリアルタイムに分析・可視化し、販促活動や仕入れ戦略にも反映できます。これにより、在庫評価だけでなく、マーケティング活動や棚卸の精度も大きく向上します。
また、RPAツールと連動させることで、日々の仕入れと出庫データを自動で処理し、平均単価の更新も自動化できます。人為的なミスを削減しつつ、効率性を保てるため、業務改善の一環としての導入も進んでいます。
総括:移動平均法を理解して実務に活かす
移動平均法は、価格変動を適切に原価に反映できる柔軟な在庫評価方法です。簿記や試験対策としての知識だけでなく、実際の業務のなかでも非常に役立つスキルです。
特に、小売業や製造業など、価格の変動が日常的にある業界では、移動平均法を導入することで原価管理や在庫評価の正確性が格段に向上します。さらに、エクセルやデータ分析ツールと組み合わせることで、業務効率を高めながら数値の正確性も保てます。
一方で、総平均法や先入先出法といった他の在庫評価法との違いや、それぞれの適用場面を理解することで、より柔軟な会計処理や経営判断が可能になります。
在庫管理や原価計算は、経営の根幹を支える重要なファクターです。本記事で紹介した知識をもとに、実務への適用を意識して、最適な手法を選択・活用していきましょう。