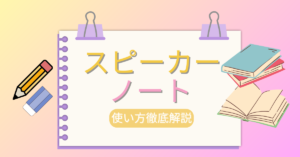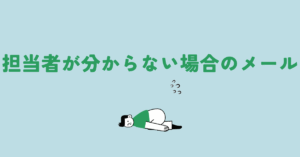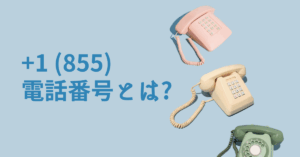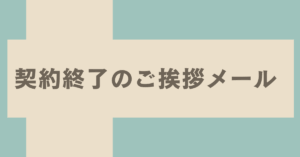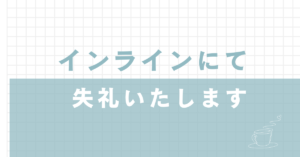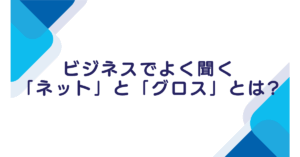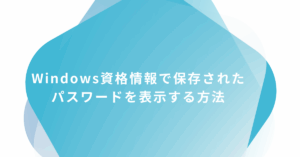ビジネスメールを送った後に「あ、内容を間違えてしまった!」と焦った経験はありませんか。
そんな時、つい使ってしまいがちなのが「ご放念ください」という言葉です。
一見ていねいに見えるものの、「失礼では?」「上から目線?」と不安に感じる人も少なくありません。
本記事では、
- 「ご放念ください」の正しい意味
- 失礼・不快に受け取られやすい理由
- 代わりに使える安全な丁寧表現
をわかりやすく解説します。
ご放念くださいの意味

ご放念くださいとは、
「気にしないでください」「心配しないでください」
という意味の敬語表現です。
- 「放念」= 気にかけない・心配しない
- 「ご〜ください」= 相手への依頼
そのため失礼になるというケースはほとんどないことがわかりますね!
結論としては無難に使用していい言葉になると思います
このあと、なぜ失礼といわれるのか使用しないほうがいいのかについて解説をしていきます。
ご放念くださいが失礼といわれる理由

結論として
文法的には問題ないのですが、使い方や相手によっては失礼にかんじとられてしまうというケースがあります。
相手に対して命令口調に響く
「気にするな」と相手の感情を一方的に制御する印象があります。
例えば相手が気にしていることだったり、不満に思っている状態で、忘れてくださいって言われてもイラっとしますよね
「ください」という依頼形を使っているため、一見すると柔らかいように見えます。しかし「放念」という言葉自体が「気にするな」と命令的に響くため、特に目上の人や取引先に対しては失礼だと感じられる場合があります。
社内でも誤解を招く恐れ
例えば上司に「この件はご放念ください」と送ると、「指示を無視してよいのか?」と勘違いされることがあります。社内コミュニケーションでも「ご放念ください 使わない」と言われる理由はここにあります。
古臭く不自然に感じられる
ビジネスメールでは「自然さ」と「相手への配慮」が重視されます。「ご放念ください」は普段の会話ではまず使わないため、違和感を覚える人が多いです。特に若い世代や外資系企業ではほぼ使われない表現です。
状況軽視に見える

トラブル・ミス・遅延などの場面で使うと下記のようなことを思われるでしょう
- 誠意が足りない
- 反省していない
- 問題を軽く扱っている
と受け取られて、さらに相手を怒らせてしまうはずです
おそらく納期遅延とかで期限を忘れてくださいというようなビジネスマンはいないと思いますが、、、
ご放念くださいの代替表現を使った実践メール例文
実際のメールで「ご放念ください」を使いたくなる場面で
かわりになる言葉を紹介します
資料送付に関するやり取りでの例
- 例:
「先日の資料送付の件はご放念ください」
(意味が曖昧で、相手は対応をやめるべきか迷ってしまいます)
↓
- 改善例:
「先日の資料送付の件は、すでにこちらで対応済みですのでお気遣いは不要です」
(状況を具体的に説明しつつ、相手への配慮を残しています)
依頼後に相手へ配慮するときの例
- 例:
「もしご都合が悪ければご放念ください」
(放念の響きが固く、断りにくさを与えてしまいます)
↓
- 改善例:
「もしご都合が難しいようでしたら、どうぞお気になさらずご遠慮なくお知らせください」
(相手が断りやすい雰囲気を作りつつ、配慮を伝えています)
社内でのやり取りでの例
- 例:
「昨日の件はご放念ください」
(上司に送ると特に違和感が強いです)
↓
- 改善例:
「昨日の件はすでに解決済みですので、ご心配には及びません」
(状況が明確で、相手に安心感を与えます)
「ご放念ください」を避けるべきなのと同じように、似たような場面でつい使ってしまいがちなNGフレーズもあります。
避けたいNGフレーズ
- 「無視してください」
(命令的で失礼な響きがあります) - 「気にする必要はありません」
(断定的で冷たい印象を与えることがあります) - 「忘れてください」
(ぞんざいに感じられ、相手の行動を否定するように響きます)
NGフレーズを避ける理由
これらの表現はすべて「相手の気持ちを切り捨てる」印象を与える点で共通しています。ビジネスシーンでは相手の立場を尊重しつつ、自分の意図を正確に伝えることが求められます。そのため「ご放念ください 失礼」と言われるのと同様に、強すぎる表現は避けるべきなのです。
まとめ
「ご放念ください」は「お気になさらないで」という意味ですが、現代のビジネスでは失礼に受け取られるリスクがあるため、基本的には使わない方が安心です。その代わりに「お気遣いには及びません」「ご心配には及びません」「お気になさらないでください」など、相手の立場を尊重した表現を用いるのがおすすめです。
また、メールでは必ず状況を具体的に説明し、相手が判断に迷わないように書くことが大切です。社内でも社外でも、「どう伝えれば相手が安心するか」を意識することで、信頼関係を保ちながらスムーズなやり取りができますよ。