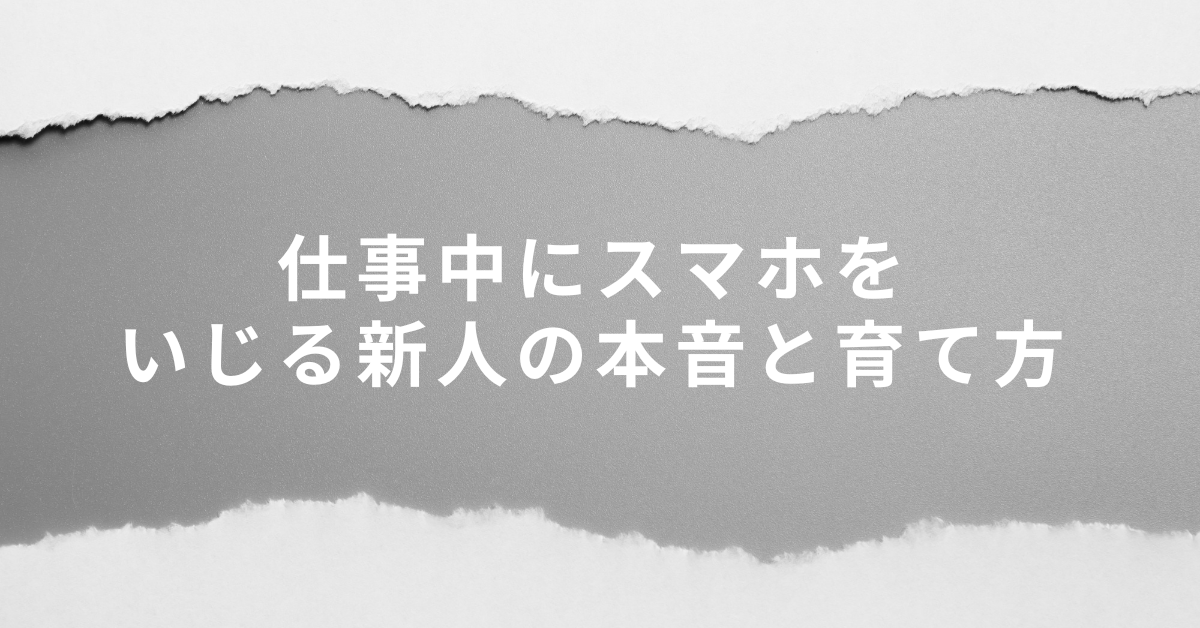「仕事中にスマホばかり触っている新人を見ると、イライラしてしまう」「注意しても響かない」「時代が違うのかもしれない」。
そう感じたことはありませんか?
実は、仕事中にスマホをいじる新人の多くは、“やる気がない”わけではありません。
彼らは自分なりの理由をもってその行動をとっており、そこには心理的な防衛や価値観の違いが深く関わっています。
この記事では、「仕事中スマホやめてほしい」と感じている上司・同僚の視点から、
新人がスマホを手放せない心理、怒っても直らない理由、そして“怒るより効く指導法”を具体的に解説します。
新人教育やチームマネジメントに悩む人ほど、読む価値のある一篇です。
なぜ新人は仕事中にスマホをいじるのか|表面的な「怠け」ではない心理背景
不安をまぎらわせる「安心ツール」としてのスマホ
あなたが新人時代、初めての職場で緊張しながら机に座っていたときのことを思い出してみてください。
右も左もわからず、上司の表情を伺いながら「これで合っているのだろうか」と思う。
その不安を、現代の新人たちは“スマホ”という道具でやわらげているのです。
スマホをいじる行為は、心理学的にいえば自己安心行動。
つまり「自分を落ち着かせるための癖」のようなものです。
例えば、
- SNSの通知を見ることで「自分には居場所がある」と確認する
- 友達からのメッセージで日常を感じ、緊張を緩める
- スマホ画面という“自分だけの小さな世界”に逃げる
これらはすべて、防衛反応なのです。
決して「サボりたい」「怠けたい」だけではありません。
怒鳴っても直らないのは、行動の根に“感情”があるから。
感情に寄り添わずに表面だけを注意しても、同じ行動を繰り返します。
デジタルネイティブ世代の「無意識確認行動」
今の20代前半~新卒世代は、生まれたときからスマホやインターネットが身近にありました。
彼らにとってスマホは“道具”ではなく、“身体の一部”のような存在です。
たとえば、通知が鳴らなくても画面を確認する、無意識にアプリを開く――。
この「無意識確認行動」は、もはや条件反射です。
心理学ではこれを情報の安心欲求と呼びます。
「今この瞬間、誰かとつながっている」「自分の存在が社会の中にある」ことを確認したいという本能的な欲求です。
つまり、仕事中のスマホも“無意識の癖”に近いのです。
この構造を理解せずに「集中力がない」「常識がない」と責めても、伝わりません。
まず「彼らの世界ではスマホが呼吸のように当たり前」という前提を共有することが、スタートラインです。
「評価」よりも「居心地」を優先する世代価値観
上司世代が「評価」や「出世」を軸に働いてきたのに対し、今の若手は「安心感」「心理的安全性」を重視します。
つまり、“上司に認められる”よりも“職場で安心していられる”ことを大切にしているのです。
この感覚のズレが、職場のスマホ問題を複雑にしています。
上司は「注意しないと評価が下がるぞ」と言う。
しかし新人は「居心地が悪い職場なら辞めた方がいい」と感じてしまう。
結果、「注意=否定」と受け止め、心を閉ざしてしまうケースが多いのです。
だからこそ、**怒るより“信頼を伝える言葉”**が必要になります。
「仕事中スマホをやめてほしい」ときに効果的な伝え方
感情で伝えず、「信頼を守る」という目的を共有する
注意の仕方で、相手の行動は180度変わります。
「なんでスマホ触ってるの!」と怒ると、相手は“自分の人格”を否定されたように感じます。
しかし、「その姿を見て誤解されるともったいない」と伝えると、“自分の信頼を守ってくれる人”だと受け取ります。
具体的には、次のような言い方が効果的です。
「〇〇さんがスマホを触っていると、仕事をしていないように見えてしまうんだ。
でも実際は真面目に頑張ってるのを知ってるから、誤解されるともったいないよ。」
このように“評価”ではなく“信頼”を軸に伝えると、素直に受け止めてもらいやすくなります。
新人は、「怒られた」より「気にかけてもらえた」と感じたときに行動を変えるのです。
注意よりも「観察」から始める
スマホを触る理由は一人ひとり違います。
仕事に関する調べ物かもしれないし、家族からの緊急連絡かもしれません。
たとえば、こんなシーンがあります。
新入社員のAさんは、入社直後から昼休み以外でもスマホをよく見ていました。
上司のBさんはイライラしつつも、一度だけ「何見てるの?」と声をかけました。
するとAさんは、「社内マニュアルが共有されているLINEグループを見てました」と答えました。
注意していたら誤解を生むところでした。
“観察と確認”を経て初めて、適切な指導ができます。
現代の職場では、スマホが仕事ツールでもあることを忘れてはいけません。
タイミングは「その場で、短く、冷静に」
後から注意するより、その場で短く伝えるのがベストです。
ただし感情的にならないことが前提。
たとえば、会議中にスマホを触っていたら、
「今は共有中だから、あとで見ようか」
とサラッと伝えるだけで十分です。
長々と説教をすると、相手は「萎縮」するか「シャットダウン」します。
必要なのは、指導ではなく軌道修正です。
職場全体で「スマホとの距離」を設計する
「禁止」より「使っていい条件」を決める
“禁止”は一見シンプルですが、現実的には逆効果です。
禁止すればするほど、隠れて触るようになります。
だからこそ、「いつならOKか」「どんな目的ならOKか」を明確にするのがポイント。
たとえば、次のようなルールを共有します。
- 休憩時間は自由に利用して良い
- 緊急時は上司にひとこと伝えれば確認OK
- 業務連絡は社内アプリ経由のみ許可
- 顧客対応・打ち合わせ中は机上に置かない
これにより、「線引きがあいまいだから触ってしまう」という問題を防げます。
大切なのは、“禁止”ではなく**“どうすれば問題ないか”を共有すること**です。
集中できない環境を改善する
スマホに手が伸びる理由の一つは「暇」や「不安」です。
つまり、仕事に没頭できない環境にあります。
指示待ちの時間が長い、進捗が曖昧、会話が少ない――そんな職場ではスマホが“心の逃げ場”になります。
改善のヒントは次の3つです。
- タスクの見える化:ホワイトボードや共有シートで進捗を見える形に。
- 指示待ちを減らす:小さな判断を新人にも任せてみる。
- 声かけの頻度を上げる:「大丈夫?」「次どこまでいった?」など。
このように職場の流れを整えることで、自然とスマホを触る時間は減ります。
新人教育は、個人の注意より環境設計のほうが効果的なのです。
女性社員の場合に考えたい「家庭と仕事のバランス」
「仕事中にスマホを触る女性社員が多い」と感じるケースもあります。
ただし、その背景には家庭や健康に関する連絡が潜んでいる場合があります。
子どもの学校からの連絡、家族の介護、体調記録アプリ――。
これらを一律で禁止すれば、職場への信頼を失います。
大切なのは、「私用=悪」ではなく「状況に応じて判断する」こと。
管理職が「どういう事情なの?」と一言聞くだけで、信頼関係が保たれます。
人間関係を壊さない指導には、“理由を尋ねる勇気”が欠かせません。
「スマホが原因でクビになる」現実と指導の伝え方
ルール違反ではなく「信頼の損失」
新人にとって“職場の信頼”は目に見えにくいものです。
だからこそ、なぜスマホ使用が問題なのかを具体的に伝える必要があります。
「サボってるように見える」ではなく、
「お客様や同僚からの印象が下がる」
「大事な連絡を見逃す危険がある」
「結果的に評価が下がる」
という形で行動の結果を可視化します。
「やる気がないと思われる」ではなく、「あなたの信頼を守るため」と伝えるのがコツです。
人は自分の“立場を守る理由”を理解したとき、自然に行動を変えます。
実際に「クビ」になるケースもある
情報漏えい・顧客データ撮影・SNS投稿など、
私用スマホが原因で懲戒処分や解雇に至る事例は少なくありません。
特に金融・医療・ITなど情報を扱う業界では、
スマホの持ち込みそのものが制限されることもあります。
指導時には、「ルールだからダメ」ではなく、
「これは会社を守るため、そして自分を守るための決まりなんだ」
と説明しましょう。
恐怖で動かすのではなく、目的を共有することで理解が深まります。
指導者としての“姿勢”が行動を変える
注意ではなく「導く」スタンス
新人がスマホを手放せないのは、本人の意志だけではありません。
“安心感を得る手段がスマホしかない”状況が問題です。
だからこそ、指導者は「禁止する人」ではなく「安心を提供する人」になる必要があります。
つまり、叱るより信頼を積む。
- 何気ない声かけで孤立感を減らす
- 成功体験を言葉で認める
- 「ありがとう」「助かったよ」を積極的に伝える
こうした積み重ねが、新人の“スマホに頼らない自信”を育てます。
信頼のない職場ではルールは形骸化します。
信頼のある職場ではルールが自ずと守られます。
指導者自身も「スマホとの向き合い方」を見直す
意外に見落とされがちなのが、上司自身のスマホ行動です。
会議中に通知を見たり、商談中に着信を確認したり――。
部下はその姿を敏感に見ています。
「上司もやってるのに」と感じた瞬間、注意の説得力はゼロになります。
新人にスマホマナーを浸透させるなら、まずは自分の姿勢で示す。
これが最も早く、最も効果のある方法です。
まとめ|スマホ問題は「価値観の違い」を超える成長のチャンス
仕事中のスマホ問題は、単なるマナーの問題ではありません。
それは「世代間の認識差」「心理的安全性」「職場の環境設計」が絡み合う複合課題です。
怒っても解決しないのは、スマホ使用の根っこが“感情”だから。
禁止ではなく理解、叱責ではなく対話が、信頼を育てる鍵になります。
もしあなたが新人のスマホにイライラしているなら、
「どうして触ってしまうのか」「何に不安を感じているのか」――その背景を一度考えてみてください。
そこから見えてくるのは、世代の違いではなく、人としての同じ不安と安心の構造です。
スマホは敵ではありません。
それを通じて“相手を知る手がかり”に変えられるかどうかが、成熟した職場の分かれ目です。
怒るより、観察する。
命令するより、導く。
それが、現代の職場で本当に“人を育てる”ということなのです。