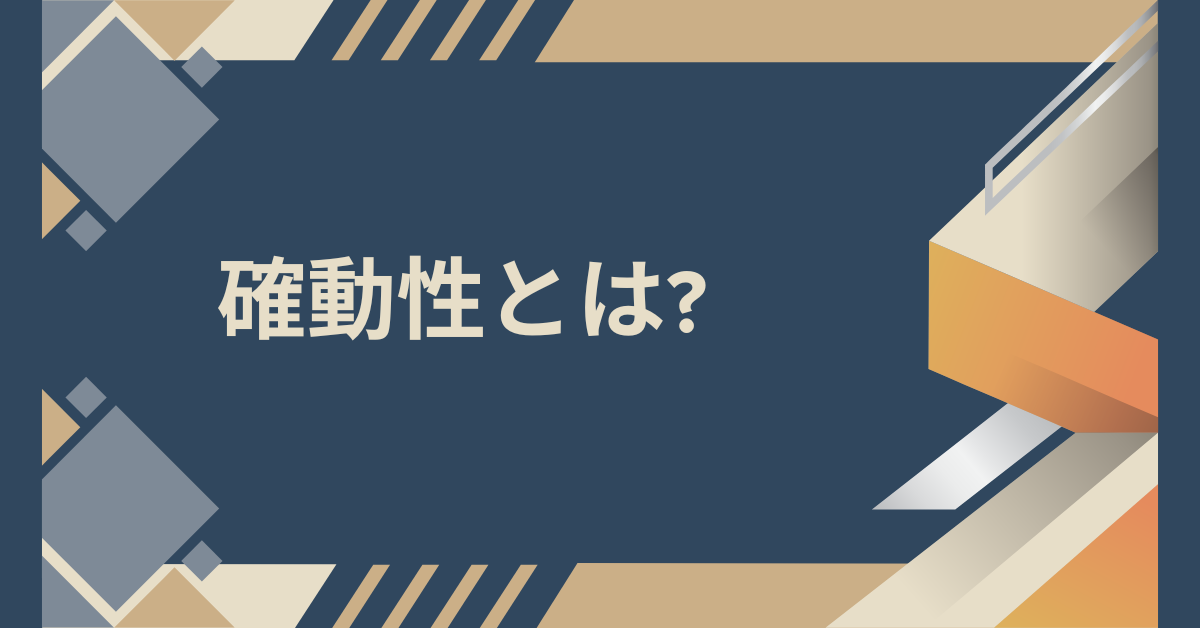仕事が「決まったはずなのに進まない」「承認は得たのに現場が動かない」。そんな停滞感のある職場に共通して欠けているのが、リクルート社で語られる「確動性」という視点です。本記事では、仕事が確実に前へ進む組織が持つ「確動性」の意味と、業務推進力を高める実践的なヒントを解説します。
確動性とは何か
確動性が高いとはどういう状態か
確動性が高いとは、仕事やプロジェクトが「決まった後に確実に動く」状態を指します。単なる計画段階ではなく、実行フェーズでの推進力や完遂力がある状態です。たとえば、会議で決まった施策が翌日には現場で実行に移されていたり、誰かに頼まれる前にタスクを完了させているような職場では、確動性が高いと評価されます。
確動性の高い組織では、担当者が指示待ちにならず自走し、周囲も「次に誰が動くか」を自然に理解して支援に回ります。単に実行力があるというよりも、「物事が自然に、滞りなく流れる状態」が保たれているのです。
リクルート用語としての起源と背景
確動性という言葉は、もともとリクルートグループの社内文化で使われていた造語に近い用語です。営業活動やプロジェクトの進行において、「ボールが止まらず、確実に仕事が前に進む」状態を指す実務的な概念として定着しています。
この言葉は、明文化された理論というよりも、現場の肌感覚から生まれた言葉です。そのため、形式的なマニュアルでは語られにくい、組織の“動き方の質”を表す貴重なヒントとなるのです。
確動性と本動性の違い
本動性とは何か
本動性とは、物事を「本当にやる」という意思決定が行動に繋がっているかを示す概念です。「やる」と言いながら実行されない、“口だけ”の状態を避けるために使われます。
本動性が高い人は、一度決めたことをやりきる習慣があり、周囲からも信頼されやすい傾向にあります。これは行動の「確度」に関する概念といえるでしょう。
両者の補完関係
本動性が「やる気」や「決意の確かさ」に関わるのに対し、確動性は「行動が継続的に動き続けること」にフォーカスしています。言い換えると、本動性が高くても、組織として確動性が低ければ、仕事は止まります。
逆に、確動性が高ければ、誰かが止まっても自然に周囲がフォローし、タスクが進み続けます。この両者をバランスよく高めることが、持続的に成果を出す組織の条件といえます。
確動性が高い組織と低い組織の違い
高確動性の組織の特徴
確動性の高い組織では、以下のような特長が見られます。
- 情報共有が迅速で、担当者が迷わない
- 推進責任が明確で、タスクの抜け漏れが起きにくい
- 一人ひとりが「次に自分が何をするべきか」を自覚している
- チーム内で進捗に対する“追い”があり、ボールが止まりにくい
このような組織では、予定外の事態が発生しても柔軟に対応でき、結果的に業務全体のスピードも早くなります。
低確動性の組織にありがちな問題
一方で、確動性が低い組織では以下のような停滞が起きがちです。
- 「検討します」のまま放置される案件が多い
- 承認プロセス後に動きが止まる
- 誰がやるかが不明確で、ボールが宙に浮いたままになる
- タスク完了の報告や成果が共有されず、次に繋がらない
これらはすべて、仕事が“動いていない”状態の典型例です。確動性が低い状態は、時間だけでなく、社員のモチベーションまでも蝕みます。
確動性を高めるためのマネジメント戦略
ボトルネックの見える化
まず重要なのは、業務フローのどこでボールが止まりやすいのかを特定することです。意思決定の遅延なのか、実行部門での着手遅れなのか、あるいはタスクの属人化が原因なのかを可視化し、改善余地を洗い出す必要があります。
明確な役割と推進責任の設計
次に、誰が“最終的に動かす責任者”なのかを明確にします。「担当者が3人」ではなく、「最終的に完遂まで持っていくのは誰か」をはっきりさせるだけで、確動性は劇的に改善します。
チーム内の役割分担を曖昧にしないことが、確動性向上の基本です。
チーム評価への導入
確動性を定量評価することは難しいですが、プロジェクトの完了率、実行までの平均リードタイム、実行後の報告スピードなどを指標として取り入れることで、チーム文化として定着しやすくなります。
確動性の高い人材を見極めるポイント
確動性と成果主義の違い
成果主義は「結果」に目を向ける一方で、確動性は「行動そのものの質と継続性」に注目します。短期的な成果ではなく、動き続ける力が評価されることで、健全な行動文化が育ちます。
面接や1on1での見極め方
確動性が高い人材は、「動いた経験」を具体的に語れることが多いです。面接や1on1では、「何をやったか」だけでなく、「そのとき誰をどう巻き込んだか」「どんな障害をどう乗り越えたか」に注目することで、確動性を測ることができます。
なぜ今、確動性が求められているのか
現代の仕事は止まりやすい構造になっている
現代の業務は分業化・プロジェクト化が進んでおり、一人の判断や行動が全体を止めるケースが増えています。だからこそ、個人の確動性だけでなく、チーム全体で「動き続ける文化」を醸成する必要があります。
リモートワーク環境での確動性の重要性
リモートワークでは、目に見える“動き”が可視化されにくくなります。だからこそ、「誰が、いつ、何を完了させたか」の共有を丁寧に行う必要があり、自走力・巻き込み力のある人材の価値がさらに高まっています。
終わりに
確動性は、単なる行動力とは異なり、「確実に動き続ける力」を意味する実践的な概念です。本動性とセットで理解し、組織や人材の評価軸に取り入れることで、業務が止まらない組織づくりが実現できます。
今一度、自社の仕事は“止まっていないか”を見直すところから、確動性の高いチームづくりを始めてみてはいかがでしょうか。